報告者 土 井
2018年6月21日(木)布袋北学習等供用施設にて社楽の会を開催しました 。
参加者(勤務校)は、土井(布袋小)、安形先生(犬山中)、坪内先生、船渡先生(古東小)、杉田先生(宮田小)、日佐先生(岩南中)、田中先生(布袋中)、玉置先生(城東中)、奥村先生(岩東小)、早川先生(尾張教育事務所)の10人でした。



第494回 社楽の会報告 第493回へ 第495回へ TOPへ
報告者 土 井
2018年6月21日(木)布袋北学習等供用施設にて社楽の会を開催しました 。
参加者(勤務校)は、土井(布袋小)、安形先生(犬山中)、坪内先生、船渡先生(古東小)、杉田先生(宮田小)、日佐先生(岩南中)、田中先生(布袋中)、玉置先生(城東中)、奥村先生(岩東小)、早川先生(尾張教育事務所)の10人でした。



土井の資料を紹介します
| 1 社会的な見方・考え方を鍛える一試案 2 平成30年度 愛知教育大学公開講座 3 研究発表会情報 4 お役立ちサイト紹介 5 おもしろ学校で授業をします |
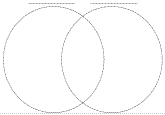 【比較思考】(ベン図)
【比較思考】(ベン図)
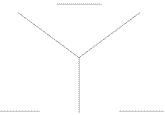
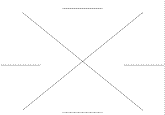 YチャートやXチャート、数が不定ならくま手チャートが使いやすい。
YチャートやXチャート、数が不定ならくま手チャートが使いやすい。
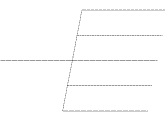
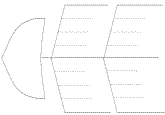 次に「ひれ」の上下に「中央政権」「地方政権」「文化」「民衆」と記入する。
次に「ひれ」の上下に「中央政権」「地方政権」「文化」「民衆」と記入する。
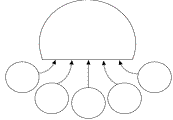 点で分析することができる。
点で分析することができる。
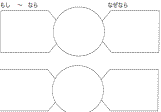 【因果思考】(キャンディ・チャート)
【因果思考】(キャンディ・チャート)
 中央にお題を書き、どんどん線でつないでいくものである。
中央にお題を書き、どんどん線でつないでいくものである。
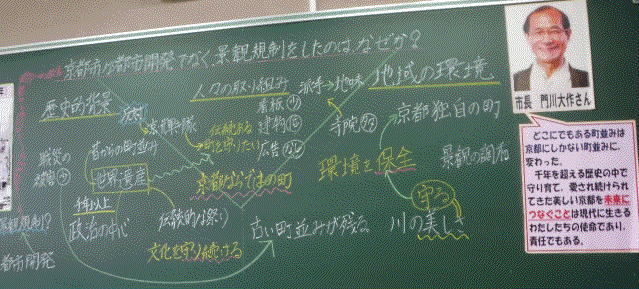 東長良中学校では、板書もYチャートになっている。
東長良中学校では、板書もYチャートになっている。
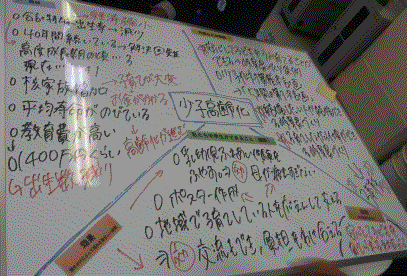
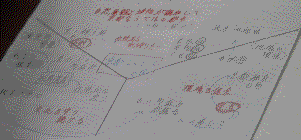 生徒はグループごとに、ホワイトボードでYチャートにまとめながら話し合っていく。
生徒はグループごとに、ホワイトボードでYチャートにまとめながら話し合っていく。
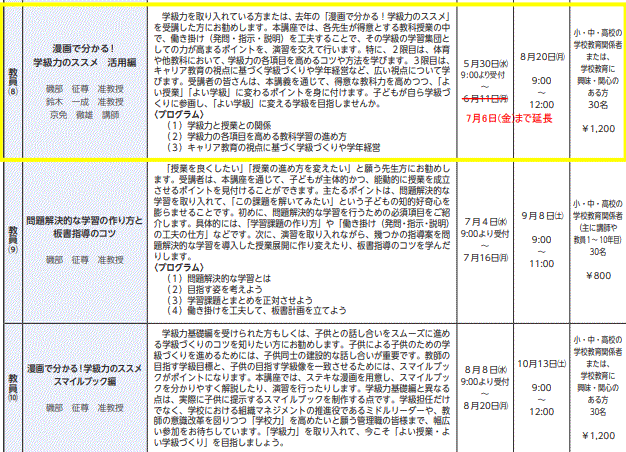
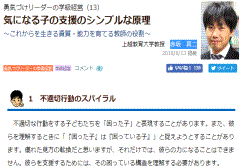 現在、13回まで続いています。
現在、13回まで続いています。
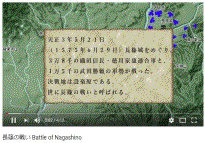

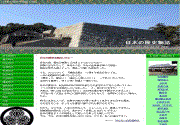 しています。
しています。
 時は戦国・・・戦国時代を駆け抜けた武将、城、合戦などを、年表を軸に追いかけるサイトとあり、その情報量は膨大です。
時は戦国・・・戦国時代を駆け抜けた武将、城、合戦などを、年表を軸に追いかけるサイトとあり、その情報量は膨大です。
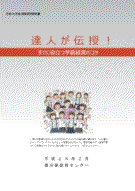 です。その他、戦国年表 国と郡 城・社寺 関連表 用語集 公開記録 参考文献 プロフィール・リンク など、歴史好きならたまりません。 http://www.geocities.jp/hosinoufo3/index.html
です。その他、戦国年表 国と郡 城・社寺 関連表 用語集 公開記録 参考文献 プロフィール・リンク など、歴史好きならたまりません。 http://www.geocities.jp/hosinoufo3/index.html