アメリカ合衆国理解を深める授業構想
-社会科学習を基盤とした総合的な学習を通して-
名古屋市立丸の内中学校
西尾 雅志
1 はじめに
「百聞は一見にしかず」。外国を訪れたのは、今回が初めてである。実際に自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の身をもって体験することがその国に対する理解を深めることに重要であるかを痛感した。
日本を出国する前、職場の仲間から「絶対に煙草を吸うことができないから、この際禁煙したらどうか」と勧められた。アメリカ合衆国の実情をよく知らなかった私は、半信半疑であった。さすがに空港、飛行機内、公共施設内は禁煙であったが、その他の場所では喫煙することができた。これは、自分が抱いていたアメリカ合衆国という国に対するイメージ、見方・考え方が変化した一例である。このような自分自身の変化が、これからの社会科の授業に反映していくと思う。
今回の研修で訪れた都市は、ボストン、ニューヨーク、ニューブランズウィック、フィラディルフィア、ランカスター、ワシントンである。これらの都市は、アメリカ合衆国の政治・経済・文化の中心であるとともに、アメリカ合衆国史に非常に関係の深い都市でもある。この研修では、それぞれの都市にある様々な博物館、歴史的建造物などを見学し、多くの資料を得てきた。
そこで、平成14年度から完全実施される学習指導要領を念頭において、こうした自分自身のアメリカ合衆国に対する見方・考え方の変化と現地で入手した資料、現地で撮影した写真をできるだけ多く生かすことができる授業を構想することにした。
2 新学習指導要領とアメリカ合衆国理解学習
(1) 学習内容の精選
平成14年度から完全実施される学習指導要領では、地理・歴史・公民の各分野で学習内容の精選が行われる。
地理的分野の「世界の国々」では「世界の国々の中から幾つかの国を取り上げ、地理的事象を見いだして追究し、地域的特色をとらえさせるとともに、国家規模の地域的特色をとらえる視点や方法を身に付けさせる」「二つ又は三つの国を事例として選び、具体的に取り扱うようにすること。なお、事例として取り上げる国については、近隣の国を含めて選び、それぞれ特色ある視点や方法で追究すること」となっている。
こうした内容を受けて教科書が編集されているが、どの教科書を見ても「アメリカ合衆国」を取り上げている。従って、アメリカ合衆国の地理的な概要を生徒がつかむことは可能である。
しかし、歴史的分野では「世界の歴史については、我が国の歴史を理解する際の背景として我が国の歴史と直接かかわる事柄にとどめること」となっている。そのため教科書の「アメリカ合衆国」の歴史についての記述が大幅にカットされている。
<参考> 歴史的分野教科書 新旧の比較 (大阪書籍の場合)
| 旧 | 新 |
|
小単元「アメリカの独立」 1ページ |
小単元では扱われていない |
こうした学習内容の精選の結果、来年度以降、アメリカ合衆国の歴史、文化、生活スタイルなど多角的・多面的にアメリカ合衆国を理解させる社会科の授業構想が難しくなることが予想される
(2) 社会科学習と総合的な学習
これまでに小中学校で取り組まれてきている総合的な学習の中には、イベント的で継続性のないものがある。新学習指導要領によって社会科の学習内容がかなり精選された背景の1つに、総合的な学習の導入がある。そこで、アメリカ合衆国理解を深める学習を展開するためには、社会科学習と総合的な学習の1領域である国際理解を関連させ、十分な時間確保と学習内容の拡張を図っていく必要がある。そして、総合的な学習がイベント的にならないようにするため、社会科で培った基礎・基本を基盤にした学習にすることが大切である。
そこで、社会科学習を基盤にした総合的な学習を通して、アメリカ合衆国理解を深める授業を構想することにした。
3 アメリカ合衆国理解を深める授業構想
(1) 単元名 「アメリカ合衆国ってどんな国?」
(2) 現在までの取り組みと授業で育てたい生徒の姿
本校では、1年生を対象に国際理解学習を行っている。主にアジア、南アメリカ、アフリカの国々が中心で、先進国を扱っていない。その理由の1つに、アメリカ合衆国を含めた先進国の情報は、マスコミやインターネット等を通して大量に提供されているところにある。特に、日本と関係の深いアメリカ合衆国の情報は毎日のように提供されている。一方、アメリカ合衆国の首都や現在の大統領名を答えられない生徒がいる実情から考えると提供されている情報が、アメリカ合衆国理解につながっていないことが分かる。そこで、本単元では今回の研修で収集した情報(資料、写真等)を提供することで、次のような生徒を育てたいと考えた。
| 調べ学習やアメリカ人とのコミュニケーションを通してアメリカ合衆国への関心を高め、自らアメリカ合衆国へ行って様々な事象を追究したいと考える生徒 |
(3) 基本的な流れ
総合的な学習(国際理解教育)
事前学習 → 体験的な学習 → 事後学習
(社会科学習) (アメリカ人との会話)(まとめ・感想)
「気付く」 「確かめる」 「深める」
(4) 指導計画(13時間)
| 事 前 学 習 | <地理的分野の学習6時間> ・多民族 ・複合文化の国 ・特色ある農業地域 ・企業的大規模農業 ・世界一の工業 ・都市と都市を結ぶ交通・情報網 ・世界の中のアメリカ |
目標 アメリカ合衆国が、多民族・複合文化の国であることをとらえさせるとともに、世界の中心的な役割を果たしている様子を理解できるようにする。 |
|
| <調べ学習 4時間> <目標> アメリカ合衆国の歴史、文化や人々の生活に関心をもち、アメリカ人とのコミュニケーションに積極的に取り組むことができるようにする。 1 3つのグループを編成し、各コース別に調べ学習を行う。 ○ 今回の研修で撮影した写真と研修行程表を各グループに提示し、調べ学習の手掛かりにさせる。その際、写真の日付に着目させる。 ○ 今回の研修で入手した資料、パンフレットを自由に見ることができるようにしておく。英語の説明が多いのであらかじめ辞書をもってくるように指示する。 |
|||
<アメリカ史> ボストンティーパーティー |
<アメリカ文化>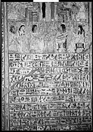 パピルス(絵文字) |
<アメリカの生活> ハンバーガー |
|
 ゲチスバーグ |
 アーミッシュの馬車 |
 ワゴンサービス |
|
 リバティーベル |
 ヤンキースタジアム |
 高層ビル |
|
|
2 調べ学習プリントに調べた内容と疑問点をまとめる。 3 各グループごとに報告書を作成し、調べた内容を発表する。 ○ 発表内容で分からないことは質問させる。 |
|||
| 体 験 的 な 学 習 | <国際理解学習 2時間> 1 アメリカ人の講演を聞く。 ○ 事前に講演内容を打ち合わせておく。できれば視聴覚機器を活用してもらうように依頼する。 ○ 講師はアメリカ東海岸出身者に依頼する。(今回の研修が東海岸中心であったため) 2 事前学習で生じた疑問を質問する。 |
||
| 事後学習 | 1時間 「アメリカ合衆国ってどんな国」をテーマにまとめ文を書く。 | ||
4 おわりに
9月に起こった同時多発テロ事件には驚かされた。2週間ほど前にはあの場所にいたかと思うとぞっとした。ほんの2週間で国際情勢が急変したわけである。自分の目で見てきた貿易センタービル、ペンタゴンが崩壊してしまった。この事件が起こったとき、社会の授業中に「貿易センタービルはニューヨークのどこにあるの」「ペンタゴンって何」など様々な質問がでた。これらの質問の多くに即答することができた。これは、今回の研修の成果である。アメリカ合衆国理解を深める授業を構想する際、最も大切なことは教える教師がもっとアメリカ合衆国について理解を深めることだと思う。今回の研修では、東海岸中心に理解を深めることができた。しかし、西海岸、南部、中央部が残されている。社会科教師として、生徒に自信をもってアメリカ合衆国を教えるためには自ら西海岸、南部、中央部に出掛け、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分で様々な経験をする必要があることを痛感した。そして、それらを授業の中で生徒に還元していくだけでもアメリカ合衆国理解を深めることになると思う。