アメリカの生活や文化を理解させる社会科指導
-2年生地理的分野「アメリカ合衆国」の教材開発-
尾西市立第一中学校
坂井 辰美
1 はじめに
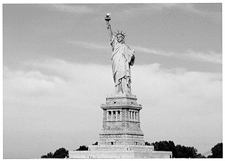 今回の研修に参加するにあたって、生徒に「もし、あなたがアメリカに行けるとしたら、どのようなことを実際に見たり、聞いたりしてきたいですか」と質問してみた。その結果、「自由の女神やグランドキャニオンを見たい」など有名な観光地をあげたり、「アメリカの生徒の生活は日本とどのように違うのか」「夏休みはどのように生活しているのか」など同じ中学生の生活に対する興味をあげたり、「アメリカの人たちの食事について知りたい」など、アメリカ文化に対する興味をあげたりしていた。これら中学生の興味・関心の対象となりうる内容や視点を今回の研修の大きな課題として参加した。
今回の研修に参加するにあたって、生徒に「もし、あなたがアメリカに行けるとしたら、どのようなことを実際に見たり、聞いたりしてきたいですか」と質問してみた。その結果、「自由の女神やグランドキャニオンを見たい」など有名な観光地をあげたり、「アメリカの生徒の生活は日本とどのように違うのか」「夏休みはどのように生活しているのか」など同じ中学生の生活に対する興味をあげたり、「アメリカの人たちの食事について知りたい」など、アメリカ文化に対する興味をあげたりしていた。これら中学生の興味・関心の対象となりうる内容や視点を今回の研修の大きな課題として参加した。
2 教材化するにあたって
今回の研修内容を教材化するにあたって、アメリカを視察することによって肌で感じ、実際に見聞きしてきたことをまとめておきたい。
(1) 地域や社会に対する貢献
今回の研修でまず感じたのは、いろいろな場で地域・社会への貢献が求められるということである。例えば、最初の研修先であったボストン日本人学校では地域の高校の校舎を借りるためには、地域への貢献を求められ、現在は日本文化を紹介する講座を開いている。また、各地の美術館・博物館などでは夏休み中の生徒を受け入れるため、サマーキャンプが開催されている。これは、各施設が地域の子供たちを育てていこうとする地域貢献の一つであると考える。
さらに、各地の大学が社会貢献に意欲的に取り組んでいることである。ラトガーズ大学での講義であったように、社会人教育に力を入れているだけでなく、今回訪れた各地の大学が、自らの研究の成果を博物館や美術館で展示することで社会に還元しようとしていることに驚いた。
(2) 自国の歴史を大切にする国
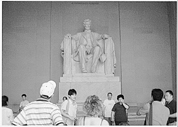 アメリカ人と日本人の国家に対する考え方には大きな違いがあると感じる。これは、アメリカが自らの力で独立を勝ち取り、南北に分裂する危機を乗り越え、その後何度も「国家とはなにか」を問い続けてきたからこそ形成されたものと思われる。
アメリカ人と日本人の国家に対する考え方には大きな違いがあると感じる。これは、アメリカが自らの力で独立を勝ち取り、南北に分裂する危機を乗り越え、その後何度も「国家とはなにか」を問い続けてきたからこそ形成されたものと思われる。
さらに、今回の研修で自国の歴史を日本に比べ大切にしているように感じた。例えば、ボストンでは、建国の歴史が学べるように町中が整備されており、沢山の人々が建国当時の人々の願いや行為を知ることができるようになっている。フィラデルフィアでは、アメリカが独立を宣言した当時の様子を理解するに適した施設を国が整備している。南北戦争の激戦地であったゲティズバーグでは、当時の様子を学べる国立の公園が整備されていた。ワシントンでは、リンカンやワシントンをはじめ、多くの大統領経験者の記念碑があり、その業績を紹介している。
ホームスティ先の高校生がゲティズバーグを訪れたとき、体が震える感情を抱いたと語った。これは、このような国としての努力があるからこそ、自国の歴史を知る機会に恵まれ、先人の努力に敬意をはらうようになるのではないだろうか。
(3) 食に対する考え方の違い
 アメリカについた最初の夜、ボストンでの夕食の量の多さには驚いた。出発前からアメリカの食事の量の多さは聞いていたが、想像以上の多さであった。ガイドブックには、「アメリカでは、食事はカロリーをとる行為であるといる意識が強かった」と書かれていたが、確かに頷ける多さである。
アメリカについた最初の夜、ボストンでの夕食の量の多さには驚いた。出発前からアメリカの食事の量の多さは聞いていたが、想像以上の多さであった。ガイドブックには、「アメリカでは、食事はカロリーをとる行為であるといる意識が強かった」と書かれていたが、確かに頷ける多さである。
ホームスティ先での食事では、夕食は自分の出身国に関係した食事ではあったが、それほど違和感のない食事であった。しかし、次の日の朝の食事風景はアメリカらしいものであった。朝食の中身はスクランブルエッグやパンなどであったが、その横にビタミン剤やカルシウムなど数種の錠剤が置かれていた。つまり、体に必要な栄養素をビタミン剤などでまとめてとろうという食事であった。確かに町中にはビタミンショップが目立つ気がした。
しかし、最近は、体に必要な栄養素を自然の食物から取った方が良い、と考える人が増えてきたとのことである。そのため、無農薬で生産しているアーミッシュの人々の野菜が静かなブームであるという。
(4) サマーキャンプ
事前の生徒向けアンケートでもっとも多かった「中学生の夏休み中の暮らし方を知りたい」という疑問について視察前に調べたところ、夏休み中は「サマーキャンプ」に参加している生徒が多いことが分かった。そこで、今回の視察では、この「サマーキャンプ」について詳しく調べてみた。(詳細はAグループ研究報告参照)
(5) 多様性を持った社会
今回、ホームスティをさせていただいたフィシャー氏は、戦後7ドルを持ってハンガリーからアメリカに移住してきた。現在は10億を超える資産を持つ、まさにアメリカンドリームを実現した人物である。このようにアメリカは、いろいろな国から移民を受け入れてきた。大都市の多くには中国系移民のコミュニティーであるチャイナタウンがある。
このように、多くの民族を受け入れてきたため、アメリカには多様な価値観が存在する。例えば今回訪れたアーミッシュの村は現代文明を拒否し、自分たちの伝統を重んじながら生活している。
これらのことから、以下のねらいを設定し、実践の計画を立てた。
| 教師が実際に見たり、聞いたり、感じてきたアメリカの生活や文化を、生徒に調べさせたり、視察の追体験をさせたりすることで、アメリカに対する理解を深められる授業構成をする。 |
3 実践内容
地理的分野「アメリカ合衆国」の単元構成を考えてみた。ただし、現在担当している2年生はすでに、本単元の授業を終えているため、アメリカの文化や生活などに絞って実践を行う。
(1) 単元の目標
テーマを追究することで、アメリカが多民族国家であり、文化や社会のしくみなどにわたって、どのような影響を与えているのかを知り、各分野で多民族国家の特色が多彩に出ていることを理解する。
(2) 単元構想図
|
第1時 アメリカ各地の工業の特徴について調べ、特徴をまとめよう。 |
(3) 単元の流れ
第3時では、今回の研修で撮影してきた写真を生徒にみせながら、アメリカで学んできたことや感じたことを話す。ここでは、生徒にアメリカへの興味を持たせたり、疑問を持たせたりすることをねらいとする。この時間に見せた写真は、「学校生活や夏休みの暮らし」「食べ物」「合衆国の建国や発展に貢献した人物」「多民族国家」などのテーマで編集し直したものである。
 スクールバス |
 サマーキャンプの様子 |
 ホストファミリーと |
 フランクリン像 |
 ワシントンメモリアル |
 ルーズベルト大統領像 |
第4時では、協同で調べていくためのテーマを設定する。(当然クラスによってはテーマ数が違ってくるが、できるだけ上記したようなテーマの設定ができるように指導する。)テーマ毎に何を調べればよいのか考えを出し合う。その後、調べるテーマの数と同数になるようにグループの人数を決め、グループ編成を工夫する。グループに分かれた後、誰がどのテーマを調べるかを決定する。
第5時では、協同で調べ学習を進める工夫として、ジグソー学習を取り入れた。この学習は、グループ内で何を調べるか担当者を決める。次に同じテーマを調べる生徒が集まりグループをつくり、協力して調べ学習を進め、お互いの情報交換をし合いながら分担したテーマを調べる。(その後、元のグループに戻り、調べてきた内容をお互いが報告し合う。第6時に行う。)また、この時間では、調べる方法、資料などの集め方やテーマに対する見通しを話し合わせる。
第6時では、第3時で調べた成果をもって、元のグループに戻り、報告をし、自分が調べた内容と他のグループ員の報告を合わせて、一枚の報告書を作成する。この報告書の最後には、アメリカ文化や生活に対する自分の考えをまとめて,報告書を完成させる。
(4) 授業を終えて
第3時に現地で撮影してきた写真を見せた。現在アメリカが注目されていることもあって、生徒たちは熱心に説明を聞いていた。時々質問をしてくる生徒も多数いて、返答に困るような質問も出てきた。この写真によって、生徒たちに十分調べようとする意欲づけができたのではないかと考える。その結果、生徒たちは「食べ物について」「アメリカをつくりあげた人々」「アメリカの中学生の生活」「サマーキャンプを調べよう」などのテーマを設定することができた。
第4時では、「何を、何で調べるのか」を話し合わせた。文献資料で調べる生徒が多かったが、インターネットを使う計画を立てる生徒もいたので本研究グループのホームページも紹介して調べる手助けとした。
第5時では、ジグソー学習を取り入れたこともあって、自分の持っている情報を教え合いながら、調べることができ、日頃はなかなか調べられない生徒が何とか自分の役割を果たすことができた。
第6時では、それぞれのグループ員が調べてきたものをコピーして、一人一人がB4サイズの紙に貼り付けて、まとめをした。さらに、全員が調べてきた内容を読んだ後、アメリカの文化や生活から考えたことを書いた。
5 おわりに
今回のアメリカ視察ほど、「百聞は一見に如かず」を実感できたことはない。教科書で教えている内容について実際に見たり聞いたり感動したりしたことを生徒に話すだけでも、興味をもって話を聞いている。来年度以降、社会科は学び方重視の傾向がますます加速していく。学び方重視の学習を支える重要な要素は、学習意欲を高める教材開発である。そのためにも今回の経験を大切にしていきたい。