F森教授が天竜市に美術館を設計した。
東洋大学の講師でもあり、実施設計を担当した内田祥士さんからお招きがあり、 現場を見学したのが昨年秋口のことだったが、竣工真近となり、 建築士会でF森先生を招いての見学会というのに出かけた。
感想は「シロウト恐るべし」というところであった。 路上観察学は余技であり、F森先生の御専門は建築歴史家であるのだが、 ここ数年の間に数点の建物を設計されており、それらが建築学会賞を始めとする主要な賞を総ナメにしている。 世にゴマンといるはずの建築設計専門家は一体何をしているのだ、という訳だ。
さて、実作の美術館を見ると、これはもうマイリマシタとしか言いようがない。 たしかに大学の授業には建築史の講義も含まれていて、ちゃんと、 とは言わずとも一通りのことは知っているのだけれども、それはそれ、知識として仕舞い込まれており、 さて、実際の設計はというと「普通は、、、」という基線から、適当に手の内の術を並べ、 問題にならないことをやっておった、というのをつくづく思い知らされた訳である。
世間の通り相場の手を使って、無難に纏める、というのだが、これが小住宅などの場合、 きちんとした技術的帰結であることは少なく、大した根拠もなく、ただ何となく、ということが多い。 それに較べると建築歴史家の「手の内」には恐ろしいものがあるのだ。 なにせ建てられた建物が100年後にはどうなっておるのかがよく解っているのだから。
F森教授が恩師と呼ぶ村松貞次郎さんには「日本近代建築の歴史」というNHKブックスがあり、 あとがきのなかで村松さんは「…古い建物をただ無闇に破壊して、計算にあった建物を惰性的に建てているにすぎない。」と断じておられる。 ボンクラ設計屋の私など、言葉で読む限りではそれなりに他人事のように納得していたのだが、 「野人」F森教授の実作を見ると、村松さんが言わんとしていたことがわが身の姿そのものに思えて、筑波山のガマと化してしまう。
たまたま同級の室井君に付き従って福島県の北で「地域型住宅計画」の手伝いをしているのだが、 相馬駅前のビジネスホテルで、近くの本屋で買い求めたF森教授の岩波新書「日本の近代建築(下)」を読み始めた。 晩年「これからは作らないことも設計の役割です。」という様なことをおっしゃっていた村松さんの本と違い、 野人の面目躍如という書き方で面白く読むことができた。バラック装飾社などにもきちんと言及しているのであります。

天竜市美術館
の近くに建てた診療所、、、ヴェントゥ−リの「母の家」みたいに階段室を大きくしてやろうと思ったのだが、工務店が怖がって2m程縮められてしまった。
残念(本文には関係ありません。)

相馬ステーションホテルより(本文には関係ありません。)
相馬駅前のビジネスホテルで、窓の雪を見つつ、「日本の近代建築」を手に、地域型住宅計画を考えていると、気付いたことがあった。 住宅メーカーが豪華なコマーシャルを振り撒く割には、住宅の「使い方」の情報が次第に痩せ細っているのではなかろうかということである。 かっての日本式の住宅では部屋は機能では呼ばれずに、「四畳半」「八畳」というようにハードウェアとしての呼称で扱われて来た。 それが住宅近代化の間に「居間」「食堂」「寝室」といったソフトウェア込みの名前で呼ばれるようになってずいぶん経つが、 現代の我々はそうした住宅の捕え方によって充分な恩恵を受けているのかどうか、もう一度振り返ってもよいような気がするのだ。
「居間」「食堂」「寝室」「書斎」といった部屋別の機能は、 九尺二間の裏長屋で四畳半に親子四人が暮らしていたような時代の夢としてはともかく、 それらを当然のことのように「消費」してしまう現代の家づくりが、それに見合うだけの豊かさをもたらしているだろうか。 家族が成長し、部屋の必要性が変化すると共に、ものとしての寿命よりはるかに早く、 室名が示す機能上の寿命を消費してしまい、立て替えざるを得なくなってしまうような家づくりは行われていないだろうか。
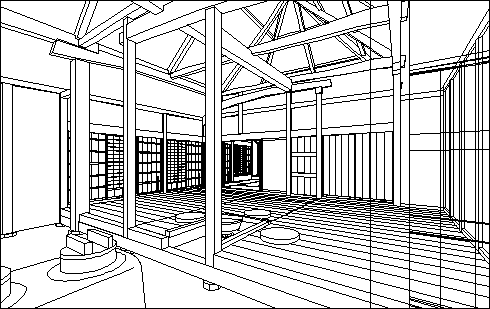
福島県新地町黒沢清之進宅内部
修復報告書より
板の間が広いのは伊達藩米倉の役宅なので、オフィス機能も兼ねているはず。
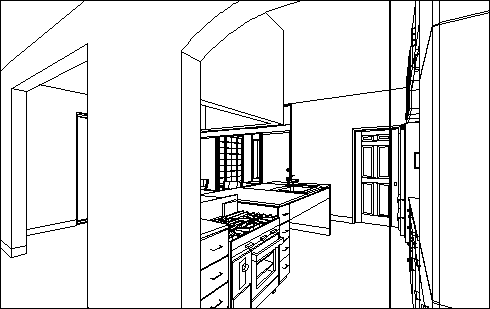
現代語訳を書いてみた。オ−プンキッチンは「土間」にある。こうしてみると住宅の機能は縄文時代からそれほど変わっていない。
気が付くとこれは何だかパソコンのソフトとハードの関係にも似て見える。
「ソフトウェアが進化したので、ハードウェアを買い換えなければならない。」と、
この15年ばかりの間に毎年の如く消費を拡大し続けたパソコンだが、
ここに来て「ソフトウェアのバージョンアップなんて、ハードウェアお買い換えの呼び水に過ぎない。」
という疑問が急速に膨らんでいる。実は同じ手が遥かに金額の大きな住宅の世界でも行われているのだ。
そしてそれで生活をしている設計屋なんて一体何だろう、と自問してしまうのだが、
何とかこの辺りのことを「地域型住宅計画」に盛り込めないかと考えている次第。