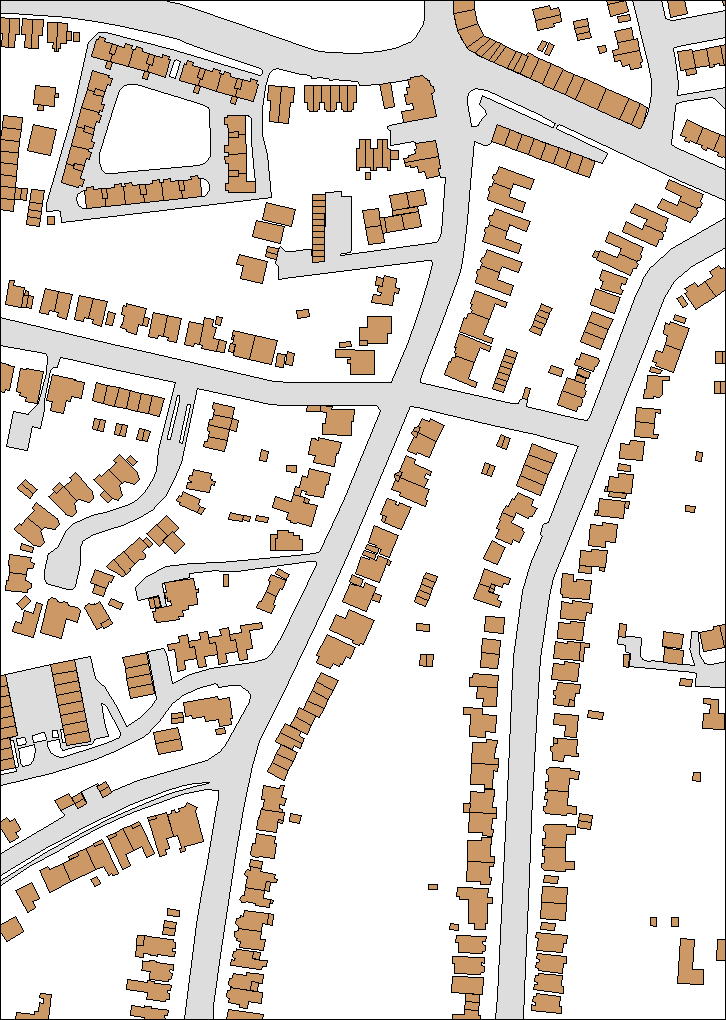マンション?
今では「マンション」という言葉もすっかり定着して、英語圏の新聞にも”manshon”として紹介されることがあるが、これは日本語なので、気を付けてほしい。日本語の「マンション」は技術用語でもなく、法律用語でもなく、単なる営業用語なので、正確を期する時には日本語の「アパート」も「マンション」も「集合住宅」と呼ぶ方が良いだろう。英語圏における”mansion”は戸建て住宅だ。
住戸タイプの英語による呼び方は下記を参考にしてほしい。
|
|
|
| detouched house | 戸建住宅 |
| semi-detouched house | 二戸一棟 |
| multi family housing | 集合住宅 |
| apartment house | 集合住宅の住戸(NYCセントラルパークに面した1戸20億円以上の住戸もアパートメントハウスだ。洒落て ”mansion”と呼ぶこともあるが、通常は”luxury apartment house”と言うことが多い。) |
| town house | 接地型集合住宅(2−4階建ての縦割り集合住宅で、各戸に階段がある。) |
| mansion | 邸宅(戸建で、米国の新築だと敷地3,000坪以上、床面積300坪以上のものが多い。) |
これがいくらぐらいかというと、米国でも地域によって収入に格差が有り、住宅価格もそれに準じている。ニューヨーク、シカゴなどの大都市では、中心市街地には低所得者と観光客しかいない、という「インナーシティ問題」があるが、セントルイスではこれが「低所得者向き近郊アパート」となって、浜松の「日本語の通じないアパート」に近いかもしれない。
家計収入中央値:$36,121 個人所得平均値:$19,775
家計収入中央値:$120,507 個人所得平均値:$50,562
$119,400、土地(多分300坪程度)はオマケだ。
セントルイスでは1960年代に開発された超高層大型団地が、立体貧民窟となって、破却される、という経験を持っている。
プルーイット.アイゴー
住宅価格が共稼ぎの年収ぐらいなら、5年程で新築住宅を購入、子供を育てられるが、住宅価格が共稼ぎの年収の3倍となると、なかなかアパートから卒業しにくいのだろう。日本ではまだまだ「土地はタダ」と行かないので、これが重荷になっている。
ネットに各国の不動産情報がどっとあるので参考にしてほしい。例えばシアトル: www.zillow.com
英国には地主が800余人しか居ないそうだ。いわゆる「貴族階級」。そこで「売地」というものは無い。不動産の殆どは99年の定期借地権、ということになる。何時のものか分からない石積みの躯体を、新築同様に改築して土地建物で20万ポンド位で売り出す。買った人は2-3回修繕して、99年目に地主に返す、ということのようだ。建物は洞穴同様、地形の一種なのだ。
第二次大戦後の戦災復興では、低所得者向け住宅政策として、政府が賃貸住宅を大量に供給した。それまではディッケンズの小説に出てくるような、屋根裏などに住んでいた低所得者は、近代的・文化的生活を出来ることになった。ところが1980年代に入り、マーガレット・サッチャー氏が「このままでは英国は倒産してしまう。」ということで公営住宅予算をバッサリ削り、公営住宅に住んでいる人に「定期借地権で買え。」ということをやった。その結果かっての公営住宅もほとんどが賃貸から持ち家に変わった。
図は英国ロンドン広域都市圏サットン市。右下、中上右と上左はセミデタッチドハウス、上右の通りに面したものは昔風のタウンハウス、その下向かい側は今風のタウンハウス。
Googlemap
http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/urbanism/m_ho/005/005.html
に写真あり。