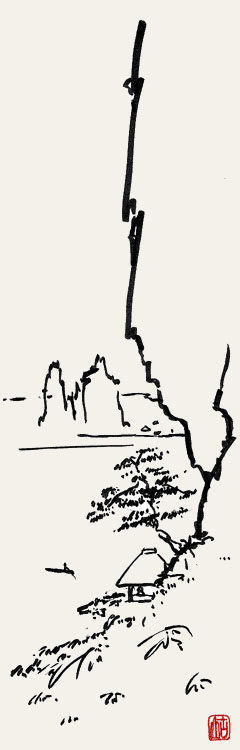
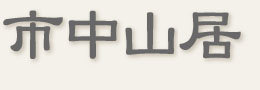
江戸時代の文人墨客の理想とする住まいに「市中山居」というのがあります。街中に住みながら、山の中に住んでいる様な気分、というのでしょう。江戸でいうと「根岸の里」あたりが有名。
床の間に南宋式の山水画を掛け、世俗の雑事に邪魔されないで、自分の求める世界に遊ぶ、みたいなもんすね。いわゆる遊び人。お金に困らない人がやるには良いが、平民が面白がっているとやがて餓死します。
障子を開けると隣の長屋で何を食べているかわかる、というのでも良いのでしょうが、お金に困らない人がやると、もっと大仕掛けになります。幕末までは「澤村」と称して田舎だったのでしょうが、御一新の後これが廣澤町となって、浜松での「市中山居」の家元になりました。
舞台装置も優れています。ちょうどアニメの「千と千尋」のイントロにあるような、トンネルを抜けると廣澤町です。

廣澤山普済寺は三方原合戦の折、徳川家康が本陣を置いたところです。その時には天守閣などなく、いまの天守台のあたりには物見櫓が作られていた程度でしょう。
門前には「酔っ払いは入ってはいけません。」という石柱があります。「なるほど小坊主どもの勉強の邪魔になる。」と納得。しかし待てよと、もう一度よく考えると、石柱を立てなければならない理由があったのでしょうね。最初は張り紙、次には木札をかけて置いたものが、いずれも酔っ払いにむしりとられてしまったのかもしれません。

普済寺の前の坂を登ると西来院があります。築山御前の墓があります。西来院の周りには生垣を回した古いお宅がいくつもあります。

西来院の裏には60バブルの前まで、戦後の市営住宅のような作りの小さな借家もありましたが、一つずつ取り払われてゆきます。。

すると「家賃に関係なく、管理できない。」ということでしょう、生垣も少しずつ減ってゆきます。

中にはまだ昔風の生垣を巡らせた借家の作りも残っているのですが、将来どうなるでしょう。

大きなお屋敷もありますが、西来院の森を借景して一回り大きく見えます。

西来院の西側は廣瀬谷と称し、西来院に続く一番の奥手は埋め立てられて分譲地になっていますが、沼のような池が残されています。これもまあ立派な借景です

覗いてみるとこの葉に隠れて水が溜まっています。築山御前の故事など考えると「触らんほうが良い。」という感じもします。

まあちょいと山椒の若芽を失敬するぐらいなら、重大な祟りを呼び込むことはありますまい。

バブルの頃には崖地を地上げして「斜面型マンション」にしよう、という話もありましたが、住民が地区計画決定をし、斜面型マンションの規制も厳しくなって着工を阻止しました。しかしこの先どうするのでしょう。

江戸時代には組屋敷の奥の山だったのでしょうが、明治の御一新の後、入殖する人がいたのでしょう。当時はまだ野菜は自給自足、という時代だと思います。「元○○藩士」みたいな構えのお宅もあります。

明石為次は元三河藩士、代々相続をすると改名して為次を名乗るのだそうです。鈴木与平と同じです。早くから石油の商いを初めて成功したとか。元々は今の図書館の敷地が明石山だったのを、こちらに引っ越したそうです

勲三等勅選貴院議員参院議員川上嘉市氏宅。活用しないと維持費だけでも大変でしょう。

おや、測候所の敷地に砂利を敷いてあります。誰が開発するのでしょう。市内のマンションも供給過剰のようです。補助金をマンション会社の工事高につぎ込むための開発は、お考えいただきたいものです。


