 |
300B(敢えてWE-300Bとは記しません)のアンプ製作集です。 中には、真似してはいけない作例も含まれていますので注意が必要です。 ある程度の真贋を見極められる目が必要な本です。 1998年1月10日発行 特に金田明彦の作例は、絶対に真似しないように。 |
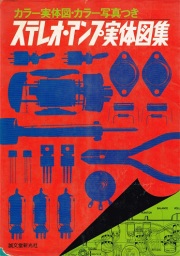 |
ステレオアンプの製作集。 全て初歩のラジオ所収のもので、タイトル通り実体配線図がついています。 作例の中には、初歩のラジオ掲載時に「完成」(失敗作)に至らなかったと記載されたものもありますので注意が必要です。 1980年6月10日第4版発行。 |
 |
これに記載されているデータや数式の多くは、信じてはいけないものです。 読み物としても、価値を見出せません。 活用方法は、常に信頼できる本を傍らに置いて参照できる状態で確認する癖をつけることにあります。 1998年12月14日発行。 |
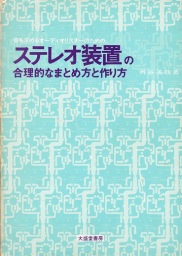 |
桝谷氏のライフワーク的製作集です。 多くの活用可能なデータや考え方が記載されていて、現在でも活用できると思われます。 1978年10月15日発行。 |
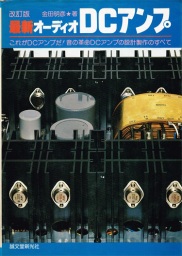 |
極めて初期の金田アンプの書籍です。 完全に宗教化する前ですので、役に立つ情報もあると思います。 現在の金田アンプは、宗教化してしまいました。 以前は、多少なりとも有益な情報を発信していたので残念です。 1978年5月10日発行。 金田アンプの信仰者には、近づきたくないネ。 スピーカのヴォイスコイルを焼いたりスピーカコードが焼失するような事故を起こして 市場では、金田と金田アンプ信者に目をつけられた部品は枯渇するとさえ言われている迷惑な存在。 近寄るな、しっしっしっw |
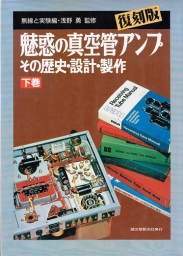 |
浅野勇氏の優良図書のひとつです。 この本に影響を受けた人は、数多くいます。 現在は、電子図書化されています。 1991年3月12日第2刷発行(復刻版)。 |
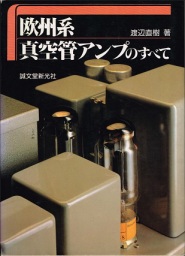 |
欧州で発表された真空管アンプの追試集のようなものです。 過去に発表されたメーカ製アンプの追試ですが、一部にデータの不手際があるようです。 故意に改竄されたのか、単なる誤植なのか、今となっては不明で確かめようがありません。 鵜呑みにせず、疑う目で見ることも必要です。 1989年12月25日発行。 |
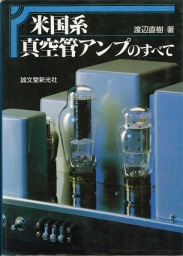 |
米国編です。 同様に一部のデータに不手際があるようで、まったく同じものを製作しても特性が悪くなる可能性が大きいものです。 1988年11月15日発行。 |
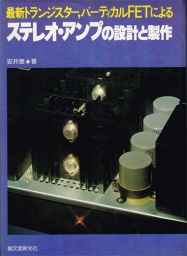 |
安井章氏の唯一の出版本です。 現在も執筆活動を行われていることを考えると意外なことですが、内容は吟味すれば今でも通用するものになっています。 1980年3月30日 第5刷発行。 |
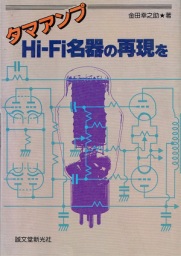 |
もう一人の金田氏です。 内容は、ほぼ同じ回路(同等管に変更したりしていますが、出力管の変更により若干定数を変更しています)で構成されています。 非常に読みやすい本でもあります。 1987年2月27日発行 |
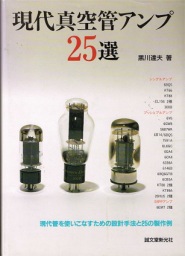 |
黒川達夫氏著の25台に及ぶアンプ製作集です。 手堅く纏め上げたアンプ、定電圧源を構成したアンプ、更にどこかの宗教家の言う「全段差動」(???)など非常に盛り沢山な内容です。 この著作者の場合、シャシ内部にぎっしりと詰め込む傾向があります。 1998年3月15日発行 |
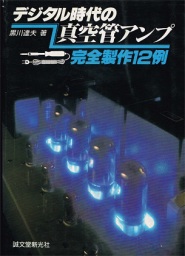 |
上記同様、黒川達夫氏著の12台のアンプの製作集です。 名古屋市中区大須にあるアメ横ビル内にない店舗を、アメ横ビル内にあると誤記したために大顰蹙を買った著作でもあります。 カソード抵抗器の変えてCRD(定電流ダイオード)を採用したのも、これが最初と思われます。 もちろん、完全差動です(^◇^)(あー、馬鹿馬鹿しい) 真空管を使用した回路に、CRDやツェナーダイオード(5.6V以外)を使用することには大いに疑問があります。 (理由はそれぞれで考えてね。)あまりに馬鹿馬鹿しいので、金田DCアンプや完全差動アンプ厨には付き合っていられません。 1989年1月25日発行 |
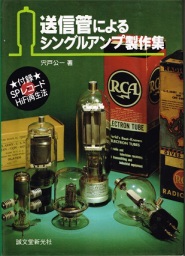 |
そこには「禁断の果実」のようなものが存在します。 1度でもその音を聞いた人は、真空管の代名詞的表現の「柔らかい」音とは無縁であると気が付きます。 しかし、あくまでも「禁断の果実」です。 プレート電圧に1000V以上がかかる作例が殆どで、初心者は絶対に触れてはいけません。 脅しではなく、少なからずこのようなアンプの製作により命を落としている方が存在することを忘れてはいけません。 1999年3月10日第3刷発行 |
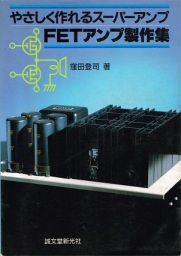 |
半導体アンプの製作集です。 1988年1月12日発行 この書籍の著作者は、アインシュタインの相対性理論を完全否定した「トンデモ」ですから。 そのあたりしっかり認識しておくように。 御多分に漏れず、後期は宗教家に。 |
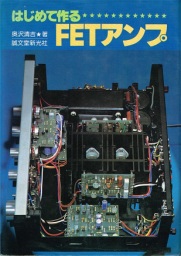 |
極めて良識的な書籍であり、製作例です。 1978年5月15日発行 無線と実験あたりでは、この手の回路は「初歩のラジオ」レベルとして相手にされません。 でも、その初歩のラジオレベルに達していない人が狂祖になっているんだけどねー。 |
 |
マニュアルとありますが、全編にわたり著名な真空管のデータ集となっています。 1992年5月10日 第6版発行 |
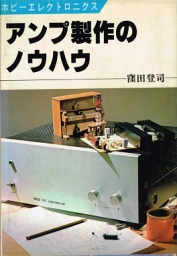 |
主に半導体アンプ製作におけるノウハウを簡潔に述べたものです。 1979年1月20日発行 この頃はまともでした。 大いに役立つ内容です。 |
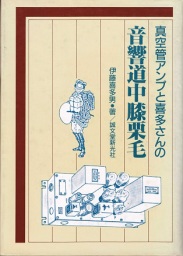 |
読み物としても十分に読み応えのある、優れた著作です。 伊藤氏は、その絶筆に至る最後の瞬間までペンを握っていたと言われています。 下手な小説家など及びもしない表現力は、誠に素晴らしい。 書中に出てくるイラストも筆者自身によるものです。 作例集としてではなく、ドキュメントとして読むに値する「書物」です。 1987年12月20日発行 |
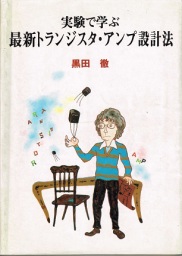 |
勉強しなくちゃと思わせる内容です。 1987年2月15日再版 |
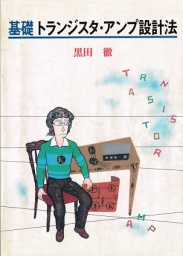 |
過去に遡りながら、最新のアンプ回路を解説していくという手法を見せています。 分かりやすく書かれています。 ラジオ技術連載をまとめたものです。 1989年2月28日初版発行 |
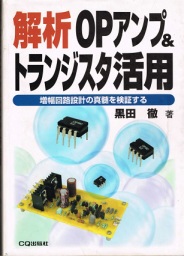 |
「はじめてのトランジスタ回路設計」の続編です。 オペアンプについて詳しく解析しています。 2002年9月15日初版発行。 |
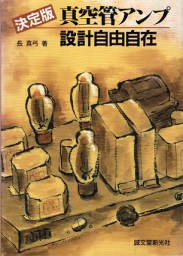 |
真空管アンプの設計技法について詳しく解説しています。 入門書ではありませんが、分かりやすい書籍です。 19990年9月14日発行 |
 |
「アンプ製作のノウハウ」の続編と称しています。 トラブルシュートなどの方法など症状別に書いてあり、役に立ちます。 1995年2月25日発行 ただし、後半は宗教色が強いですから気をつけましょう。 |
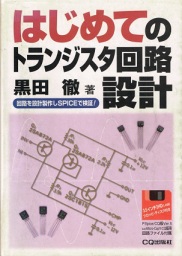 |
実験で学ぶ最新トランジスタアンプ設計法」の続編にあたるもので、ラジオ技術掲載の連載に大幅な加筆を行ったものです。 1999年5月1日初版発行 黒田氏の書籍は宗教色が薄いので、それを好む「スキモノ」には面白くないでしょうが、まともです。 |
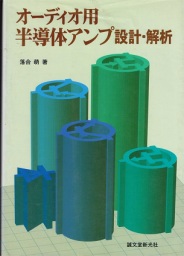 |
章節を細かく区切り、分かりやすさを追求しています。 1998年8月3日発行 ほらほら、大好きなDCアンプや差動アンプについて解説していますよ。 読まなくちゃ。 狂祖様の御神託をそのまま受け取るから考えることは必要ないのかなw |
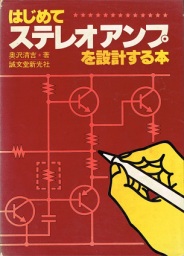 |
当たり前なことを良識的に述べています。 非常に参考になる書籍です。 1981年8月29日第2版発行 |
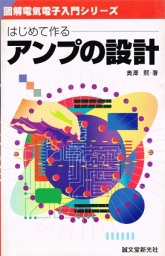 |
「はじめてステレオアンプを設計する本」を抜粋加筆修正したものです。 1996年9月10日発行 |
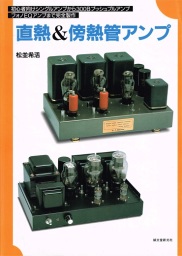 |
無線と実験にて発表された松並氏の製作例集です。 使用真空管も多岐に渡り、初心者でも作りやすいように配慮されています。 2002年8月8日発行 |
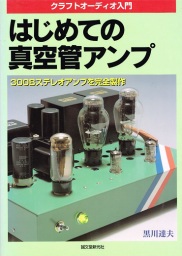 |
300Bステレオアンプを題材にした、初心者向け解説書です。 他の製作集と違い、1冊を1機の製作に充てています。 パーツの入手方法から解説してありますから、まったくの初心者に向けた書籍でしょう。 1999年11月11日発行 |
 |
これも初心者向け解説書です。 こちらは6L6GCを使用したアンプを、同じくパーツの入手方法から解説しています。 巻末には、ほかの真空管を使用したアンプの回路図のみ掲載していますが、この書籍が必要な方に理解できるか大いに疑問です。 1995年8月25日発行 |
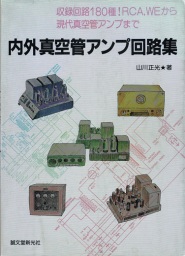 |
1993年12月20日発行 間違いが多すぎます。 あてにしてはいけません。 インターネットなどで回路図を検索し確認しながら使用するのが、その使用方法となります。 |
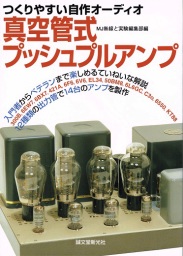 |
無線と実験に掲載されたプッシュプルアンプに焦点を当てた書籍です。 メジャーな真空管が使われていますから、追試するのにも良い題材となり得ます。 2007年9月25日発行 |
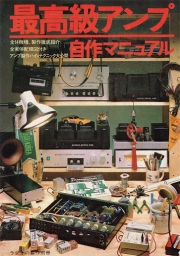 |
全編非常に丁寧な作りのアンプで、配線技法は非常に参考になります。 1979年4月30日発行 |
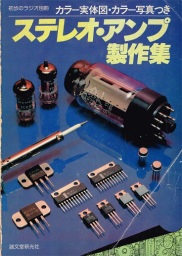 |
初歩のラジオに掲載されたアンプの製作集です。 現在でも使用に耐えうる製作ばかりですが、一部リニアICを使用しているものがあり、これらは製作できないと思われます。 1981年2月10日発行 |
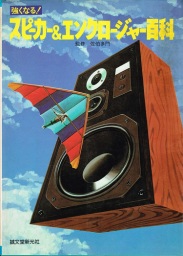 |
スピーカシステムをまとめるための技法などが詳細に記載されています。 1982年12月17日新装2刷 |
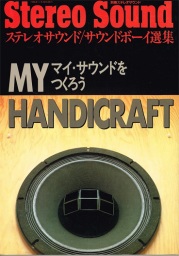 |
スピーカからアンプまで、製作を記述しています。 特にアンプの章は、伊藤喜多男氏の詳細な解説があり、非常に参考になります。 1996年11月30日発行 |
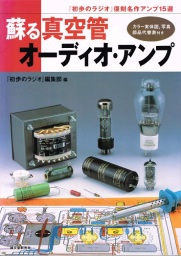 |
「ステレオアンプ製作集」と「ステレオ・アンプ実体図集」から真空管アンプを抜粋したものです。 2007年7月31日発行 |
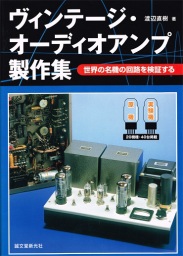 |
ヴィンテージアンプの原器と原器を基にした試作機とを掲載した製作集です。 これはこれで価値はあると思いますが・・・ 2005年6月28日発行 |
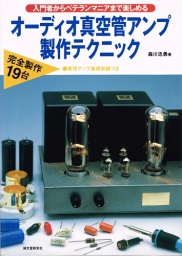 |
人間性はともかく、 無線と実験に掲載された製作記事をまとめたもので、丁寧に書かれています。 資料性もあります。 2004年8月3日発行 |
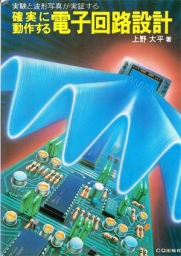 |
ここで例題として使用されているICの多くは現行商品です。 それぞれの回路での注意すべき点も述べられていて役に立つことも多いでしょう。 1988年8月10日第10版発行 |
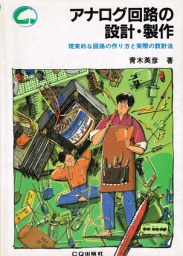 |
エレクトロニクスの製作集です。 1990年8月10日第2版発行 |
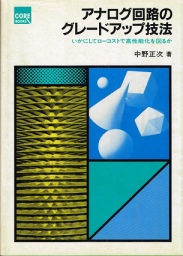 |
1989年8月1日初版発行 |
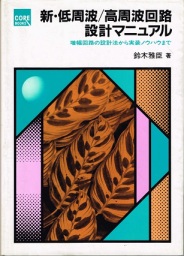 |
1997年7月1日第11版発行 |
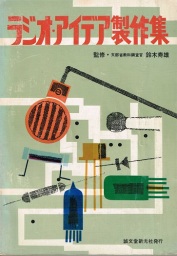 |
時代的に真空管が主体になりますが実体配線図もあり、初心者に親切な内容です。 1972年9月25日第3版発行 |
 |
ラジオの技術を通してトランジスタ回路を設計するという趣旨の入門書です。 1971年8月20日第8版発行 |
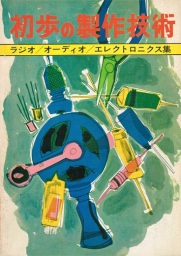 |
数多くの製作例を通じて製作技術を磨きます。 1972年5月15日第7版発行 |
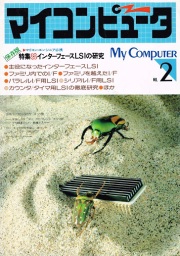 |
1985年2月1日第9版発行 |
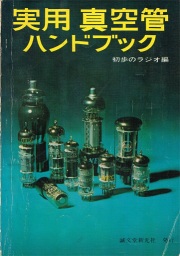 |
一般に入手しやすい(当時)真空管の資料集です。 現在ならば「データベース」と言えます。 1971年8月30日第7版発行 |
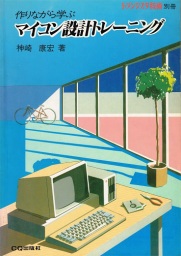 |
1983年5月20日初版発行 |
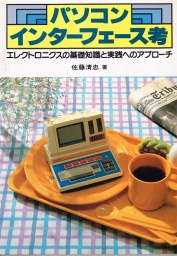 |
1985年7月1日第3版発行 |
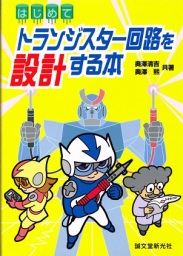 |
2005年8月10日第3版発行 |
 |
OPアンプ回路の設計の続編です。 1979年12月15日第2刷発行 |
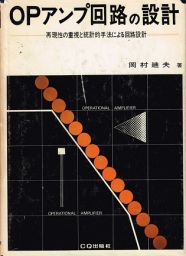 |
1979年8月1日第13版発行 |
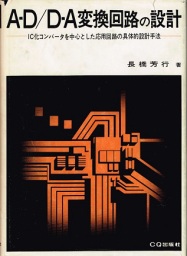 |
1983年9月10日第5版発行 |
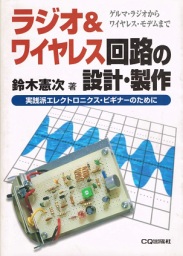 |
2000年3月1日第2版発行 |
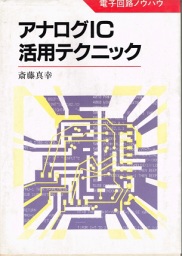 |
1987年11月20日第1刷発行 |
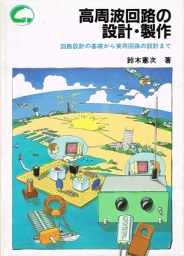 |
1997年8月20日第6刷発行 |
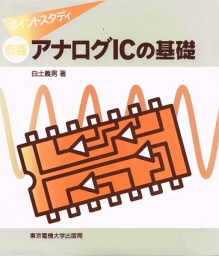 |
1994年5月20日第2版第2刷発行 |
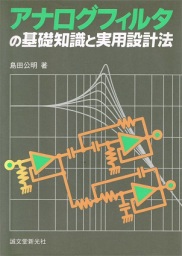 |
1993年7月25日発行 誠文堂新光社にしてはまともな本・・・ |
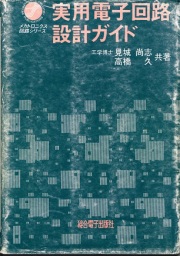 |
1997年3月12日第14版発行 |
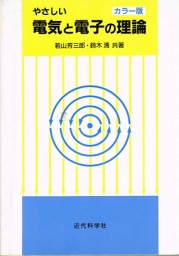 |
1999年6月10日初版第8刷発行 |
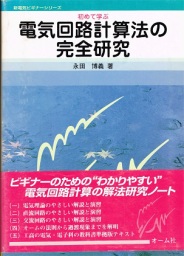 |
1998年1月20日第1版第1刷発行 |
 |
1999年12月20日初版第15刷発行 |
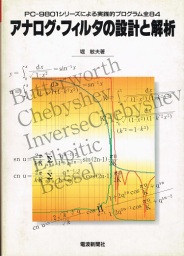 |
1989年10月20日第1版第1刷発行 |
 |
「1」とありますが、「2」はありません。 1989年7月31日初版発行 |
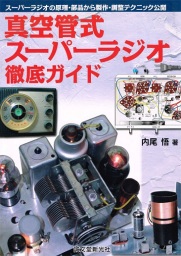 |
真空管ラジオの作り方です。 2008年11月28日発行 |
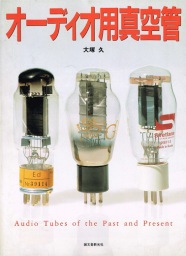 |
真空管の写真集です。 それだけ。 1996年6月11日初版第1刷発行 |
 |
1999年4月20日発行 |
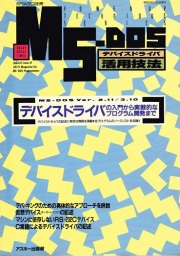 |
1988年3月31日発行 |
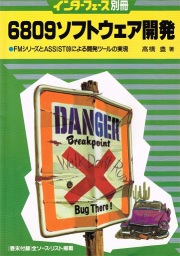 |
1984年11月15日初版発行 |
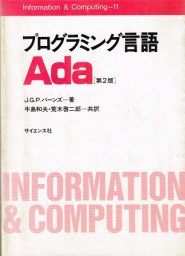 |
プログラミング言語Adaの教科書です。 1987年6月10日初版発行 |
 |
プログラミング言語Adaの入門書です。 Adaは、中間言語「DIANA」を実現し、プログラムコードを記載するエディタやデバッガも包括する統合環境を目指していました。 本書では、そこまでは言及せず、プログラム言語Adaの入門書として徹しています。 1986年11月21日 第1刷発行 |
 |
1991年2月10日初版発行 |
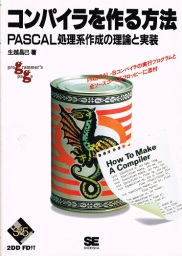 |
1993年11月30日初版第1刷発行 |
 |
C言語の「教科書」です。 副題としてUNIX流プログラム書法と作法とあります。 内容は時としてPascalとの比較を含めながら、UNIXを構築するためのアセンブリ言語の代替としての高級言語を解説しています。 1988年6月10日初版117刷発行 |
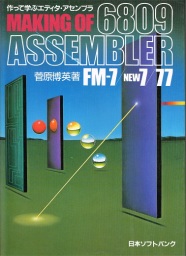 |
1985年12月18日初版発行 |
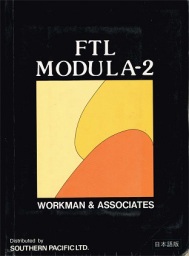 |
マニュアルです。 |
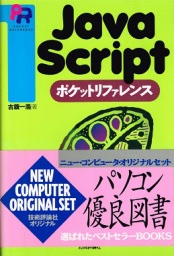 |
1998年7月5日初版第1刷発行 |
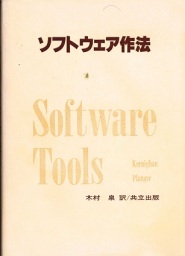 |
1987年9月20日初版第25刷発行 |
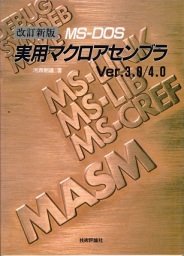 |
1987年7月5日改訂新版第1刷発行 |
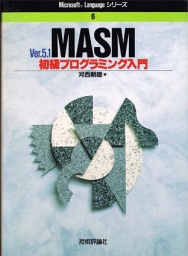 |
1991年10月15日初版第1刷発行 |
 |
ウィルト氏によるプログラム言語Pascalの教科書です。 教科書ではありますが、入門書ではなく、言語仕様書に近い形態です。 しかし、初心者にも非常に分かりやすくまとめてあります。 あくまでも教育用途として、現在でも有用性を強く感じえます。 1985年3月20日 初版第8刷発行 |
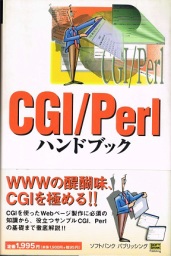 |
1999年9月27日初版発行 |
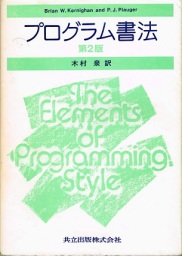 |
1988年3月5日第2版第24刷発行 |
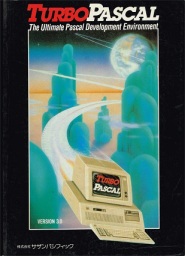 |
マニュアルです |
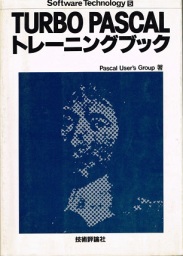 |
1986年7月1日初版第3刷発行 |
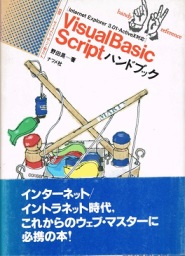 |
書評のしようがありません。 1997年4月30日発行 |
 |
Modula-2による実践的なプログラム記述の方法を述べたものです。 1992年2月1日初版第4刷発行 |
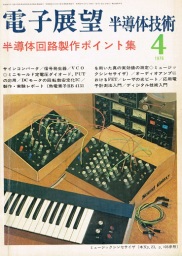 |
定期刊行物であり第3種郵便物認可を受けた雑誌、電子展望です。 1976年頃より1980年代まで、定期的にシンセサイザの製作レポートが掲載されていました。 これに影響を受けた人も数多くいます。 |
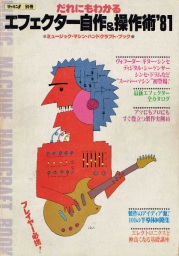 |
エフェクタ製作の書籍ですが、巻末にシンセサイザの回路が掲載されています。 これを見て製作された方も多いと聞いています。 1981年5月1日発行 |
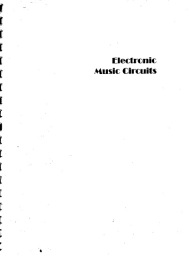 |
Barry Klein氏によるElectronic Music Circuitsです。 アナログシンセサイザの各回路を詳細に解説しています。 |
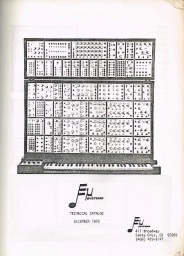 |
E-muモジュラシステムのテクニカルマニュアルです。 当時、5,000円程度で入手したと記憶しています。 |
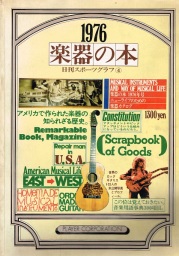 |
ギターやなどを中心にした本ですが、僅かに数ページ、シンセサイザが取り上げられています。 アープのオデッセイなどは、固定為替($1=¥360)の時代で60万円と記載されています。 1976年6月30日発行 |
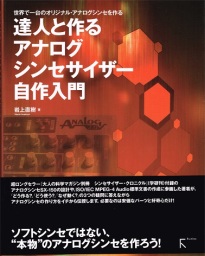 |
30年ぶりに刊行された自作シンセサイザの書籍です。 非常に分かりやすく丁寧に書かれています。 VCOやVCFなどは、やはりMOOGを意識して書かれています。 2011年2月25日発行 |
 |
MOOGとBuchlaのシステムを再現したシステムシンセサイザの製作です。 特に921や904、902、911などは、ほぼそのまま再現しています。 1979年10月30日第1版第1刷発行 |
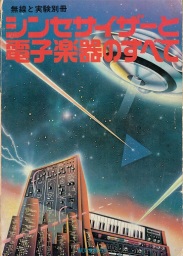 |
歴史から実用回路まで、幅広く纏めてある書籍です。 ただし、所収の製作記事は、電子展望誌掲載時の誤植もそのままですので、注意が必要です。 1980年5月20日発行 |
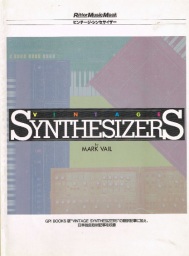 |
「VINTAGE SYNTHESIZER」の邦訳版です。 が、原書に対して忠実に和訳したものではなく、随所に加筆が見られます。 原書には当時のシンセサイザの価格表なども掲載されていましたが、何か都合が悪かったのか、本書では割愛されました。 また、原書では触れられていない日本製シンセも触れられていますが、それに伴い写真などの差し替えも多く、残念な内容です。 1995年4月1日発行 |
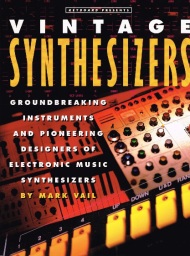 |
主なヴィンテージ・シンセの当時の価格なども掲載されています。 邦訳版に対して、資料性が高いと思います。 1994年頃発行 |
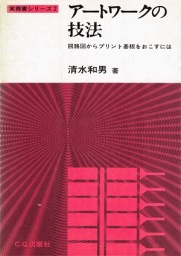 |
この頃のトランジスタ技術関連書籍はまともだった・・・ 1978年2月1日 第8版発行 |
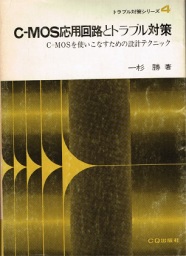 |
C-MOSゲートの応用回路について述べられています。 1979年2月1日 第3版発行 |
 |
一言では言ってはいけない部分もありますが、アースというものに対して考えさせる内容になっています。 低周波回路には一点アースが良いと言われたら、何がなんでもそれを通そうとするような人が読む本ではありません。 1999年4月30日初版第10刷発行 |