愛知教育大学附属名古屋中学校第50回教育研究発表会 講演会
平成19年10月5日
演題「学力と評価の新しい地平」
京都大学大学院教育学研究科教授 田中耕治
文責 土 井
京都大学で教育方法学講座に所属して、教育方法学という勉強をしている。その中でも、学力と評価の問題を中心に研究をしている。
本日、附属中の研究指導案、授業を見て、日本の教育実践の最前線を切り開いていると思った。そのすばらしい研究発表会にお招きいただき光栄に思う。また、研究発表会を準備された、先生方、関係者のみなさん、ご苦労様でした。

「
学力と評価の新しい地平」このテーマで話す。
附属中のテーマが、「子どもの知を拓く授業の創造」なのでここに焦点を絞って話をしたい。、
レジメが入っているので、見ながら話をしていきたい。
新しい地平の「新しい」とは、ルーブリックという言葉も出てきた。さすがは附属だ。多分初めて聞いた人も多いはずだ。今日はその考え方がどうして出来たかについて話したい。
まず、なぜそういうことが求められるようになったのかを話したい
「知を拓くが」にテーマになり、さらに「思考力を伸ばす」というのがテーマに入ってきた。これは、21世紀に入ってからの情勢を反映している。すなわち、学力問題が社会問題してきた時代を反映している。学力という言葉は、使い古した言葉である。その言葉が、現場の中で使い始められたのは、第二次世界大戦後である。
実はこの言葉は江戸時代からあったが、現場の中で研究として使われたのは第二次大戦後。
「学力」、すなわち、学校でつける力が様々な国民の関心の的になった。戦前は、そういう知識は弱かった。戦後になって、学校ができ、高度経済成長が始まり、学歴社会に入り、学力を国民が求めるようになった。
こうして「学力問題」が浮上した。
戦後の歴史をみると、学力問題じゃ4回くらい問題になった時期がある
1回目 戦後初期 学力問題が起こった。学力が戦前に比べて低下したと言われた。
2回目 1960年代始め。全国学力テストが起こったとき。
3回目 1975年前後。高度経済成長が終わりかけ。子どもたちの中に現れた
4回目 これが今だ。
学力の社会問題化の直接の原因は、二つある。
一つは学力の低下論争。1999年、2月から、2004年ぐらいまで続いた。
『分数ができない大学生』(東洋経済新報社)は、京都大学の西村和雄先生たち、経済学の先生が書いた。これが大評判になた。大学生だけでなく、高校生も中学生、小学生から基礎学力が弱くなってきているのではないかといわれ、それ以降、ドリル学習が盛んになった。今も多い。
基礎学力がひどくなったと問題になった今回は、理由がもう一つある。「国際調査」だ。
一番有名なのは、IPAの調査が有名。1960年代の中ごろからやっており、現在5~6回目になる。
それ以上に、PISA(OECD生徒の学習到達度調査)が大きな話題をさらった。
高校の1年生の全員に行った調査で、日本の義務教育、特に中学校の成果が試された調査。だから、中学校に勤める皆さんは注目をされていると思う。
では、なぜ有名になったのか?これは、いわゆる、学習指導要領でどれだけなったかという調査ではない。
高校1年生の生徒が、義務教育で学んだことを、実際に社会的自立のためにどれだけ活用し応用することができるだろうかというのを調査問題としている。
数学も、読解力の問題が話題になった。どちらかというと、国語の読解力と違って、欧米型のテキストを批判的に読むように試された。
日本の子どもたちは芳しくなかった。しかし、ここは注意した方がよい。PISA型学力は低下したのではなく、教えていなかったということ。教えればできるようになる。学習指導要領になかったのである。
欧米では、自立を目指す力、リテラシーをどう考えるかが国際調査では大事になる。一方、日本では、漢字は書けるのか、計算はできるのかにこだわっている。
もう一つは、発展的な学力としてのリテラシーの両方に関心が寄せられた。一つの現れが、4月の全国学習状況調査。AB問題が出た。B問題は活用問題。国語はPISA型の考え方がかなり入っている。この問題を見て、教える側の方が驚いた。PISAテストの影響が、こんな形で表れた。
《解 説》
講演の中では触れられなかったが、レジメには次のように書かれている
学力調査分析の四つの視点-「学力の水準」、「学力の格差」、「学力の質と構造」、「学習への意欲」
|
同時に、今ちょうど学習指導要領の改訂作業が急がれている。
今回の特徴をまとめると、「新しい学力観」から、「PISA型学力観」への転換をしたことだ。この10月末になると、ほぼ中間まとめが出る。それが、実質はほぼ最終まとめになる。
文科省のHP見ると、検討素案が出ている。
「知識基盤社会」の中で、「生きる力」としての「学力」をどうつけるのか?それが「確かな学力」である。
それでは学力とはなんだ?
当初は「習得、活用、探究」だった。最近は「習得、活用、学習意欲」で、探究に換わり意欲になった。
探究はどうなったのか?これは大きな影響を与える。たとえば、「総合的な学習の時間」はどうなるか?
「探究」から「意欲」。微妙に変化した言葉だ。学習指導要領についてはこんな情勢だ。指導要領の中でも、習得や活用が言われる。
今日の話は3つある。
一つ目「現代の子どもたちに求められる学力像をどう考えるのか」
二つ目「学力像が実際に子どもたちにどの程度身についたかをどうとらえるか、学力と評価の 問題」この評価の問題が、研究協議会でも議論されたと思う。
三つ目「学校の取り組みの中で、授業の研究をどう進めるか」
1 現代の子どもたちに求められる学力の姿は何か
私は、「リテラシー」としての学力という言葉を使って説明したい。もともとは、「読み書き能力」という意味だ。識字能力ともいう。
これが1980年代になると、もう少し拡大する。「コミュニケーション能力」にまで広がる。コンピュータリテラシー、メディアリテラシーなど、広範囲に使われるれるようになった。
そうなると、今度は、リテラシーの中身を考えてみたい。最近の規定をいうと、こう言い換えられる。
「文化を読み解き、再構成する能力」
前に、「社会的自立に向けて」とつけるともっとよくわかる。「社会的自立に向けて、文化を読み解き、再構成する能力」
私は、この規定は、日本の先生たちが初めて出会ったわけでなく、以前から、学力を生きて働くといっていた時代からあった考え方だ。その現代版と考えていただきたい。
その規定は、2つの意味が込められている。
特に、レリバンス(適切性)の回復。
これは、子どもたちに「勉強しているということは、生きていくためにどうして必要なんだ?どういう意味があるんだ?」という問いかけをするのは重要だということ。これをレリバンスの問題といっている。 ※ レリバンスは、「有意性」、「関連性」とも訳す。
少し前は、「何が何でも勉強!」といっていたが、今はこれだけではだめ。なぜ、エネルギーの転換を学ぶのか?なぜ一次関数を学ぶのか?など、「なぜ、○○を学ぶのか?」について納得させるのがレリバンスだ。
そしてもう一つは、リテラシーということは、「機能」と「批判」であるということ。
機能は、学ぶことによってきちっと適応できる。
もう一つ。今の社会にしっかり生きていける力は必要だが、今度は適応しながらも、もう一歩前に進んでほしい。批判的に今の社会を見て、新しい社会をつくってほしい。PISA型学力観は、歴史と批判を重視している
有元秀文先生は、「トロッコ」「ごんぎつね」を味わうとき、感動して「よい作品だ」というだけではだめだといっている。
PISA型では、「ごんぎつね」はよい作品なのか?と、突き放して批判的に考える。もちろんしっかりと読んだ上で。構造的に読んで、文学作品としての完成度はどうなのかを読み取る。
《解 説》
これは、おそらく有元秀文先生(教育課程研究センター基礎研究部 総括研究官)の次の論文を指している。
「国際的な読解力を育てるためのPISA型問題開発の理論と方法 」
http://www.nier.go.jp/arimoto/PISA/PISAThesis/PISAtheorymethod.html ←URLをコピーし て貼り付けて見てください。
このほか、有元先生のHPからは、これまでの国語の枠にとらわれない論文や実践が多く紹介されている。 http://www.nier.go.jp/arimoto/home.html
|
これは、ユネスコの「ペルセポリス宣言」(1975年)で規定している。
《解 説》
ペルセポリス宣言(識字のための国際シンポジウムでの宣言)ユネスコ
識字を、「単に読み・書き・計算の修得能力にとどまらず、人間の解放とその全面発達に貢献するもの」と定義。
|
こういうリテラシーを実践の中で実現しなければならない。
その時に、3つの接近の仕方がある。ここでは「相」(フェイズ)と書いた。これらが順番ではなく、同時併用的に実践が行われる。
1 「本」を読むこと。これは習得に近い。
2 「本」で世界を読むこと。活用である。
3 自分の「本」を創ること。探究と言えよう。
こういってみた。「本」は、広く「文化」という意味でとらえてほしい。「本」は象徴的に言い表した。
このように、3つのフェイズがある。
「本」を読むということは、文化を身に付けていくということ。
最近ドリル学習がはやった。習得は知識を暗記させるという誤解があった。それは違う。
新しい知識を身につけるときに、自分たちが生活で用いている知識と、先生たちが教えてくれた知識、いわゆる文化の知識との間で葛藤が起こる。そうして組み替えた知識が「知識」になる。
《解 説》
今ひとつわかりにくいが、別の会では次のように話された。
本物の学力とはイコール「生きて働く学力」すなわち生きる力なのです。それは「生活知」と「科学知」を相互作用させることです。生活知とは生活の中で自然と得る知識、例えばふと目を下にやるとアリの足は6本であった。これは生活知です。そして科学知とは科学によって解明されている知識、例えばアリは昆虫であるから足は6本あるということです。
|
素朴概念(ナイーブコンセプト)とは、理科教育の世界から生まれた言葉だ。最近では、すべての教科でいわれるようになってきた、それはなにか?大人から見ると間違っているが、子どもから見ると納得している考え方のこと。
素朴概念 naive conception.
学校などで系統的な科学教育を受けなくても、人は日常の経験から"自分なりの"自然現象に関する理解を作り上げている。こうして作られ、利用され、保持されている概念を素朴概念という。
|
これを最初に定義したのが、ニュージーランドのクライバールたち。彼らがいうには、例えば、乾電池に豆電球をつける。そのときに、電流はどう流れるかと聞くと、子どもたちは電流は衝突をしていると答える。
外国でも同じ反応だ。科学的には確かに間違いだろう。そうすると、先生は、「まだ学校で勉強していないから間違えるのかな。」と思うかもしれないが、子どもは、前に金属と石がぶつかって光が出たことを知っている。それを踏まえて、子どもの論理で答えている。
今日の理科の授業。電気エネルギーが熱エネルギーに変わるという授業だったが、みんなそれぞれの論理があった。
それは学習経験を総動員して、納得いく答えを出そうとした。それをみると、今まで「つまずき」といっていた言葉に注目したい。「つまずき」は「嫌な言葉」と考えていたが、子どもたちの論理があるから、すなわち考えているということだ。「つまずき」観の転換である。
じゃ、電流というのは何?と口でいう。3日後にテストをやるとだいたいできる。先生が言ったことを聞いていたから。しかし、1年後にテストをやると間違えている。心から納得していないから。本当に認識の点ができていない。
「つまずき」観を転換できるように指導がいる
詰め込み教育が悪いというが、それは実際に詰め込めないからだ。自分の考え方があって、詰め込もうとしても詰め込めないのである。そういうことを意味している。
本を読むは、授業をダイナミックに展開しろということだ。
「本」で世界を読む
これは、活用するということ。応用していくことでもある。
今日の数学の授業で、正比例・反比例を見た。基礎的な理解の仕方を学んだ。問題は、それを使って、総合的な問題ができるかどうかである。活用することによって、自分の勉強したことがわかっているかどうか確かめている。
勉強していることが、自分にどのように関係しているか、生活にどう活用していく。今それが重視されている。
活用場面では、「生活の場面を使いなさい。」「本物の生活を使いなさい。」と言っている。実際に生活をしている状況の中で勉強したことが使えるかどうかが重要だからである。
自分の「本」をつくること
探究ということ。これは、総合的な学習が追究しようとしたことだ。各教科の探究は、考え方を身につけさせようとするものだが、「総合」はこれは違う。考え方を自分のものにしようということだ。
今日もあった。勉強したことをどう表現するか。実はあれは評価の場面でもある。何を勉強したのかを問うている。ただ、最近、「総合」は分が悪くなっている。
「総合」には、もともと賛否両論あった。
私は、大学で講義とゼミがある。このゼミは、大学だけでなく、高校や中学校、小学校でもやってほしい。
探究の力は、自分で自分の「本」をつくっていくという意味で大切だ。今までは、習得型と探究型が対立していた。これは、戦後の学力論争の重大なテーマだった。
今では、どちらも必要だとなってきた。
まだ、活用ばかりがクルーズアップされているが、習得がなければ活用はできない。活用の一人歩きは心配。
これは、3つは、段階的なものではなく、同時並行に進む。リテラシーは、3つのフェイズでとらえる。
2 学力と評価の問題
教育評価の歴史を振り返ると、教育評価は第二次大戦後に使われるようになった言葉で、当時は相対評価という意味だった。成績といえば5段階。評価は順番をつけることで、こういう時代が長く続いた。教育実践上では、あまり意味がなかった。
2000年、目標に準拠する評価が始まった。子どもたちにできたかどうかをみるのではなく、学習の活動や教え方をどう改善していくのか、そのためには、目標準拠の評価ではなくてはならない。
もしついていないときは、どうする?そこが、こう定義した大きな意味だ。注意するのは、目標、学力のレベルである。
基礎的な学力を、低い目標で考えるなら、それほど難しくはない。知識の量を測るのは比較的やりやすい。
難しいのは、判断力、思考力という学力の発展的な部分だ。活用、探究などを目標にしたときにはどうなるのか。大きな課題になった。
目標を質の高いものに拡大して、学力を考えるようになった。それが新しい地平。
低いレベルは ドメイン評価、高いレベルは スタンダード評価
目標のレベルが高くなった。
ここでは、3つくらいのことを考えなければならない。
学力の質が高くなってきたときの目標準拠評価で考えるべきこと。
① 妥当性、カリキュラムの適合性
カリキュラム領域と評価のレベルが適合しているか。
日本の教師は授業がうまい。しかし、テストになると、客観テストだけで終わってしまう。
子どもには調べろとか発表しろというが、テストでは鎌倉幕府は何年から?目標と評価が適合していない。それは違う。ちゃんとカリキュラムと評価を適合させないといけない。客観テストは○×でもいい。
活用 パフォーマンス評価
探究 ポートフォリオ評価
評価法を変えよう
② 比較可能性(信頼性)
「小論文書かせたけど、どういう基準で評価するんだ?」
先生によってまったく違う評価になる。主観的になる。これでは困る。信頼性を獲得しなければならない。いつだれがやっても評価が変わらないようにすること、それが比較可能性だ。
そのためにルーブリックをつくる。モデレーション;相談する。
ルーブリックについては次のサイトが参考になる。
[PDF] 「評価規準」と「評価基準」http://www.shinko-keirin.co.jp/csken/pdf/51_08.pdf
見える「評価」で授業が変わる! ~ルーブリックで授業作り~
http://www.justsystems.com/jp/school/academy/hint/rubric/index.html
|
妥当性と信頼性はこれまではアンバランスだった。
妥当性を考えると信頼性が落ちてくる。信頼性を尊重すると、客観テストばかりになり妥当性が低くなる。それを両方追究していこうというものだ。
今回の学力テストのB問題は、妥当性を追究した。
採点をどうするか?学校単位なら採点者が相談すればよいが、全国だとそうは行かない。混乱しているだろう。
妥当性と信頼性の関係。全国的なテストは信頼性を確保してきたので客観的だったが、今回は超えた。
③ 結果妥当性
評価の方法が現場にどういう影響を与えるか。これを結果妥当性という。
「B問題を来年もやるなら、日頃のテストでこういう問題を設けるようにしよう。」という議論がでてくる。この考え方を否定するわけではないが、テストの問題に特化した形で訓練しても、リテラシーにはならない。それに応用力がつくかどうかは別問題。実践をやらなければならない。
今日の授業は、活用に迫っていた。
「真正の評価」と「パフォーマンス評価」「ポートフォリオ評価」
「真正の評価」とは、本物という意味。実際の生活の場面で評価を行うということ
それが、「パフォーマンス評価」と「ポートフォリオ評価」
ある重要な、ここは活用させて子どもの力を伸ばしたいというものは、実際に演技をさせて、複数の専門家が一定の評価指標に従って評価することが大切。
例えばフィギアスケート。あれは評定だが、実際に評価しなければならない。見えにくいものを、実際に表現させて、見える形にして評価する。そのときに、ルーブリックが使われる。
附属中学校のルーブリックを見たが、うまくできている。英語のところがわかりやすくつくってある。
歴史新聞づくりがはやっている。子どもは喜んでやる。歴史学習のよい評価方法だ。でも、出てきたものをどう評価するかは先生の勘に頼っている。基準づくりが必要だ。
30枚の新聞に対して、まず3段階で評価する。そして、共通に3がついているものについて、その理由を話し合う。
「よく調べてある。うまくレイアウトしている。自分の言葉で表現している。」など。
2はどうか。1はどうか。
ルーブリックは、先生の経験を表に出して、きちっと文章化する。作品も残しておく。3のものはこれ、2のものはこれなど。
さらに、子どもたちにオープンにしていく。評価基準を子どもたちにオープンにしていく。
ポートフォリオは、私が日本に紹介した一人なので、最近、ワクチンの名前かといわれなくなった。やっと市民権を得てきた。
ビデオをみてほしい。
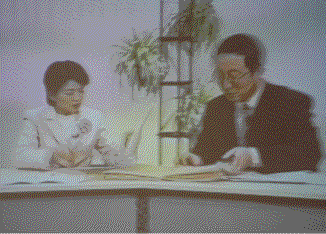 相模原市立谷口中学校での実践
相模原市立谷口中学校での実践
(ビデオ内容略)
日本の実践の中にある、大村はま先生の「学習記録」、東井義雄先生の「学習帳」では、すでに近いものが実践されていた。
それを意味付け直すことをやっている。
収集されるのは完成品だけでなく、そのプロセスで生み出された、先生や親たちからの、また、子どもたちからの評価記録も含み、文字による記録類だけでなく、図示や描画など、様々な媒体が利用される。そして、検討会を重視する。
3 学力を育てる学校の取り組み-学校再生の鍵としての「授業研究」
最後に、日本の教師たちの力量が世界的なレベルで注目をされるようになってきた。
アメリカのスティグラーは日本の学校に入って研究している。かれは、日本の教師の優れた文化は「jyugyou kenkyuu」だと日本語で言った
『日本の算数・数学教育に学べ―米国が注目するjugyou kenkyuu』教育出版(2002年)J.W.スティグラー・J.ヒーバート 著・湊三郎訳
特徴は、3つ
1 授業研究を日常的にやっている。
2 個人だけでなく、協同でやっている
3 学者の下請けでやっているのではなく、自分たちでやっている。
我々が忘れかけたものを世界的レベルで国際評価が始まっている。授業中心でいっしょに切り開いていければいい。今回のような公開研究会がきっかけになるのではないか
これで終わる。
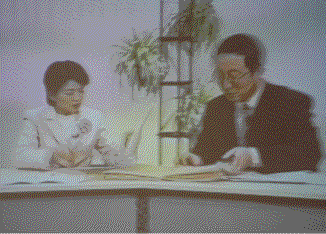 相模原市立谷口中学校での実践
相模原市立谷口中学校での実践