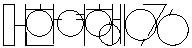
1972年と1976年に韓国へ行っている。1976年には写真を撮る代わりに、毎日宿で旅行の記録を付けた。それが残っているので、韓国へおいでになろうという方には興味があるかも知れない。例によって恥を書いて見ようと思う。文章は当時のままである。コヤマ君も若かったなあと、自分でも赤面してしまうようなことも書いてあった。
日本人と韓国人の関係も、僕達のような既におじさんという歳になってしまったものと、若者ではだいぶ違うようだ。けれども、現在でも変わらない面もある。
その後たしか1990年には焼肉店を開くという方のお供でソウルに行っている。このときは3日3晩焼肉攻めで閉口した。 注釈欄を作って自分の文章に現代からの注釈を入れてみようと思う。注釈が入ると何だか大作家になったようで気分が良い。
釜山港に帰ったぞ
4年前と同じく通関を済せて、フェリーターミナルを出ると、僕は足早に市内に向かった。釜山には泊まらず、直ぐに慶全線で順天か、あるいはもっと先まで行くつもりなのだが、その前に、この国の空気に慣れること、それにもうひとつは、手持ちの不完全な地図より使いやすいものを手にいれるため、書店を覗いてみることにした。
旅行目的はビザの申請書にも書いたとおり、「観光旅行」である。ただ、観光産業のために明るく光を当てられた所だけを観るのでなく、とりわけ、現在の日本を光源にして造られる明暗のくまの両方を観ることが目的であった。ズックの少しルーズなショルダーバッグひとつで、なるべく目立たないつもりの僕は、いかにも知った道を歩くような顔で市内に向かった。
けれどもフェリーの入港する朝、フェリーターミナルの近くをプロに見付けられずに歩くのはそうたやすいことではない。前回同様、後から僕と並んで歩きだしたそれらしい人が「今夜お泊まりのところはお決まりですか。」と日本語で話しかけてくる。「知ってる方の家に泊めてもらいますから。」ととっさのデタラメを答えると、彼は「これはダメか。」というふうにまた港の方にへ引き返していった。
結局、光復洞の古本屋で高校の教科書用の地図を手にいれた僕は、それをバッグに突っ込んで国際市場のはずれに来ていた。フェリーに乗る前に見た下関の魚市場を思い出し、国際市場を抜けて南港の魚市場を覗いてから駅に行こうと考えた。道の両側には食料品から雑貨に至る製造、卸し、小売りの様々な小店舗がひしめき合っている。その歩道をいかにも当てのない旅行者といった姿で歩いていただろう僕に声を掛けたのが彼、「金英福氏」であった。
僕と並んで歩きだし、たどたどしい日本語で話し掛けてくる彼を見て、僕は先ほどの客引きのおっさんを思いだし、「一体この男は何物だろう。」と思った。こざっぱりはしているが、街頭にあふれる「ヒマな青年」という風体で、彼は「日本の方ですか。」に始まる会話を始めた。けれど同年配でもあり、「電気技術者で、今年にはつてをたよって大阪の大学に留学する「予定」である。」という彼を、僕はうるさい男だとは思いながら、その人物については信用してしまったらしい。
彼は魚市場まで付いてくると、そこの加工場兼売場になっている建物の中を案内してくれた。豊富な魚類、タコ、エビ、イカ、貝類等が次々開かれて行くのを、いささか的外れな彼の説明を聞きながらしばらく見ると、僕は彼をさそって、すぐ近くにあった喫茶店に入った。後日、「それから喫茶店に入ってしばらく話をして・・・。」と言うと、居合わせた人が笑い出したのだが、全くもって街をうろつく「ヒマな青年」「不良」「パーボ」という行動だったのだろう。
で、「どこに行くのですか。」彼に聞かれるまま、「南部の田舎、それに漁村が見たい。」と言うと、「それは危険だから止めたほうがいい、特に海岸では最近スパイが動いているから。」とこればかりは真剣な顔をして言う。それからバッグをひっかき廻してさっき買ったばかりの地図を拡げ、しばらく話をしていると、いきなり「馬山に僕の友達がいるので、今日はそこまで行くことにしたら、僕も一緒に行くことにするよ。」と言う。「なに、その友達には会わなくてはいけなかったのだから、今、電話してみるよ。」とカウンターに行ってなにやら電話をしている。
最初は断ったのだが、結局彼の熱心さに負けて、「馬山を見るのも良いかな。」と一緒に行くことにした。彼は先に立つとこの喫茶店でのコーヒー代、釜山駅までのバス代、駅前で取った食事代から馬山までのキップ代まで払ってくれた。そんなことをしてくれては困ると言ったのだが、「あなたは遠くから来た人であり、こうして歓待するのが僕達のやり方だから。それにいずれ日本に行けば世話になることだってあるかも知れない。」と言われるとそれで納得してしまった。
金英福氏
僕達は古馬山駅で下車すると、市街地を北に向かって歩き、彼の友達の家があるという馬山工業高校近くに着いた。彼は友人の家に行く前に宿に荷物を置いて言った方が良いと言って、近くにあった近くにあった旅人宿(素泊まりの民宿のようなもの。沢山ある。)に僕を案内する。
輸出自由地域のすぐ近くであり、建物は鉄筋コンクリートの2階建で「このあたりは最近まで家の無かったところ。」という、新築の家の多い中でも、こざっぱりした造りだった。ちょうど日本の学生下宿の様に、2階に上がると廊下の両側に4帖半よりやや小さな部屋が並んでいる。ここでも金氏は宿代の数千ウォンをさっさと払ってしまっている。僕は彼にとってのその金の重みを測りかね、また親切でしてくれるものという安易な気持ちでそれもそのままにしてしまった。
部屋に荷物を下ろすと、彼は僕の頭を眺め、「友達のところへ行くにしても、あなたの髪、少し長すぎますね、散髪に行ったほうがいい。」と言う。実際、前回来たときには釜山入国後10分と経たないうちに交通整理の警官に呼び止められ、「オイ、そこの若いの、キサマの髪は何だ。」とやられたことがあるので、散髪は僕も望むところであった。荷物、と言っても貴重品はカメラだけなのだが、「部屋においていっても大丈夫かな。」と聞くと、かれは「大丈夫でしょう。鍵もちゃんとしているし。」と言うので、荷物をそのままに、ポケットの小銭とパスポートだけをもって宿を出た。
近所にあった理髪店は生憎定休日らしく閉まっている。聞いてもらうと少し遠くの店なら開いているというので、仕方なくバスに乗って出かけることにした。しばらく街と反対側に走り、郊外の田園地帯と言ったところでバスを降りる。見れば有難いことにバス停の真前に理髪店がある。僕はすっかり安心して、椅子に伸びると髪を切ってもらうことにした。
彼はしばらく理髪店の若者と話をしていたが、そのうち退屈したらしく、「何か食べてくる。」と言って店を出ていった。舗装していない道が、土埃で白くなった硝子戸の向こうに明るく見える。僕の頭を見てびっくりした理髪店の若者が「どういう様にしますか。」と聞いたので、「短く、韓国の若者風に。」と注文したら、大仕事らしく、頭の上では途切れることなくはハサミの音が響いている。金氏はなかなか帰ってこない。ここではぐれては帰り道がわからなくなると思い。また、ある恐れ、そのために釜山からの汽車の中で「君は一体何が欲しいんだ。」と口走りそうになって気まずくなり、それ以来意識的に避けてきた恐れのため、再び心配になってきた。けれどもむやみに人を疑っても悪かろうと、それから小一時間も掛けて散髪をしてもらい、500ウォンを払って店を出た。
金氏の姿は理髪店の近所には見えない。一軒きりある食堂にも、バス停の横の駄菓子屋にも彼は居ない。あとは電気屋と、韓服屋が一軒づつあるだけだ。ここまできて、なるほど、これではっきりしたな。と妙にサバサバした気分になり、理髪店で聞いたとおり、やって来たバスに乗って宿に帰った。庭でせんたくをしていたおかみさんに鍵をもらうと、部屋に入る。荷物はちゃんとある。開けてみるとカメラとレンズだけがきれいに無くなっていた。後は触りもしなかったらしく、よれよれの袋に入れておいた4万ウォンはそっくり残っている。
今にして考えてみれば、彼がシナリオの制作に取り掛かったのは、僕が開いたショルダーバッグの中にカメラとレンズを見付けた釜山南港魚市場の喫茶店であろうし、多分それ以前にこんなことを微かに期待しながら国際市場を歩いていたのかもしれない。
とにかく彼は彼なりの「日本人と付き合う法」を通したわけである。僕は10年前の横浜を思い出して居た。ヴェトナム戦争が終末的様相を示し始める少し前、僕は悪友にさそわれて後日、「戦車を止めろ」で有名になった横浜港の米軍瑞穂埠頭に港湾荷役のアルバイトに行ったことが何度かあった。そこでは、米軍相模原補給廠に運ぶという被弾した兵員輸送車のあちこちに、「干涸びた人間の肉片が貼り付いていて、それを見たやつはもう瑞穂埠頭には行かないといっている。」という学生仲間の伝説だけでなく、沖縄かグアム島あたりで野晒しになっていたらしい木箱にワイヤを掛けて引っ張った途端、崩れた木箱の中から軍用トラックのエンジンが落ちて来て、僕自身命拾いしたことまであった。
それらの全ては日常生活にぴったりと重ねられた巨大な虚構の中の出来事のようで、妙に現実感がなかった。毎日数隻が横浜港を出入港していた米軍の軍用船の中で、僕達は荷役労務の合間に船のキッチンに忍び込み、そこにあるまるでアメリカ風の食料を食い散らかしたり、積荷のトラック、乗用車からアメリカのナンバープレートを剥がし、ゲートの税関職員、カービン銃を持った衛兵の目を盗んで持ち出したりしていた。
あるときなど荷が崩れて船底のゴミの中に散乱した軍服用の米国陸軍のバッジをポケットに詰め込めるだけ詰め込んで盗み出したこともあった。悪友はそれを一個400円也で友人に売り付け、果ては残りを御徒町にあるモデルガン屋に売るのだと言っていた。そこには日本の中に居ながら「豊かなアメリカ」に触れているという興奮があり、「ヴェトナム反戦スト」でバリケード封鎖をした近くの大学の校舎に潜り込んで、そこからバイトにでかけてくる僕達にとって、米軍は「悪いやつ」であり、おまけに金持ちで僕達が少しくらいのものをかっぱらって来ても当然だという意識があった。そんなことを思い出すと、金英福氏の「日本人と付き合う法」にも僕にはしっくり来るものがあった。
彼にとっての日本は、歴史の授業で習った「秀吉倭乱」から「日帝三十六年間」、あるいは朝鮮戦争の生き血を吸って肥った、「日本」であると同時に、日常生活にぴったりと重なって玄海灘越しにテレビで見る「日本」であり、南浦洞のショウウインドーの上段に並べられて照明に浮かび上がる「日本」、もっと巨大な馬山自由貿易地区の工場の向こうに見える「日本」であるのだろう。何年か前に、彼が日本語の勉強を始めようとした時にもそんな日常生活を取り巻く「豊かな日本」の影があったに違いない。彼が「大阪の大学に行って電子工学の勉強をする。下宿ももう決まっていて、大阪府阿倍野区阿倍野筋○○番○○方になるはずだ。」と淀みなく自称したのも、彼にとっては決して根拠のない唐突なものではなく、彼が彼を取り巻く虚構の中で気持ち良く暮らすために造り上げた、彼自身のための虚構なのだろう。
けれどもやがて兵役がやってくる。そして兵役から帰って釜山で暮らすうちに「日本」の姿は彼にとってのリアリティーを増してきたのだろう。一応の日本語をマスターした彼にとって「日本」は、高校時代にカメラ屋のショウウインドーで輝いていた日本製カメラといった「商品」、「もの」としてだけでなく、その背後に見えてくる「関係」としても見えてくる。ショウウインドーの日本製カメラはなぜか彼に手の届く値段ではないし、釜山、あるいは馬山で見かける「日本人」は彼とは違う世界の生物であるかのようだ。そして最後にはあの釜関フェリーが目に浮かぶ。「玄海灘を結ぶ懸け橋」は、彼にとっては日本からの招請状がないと乗れないという、1945年以前と何ら変わらない代物だし、その船に乗って玄海灘を行き来する「担ぎ屋」のおばさん達と、港の出入国管理官とのやり合いは、高校時代の金英福氏であれば見たくないものであったかも知れない。彼にとって「日本」は知るほどに心を許し合える相手ではなくなっていっただろう。
かって、バイトと称して横浜港の米軍瑞穂埠頭に潜り込んでいた僕と金英福氏とを隔てているものの一つはお金であろう。僕にとって米軍の下請荷役業者からせしめた数万円は、親の仕送りで暮らす学生の常としてステレオに化けてしまった。しかし金氏の場合はどうなのだろう。
僕が金氏に貸した(当時の僕達にしてみれば、米軍から物をかっぱらって来るのは大それた「盗み」などではなく、それがなくても困らない相手から、長期、無断で借用するのであった。)カメラは全て中古品で一式12・3万円の物であった。僕にしてみれば1.5ヶ月分の給料である。しかし釜山のカメラ屋を覗いてみれば、同じものが国際市場の電気屋の手伝いをしているという金氏の年収以上の値札を下げているのだ。これでは「金持ちの」「悪いやつ」から「無くても困らないものを」無断で長期借用すべきであるとも言えるではないか。僕はよれよれの袋の4万円を確かめるとパウポートに挟んだ残りの100ドル弱と、ポケットの3千数百ウォンを思いだし、これから10日程の旅行には致命的ではないなと考えた。カメラがなければサインペンと紙がある。「あいつ、うまいことやったな。」とも思った。
とにかく階下に降りると、おかみさんを呼んで、辞書を引き、「派出所」と言ってみた。けれども彼女は日本語を話すわけでもなく、なにかさかんに説明しようとする。僕は交通公社の「6ヶ国語会話帳」をみて(これにはちゃんとそんな言い方まで載っている。)、「カメラを盗られました。」と言ってみる。彼女は別に驚いた様子もなく、さっきから同じことを繰り返している。どうやら「・・・友達・・・。」と言っているらしく聞き取れたので、友達、つまり金英福氏が持っていったのであって、盗難ではないということを言いたいらしい。「その人」「友達」「違う」と単語を並べて数回繰り返すと意味が通じたらしい。驚いたように奥に向かって叫ぶと、おかみさんがもう一人出て来て、一通り話を聞き、びっくりした顔で「・・・日本語・・・。」と言いながら外に走っていった。すぐに近所から「日本語のわかるおばさん」をつれてきてくれ、この人を間にはさんで、既に大体の様子が想像できることを確認した。
僕と金氏が出掛け、30分程すると金氏が一人で帰ってきて、「鍵をくれ。」と言ったとのこと。宿のおかみは当然のこと僕の連れである彼に鍵を渡した。あるいは2人で泊まることになっていたのかも知れないが、そこまでは確かめなかった。金氏は部屋に上がって行くと、カメラを持って出掛けたとのことであった。「警察に届けて探してもらわなくては。」と言うと、「日本語の解かるおばさん」は「どうせ行っても出るはず無いよ。それに警察に行くと後が色々面倒だしね。とにかく、ここの主人が帰ってからにしなさい。」と言うので、その言葉に従うことにした。部屋に戻るとおかみさんが上がって来て、荷物を指差すと、「下に来い。」と言う。で、2階から1階の家族の居間の横の部屋に移ることになった。
しばらく持っていた会話帳と辞書を代わる代わる引いては見せたりするうち、御主人が勤めから帰ってきた。彼は日本語が少し出来る。と言うのは勤め先が自由地域の日系資本の工場で、仕事のために勉強中なのだそうだ。両方の腕に包帯を巻いていて、何か怪我をしているらしい。そう思いながら見るともなく見ていると、話をしながら何食わぬ顔をして包帯を解き始める。手首から肘に掛けてブツリ、ブツリと直径1cm、深さ5mm位の円形に薬品か何かで皮膚と肉が解けてしまったような穴が開いている。「それは困りましたね。出もちょっとカメラは出てこないでしょう。」などと言いながら立ち上がると、ズボンをはき替えてテレビのスイッチを入れる。
画面は高校野球らしい。「釜山商業がね、なかなか強いですよ。」と言う彼は、足もちょうど靴下の上端になるあたりが赤く、病的に腫れている。良く見るとそこにも手よりは小さいけれど、同じような穴がいくつか見える。「手はどうなさったんですか。」と聞くと、「これは仕事ですよ。メッキの薬品の所為でね、仕方ない。」と事もなげに言う。健康を売って暮らしていることを十分承知しているような口ぶりだ。彼にとっての日韓経済協力は健康を金に変えて日系企業に売ることであるらしい。彼が日本語を習っているのもそのための手段の一つだ。おそらく彼の勤めるメッキ会社でも、日本国内の工場ではこうして従業員の健康をむしばむことはしていないだろうし、出来ないであろう。馬山自由貿易地域では人が自分の健康を金に変えるのも自由であるらしい。
「警察に行っても出て来ることはないし、でも、カメラが無いと困りますね。何処かで借りられるとよいが。」と彼は話を続ける。それから立ち上がって大型の日韓辞典を持ってくると、僕の持っていた「6ヶ国語会話帳」「朝鮮語小辞典」を拡げ、おかみさんを交えてしばらく話をする。で、結局「ま、それは皆が揃ってからにしましょう。」ということになった。彼はこの民宿の主人の弟で、ずっとソウルで映画会社の技師をしていたのだが、自動車修理工場をやっている兄が、「家も新しく建てて、民宿をやることにしたし、輸出自由地域が出来て仕事もありそうだから、お前も帰ってきて一緒に住もう。」と言うことになったのだそうだ。
そうこうするうち、ちゃぶ台が用意されて僕も夕食を食べさせてもらうことになった。日本人の目で見ると「つつましい」食卓であろうが、家庭的で、日本の市販の味噌と違い、味噌汁の臭いが何ともおいしかった。食べ終わってお湯を飲んでいると、テレビでは時代物のコメディーをやっている。隣のへやの襖がテレビの見えるように開けられていて、穏やかな顔のおばあさんがお膳を置いてもらってテレビを見ながらゆっくりと食べている。
やがてこの家の主人が帰ってきた。僕と会釈を交わすと、どっかり腰を据えて弟さん、おかみさんの話をしばらく聞いて、いきなり二人を叱りつけた。「お前がその変なのに鍵を渡さなければこんなことにはならなかったのだ。」「だってこの人の連れだって言うから。」「連れもへったくれもあるか。今すぐ警察に電話して、来てもらえ。」とでも言うのであろうか、物凄い権幕である。弟さんが派出所に電話をして「すぐ来てくれ。」と言うのであろう、しばらく話をしている。
韓国人の口論は日本人には歯が立たない。と聞くが、ご主人とおかみさんの言い争いは激しかった。僕は日本人の感覚で、辞書を引き引き、「仕方有りません。」と中に入ろうとするが、二人とも耳を貸さない。警察からは誰も来ない。「一体警察は何をしてるんだ。もう一度電話をしてみろ。いや、俺が掛けてやる。」
さらにしばらく経って、やっと警察官が登場した。後で自己紹介したところによると、「大韓民国馬山警察署巡警」である李○○氏は、金石範さんの小説にでも出てきそうな、自分でもその制服と制帽が窮屈で仕方ないという様子の「おっさん」であった。彼は先ずおもむろに手帳とちびた鉛筆を取り出し、2・3行書き付けてからおかみさんに事情を聞き始める。が、どうせ後で派出所に来させるんだから。というのか、途中でメモを取るのは止めてしまった。
「ふむふむ。」といかにもそれらしく一通りの話を聞き終わると、さっき、この家の御主人がやったのと同じように「それはあんたが鍵を渡したのが悪い。」と決め付けたらしく、これまたさっきと同じようにおかみさんに逆捩じを食らっている。再び韓国風の口論が続いた。それから僕の荷物を型通りに調べると、「・・・金・・・?」と僕に聞くので、よれよれの袋から4万ウォンを出して見せ、元通り荷物の間にしまった。李巡警は「うーむ、金は盗らなかったのか。うーむ、4万ウォンか。こいつは話に聞く「金持ち日本人」でも無いらしい。」と思慮深そうに首を傾げ、「もう荷物はしまってよろしい。」と手を振った。それからおかみさんの御亭主、元映画技師に向かって「あんたも派出所まで来てもらうよ。わしは先に自転車で行っとるから。」と言うふうに話し掛け、制帽を取ってぐいっとかぶると出ていった。こうして僕は日系メッキ工場に勤める元映画技師に連れられて夜道を歩き、馬山市郊外、輸出自由地域に程近い派出所に着いた。