愛知の産業遺産を歩く 25
明治村機械館
The Machinery Hall of the Museum MEIJI-MURA
-鉄道寮新橋工場-
Shimbashi Factory of the Japan National Railways
ISHIDA Shoji
犬山市の郊外にある博物館明治村は、1965(昭和40)年3月に開館、今日では老舗の部類に入る野外博物館です。風光明媚な入鹿池に面し、自然の美しい丘陵地約百万平方メートルの広大な敷地に明治期の建築物を多数移築復元して展示しています。瀟洒な、あるいは華麗な多くの欧風建築物は豊かな緑に囲まれ、四季折々に樹木は装いを変えて訪れる人々の目を楽しませてくれます。
さて、明治村は、教会、県庁舎、病院、ホテル、文豪夏目漱石の住まいなど建築物の博物館ですが、中には産業遺産と呼ぶことのできる展示物も少なくありません。例えば、名鉄岩倉変電所、工部省品川硝子製造所、菊の世酒造、蒸気機関車、京都市電の車輌、六郷川鉄橋などがあります。今回は、その中でも特に注目してほしい機械館を紹介しましょう。
鉄道寮新橋工場
 |
機械館は、博物館のほぼ中央部、Ⅴ号地と呼ばれる区域にあります。外観は白板壁、切妻の細長い建物で秀美な建物が多い中にあってはあまりめだたない地味な存在です。建物は、1872(明治5)年開業の鉄道の機関車修復工場でした。新橋にあったので鉄道寮新橋工場と呼んでいます。
わが国の鉄道技術はすべてイギリスからの移植でした。この新橋工場も、柱、外壁の鉄板、サッシなどの建築資材をイギリスから輸入し、イギリス人技術者の指導によって建設されました。屋根を載せる小屋組は細い鉄材でトラスを組み、鋳鉄の柱を使用など鉄材プレハブ建築物として歴史的に価値ある建物です。大正のはじめ、工場は新橋から大井町に移転することになり、最初の一棟から二棟合わせた現在の大きさに拡張されました。その時には、国産の鋳鉄柱を他から転用しています。写真に示すように、「明治一五年東京銕道局鋳造」の銘があります。
|
鉄道寮新橋工場
Shimbashi Factory of the Japan National Railways
(The Machinery Hall), built in 1868 |
|
 |
機械館の鋳鉄柱
「明治一五年東京銕道局鋳造」の銘 |
菊花御紋章付平削り盤
機械館内部には、紡績機械、工作機械、印刷機械水車発電機など多数の明治期の機械類が展示されています。それらを丹念に見ていきますと、多くは外国製のものであることに気づきます。この明治時代は、そうした鉄製の大形の機械を自製することはまだできなかったのです。まず、輸入し、機械の使い方やその修理に習熟したのです。
輸入技術が隆盛する中で、一方では国産技術が芽生えつつありました。その証がこの平削り盤という機械です。平削り盤は文字通り金属を平らに削る機械で、機械のベッドなどの比較的大きな平面を加工します。
展示の平削り盤のベッドの側面には、「明治一二年 工部省工作分局 東京赤羽」との銘があります。この銘が示す赤羽(現在の東京都港区芝赤羽、旧久留米藩邸跡)にあった工作分局は明治政府工部省の直轄工場で、殖産興業政策を推進するために造られた機械工場でした。機械上部の横はり(トップビーム)に菊の紋章が三つ掲げられているのは、明治政府が造った機械という意味です。この平削り盤は、1879(明治12)年に岩手県盛岡市が設置した船舶修理工場に工作局から払い下げられた機械のひとつです。工場はその後岩手県立実業学校(現在の盛岡工業高校)に引き継がれて実習工場となり、戦後もその機械設備は教育用として大切にされてきたのです。
|
菊花御紋章付平削り盤
The planer with the chrysanthemum crest, built in 1879.
|
ゐのくち式両吸込渦巻ポンプ
国産の機械をもうひとつ紹介しましょう。写真の渦巻きポンプは、東京帝国大学教授井口在屋の理論を実用化した揚水ポンプです。井口在屋は、1905(明治38)
年に「渦巻ポンプの研究」として羽根車の作用とポンプの損失を明らかにした理論を発表しました。わが国の機械工学が黎明期であったこの時代、独創的な研究が少なかった中で井口在屋の理論は画期的なものでした。イギリスのエンジニア誌に紹介されるなど世界から称賛される理論であったのです。
井口在屋は、畠山一清と共同で流体機械の改良に関する特許を1914(大正3) 年に取り、この実用化のために畠山一清は、井口機械事務所(現在の荏原製作所)を設立、ゐのくち式渦巻ポンプを製作するようになり、わが国の機械技術がこの分野では世界的な水準となったのです。
展示の渦巻きポンプは、千葉県香取郡東庄町の桁沼揚水機場で使用していたもので、国友機械製作所が1912(明治45)年に製作、現存最古のゐのくち式渦巻ポンプです。
|
現存最古の国産渦巻きポンプ
Oldest Inokuchi-type volute pump in Japan, buit in 1912.
|
◇メモ
◆平削り盤の大きさ
平削り盤の大きさは、工作物を載せるテーブルの大きさで表す。展示の平削り盤のテーブルの大きさは、長さ2060mm、幅1165mmである。
◆井口在屋(1853-1923)
石川県金沢市出身、1882年に工部大学校機械科を首席で卒業、工部大学校教授補となり、後に教授となる。流体機械の研究とその理論は著名であるが、大学では応用力学、水力学を40年間に渡り講じて後進を育成するなど、工学教育にも大きな貢献をしている。
http://www.tcp-ip.or.jp/~ishida96
This site is maintaind by ISHIDA Shoji. For more information about the
this site, please write in Japanese, in english, auf Deutsch : ishida96@tcp-ip.or.jp
本文並びに写真の無断転載をお断りします。論文等に引用される場合は、石田正治 ishida96@tcp-ip.or.jp にお問い合わせ下さい。商用に利用される以外、特に不都合がない場合を除き、本文の引用並びに写真の転載を許可致します。その場合、通常の印刷物と同様に出典を明記していただきます。
Copyright(c)1997 by ISHIDA Shoji. All rights reseaved. Update : 2010/10/11
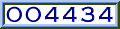 since 2007/2/19
since 2007/2/19





