愛知の産業遺産を歩く 36
長篠発電所
Nagashino Power Station
−革新のナイヤガラ式発電技術−
Hydoroelectric power station introduced new technology
of the Niagara Falls Power Station.
ISHIDA Shoji
奥三河の清流寒狭川は、鮎釣りの名所。段戸山を水源とする清流は、南設楽郡鳳来町長篠のところで豊川に合流し、三河湾に注いでいます。合流点の長篠の地は、戦国時代の織田徳川連合軍と武田軍の合戦場としてよく知られています。この歴史あるところに、現在3つの水力発電所があります。下流から順に長篠発電所、横川発電所、布里発電所とそれぞれ地名を冠して呼んでいます。いずれも豊橋電気株式会社(旧豊橋電燈株式会社)が建設した水力発電所です。発電設備はそれぞれ改修されていますが、小出力ながら今なお健在で、現在は中部電力株式会社の管理する発電所です。その内の最古の発電所、長篠発電所を紹介しましょう。
東三河水力開発小史
明治の末期になると電気は広く一般に普及するようになり、高まる電力需要に対応するために豊橋電燈は、水量豊富な奥三河山間地に水力発電所建設の計画を立て、豊橋電気株式会社(以下豊橋電気と略)と社名を変更するとともに資本金を増資して1907(明治40)年作手村見代に出力360kWの水力発電所を建設、さらに市内には出力150kWの下地発電所をつくり、需要に応えました。しかしながら電力需要はさらに増えるばかりでした。
 そして1910(明治43)年、急増する電力需要に応じるために、豊橋電気は子会社の寒狭川電気株式会社を設立し、京都帝国大学を卒業したばかりの気鋭の電気技術者今西卓を技師長に任じて長篠に発電所を建設します。長篠発電所は同年12
月に起工、1912(明治45)年2月に竣工して、同年の4月1日に送電を開始しました。
そして1910(明治43)年、急増する電力需要に応じるために、豊橋電気は子会社の寒狭川電気株式会社を設立し、京都帝国大学を卒業したばかりの気鋭の電気技術者今西卓を技師長に任じて長篠に発電所を建設します。長篠発電所は同年12
月に起工、1912(明治45)年2月に竣工して、同年の4月1日に送電を開始しました。
豊橋電気は、長篠発電所に続いて同じ寒狭川水系に、1919(大正8)年に布里発電所、1922(大正11)年に横川発電所を建設しています。いずれも今西卓の仕事でした。長篠発電所は外国製の設備でありましたが、布里発電所の設備は国産の水車と発電機が使われました。ちょうど第一次世界大戦が終結したばかりであり、その影響で外国からの機械類の輸入がむずかしくなってきた時代でありましたから、国産技術に頼らざるを得ない状況であったのです。それはわが国の発電技術が技術移入の時代から自立の時代へと移行する好機となりました。
ナイヤガラ式発電所
長篠発電所を眼下に見下ろす山手に1920(大正9)年に立てられた
長篠発電所竣工記念碑 があります。 碑の裏面には、「水車発電機共ニナイヤガラ型ト称シ本邦ニテ本発電所ヲ以テ使用ノ嚆矢トナス」と書かれています。取締役社長として電力王福沢桃介の名があり、技師長として
今西卓の名 が刻み残されています。碑文にあるナイヤガラ型の発電設備とは一体どのようなものなのであったのでしょうか。また、今西卓はどのような水力発電所を設計したのでしょうか。
その名のルーツであるナイヤガラ発電所は、アメリカとカナダの国境にある有名なナイヤガラ瀑布の落差を利用した発電所です。ナイヤガラ発電所は当時はその規模からして着工前から世界が注目する発電所でした。まだ発電技術が確立していない時代でありましたから水流の導き方や利用方法、発電方法あるいは送電方法は専門家の間で議論を呼んでいました。結局は、水は垂直に落とし、タービンを回して発電機を縦軸でつなぐ方式が採用されました。5000馬力の二相式交流発電機で発電し、それを三相交流に変換して送電するというものでした。ナイヤガラ発電所は1890年に工事が始まり、1895年に完成しています。
今西卓は、電気工学専攻でしたから、在学中にこの新鋭のナイヤガラ発電所のことを学び、その技術を長篠発電所の設計にいち早く活かしたと思われます。その設計のポイントは水車と発電機を縦軸で結ぶことでした。水を発電所まで水路で導き、そこから真直下に落としてタービンを回し、そのタービンの真上に発電機が位置する構造です。それまでは、水車と発電機を水平に置き、横軸でつなぐ方法が一般的でした。発電出力は比較にならないにしてもまさにナイヤガラ式でした。おそらく今西卓の採用した縦軸の水車発電機は日本の発電所技術史上でも画期的なものであったのでしょう。その最初の発電設備は、水車がフォイト社製九百馬力、発電機はジーメンス・シュッケルト社製で500キロワットの出力のものです。発電所の完成後は、革新技術の見学者が絶えなかったと伝えらています。
発電所建屋は1947(昭和22)年に落雷で焼失しているので現在のものは二代目ですが、当時の図面のままに復旧したようですから初期の面影を伝えています。発電機はコイルなどが交換されていますが当時のものです。この二代目もすでに半世紀の時を刻んでいます。現役ではありますが発電技術の歴史上注目すべき発電所です。
 |
長篠発電所発電機室、発電設備はドイツのジーメンス社製。
Generator house of the Nagashino Power Station. The generator made by Siemens-Schuckelt
in Germany. |
発電所の水路と溢流堤
長篠発電所の水路は、寒狭川の大岩小岩、奇岩の林立する景勝の地にあります。降雨の後は川の水位が上昇し、水路から余水が滝のごとく流れ落ちています。初めて見る人は、自然の滝のように思われることでしょう。この見事な演出のために意図して水路をこのように設計したのかどうか定かではありませんが、今西卓のナイヤガラ式発電にかけた技術者の気概をこの風景が語っているように思われます。
1983(昭和58)年、その水路は、鉄管や沈砂池とともに全面的に改修されました。その時、水門上部に取り付けられていた石の題額が前述の発電所竣工記念碑の隣に移されて、記念碑となっています。「沐浴羣生通流万物」と時の逓信大臣林董が揮毫したもので、題字は「多くの人が湯浴みし、万物が通り流れる」の意で、水の流れの功徳を讃え、発電所の悠久を祈念したものです。
(いしだ しょうじ・愛知県立豊橋工業高等学校)

|
長篠発電所 溢流堤
Overflowed bank of the Nagashino Power Station.
|
 |
「沐浴羣生通流万物」の碑
Monument of the Nagashino Power Station, write by the Minister of Communication
Mr.HAYASHI Tadasu. |
◇メモ
豊橋電燈株式会社
1894(明治27)年設立。略史について、本シリーズ「牟呂発電所遺構 13」で紹介している。
http://www.tcp-ip.or.jp/~ishida96
This site is maintaind by ISHIDA Shoji. For more information about the
this site, please write in Japanese, in english, auf Deutsch : ishida96@tcp-ip.or.jp
本文並びに写真の無断転載をお断りします。論文等に引用される場合は、石田正治 ishida96@tcp-ip.or.jp にお問い合わせ下さい。商用に利用される以外、特に不都合がない場合を除き、本文の引用並びに写真の転載を許可致します。その場合、通常の印刷物と同様に出典を明記していただきます。
Copyright(c)1997 by ISHIDA Shoji. All rights
reseaved. Update : 1997/4/5
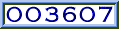 since 2007/2/19
since 2007/2/19
 そして1910(明治43)年、急増する電力需要に応じるために、豊橋電気は子会社の寒狭川電気株式会社を設立し、京都帝国大学を卒業したばかりの気鋭の電気技術者今西卓を技師長に任じて長篠に発電所を建設します。長篠発電所は同年12
月に起工、1912(明治45)年2月に竣工して、同年の4月1日に送電を開始しました。
そして1910(明治43)年、急増する電力需要に応じるために、豊橋電気は子会社の寒狭川電気株式会社を設立し、京都帝国大学を卒業したばかりの気鋭の電気技術者今西卓を技師長に任じて長篠に発電所を建設します。長篠発電所は同年12
月に起工、1912(明治45)年2月に竣工して、同年の4月1日に送電を開始しました。

