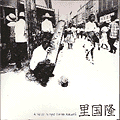 |
▲路上に現れた、裸の唄 『あがれゆぬはる加那』里国隆
| 里国隆/あがれゆぬはる加那;オフノート、1996 音楽は偶然の産物だ。その最たるものはそらく路上だ。いつどこに現れるかわからない。大道楽師。いや、「師」というのはおこがましい。時にそれは「人」ですらなくなる。風邪をひいて声が出なければその日のおまんまは食い上げ。暴力は自然のものも人工のものも直接関ってくる。間に入って遮ったり、和らげたりしてくれるものは、有形のもの(建物や組織)も無形のもの(共同体意識や制度)もない。だからそこを生抜いた芸は、室内の芸には絶対獲得できない次元の密度とエネルギーを獲得する。そして里国隆は路上楽師の無冠の王と呼ばれるにふさわしい、エネルギーと密度を備えるにいたった。ここに断片的に捉えられた里国の音楽の圧倒的な魅力、行きずりの人間の耳を掴んで惹きつける力に多少とも肩を並べるものは他には知らない。多少は耳にしている奄美の伝統歌謡とも、決定的に違っている。この歌には命がかかっているからだ。歌わなければ死んでしまうのだ。文字どおり。 はじめ聞いたとき、なんと暑苦しい声かとあきれた。確かにこの声では、室内では暑くて暑くて二、三曲も聞けばもういやになるだろう。録音のせいか、三板もやけに耳に響く。たて琴というが、要するにふつうの琴を立て、弦を金属に変えただけだ。あざやかなテクニックがあるわけでもない。 しかしなぜか、聞かずにおれない、という想いがはじめ小さく、だんだん膨れあがってきた。ジャケット写真の力は確かにあった。缶カラひとつ前において、電柱を背に腰を降ろしたグラサン男。見えている顔と手の先は日焼けで真っ黒。その腰の降ろし方が絶妙だった。いつ何時でもさっと動けるはずだ。といって腰が浮いているのでもない。しっかりとおちついている。一体何度ぐらい路傍に腰を降ろせば、このようなすわり方になるのか。口を見ればこの男は歌っている。周りを歩いている人びとは誰一人何の関心も払わない。 その写真を見ながら聞いていると暑苦しい声がうたう、そこでそうして聞いているおまえは一体何者だ、と。何のためにおまえはこんな歌を聞いているのだ。 音楽を聞くのに理由など要らないという抗弁も空しい。命懸けでうたっているのをなぜおまえは聞く。投げ銭もできないくせに。できないから聞いてやる。何回でも聞いてやる。おまえのためじゃない、オレのために聞いてやる。 里国隆。地元・奄美では「乞食の里国」と呼ばれた盲目の路上唄者。徹頭徹尾路上でうたい、うたいながら死んでいった人。裸のうた。聞けば裸になるうた。覚悟はいいか。 |
大島 豊@厚木 |