
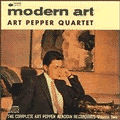
アート・ペッパー『モダン・アート』
Art Pepper 『Modern Art』
INTRO ILP606
------------------------------------------------------------------
Recording Data:Dec,28,1956 Jan,14,1967, Studio Recording in L.A.
Kendun Recorders Inc. Burbank, Calif.
Personnel :Art Pepper (Alto sax)
Russ Freeman (Piano)
Ben Tucker (Bass)
Chuck Flores (Drums)
-----------------------------------------------------------------
Tunes Side A:
Blues In (6:04) (Art Pepper)
Bewitched (4:26) (Rogers, Hart)
When You're Smiling (4:51) (Shay,Fisher,Goodwin)
Cool Bunny (4:15) (Art Pepper)
Tunes Side B:
Dianne's Dilemma (3:48) (Art Pepper)
Stompin' At The Savoy (5:04) (Sampson,Webb,Goodman,Razaf)
What Is This Things Called Love (6:04) (C.Porter)
Blues Out (4:46) (Art Pepper)
-----------------------------------------------------------------
| 【解説】 かつて幻の名盤といえば、その筆頭にあげられていたのがこのアルバム。西海岸のマイナーレーベル「イントロ」に録音され、内容の良さに希少価値がともなって、数十万のお値段がついたとか...。今では、「ブルーノート」が権利をもって、いつでも聴くことができるようになっています。そんないわく因縁を差し引いても、これが、50年代のアート・ペッパーの絶頂期をとらえた、傑作アルバムであることにはかわりありません。 メンバーは、気心の知れた当時のレギュラーメンバー、ラス・フリーマン、ベン・タッカー、チャック・フローレス。「ベサメ・ムーチョ」の名演で有名な、タンパレーベルのアルバムと同じメンツ。 アート・ペッパーがいかにユニークで、優れたジャズアーチストであるかがここに凝縮されています。 ----------- 【モダン・アート】 ---------- 以前中古盤屋で一度だけ、オリジナル盤を見たことがあります。もちろん手に取ることはかなわず、ましてや自分のものにするなど恐れ多いほどのお値段が...。 壁に掛けられた、現代絵画をバックに一人思いにふけるようなアート・ペッパー。その視線の先には、横たわるさくっす。生々しいライティングと全体に押さえた色調。そっけないほどのレイアウトだけれど、くすんだエメラルドグリーンと小豆色のロゴタイプは、計算し尽くされた色彩で、マイナーレーベルの作品とは思えない格調を感じさせます。 このアルバムの冒頭の曲「ブルース・イン」。初めて聴いた時の感動は、今でも忘れません。ベン.タッカーのベースだけをバックに、次々と魅力的なフレーズを繰り出してくるペッパーに、ただただ聞き惚れるばかり。今でこそ珍しくもないサックスとベースのデュオも、当時の感覚からすればまだまだイレギュラーなフォーマット。そんな演奏を最初と最後に置き、間をカルテットの演奏で構成したアルバムが、どういう考えで作られて、どのように受け止められたのか興味深いところです。 アート・ペッパーといえば、「陰影に富んだ」「翳りのある」「悲哀を感じさせる」「屈折した」「切々たる愁い」etc...まぁ、だいたいこういう表現をされることが多くて、それは全くその通りなんだけど、そればっかりじゃまるで、ねちねち吹いてるムードサックスのようで、いけません。一般的な「ウェスト・コースト・ジャズ」のイメージには収まりきらない、「激情」や「狂気」をも感じさせる彼のジャズは、まさにワン・アンド・オンリー。アート・ペッパー、それも50年代の彼に一家言持つ方も大勢おられることと思いますが、以下順を追ってディスク・ジョッキーをして参りたいと思います。 1."Blues In" & 8."Blues Out" アルバムの冒頭とラストにおさめられた対になる二曲は、ベン・タッカーのベースだけをバックにした、ブルースナンバー。アート・ペッパーに対して、僕が特に魅かれるところは、彼のリズム感なんですね。これが、どこか妙で、ずれたり引っ掛かったりしてるようでいて、心地よいという、なんとも絶妙な乗り。 「ブルース・イン」「ブルース・アウト」の2曲では、ベン・タッカーの正確無比なリズムとのコントラストが、常に適度な緊張感を生んでいます。これがスコット・ラファロだったら....。ベン・タッカーは、完全にリズムキープに徹してはいるが、これが逆にペッパーのリズム感、タイミング、アクセントを見事に浮かび上がらせる背景となっています。 「ブルース・イン」は、まさに抑制の美学。「都市の音楽」であるジャズにとってのブルースってのは、こういうものかもしれない。とらえどころの無い孤独感を、日常の中に誤魔化して生きている男が、ぼそぼそと愚痴ってみたり、時々感極まって叫んだりするように、ペッパーの演奏は、時に淡々と時に切々と。 「ブルース・アウト」は、よりアグレッシブな演奏。ペッパーに「アグレッシブ」なんて形容詞はにつかわしくないようだけれど、ここでのペッパーは、構成など考えずに感情のおもむくままに、叫んだり呻いたりして、後年のフリー系ミュージシャンのソロサックスを想わせる瞬間さえあります。試しに、音量を下げてベースの音が聞き取れないくらいで聴いてみると、そこには、「端正」などというのとはほど遠い、感情を剥き出しにした、歪んだ音の塊が投げ出されているはず。そして、唐突に終わる... 2."Bewitched" 「魅せられて」という邦題で知られるリチャード・ロジャースとロレンツ・ハートの有名なスタンダード。1曲目の「ブルース・イン」が、芝居の冒頭、幕前での主人公の独白だとすれば、この2曲目は、幕が上がり登場人物も出そろっていよいよ、ストーリーが展開し始める第2幕目といったところ。ラス・フリーマンのイントロは、「さぁ、気分を変えて」とでも言うように優しく、主人公の登場を演出しています。 ペッパーは、原曲のメロディーに沿って展開していきますが、付かず離れずで彼流のメロディーに作り替えていきます。甘ったるいポップソングが、愁いを帯びた意味深長な唄に変わっていく様は、見事というほかありません。まるでペッパーと双子のように、ラス・フリーマンのソロはペッパーの作ったイメージをそのまま持続させる。ピアノソロを挟んで、気の向くままに8小節、そして再びテーマに戻る。 3."When Your're Smiling" 1928年に発表された「君微笑めば」。典型的な明るいアメリカンポップソング。スイング時代は人気のある曲だったようですが、最近は聴く機会が減っているかな。有名なところでは、ビリー・ホリデイ〜テディ・ウィルソンの録音でのレスター・ヤングのソロがありますね。 どちらかというと、「陰」のイメージが強いペッパーが、明るい曲をやると彼にしか出せない魅力がこれでもかと溢れ出てくる。これって、ビリー・ホリデイが明るい曲を歌ったときと同じじゃないかな。 ストレートにやると間延びしてしまうテーマ部分を、抜群のセンスで何倍も魅力的なメロディーに変えてしまう。これこそペッパーを聴く喜び。そのまま、アドリブに入ってもイメージは一貫していて、めくるめくペッパー・ワールドが展開されていきます。 4."Cool Bunny" ペッパーのオリジナル曲。4人が一体となって一気に駆け抜ける。テーマの前に、徐々にメンバーが入ってくる短いけれど効果的なイントロがついています。ペッパーのソロは、こんな速いテンポの曲でもアドリブ臭さを感じさせず、メロディックでいて勢いを失わない。ピアノソロを挟んで、ドラムとのバース。相手のドラムとは役者の格がちょいと違うところが歯がゆくもあるけれど、ペッパーの必殺技は切れ味抜群。 5."Dianne's Dilemma" さて、ここからがB面。個人的に、このアルバムの中でいちばん好きなのが「ダイアンズ・ジレンマ」ペッパーの奥さんだった人の名前を付けた曲。この時期に他にも数曲、彼女の名前の付いた曲があります。ペッパーのアルバムで好きな曲と言いながら、こんなことを言っては何ですが、ここでの主役はラス・フリーマン。ペッパーが悪いわけではなく、フリーマンが良すぎるだけなんですけどね。 サックスとピアノのユニゾンで奏でられるテーマ部分は、輝くような響きとうきうきするようなリズムで、いやでも気分が良くなってしまう。そのまま、ペッパーのソロは力強く、変化に富んだフレーズで、アドリブを繰り広げていく。そしてそれに勝るとも劣らない、ピアノソロ。テーマメロディーの持っているサウンドを活かしながら、歌う歌う。よく聴くと、弾きながらうなっているのが聞こえます。サックスのバックに回っているときも、まるでペッパーのやることを先読みしているかのような、絶妙のコンピング。ピアノだけに耳を傾けていても、十分に楽しめます。 ピアノソロから、最後のテーマに。フリーマンはソロの勢いをそのままに、なだれ込んでいきます。おかげでペッパーは、守りに入ったような印象を受けてしまいます。最後は主従交替してしまいます。アルバム中もっとも短い曲ですが、これ聴いてからだが動かない人はいないでしょう。 6."Stompin' At The Savoy" 「サヴォイでストンプ」なんとも、身も蓋もないタイトルでございます。1934年に作られ、チック・ウェッブ楽団、ベニー・グッドマン楽団でヒットをして、歌詞がつけられたのが1936年。スウィングジャズ華やかかりし頃の唄って踊ればすべてはハッピーってな曲で、ペッパーのイメージとは、てんで正反対。 エラ&ルイの超ハッピーノリノリスウィングいけいけバージョンが大好きな僕としては、期待半分心配半分で聴いたのですが...。ペッパーの手にかかると、実にモダンなナンバーに早変わり。これを聴いて「サヴォイでストンプ」ってこんな曲なんだと思ってはいけません。原曲は似ても似つかないものですから。 ペッパーは、ぐっと押さえたスウィング感、微妙な音色の変化、タイミングのずらし、ブルース感覚溢れるフレージング、あれやこれやのテクニックでまるで違う曲のように作り替えてしまいます。ミキシングのバランスが他の曲とは違うようで、ピアノは控えめでベースがぐっと浮き上がって聞こえます。そして、それが余計にこの演奏をモダンなものにしているような気がします。どっしりとしたベン・タッカーのベースは、なんの芸もない武骨一直線ですが、これが素晴らしい。今どきこんなベース、なかなか聴けないですからねぇ。 ピアノソロの後のストップタイムを用いた展開は、とてもスリリングで、思わず体中の筋肉がぐっと引き締まる感じがします。最後のテーマに戻る寸前にベースのラインがグワァッと盛り上がってくるところは、何度聴いても鳥肌もの。ベン・タッカーに10000点。 7."What IS This Thing Called Love" モダンジャズの素材として取り上げられることの多いコール・ポーターの名曲「恋とは何でしょう」。数々の名演が録音されています。テーマのペッパー流解釈がいいですねぇ。たいていもう少し粘っこくやる場合が多いように思うんですけど、軽くいなすように吹きながら、緊張感も感じさせる。アドリブパートに入ると、もう絶好調。このままずっとやり続けられるんじゃないかと思うほど、次から次へと魅力的なフレーズを繰り出してきます。 ピアノソロも悪くはないんだけど、そこまでのペッパーが良すぎて見劣りがしてしまいます。ドラムとのバースに至っては、ちょっと相手の役不足の感が否めない。ペッパーの一人勝ち状態ですね。エンディングの構成が少し変わっていて、ちょっと鳥肌の立つようなスリルがあります。 ----- "Dianne's Dilemma"別テイク ----- 「モダン・アート」のセッションで、オリジナルに収録されていなかった録音が後に、聴けるようになりました。その内の一つが、70年代の終わりに、うっかり発表されてしまった「ダイアンズ・ジレンマ」の別テイク。 ブルーノートが、この時期のペッパーの編集盤「アーリー・アート」を発売した際、初回プレスで「ブルース・アウト」のはずが、「ダイアンズ・ジレンマ」の別テイクが収録されてしまったもの。本テイクよりも1分以上も長く、後半にピアノとのバース部分が追加されています。テンポ自体は別テイクの方が少し早いかな。ドラムのバッキングがブラシに変わっています。 録音のバランスが少し違うせいもあるかもしれませんが、ピアノが引っ込んでいるのと、ドラムがブラシのスネア主体になっているのとで、本テイクのサウンドとはずいぶん印象が違います。あの、輝くような感じが無くて、少しくすんだ印象を受けます。後半のバースも少し間延びした感じで、コンパクトにまとめた本テイクの鮮やかさに軍配を上げたいですね。 ----- "Summertime"未発表録音 ----- もう一つのオリジナル未収録曲は、87年にCD化された際に、初めて日の目を見たもの。有名なガーシュインの「サマータイム」。この曲も、録音の多い曲で名演と呼ばれるものも数多くあります。僕が好きなのは、パーカーの「ウィズ・ストリングス」での演奏。この重い曲を軽々と、それていてとても優雅に歌いきっていて、すばらしい。 さて、このペッパーの演奏ですが、これがオリジナルアルバムに収録されなかったわけは、聴いてみればすぐわかります。これは入れちゃいかん。そもそも、同じ時の録音とは思えないくらい、違和感があります。正直言って同じ精神状態でやってるとは思えないくらい。 感情のコントロールを失う寸前のような、正気と狂気の際どい所で踏みとどまっているような、なんとも鬼気迫る演奏です。初めて聴いたとき、思い浮かべたのはアルバート・アイラーの「サマータイム」。それくらい、衝撃的でした。 -----【Modern Art】録音データ----- LPの頃の録音データを見ると、A面が1956年12月28日、B面が1957年1月14日となっていました。これが、CD化の際の新しいデータでは、"Bluse In" "Bewitched" "Stpmpin' At The Savoy" "What Is This Thing Called Love" "Blese Out" の5曲が1956年12月28日、残りの3曲と"Summertime"が1957年1月14日と訂正されました。 以前のデータで"Bluse In" "Blese Out"が、別の日に録音されたというのがどうも不自然な感じがしていたので、新しいデータで納得。後は録音された順番がはっきりすれば、嬉しいんですけどね。 ベースとのデュオを最初と最後に据えたこのアルバムの構成が、最初から意図されていたものなのか?最初から意図されていたとしたら、いったい誰の意図なのか?意図されていなかったとしたら、どういういきさつでこの2曲が録音されることになったのか? ------ 【Modern Art】雑感 ----- 今回、このアルバムを久しぶりに聞き直してみて、その素晴らしさを再認識したわけですが、サイドメンの活躍も素晴らしいものがあります。 ラス・フリーマン、ベン・タッカー、チャック・フローレス。「ベサメ・ムーチョ」の名演で有名なタンパのアルバムも同じメンバー。2枚のアルバムを聴いてみれば、このグループがこの時期とても充実していたことがわかります。 ペッパーの代表作としては、「ミーツ・ザ・リズム・セクション」があげられることが多いですが、僕としては「モダン・アート」の方が数段上だと、思っています。ペッパーのプレイはともかく、バックとの相性がずっといい。 ラス・フリーマンのピアノは、あらかじめペッパーのやることがわかっているんじゃないかと思うような、絶妙のサポート。インタープレイというんじゃなくて、あくまでもバッキングとして最高レベルじゃないかと思います。そして、一転ソロに回ると、ペッパーの作ったイメージを完璧に再現しながら彼の個性であるキラキラ輝くようなサウンドを繰り広げる。ペッパーの「陰」に対する「陽」として、フリーマンのピアノが作用して、より深みのある演奏になっているように思います。 そして、ベン・タッカー。今どきのベーシストにこんな演奏をさせたら、欲求不満で憤死してしまうんじゃないかと思うほど、ひたすらビートを刻み続ける。でも、彼の重いベース・ラインがこのグループのサウンドの骨格を作って、ペッパーの特異なタイム感覚を浮き彫りにさせています。その禁欲的な演奏に耳を澄ましていると、感動的ですらあります。 チャック・フローレスは、決して一流のドラマーとは言えないかもしれません。でも、バンドのバランスではこの位がちょうどいいのだ。リズムの土台はベースに任せて、軽めのドラムは全体のサウンドを補完するために機能している、ってのが実態でしょうか。 |
| text by DINO |