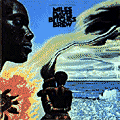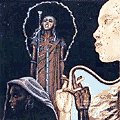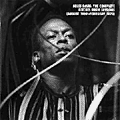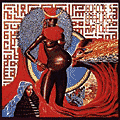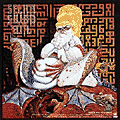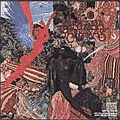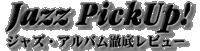
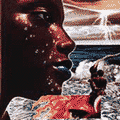
マイルス・デイヴィス 『ビッチェズ・ブリュー』
Miles Davis 『Bitches Brew』
------------------------------------------------------------------
Personnel :
[On (a), August 19, 1969; Columbia Studio B, New York]
Miles Davis (tpt)
Wayne Shorter (ss)
Bennie Maupin (bcl)
Joe Zawinul (el-p - left)
Chick Corea (el-p - right)
John McLaughlin (g)
Dave Holland (b)
Harvey Brooks (el-b)
Lenny White (d - left)
Jack DeJohnette (d - right)
Charles Don Alias (cga)
Jumma Santos (Jim Riley) (shaker)
[On (b), August 20, 1969;Columbia Studio B, New York]
Miles Davis (tpt)
Wayne Shorter (ss)
Bennie Maupin (bcl)
Joe Zawinul (el-p - left)
Chick Corea (el-p - right)
John McLaughlin (g)
Dave Holland (el-b)
Harvey Brooks (el-b)
Charles Don Alias (d - left)
Jack DeJohnette (d - right)
Jumma Santos (Jim Riley) (cga)
[On (c), August 21, 1969;Columbia Studio B, New York]
Miles Davis (tpt)
Wayne Shorter (ss)
Bennie Maupin (bcl)
Joe Zawinul (el-p - left)
Larry Young (el-p - center)
Chick Corea (el-p - right)
John McLaughlin (g)
Dave Holland (b)
Harvey Brooks (el-b)
Lenny White (d - left)
Jack DeJohnette (d - right)
Charles Don Alias (congas)
Jumma Santos (Jim Riley) (shaker)
Engineer :Stan Tonkel
Cover Painting:Mati Klarwein
Produced by :Theo Macero
--------------------------------------------------
Tunes Side A: Pharaoh's Dance (c) (J. Zawinul)
Side B: Bitches Brew (a) (M. Davis)
Side C: Spanish Key (M. Davis)
John McLaughlin (b) (M. Davis)
Side D: Miles Runs the Voodoo Down (b) (M. Davis)
Sanctuary (a) (W. Shorter-M. Davis)
-----------------------------------------------------------------
| 【解説】 今回はマイルス・デイヴィスの「ビッチェズ・ブリュー」を取り上げたいと思います。今まで、過去にマンスリー・ステージで取り上げられたアーティストの作品は、このPickUp!では意図的に取り上げていなかったのですが、昨年暮れに"THE COMPLETE BITCHES BREW SESSIONS"と称した箱ものがリリースされたことでもあり、この『世紀の名盤』を改めて聴き直してみるという企画も悪くないかな、と思った次第です。 しか〜し! この4枚組の“コンプリート版”は、既に多くの方が憤慨されているとおり、はっきり言って看板に偽り有り、です。一つ前の発言にあるデータ関係をご覧の通り、この「ビッチェズ・ブリュー」というアルバムは、1969年の8月の3日間のレコーディング・セッションを収録したもので、言い換えれば、その3日間が「ビッチェズ・ブリュー」なのですが、その日に録音した別テイクであるとか、未発表曲というものは一切ありません。ただ、曲によってフェイドアウトする箇所が数秒遅い(=少し曲が長さが変わってお得になった^^;)とか、何より音質面での向上が著しいので、既にこのアルバムをお持ちの方も、追加購入する価値は充分にあります。 さて、それでは1曲ずつ順を追って聴いていくことに致しましょう。尚、アルバム名の"Bitches Brew"はビッチズ・ブルーと読むのが、より正しい発音に近いとは思いますが、ビッチェズ・ブリューという読み方が既に定着していると思いますので、敢えて表記はそちらを採用することにします。皆さん、お知り合いの外人の方^^;とこのアルバムについて語り合う機会がありましたら、どうぞビッチズ・ブルーと発音なさってください。さもないと、通じない可能性が高いので(苦笑)。 ----- 1969年8月のちょっと前----- 僕は何と言っても、このアルバムをリアルタイムで聴いているわけではないので、その当時の事情は分かりませんが、多くの方がこのアルバムを聴いてびっくりしたと言っているようです。それは、マイルスがそれまでの音世界から大きく異なった方向に踏み出した、ということに対する驚きだったのではないかと想像しています。でも、現代のマイルスのファンが、歴史を紐解きながら聴いていっても、ここで展開される音楽がそれまでのツアーでの演奏と大きく異なることに、驚きの感情を隠すことが出来ません。 この年の2月に前作"In a Silent Way"を録音しているわけですが、この作品は編成の拡大に伴いサウンドがカラフルになり、"Nefertiti"を録音した後で模索していた非4ビート音楽として、ようやく形になってきたものの、まだジャズ的な色彩の強いものでした。そして、その翌月の演奏の海賊盤(僕は未聴ですが)の曲目を見ると、 という具合に、何事もなかったかのように(笑)、クインテットのレパートリーに戻っているわけです。"In a Silent Way"と"Bitches Brew"の間に正規盤1種と海賊盤6種のライブが残されていますが、"Bitches Brew"でスタジオ録音される曲、"Spanish Key"や"Miles Runs the Voodoo Down"が登場し始めるのは、7月ぐらいからです。さらに、以前アコースティックで録音したこともある"Sanctuary"が復活してきます。そして、8月を迎えます。 "Bitches Brew" まずはタイトル曲です。この曲はLPで言えば1枚目のB面に当たるわけですが、録音はセッション初日の最初に行われているようです。 ビッチェズ・ブリューという曲を思い浮かべるとき、ほとんどの人が曲の冒頭、途中、そして最後に登場するエコー付きファンファーレ^^;のことを思い出すのではないでしょうか。それほど、この部分は印象的だといえます。かなりディレイタイムを長めにして左右に振り分けるという、かなりわざとらしいやり方で、今ではそんな技法は使わないんじゃないか^^;とも思えますが、その当時には(少なくともジャズファンの耳には)聴いてびっくりするようなものだったのでしょうか? いずれにしても、このサウンドは現代の我々にも依然として非常に魅力的であることは確かです。昨年、ニルス・ペッター・モルヴァーのクメール・バンドを生で聴く機会があったのですが、ターンテーブル^^;の兄ちゃんがステージの途中で、このビッチェズ・ブリューの冒頭部分を素材にしていたりしました。当人たちの演奏より何より、マイルスのレコードの方がカッコよくて、聴いていて困ったりしましたが(^^ゞ。 このファンファーレは、『展覧会の絵』のプロムナードみたいな雰囲気ですね。今改めて考えてみると。15分過ぎ辺りで再び登場するわけですが、全体としては構成がシンプルな中で、チェンジ・オブ・ペースの役割を果たしています。最初と最後は同じテープの使い回しだと、中山康樹は著書で書いていますが、ちゃんと聴き比べていないので本当かどうかよく分かりません(^^ゞ。 さて、そのファンファーレの後でインテンポとなっていくわけですが、最初からバスクラがモヘヘッ、モヘヘッ、と怪しげに吹いてくれるところが気持ちいいですね^^;。多くの方が指摘しているとおり、このアルバムのサウンドイメージを規定する大きな要因となったのが、バスクラの参加であると思います。マイルスがバスクラを起用したのは、ほとんどこの時期のスタジオ録音のみで(後は最晩年にマーカス・ミラーにバスクラを吹かせてます)、それだけにここでの起用は唐突という感もあります。それ故に、このアルバムへのギル・エヴァンスの関与という説が出てくるのでしょうか。真偽のほどは僕には分かりませんが。 ドラムは後にコリアとRTFで一緒にプレイするレニー・ホワイトとディジョネットの2人いるらしいのですが、右チャンネルがディジョネットということになるのでしょうか。役割分担としてはディジョネットが基本リズムをわりとちゃんと叩いていて、レニー・ホワイトが自由に叩くという感じ。 一方、エレピはコリアとザヴィヌルが右チャンネルと左チャンネルということになっているのですが、こちらはちゃんとは左右に分かれて聞こえてこないので、どっちがどっちなのかよく判別できません^^;。誰か分かる人は教えてください。m(__)m でも、途中でフィーチュアされるソロはコリアだと思うんだけど、それってむしろ左チャンネルに寄っているような気がするし... ひょっとして僕のところのステレオは、配線を逆にしちゃってるか? ----- Bitches Brewの演奏履歴----- このBitches Brewという曲について、残っている音源としてはマイルスが演奏しているものは、下記の通りです。
つまり、スタジオ録音が初出、ということですね。その後、しばらくの間ライブ演奏でも重要な位置を占めていますが、キースの離脱後はレパートリーからも削られているようです。 そのうちの一つ、1969年11月3日のパリ(サル・プレイエル)での演奏を聴きながら、これを書いていますが、常に決まったパターンを弾き続けていたハーヴェイ・ブルックスがいたことで、必然的にある程度の秩序が保たれていたスタジオ録音に比べると、かなりフリー的な展開を見せています。特にコリアのやりたい放題が目立ちます。 "John McLaughlin" というのは、言わずとしれたエレクトリック・ギタリスト^^;であるわけですが、この人をフィーチュアした演奏を、そのまま曲のタイトルにしたものがアルバムに収録されているわけです。 これをやっている間、マイルスとショーターは飯でも食いに行っていたのでしょうか?と思わずにいられないのは、この2人が演奏に参加していないからです。あと、エレベのハーヴェイ・ブルックスもここでは弾いていません。 かと思っていたら、4枚組の“コンプリート版”にドン・アライアスの証言がありました(輸入盤で買ったので、面倒でライナーはちゃんと読んでない^^;)。この演奏はもともとBitches Brewの一部で、しかも2つのテイクを合体させたものだそうです。というわけなので、このスタジオ録音の後、"John McLaughlin"としての演奏履歴はありません。 このテイクを聴いて最初に思うのは「あっ、Return to Foreverだ^^;」ということです。演奏全体を支配するコリアの左手のパッセージが、後に“カモメ盤”の表題曲の中間部に現れるもの(フローラ・プリムが歌ってるわけですが)と同じだからです。コリアはその場で思いついて弾いていた(多分)このパッセージを、あとで自分のアルバムに使ってみようと思ったのかもしれません。 コリアの後ろでかすかに聞こえる、ザヴィヌルのエレピが結構ファンキーでナイスです。そう言えば、この人はキャノンボールのところにいたくらいですから、ファンキーで当たり前!なのでした^^;。謎の中近東スケールと、共存するのが謎ですが^^;。 "Sanctuary" これは、いきなり演奏履歴から行きます。
最初にスタジオで録音された1968年2月15日の演奏というのが、10年ぐらい経ってから一時引退中にコロンビアが出した"Circle in the Round"で日の目を見たものです(その後、藤色のマイルス黄金のクインテット箱^^;にも収録されてます)。 このときにはアコースティックで“静かに”演奏されたものが、この「ビッチェズ・ブリュー」セッションでは、ライナーノートの言葉を借りれば“オペラ的な”ものに変貌しています。1ヶ月前のライブ(「1969マイルス」として正規盤で出ているもの)を聴いても、これほどドラマティックな展開は見せていません。 この曲についてもライナーに面白いことが書いてあります。1963年以来、マイルスはライブで"I Fall in Love Too Easily"という曲を、聴衆の興奮を冷ますために演奏することが多かったのですが、その同じような意味合いを求めてこの"Sanctuary"を演奏するようになったということのようです。それでステージのクロージングに使われることが多かったんですね。 尚、レコードで聴けるこの演奏も、2つのテイクを合体させたものだそうです。おそらく、オリジナルテープとしてはマスターの編集前のテープが残っている(今回の4枚組は、それを元にLP発売時のマスターと“同じように”編集し直したと思える節がある)のでしょうか。そうやって考えると、この時代以降、それ以前のジャズの別テイク有りみたいなものと同列には語れないわけで、ほとんどマイルスの“コンプリート・レコーディングス”というものが意味を為さないという感じですね。もちろん、未発表曲というのは大歓迎なのですが。 ----- ジャケット ----- 何しろ有名な作品の有名なジャケットですから、皆さんご存じだと思いますが、表は思い出せても裏は思い出せないという方が多いかも知れないので(笑)
ここまではオリジナルの方でして、最近リリースになった4枚組“コンプリート版”はこのようになっています。
LP版では6枚組になるのですが、こちらをご覧になったことが無い方は結構いらっしゃるのでは? -----8月4日のインタビュー----- 「ビッチェズ・ブリュー」録音セッションの始まる半月前に、マイルスは日本のジャーナリスト(複数?)からインタビューを受けています。マイルスがその当時住んでいたWest 77th Streetの312番地で、そのインタビューは行われているそうですが、その際にテオ・マセロ、その時点での最新作であった"In a Silent Way"、ストラビンスキーやラフマニノフ、それにブラック・ミュージシャンや聴衆のことに関して話したとのこと。23分50秒のテープが残っているらしいのですが、その内容は当時スイング・ジャーナルに掲載されたんですかね〜?どなたか昔のジャーナルを収集されていらっしゃる方、こちらを読まれてませんか? -----マティ・クラーバイン----- この有名なジャケット(の絵)を描いた人はマティ・クラーバインという人なのですが、名前が示すとおりドイツ人です(Klarweinというのは“澄んだワイン”の意)。1932年ハンブルクに生まれましたが、ユダヤ人の血を引く彼の一家はそのわずか2年後に、ヒトラーの権力掌握によりパレスチナ(現在のイスラエル)に移住します。 彼は本当はハリウッドに渡って映画監督になりたかったそうですが、1950年代にはパリに行き、フェルナン・レジェに師事して絵画を学んでいます。しかし、師のことを非常に尊敬しながらも、アーティストとしてもっとも影響を受けた存在は、サルバトール・ダリだったそうです。同時にイタリア・ルネッサンスや、フランドル派の画家たちにも影響を受けたと述懐しています。 彼が最初に音楽界と接触を持ったのは、50年代終わりに彼がユセフ・ラティーフに肖像画を送ったときでしょうか。ラティーフと電話で話し、ちょうどそのときにラティーフが出演していたビレッジ・バンガードに来るように言われ、送った肖像画がレコード・ジャケットに採用されることを期待して、彼はバンガードを訪れます。しかし、白人嫌いだったラティーフは(当時アブドゥル・マティと名乗っていた)クラーバインのことをそのときまで非白人だと思いこんでおり、彼に初めて会った瞬間、もう全く話をしようとしなかったそうです。 1964年に発表した"Crucifixion"という絵の大胆な構図で、絵画界及び社会に大きな波紋を投げかけた彼は、暴漢に襲われたりしたこともあるそうです。 さて、「ビッチェズ・ブリュー」のジャケットは表と裏で1枚の絵を構成しているもので、その点では少し小さいのが残念ですが、4枚組セットのブックレットの裏表紙の内側に並んでいるのを見ていただければ、全体像が分かります。でもLPだったら、広げればだいたい感じはつかめますね(苦笑)。 マイルスの作品としては他に「Live-Evil」に、クラーバインの作品が採用されています。
さらに彼の作品はジミ・ヘンドリックス(同じ洋服の仕立屋に行っていたのだとか)がギル・エバンスと共に録音していたアルバムのジャケットになるはずでしたが、残念なことに完成する前にジミ・ヘンドリックスが急逝したため、録音済みのマテリアル共々お蔵入りになってしまったそうです(幻のジャケットの方はジミ・ヘンドリックス展で全世界を巡回しているらしい)。 「Abraxas」のオリジナルは現在はモロッコの王族?が所有しているそうですが、「ビッチェズ・ブリュー」の方は描いた本人もどこにあるのか知らないのだとか。こういう作品こそ、MOMAでもグッゲンハイムでもいいですが、購入してもらいたいですね。 マティ・クラーバインは今でも健在で、地中海に浮かぶマジョルカ島に住んでいるそうです。彼のその他の作品について、 [The Manic Landscape: Mati Klarwein] (http://art-bin.com/art/aklarwein.html) で、その幾つかを見ることが出来ます。是非、ご覧ください。 "Miles Runs the Voodoo Down" レコーディングは2日目に入りましたが、メンバーに若干の変更がありました。この日の録音にはレニー・ホワイトは参加していません。替わりに左チャンネルで聞こえるドラムを叩いているのは、他の曲ではドラムを叩いているドン・アライアスであるようです。そして、長い間この曲ではザヴィヌルに替わって、ラリー・ヤングがエレピで参加していると言われてきましたが(元々のライナーに書いてあったメンバー表でもそうなっている)、実際にはこの日も左チャンネルで弾いているのはザヴィヌルであったようです。 また、この曲では3日間のセッション中で唯一、ホランドがエレキ・ベースを弾いているようです。とは言え、延々と同じベースラインを弾き続けているのは、多分ハーヴェイ・ブルックスの方でしょうか。右チャンネルの奥の方で、(ベースとしては)高音域でいろいろと弾いているのがかすかに聞こえるのが、ホランドなのではないかと思います。 で、延々と続くベース・ラインと書きましたが、このリズム・パターンこそが"Miles Runs the Voodoo Down"という曲の最重要要素だと、言い切ってしまってよいでしょうか。この引き締まったラインに乗って、マイルス、ショーター、マクラフリン、コリアなどが、アルバムの全曲を見渡してもかなり素晴らしい方に属するソロを展開します。 尚、この曲は幾つかの部分に区切って録音がされた後、結局全曲を通して演奏したテイク(Take 9)がマスターとなったそうです。 ----- Miles Runs...の演奏履歴----- "Miles Runs the Voodoo Down"について、残っている音源としてはマイルスが演奏しているものは、下記の通りです。 この中で正規盤は7月25日の演奏と、この8月20日のスタジオ録音であるわけですが、7月時点の演奏ではホランドの弾くベースラインはかなり違った感じです。もっと自由に弾いている感じがしますね。それが秋のツアーでの演奏では、だいぶスタジオ録音でのそれに近い感じになっています。これは、ブルックスがバンドにもたらしたものだったのかも知れないですね。 ライブ録音のものと比べてもスタジオ録音のこの曲は、エキサイティングという面では一歩譲るとしても、はるかに無駄なところがない引き締まった演奏だと思うのですが、唯一残念なところはあのカッコいいオープニングのところが省略されていることです。 "Spanish Key" レコーディングもいよいよ最終日に入り、2日目は欠場したレニー・ホワイトが戻ってきました。そして、この日には3人目のエレピ奏者としてラリー・ヤングが参加します。 前に書いたように、今回リリースされた4枚組セットでは何曲かが数秒長くなっているのですが、この曲もその一つです。曲の最後で静かになって終わったところで、ジュマ・サントス(ジム・ライリー)のシェイカーがシャラシャラ〜と鳴って、マイルスが何かを言っている声までが収録されています。 また、この曲でもキーボード類の定位が、今回のセットではこれまでのものと大きく異なっているようです。僕の聴いたところ、ここでは意外とおとなしく右チャンネルで細かい音符を弾いているのがコリア、真ん中で狂ったように鍵盤を叩きつけているのがヤングだと思うのですが、ザヴィヌルの音はもうほとんど聞こえてきません。14分過ぎ辺りから3台のエレピがフィーチュアされるのですが、レギュラー盤(って言えばいいのか^^;)の方がよく聴くと3人の弾いていることが、はっきりと聞き取れるようです。 ドラムについては、トップシンバル中心にわりとジャズ的に叩いているのがディジョネットで、ハイハットとスネアを中心に細かめに叩いているのがレニー・ホワイトのようです。躍動的なベース・ライン(ブルックスという人はここで本領を発揮しているという感じがします)と共に、全2枚組中もっとも成功したテイクと言っていいかも知れません。ただ、バスクラのソロは結構カッコ悪いです^^;。 尚、トランペットやギターのソロが何回も出てくることから、複数のテイクをつなげたものかと思ってしまいますが、続けて最初から最後まで録音したテイク4が、そのままマスターになったようです。 "Pharaoh's Dance" アルバムではA面に収録されていますが、実際にはレコーディングがされたのは3日間のセッションの最後ということになります。 まず曲名について。「ファラオの踊り」というタイトルであるわけですが、これは、あのエジプトの王の呼称であった、ファラオのことでいいんでしょうかね。ジャズ界でファラオというと、我々は“ファラオ”・サンダースのことを思い出すわけですが、実際にはあの人はファロア(Pharoah)・サンダースというのが正しい名前だったりします。そのせい?かどうか分かりませんが、この曲名も"Pharoah's Dance"だと思っている人が多いようです。「ビッチェズ・ブリュー エレクトリック・マイルスのすべて」という、我が国におけるマイルス学^^;の権威であるところの中山康樹氏の著書に堂々と、そう表記してありますし、今回の特集に関してネタ^^;にさせてもらった、インターネット上のマイルス関係のサイトの幾つかでも、曲名はそうなっています。これは一体、どうしたことなんでしょうね? それはさておき、演奏については最早ああだこうだ能書きを並べられる域を超えているように思えます。ここで聴ける音は、まさに桃源郷のそれのようです。やっぱり、僕にとってはサウンドが比較的「イン・ア・サイレント・ウェイ」に近い、この曲がいちばんジャズ的に安心して聴けるようです。70年代マイルスのLPには、「このレコードは住宅事情の許すかぎり、ボリュームを上げて、お聴き下さい」なんて書いてあったりしましたが、この"Pharaoh's Dance"もまさにそれですね。いや、素晴らしい。特に16分40秒が経過した辺りからマイルスがテーマを吹き続けるところは、あまりのカッコ良さに気絶しそうになります(^^ゞ。 今回出た4枚組セットのライナーによると、この曲は超複雑な編集によって成り立っているようです。いや、聴いていればそれは分かりますね^^;。ところどころ、音のつなぎが不自然な箇所もありますし。 以前の書き込みで、今回のセットでは曲によっては長くなっている(フェイドアウトの箇所が少し後になっている)ものがあると言いましたが、この曲もその一つです。僕が以前から持っていたアメリカ盤のG2K40577という2枚組では、演奏時間が19分57秒になっていたところ、今回の4枚組では20分05秒になっています。しかし、よく聴いてみると、相違点は最後が長くなっただけではないようです。 最後の部分で(誰が弾いているのかよく分かりませんが)エレキピアノで、ドードーシーソーラーラーソーミーと下降してくる印象的な楽句があるのですが、以前のものでは19分40秒ぐらいから始まっていたわけです。それで、それが終わるとすぐにフェイドアウトしているのですが、今回新しく編集したものでは19分34秒ごろに始まり(つまり始まるのが早い)、そのフレーズが終わった後にも少しあって、それで最終的に長く時間的にかかっているんですね。ということはつまり、途中が短くなっている、ということを意味しているわけです。 そんなわけで、4枚組セットのブックレット129-130ページのタイムチャートを眺めながら、以前のものを聴いてみたところ、もっとも顕著に違うのがPart 2の始まる直前の、Vamp#1と呼ばれている箇所であるようです。ここは編集に無理がある箇所で、Vamp#1の頭で拍子がひっくり返ったようになるのですが、ここをこらえて^^;小節数を数えていくと、(元の方では)Vamp#1は27小節あって、正確には27小節目の3拍目と4拍目はパウゼのようになっていて、28小節目の頭がバーンとPart 2の始まりとなっていますが、“新編集版”では26小節目の引っかけ(アウフタクト)からPart 2が始まってます。 この部分の差異だけでは6秒も違いが出ないので、他の箇所でも少し異なる部分があるのかも知れませんが、あとはきちんと検証する元気が出ませんでした(苦笑)。 いずれにしても、今回のセットではオリジナル発売時のマスターを使ったのではなく、元のraw materialを当時編集したのと同じように、最新の技術を使って再現するという方法を採っているようで、それだけにこの"Pharaoh's Dance"のような複雑な編集を施したものでは、若干のずれが生じてくるのは致し方ないかも知れません。 -----これでおしまい----- さて今回の「ビッチェズ・ブリュー」特集ですが、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は調べものをしながら、いろいろと勉強になることや発見もありました。 やり始めてから気がついたのですが、今年はこのアルバムが録音されてから30周年という年に当たるのでした。そう考えると、改めて聴き直してみても、依然として古さをほとんど感じさせないことに、驚きの念を隠せません。うまく言葉に表現することができませんが、このヒューマンなサウンドが、年月を越えて聴き手に何かを伝えるのでしょう。その意味では、この響きを触媒として、聴き手は何かを自ら体験することになると言えます。音楽とは皆、本来そういったものであると思いますが、このアルバムほどにそれを強く感じさせるものも少ないと感じます。 では、この会議室で特集を担当するときはいつも言ってますが、ここを読んで新しく出た4枚組セットを買って聴いてみようという人が、5人ぐらいはいるといいな、と思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| text by TAKE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||