| 発 表 者 | 概 要 | |
| 発 表 1 |
名古屋市立港南中学校 濱地 光大 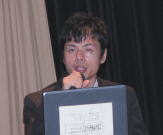 |
「わかった!」と思える理科学習 〜学びを生かした話し合い活動を通して〜 |
| 単元 電流とその利用(中2) 研究のねらい 論理的な思考力が,さまざまな状況において自分のすべきことを判断する力を高め,生徒の日常生活にも生きると考える。そこで,理科学習を通して得た情報を整理し,論理的に考えることができる生徒の育成を目指した。 基本的な考え方 学習においてある程度知識を身につけた後,生徒が「なぜだろう?」と思うような不思議な事象を提示する。知識が身についた生徒は,簡単には説明できない事象に出会うと,学んだ知識を生かして考察することができるようになると考えた。 また,考察の場面で論点を絞った話し合い活動を行えば,既習の学習内容についての不足を補ったり,考察を深めたりすることができると考えた。本研究を通して,実験結果を基に結論を見いだし「分かった!」と思える生徒の育成を目指す。 手立て ① 学びを生かす場面の設定 ② 論点を絞った話し合い活動 実践の流れ ① 静電気を電子の動きで考えよう 静電気の学習の後に電子の動きを考える事象を提示する。 ② 電磁誘導による不思議な現象を調べよう 電磁誘導の学習の後に,導線を使わずに電磁誘導を起こす事象を提示する。 成 果 ◎学んだことを生かす場面を設定し,論点を絞って話し合いを行うことは,実験結果を基に結論を見いだす力を高めるのに有効である。 ○学習過程の中に学びを生かす場面を設定することによって,目の前の不思議な事象に驚くだけだた生徒が,身に付けた知識を基に実験の仕組みを考察できるようになった。 ○論点を絞った話し合い活動を行ったことによって,考察を深められるようになった。 |
||
| 発 表 2 |
名古屋市立明豊中学校 安武 宏  |
生徒の見方や考え方を変容させる理科学習 |
| 単元 細胞と生物のふえ方(中3) 研究のねらい 単元で扱う自然現象に対する生徒の見方や考え方を表出させ,生徒自身にそれを認識させながら学習を進めていきたいと考えた。そして,授業で学習した内容の確実な定着を図る中で,生徒なりの見方や考え方を修正したり,補強したりして,少しずつより適切で確かなものへと変容させていきたいと考えた。 基本的な考え方 ① 見方や考え方を「調査問題」で表出させる 学習の各段階(単元の始め,中間,終わり)で,単なる知識量を問うものではなく,見方や考え方問う調査問題を取り入れることで,生徒なりの見方や考え方を表出させやすくしたい。 ② 見方や考え方を「学びのあしあと」で修正・補強する ○単元の始めから終わりにかけて,自分の見方や考え方がどのように修正されたり,補強されたりしていったかを,一目で感じ取ることができる。 ○学習したことが確実に定着していない生徒が,手軽に要点のまとめを確認することができ,調査問題を解く手がかりとして活用するとことができる。 ③ 見方や考え方を「身近な事象」で応用する 授業を通して変容した見方や考え方が,日常生活で見られる身近な事象の説明にも通用することを実感させるために,単元の最後に身近な事象を教材とし,見方や考え方を応用する活動を行う。 成 果 ○調査問題により,学習の各段階で生徒の見方や考え方を可視化できる形で表出させたことで,一人一人異なる見方や考え方をもつ生徒に,自らの見方や考え方が授業を通してどのように変容していったかを感じ取らせることができた。 ○学習履歴として一目で見渡すことができる「学びのあしあと」に,生徒自身に要点の再まとめをさせたことにより,単元で学習する語句や用語について,その意味や関連も含めた理解へとつなげることができた。 ○見方や考え方を応用する場面で,今回は身近で手で触れるトウモロコシを教材にし,検証実験の形で取り組ませることができたことで,学習した内容についての理解がさらに深まった。 |
||
| 発 表 3 |
名古屋市立常磐小学校 宇佐美宏幸 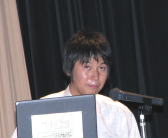 |
追究意欲あふれる子どもが育つ理科学習 |
| 単元 植物の育ち方・こん虫をしらべよう・こん虫をさらにしらべよう(小3) 研究のねらい 疑問を追究する楽しさを実感し,進んで学習に取り組むことのできる子どもを育てていきたい。三年生で学習する昆虫や植物の成長のきまりや体のつくりについての学習では,観察を通して生まれた気付きや疑問を進んで追究する楽しさを,ぜひ子どもに味わわせたい。 基本的な考え方 観察にゲームの要素を取り入れることで集中力が高まり,今まで以上にしっかりと観察できると考える。その上で,子どもに観察の観点を与えることと,観察しながら気付きや疑問について意見交換できるようにすることの2点を手立てにする。 ① 観察の観点を与える 子葉が生えたオクラとホウセンカを見分けるゲームなど,ゲーム性を取り入れることで観察の観点を与える。 ② 観察しながら気付きや疑問について意見交換できるようにする 生き物をあらゆる角度から観察できて,観察しながら気付きや疑問の意見交換ができるような教具(ヘキサゴンレンズ)を用い,子どもが新たな気付きや疑問を数多く生み出せるようにした。 ※ヘキサゴンレンズ フレネルレンズを6枚つなぎ合わせて六角形をつくり,その中に昆虫など観察物を入れると,360度の視野で,拡大させた像が観察できる。ヘキサゴンレンズという名前は,本研究における独自の呼び名であり,商品名ではない。 成 果 ○葉の葉脈や毛に対して,形をよく見て気付きや疑問が書けていたことから,観点を意識して観察ができた。 ○観察にゲームの要素を取り入れて,観察の観点を与えることと,観察しながら気付きや疑問について意見交換ができるようにしたことにより,気付きや疑問を数多く生み出すことができる児童の育成ができた。 ○追究することの楽しさを味わった子どもは,真剣な表情で観察や図鑑による調べ学習に取り組めるようになった。 |
||
| 発 表 4 |
名古屋市立ほのか小学校 西谷 一孝 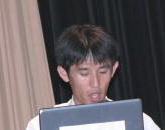 |
気象現象について確かな考えをもつ理科学習 〜高層ビルにかかる雲をきっかけに〜 |
| 単元 天気と情報(小5) 研究のねらい 雲に対する見方を深めるには,画像や動画の活用だけでは不十分であると考える。そこで,地域にある高層ビルにかかる雲を利用することで,雲に対する見方やとらえ方を高め,気象現象に対する確かな考えをもたせようと考え実践に取り組んだ。 基本的な考え方 高層ビルにかかる雲を利用することで,次のような効果が得られると考える。 ○雲を外側から観察するだけでなく,雲の中に入って観察・実験が行える。 ○普段雲を見るときは,下からの目線である。それが上空からの目線へと視点を移動し,実際の雲と雲画像を結びつける活動ができる。 これらの活動を通して,雲に対する見方やとらえ方が高まり,気象現象についての確かな考えをもたせることができると考える。 単元構成 ① 晴れと雨のときの雲の違いについて考えよう 雲があっても雨が降らないときがある。雨が降るときの雲と違いがあるのかな? ② 雲について考えよう 雲について調べるとしたらどんなことをしたいかな? ③ 高層ビルにかかる雲を調べよう ④ 実験から分かることを考えよう ⑤ 高層ビルの上空のようすを考えよう ⑥ 天気と情報(2) 雲画像を活用した学習 成 果 ○身近な自然現象として,高層ビルにかかる雲を活用したことにより,雲は水の粒が浮いたものが動いてくるという考えをもち,雲に対する見方を高めることができた。 ○高層ビルの高層部から,さらに上空に視点を移動させていく活動をすることで,自分たちの見ている雲は,大きな雲の一部であることや,宇宙から見ると広い範囲の雲が見えるという考えをもち,雲に対するとらえ方を高めることができた。 |
