

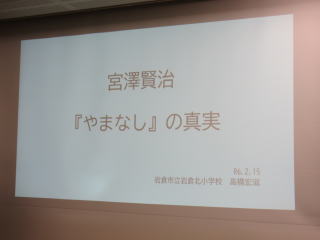

今年のシーズンオフシリーズが始まりました。
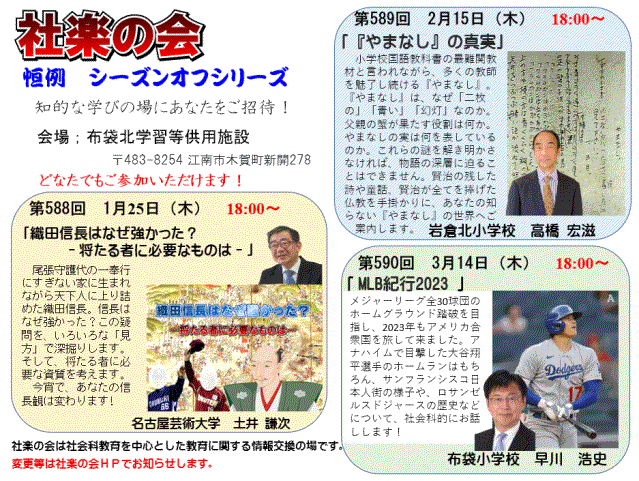
1 東京学芸大学附属小金井小学校KOGANEI授業セミナー ICT部会
令和6年2月3日(土)KOGANEI授業セミナーにお参加しました。
社会科は、こうした研究会には珍しい学習計画を立てるところ。あまり見たことがないので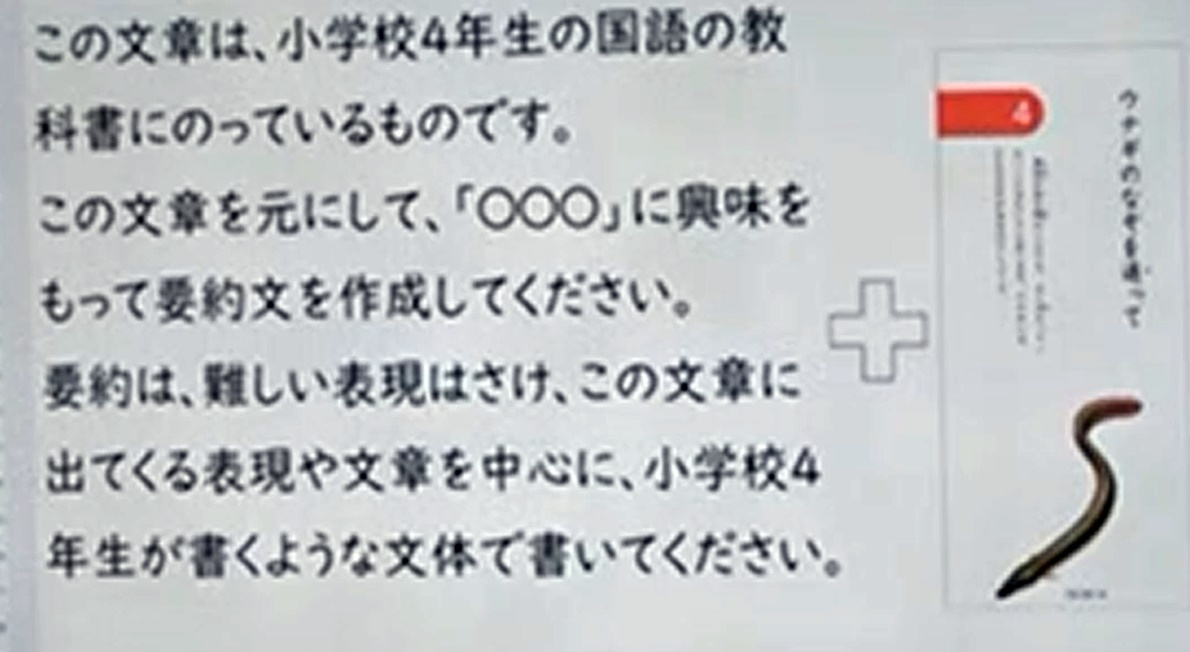 興味はありましたが、あえて4年生国語の鈴木先生の授業(ICT部会)を見ました。
興味はありましたが、あえて4年生国語の鈴木先生の授業(ICT部会)を見ました。
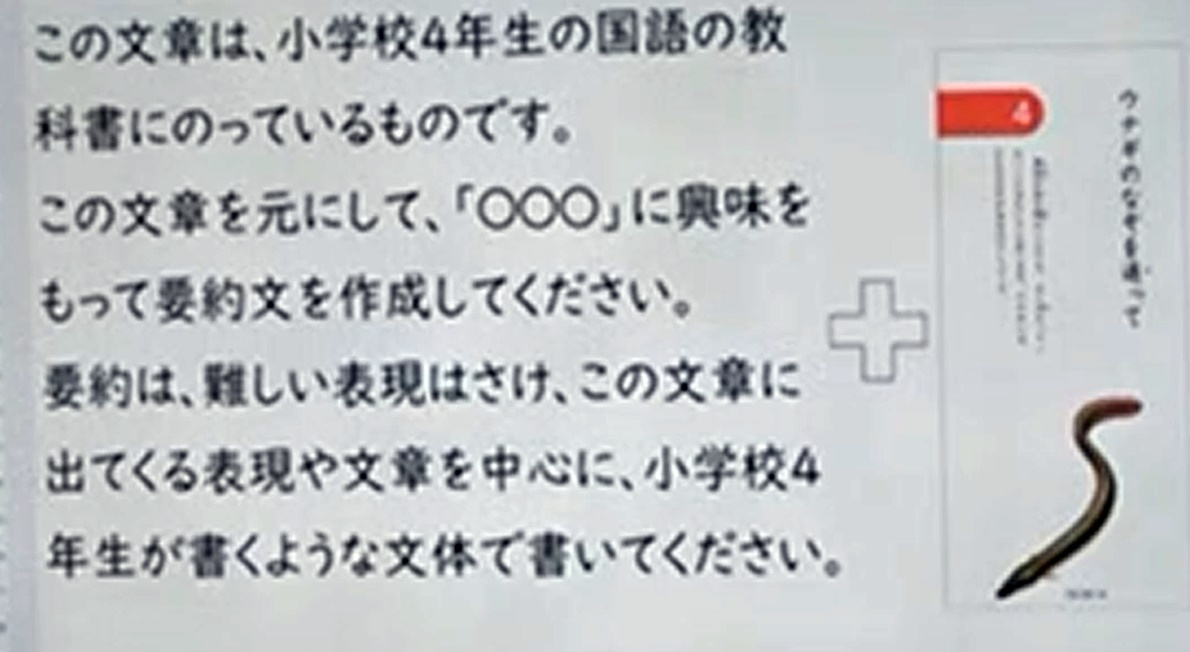 興味はありましたが、あえて4年生国語の鈴木先生の授業(ICT部会)を見ました。
興味はありましたが、あえて4年生国語の鈴木先生の授業(ICT部会)を見ました。
あらかじめ異なったプロンプトによる3種類の生成AIの要約文を見て、それぞれのプロンプトを考え、自分の要約文は何を大事にしているのかを考えるというものです。右がそのプロンプトで、〇〇〇には、教科書の「文章への着目の仕方の例」を使っています。
基本的な立ち位置は、あくまでも生成AIは不完全であり、批判的に創造することを目的にしていると感じました。 私がよくやるのは、「生成AIのこの回答は70点です。100点に近づけるように考えてください」と同じような発想です。
もう1人のICT部会の小池先生では驚きの場面がありました。それは口頭で・・・・。
2人の指導案と、社会科清水先生の指導案を添付します。
2 愛知の街道を行く シリーズ1「宮宿」
2024年1月27日(土)、栄中日文化センター主催、「愛知の街道を行く シリーズ1」「宮宿」へ行ってきました。 講師は、七種英康先生です。今回のルートです。左やや下の宮から右下の「桜」駅の近くまで歩きます。
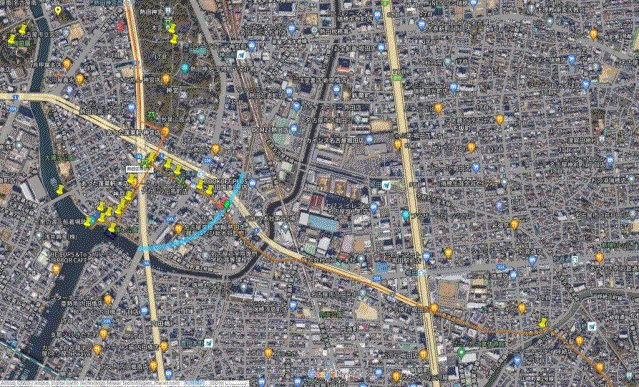 詳しくはhttps://blog.goo.ne.jp/syaraku0812/e/4992812908b032ef01eab62caea61ba0 をご覧ください。6回にわかって説明しました。
詳しくはhttps://blog.goo.ne.jp/syaraku0812/e/4992812908b032ef01eab62caea61ba0 をご覧ください。6回にわかって説明しました。
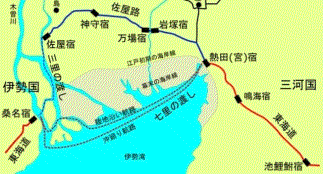 第1回;七里の渡しの概要、誰が陸路を作っ たのか?どれぐらいの人が海路を選んだの か?など
第1回;七里の渡しの概要、誰が陸路を作っ たのか?どれぐらいの人が海路を選んだの か?など
第2回;この辺りの地形は?古代から江戸時 代まで。宮宿周辺の様子。旅籠屋・伊勢久、 熱田荘
第3回;西浜御殿跡、宝勝院。あつた蓬莱軒「蓬莱陣屋(赤本陣跡)」、源太夫社(上知我麻神社)、ほうろく地蔵、など
第4回;伝馬町、徳川家康幼時幽居地(羽城)、裁断橋跡、伝馬町一里塚、鈴之御前社、ほか
第5回;法泉寺、山崎城跡・安泰寺、山崎の長坂
第6回;熊野三社、松巨嶋、鎌倉街道、白毫寺「年魚市潟景勝の地」の石碑」、
次回のは2月25日に、笠寺を経て鳴海塾へ向かいます。
3 水軍の城・大野城と知多の名城・大草城へ
2024年2月10日(土)、栄中日文化センター主催、「歩いて巡る愛知の古城と史跡」シリーズ「水軍の城・大野城と知多の名城・大草城へ」へ行ってきました。 講師は、七種英康先生です。今回の訪問地は次。0;名鉄大野町駅 ①齋年寺 ?大野城 ③蓮台寺 ④大草城
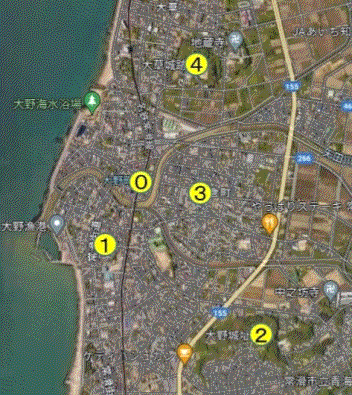
①齋年寺
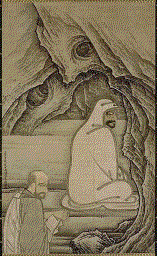 斉年寺は、曹洞宗の寺院で、大野城主佐治家の菩提寺です。佐治家は、大野水軍、あるいは、常滑焼などの水運で織田家を支えました。
斉年寺は、曹洞宗の寺院で、大野城主佐治家の菩提寺です。佐治家は、大野水軍、あるいは、常滑焼などの水運で織田家を支えました。
寺宝に、雪洲の国指定重要文化財の「達磨大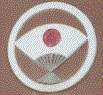 師二祖慧可断臂図(えかだんぴず)」
師二祖慧可断臂図(えかだんぴず)」
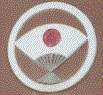 師二祖慧可断臂図(えかだんぴず)」
師二祖慧可断臂図(えかだんぴず)」
寺紋は扇紋です。
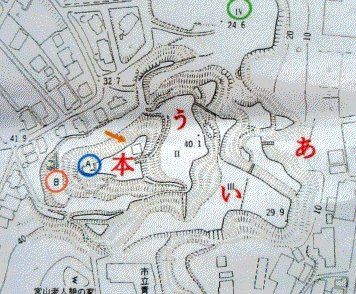 ?大野城
?大野城
大野城は、知多半島の水運を担った佐治氏の城。今回の主人公、佐治一成(さじ-かずなり)は戦国時代の武将で佐治信方の嫡男として1569年に生まれました。そして、お市の3人娘の末っ子お江の最初の勤め先です。。
母はお犬の方(織田信長の妹)。織田信秀は佐治家に娘を嫁に出しているので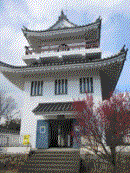 す。
す。
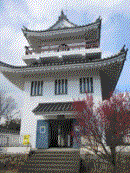 す。
す。
展望台は当時のものを再現したものではありません。
櫓があったところ に佐治神社がありました。佐治一成の像がありました。
に佐治神社がありました。佐治一成の像がありました。
 に佐治神社がありました。佐治一成の像がありました。
に佐治神社がありました。佐治一成の像がありました。
ちなみに、師崎の千賀水軍は、 佐治氏から養子に行った千賀 重親 が家を大きくしています。
佐治氏から養子に行った千賀 重親 が家を大きくしています。
 佐治氏から養子に行った千賀 重親 が家を大きくしています。
佐治氏から養子に行った千賀 重親 が家を大きくしています。
これが千賀水軍の家紋。やはり扇紋ですが、骨の本数が違います。
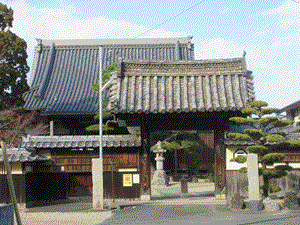 ③蓮台寺
③蓮台寺
境内には江戸幕府二代将軍・徳川秀忠の正室、江の最初の嫁ぎ先である佐治氏の初代大野城主・佐治宗貞のお墓「寿山塚」があります。
大野城の落城で江が逃げ落ちる際に自害を装ったとされる衣掛けの松は枯れました。身を投げた振りをした井戸は今でもあります。
④大草城
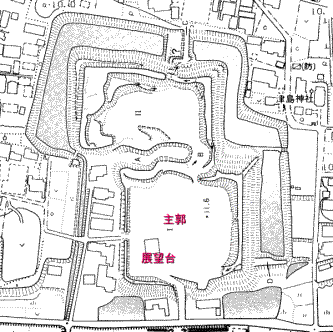 大草城は、織田信長の弟で、後に茶人としても名を挙げた源五長益(有楽斎)が、築城しようとして途中で断念した”幻の城です。大野谷を拝領していた長益は、大草の地に城を築き始めました。しかし、天正十年に本能寺の変で信長が暗殺され、長益も天正十二年の長久手の合戦後、しばらくして秀吉に仕え、摂津国味舌に転封されました。お伽衆に選ばれたからです。このため、地形(ちぎょう)などの普請が大体終わったところで放棄され、廃城となり、幻の城と呼ばれるようになりまた。
大草城は、織田信長の弟で、後に茶人としても名を挙げた源五長益(有楽斎)が、築城しようとして途中で断念した”幻の城です。大野谷を拝領していた長益は、大草の地に城を築き始めました。しかし、天正十年に本能寺の変で信長が暗殺され、長益も天正十二年の長久手の合戦後、しばらくして秀吉に仕え、摂津国味舌に転封されました。お伽衆に選ばれたからです。このため、地形(ちぎょう)などの普請が大体終わったところで放棄され、廃城となり、幻の城と呼ばれるようになりまた。
現在、大草城址は、本丸、二の丸と周囲の土塁、堀の大部分が、ほぼ完全な形で残っており、このような城址は愛知県下でも数が少ないのです。このように保存状態がよいのは、尾張藩の徳川義直、光友に仕えた重臣、山澄淡路守英龍が大草を給知され、保存したから。感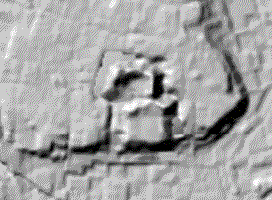
 謝です。
謝です。
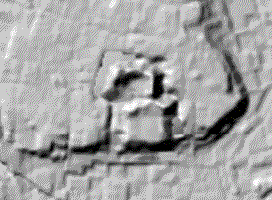
 謝です。
謝です。
何がすごいのか?
地理院地図で見ると、台形の上部の平らなところに作られていることがわかります。すなわち、堀を掘って土塁を造ったのです。
すなわち、下の黄色の部分を掘って、左の土塁を盛り上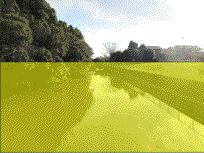
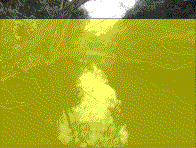 げたのです。これは西部の浅い堀で、東部では、もっと深くなっています。重機がない時代です。どうやったのでしょうか?
げたのです。これは西部の浅い堀で、東部では、もっと深くなっています。重機がない時代です。どうやったのでしょうか?
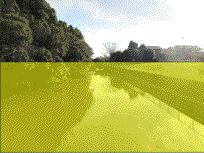
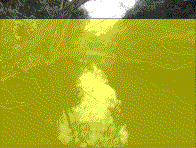 げたのです。これは西部の浅い堀で、東部では、もっと深くなっています。重機がない時代です。どうやったのでしょうか?
げたのです。これは西部の浅い堀で、東部では、もっと深くなっています。重機がない時代です。どうやったのでしょうか?
とにかくすごい城跡でした。
詳しくは、私のブログをご覧ください。
次回は犬山城を深掘りします。