 |
 |
 |
 |
|---|
1 城東中学校現職教育に伺いました
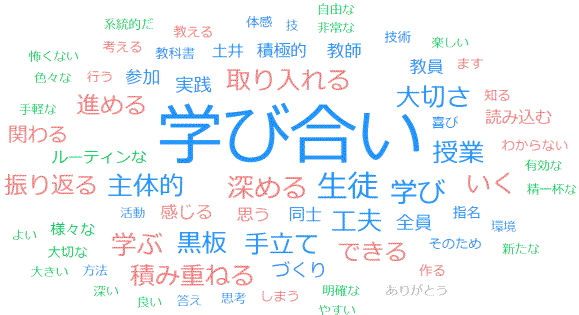
2 テキストマイニングの活用
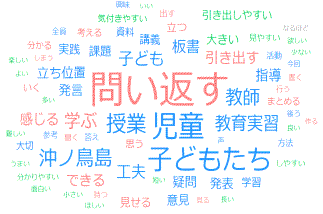
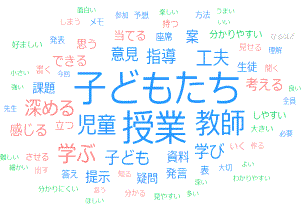
3 東海道 有松~富士松FW
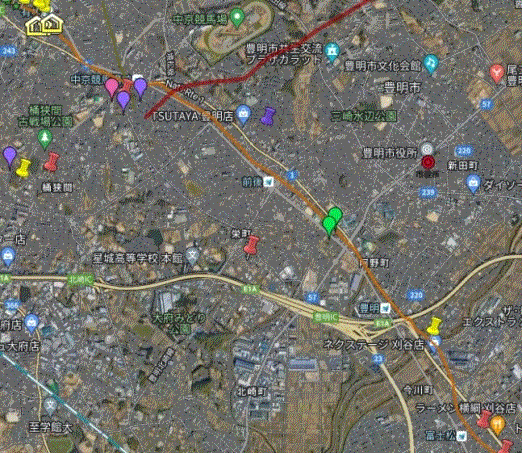
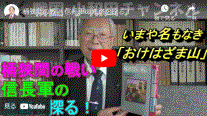 小和田先生は,次の動画で明確に言っておみえです。
小和田先生は,次の動画で明確に言っておみえです。
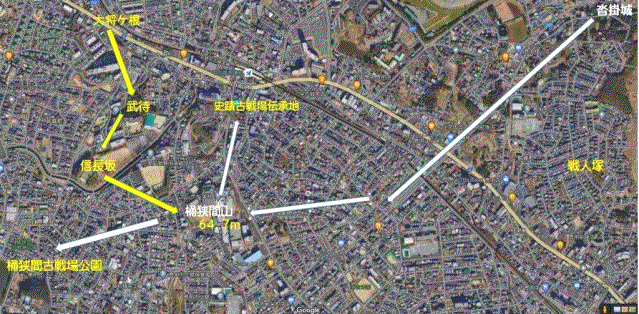 阿野一里塚
阿野一里塚
 旧東海道の一里塚で、慶長9年(1604年)、徳川家康の命により、街道の両側に一里ごとに設けられました。
旧東海道の一里塚で、慶長9年(1604年)、徳川家康の命により、街道の両側に一里ごとに設けられました。
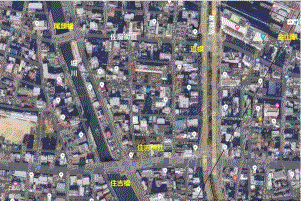
 日置橋 納屋橋
日置橋 納屋橋
 伝馬橋(清州から移築)・中橋
伝馬橋(清州から移築)・中橋  五条橋(清州から移築)
五条橋(清州から移築)
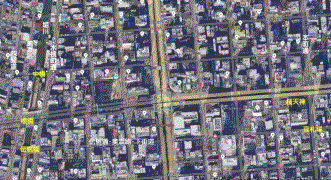 この川沿いには、多くの史跡が残っています。み
この川沿いには、多くの史跡が残っています。み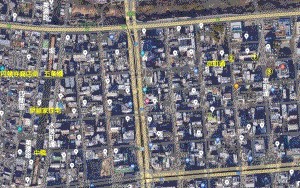 なさんも歩いてみてください。
なさんも歩いてみてください。
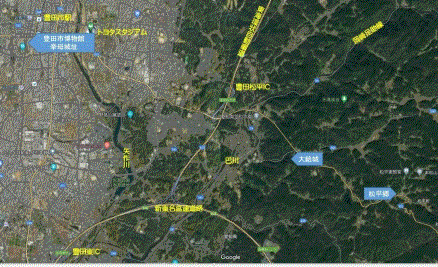
5 大給城~松平郷FW
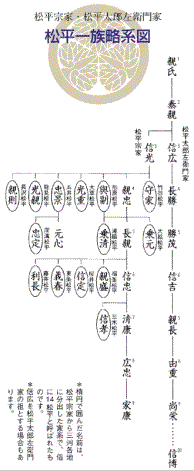 5月5日に、豊田市の大給城、
5月5日に、豊田市の大給城、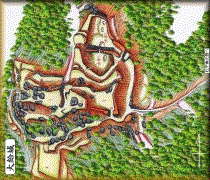
「ともに学ぶ」というテーマのもと、60分に詰め込んで行いました。
感想をいただきました。
驚きの連続で、非常に学びがあった1時間でした。最も印象に残った点は、「学びに向かう力」はわからないときに、自分で聞きに行けることを指しているということです。全員参加の授業を作るうえで、少しでも子どもたちが周りの級友に尋ねることができる瞬間を教員が設けていきたいと考えました。
授業の中のすこし工夫を凝らすことによって、生徒の学びが深さが大きく変わってくるということを改めて感じました。特に生徒を指名する際に、挙手ではなく意図を持って指名することで多くのメリットがあるということを理解することができたので、すぐに実践していきたいです。 など
みなさんの感想のマイニングです。
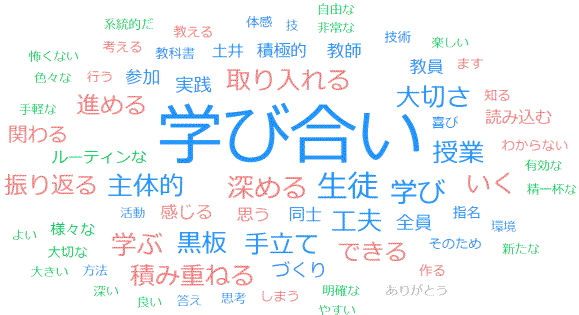
2 テキストマイニングの活用
テキストマイニングアプリは、有料版ではいろいろありますが、たいへん高価です。無料版では、研究用に作られたものがありますが、あくまでも研究用。簡単に使えるのは、上記で利用したユーザーローカル テキストマイニングツールhttps://textmining.userlocal.jp/ のみです。
では、そのメリットは?
私は、「振り返りの振り返り」に活用しています。振り返りは、やりっ放しではもったいない。しかし、全員の振り返りを取り上げるのは時間的にも不可能。そこで、全員の振り返りのマイニングに、ある人の振り返りの抜粋を例に説明しています。
初等社会科教育法、第4回の授業の振り返りをマイニングしてみました。全く同じ授業内容ですが、大学4年生、3年生のものですです。どちらが4年生の振り返りでしょうか?
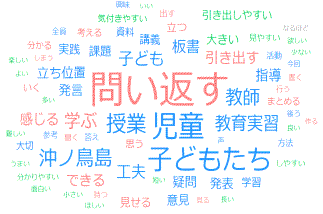
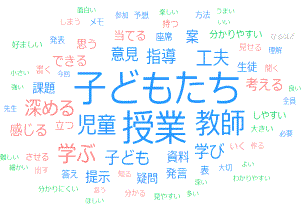
他の活用法を考えてみましょう・・・・
| 導入に使う 疑問をマイニング 学級目標 道徳的価値のはじめと変容後を比較 単元の始めと終わりを比較 言葉の解釈 |
3 東海道 有松~富士松FW
今回のルートです。前回のゴール有松駅(左上)から富士松駅(右下)までオレンジ色の線を歩きました。https://blog.goo.ne.jp/syaraku0812/e/be9c5fefdeef55a21684b639f6b115af
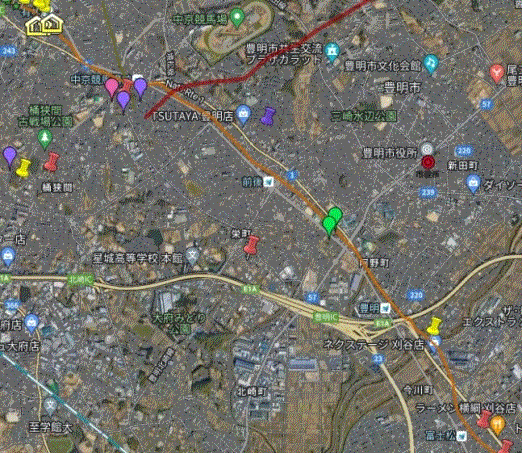
有松駅→有松宿(橋本家等)
→ 大将ケ根→豊明側の「史蹟 桶狭間古戦場 伝説地」
桶狭間古戦場 は 名古屋市緑区「桶狭間」・ 豊明市「南舘」のどっち?
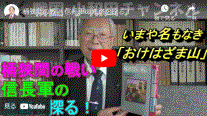 小和田先生は,次の動画で明確に言っておみえです。
小和田先生は,次の動画で明確に言っておみえです。
信長軍は、中島砦を出て、ほぼ(後の)東海道を東進し、「大将ケ根」を南進し、武待で待機します。
今川軍は、前日泊まった沓掛城を出て、「桶狭間山」と思われるホシザキ電気の高台で休憩しています。
ここで、雨がやみ、義元の居所をつかんだ信長軍が、信長坂を駆け上がり、桶狭間山を急襲します。北へ逃げる兵、西の大高城へ向かう兵、来た道を引き返す兵などバラバラになります。
そこで、北へ逃げる兵と戦ったのが「史蹟 古戦場伝説地」、西へ向かう兵と戦ったのが「古戦場公園」、戻る兵を襲ったのが「戦人塚」の辺りと考えるとしっくりきます。
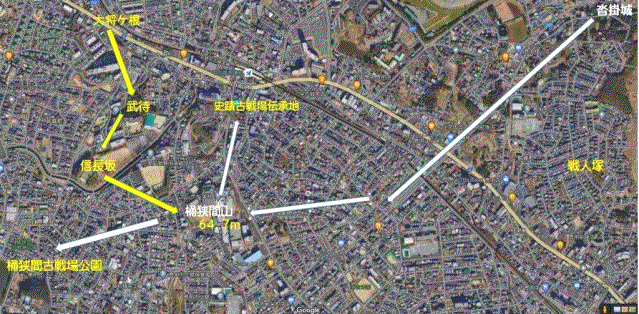 阿野一里塚
阿野一里塚
 旧東海道の一里塚で、慶長9年(1604年)、徳川家康の命により、街道の両側に一里ごとに設けられました。
旧東海道の一里塚で、慶長9年(1604年)、徳川家康の命により、街道の両側に一里ごとに設けられました。
現在も道の両側に塚が残っているのは全国でも珍しく、貴重な史跡で「国指定史跡」になっています。
そのほかはブログをご覧ください。
堀川七橋とは、家康がつくった名古屋の街に、堀川に架けた七つの橋です。
尾頭橋 古渡橋
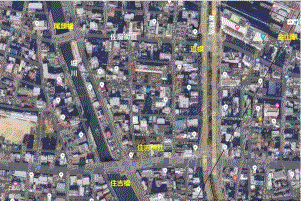
 日置橋 納屋橋
日置橋 納屋橋
 伝馬橋(清州から移築)・中橋
伝馬橋(清州から移築)・中橋  五条橋(清州から移築)
五条橋(清州から移築)
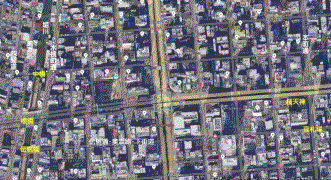 この川沿いには、多くの史跡が残っています。み
この川沿いには、多くの史跡が残っています。み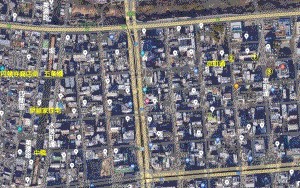 なさんも歩いてみてください。
なさんも歩いてみてください。
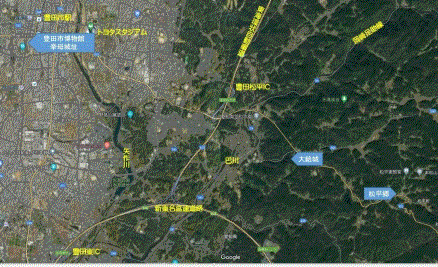
5 大給城~松平郷FW
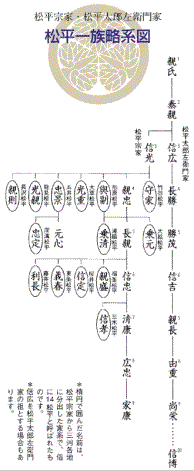 5月5日に、豊田市の大給城、
5月5日に、豊田市の大給城、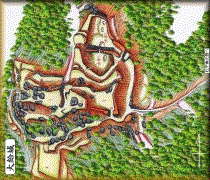
松平郷(松平東照宮、高月院等)、
野見山展望台、豊田市博物館、挙母城祉を訪ねました。
大給城は山全体が花崗岩でできており、土塁ではなく石塁で、
ロック式ダムのような水曲輪には驚きです。