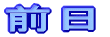

7月22日(金)
この日は成田で集合のため、自宅から新幹線で成田へ向かった。以下、新幹線車中でのモバイルでの記録である。
人民元切り上げ
出発当日の朝、いきなりの大ニュースが飛び込んできた。
人民元の切り上げだ。今回はまだ2.1%だが、今後段階的に上がっていくことだろう。
日経新聞がこの記事に8ページ割いているところを見ると、ある程度事前に予想されていたことだろうが、大方の人には意外であったに違いない。胡首相が訪米する9月に向けて行われるだろうという予測よりも、ひと月は早かったようだ。
素人判断だが、これは、対中ODAにも大きな影響を与えるだろうと思われる。
1971年のニクソンショックの時は、一度に17%近く円が切り上げられ、日本の産業が大打撃をくらった。それ以後も円高が続き、360円が100円前後にまで至った。人民元についても、ゴールドマン・サックスのジム・オニール・グローバル経済調査部長が「長期的には元はドルに対し、三倍に切り上がるだろう」と予測する。(日経7月22日11p)
ではどうするか。日本のニクソンショック後の動きを見れば予測ができる。
日本が急激な円高に対応できたのは、技術力のおかげである。それは中国政府もよくわかっているだろう。しかし、それを今の中国に求めるのは酷である。本質的に、中国は他国の真似はうまいが、創造力を育成するシステムは十分ではないようだ。創造力は自由な体制と、公正な競争力の中でこそ伸びるものと考えている。今の中国は、現在でも知的所有権に多くの部分が抵触している。
今後、日本の取るべき道は、中国の創造力の向上のためのシステム作りとそのための人材交流であろう。
中国のこれまでの競争力 は、ただただ人件費の安さに頼ってきた。中国国民は元来器用な人たちである。それは土産物を見ればわかる。両面刺繍やコルク細工などの細密な加工は驚きだ。20年前、バスの運転手が、隣の車と1センチの距離をすれ違うテクニックにも驚いた。この中国人が競争力を身につければ、価格が上昇しても売れるだけの付加価値のある商品の生産は可能であると考える。
が、そのためには、繰り返すが、自由な研究体制と競争するシステムが必要だ。後者は、かなり進んではいるが、前者は政治体制にも関わる根本的な問題につながる。今後の中国には目が離せない。その生きた手本は、日本である。
人民元切り上げに関するサイトはいくつもあるが、『人民元切り上げ』について考える を見ていただきたい。
資料 中国人の平均収入
日本ではよく「大卒の初任給」や「39歳妻、子2人」の給与などと給与水準を表現するが、中国では地域や職種により格差が大きすぎるため、一概に表現できない。ただ、対中国を語る時には必要なデータなので、参考のために読売新聞シリーズ「膨脹中国」より、次の記事を紹介したい。(H17.8.19 6面)
「昨年の都市人口の1人あたりの所得は、9,422元(1元は約14円)なのに対し、農民の収入は2,936元で、3分の1以下になっている。」
さらに、〈中国の省別農村住民収入 −1人あたり、2003年−〉として、次の数字が載っている。
上海6,653元 北京5,601元 浙江省5,389元 広東省4,054元
青海省1,794元 甘粛省1,673元 貴州省1,564元
これはあくまで平均である。それぞれに、裕福な人もいれば、さらに貧しい人もいる。その貧富の差は、数十倍になるといわれている。
|
以下、訪問にあたって思うことを書き並べてみる。
日中関係とODA
ODAモニター第1期は、中国、パキスタン、パプアニューギニアの3カ国で実施される。個人的にはどこも魅力的であり、希望地を指定しなかったところ、中国に決まった。 中国のページ(外務省)
ところが、決定してから、改めてODA問題の根深さ、複雑さを思い知らされた。
・ 政府与党を中心に中国向け円借款の廃止論が高まっていること。どうも2008年で終わりらしい。
・ ODAの対国民総生産(GNP)比0・7%が国連常任理事国入りの条件のように言われていること。
・ 町村外相が、靖国問題に関して、「赤字国債を出してまでODAにお金を出している」と発言。
それに対して、中国外務省の劉建超副報道局長が「経済援助を理由に過去の歴史を抹殺することはできない」と反論。
・ 何より北京や上海で起こった対日暴動
・ そもそも屈指の外貨保有高を誇り、有人宇宙飛行を行う力のある国に援助が必要か?
先のサミットで、小泉首相は、今後5年間でODA(政府開発援助)の100億ドル増額、アフリカ向け援助の3年間での倍増を約束した。日本の常任理事国入りのために、アフリカ諸国の支持を得るためでもある。
一方、中国は日本の常任理事国入りに反対している。
政治とODAは切り離して考えるべきものかどうなのか、そして、国民が納得する使い道なのかをじっくりと見極めたい。
対中ODA実績概要 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/kunibetsu/china.html
永続可能なODAへ
ODAは自助努力をうながすものでなければならないと言われている。よく援助の世界では「千匹の魚を与えるより、一匹の魚の釣り方を教えよ」と言う。対中ODAが、税金のばらまきか、それとも自助努力をうながし、永続可能か、これも自分の目で見極めたい。
顔が見える国際貢献を
国際貢献というと思い出されるのがイラクのクェート侵攻である。日本は、多国籍軍に130億ドルの資金を出しながら、クェートのNYTの感謝の記事に日本の名前がなかったのは有名な話だ。(それがPKO法の成立につながった。)
貢献とは、やはり顔が見えないといけないことを日本はその時に学んだ。
日本の対中ODAは顔が見えるのか、見てみたい。顔とは、軍事力だけではない。
モニター派遣制度の意味
今回モニターとして派遣されるメンバーは、1,844名から選ばれたとあって、さすがに強者ばかりである。それぞれ個性豊かで、それぞれにキャリア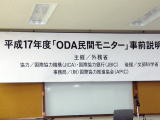 があり、会話を交わすだけでもおもしろい。そんなメンバーが、それぞれ感じたことをまとめる。行く前から、「あの人はどんな感想を持つのだろう。この人は、ODAをどうとらえるのだろう」などと考えると、今から楽しみである。それぞれ、異なる人生があり、当然見方・考え方が異なる。
があり、会話を交わすだけでもおもしろい。そんなメンバーが、それぞれ感じたことをまとめる。行く前から、「あの人はどんな感想を持つのだろう。この人は、ODAをどうとらえるのだろう」などと考えると、今から楽しみである。それぞれ、異なる人生があり、当然見方・考え方が異なる。
しかも、全員ODAに関しては素人である。今回は、素人だから見えるものを大切にしたいと思っている。
中日新聞の小出元編集局長は、次のように言っている。
記者とは、永遠に素人であることが専門なのかもしれない。戦争を取材しても軍人ではないし、宮内庁を担当しても皇族ではなく、首相官邸を回っても政治家ではない。こうした専門領域に、素人の目線でタマを投げることが任務であるからだ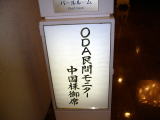 ろう。
ろう。
素人について、夏目漱石がこんなことを言っている。
どんな物事でも、人間はまず全体の輪郭を見る。そこから、玄人と称する専門家は局所を観察して、細部に至る。細かくなればなるほど、全体の輪郭を離れる。離れることは、忘れることだ。
対照的に素人は、全体の輪郭を決して離れない。ジャーナリズムの根幹だと思う。
出展 http://www.chunichi.co.jp/00/desk/20050625/col_____desk____000.shtml (現在リンク切れ)
素人だから、素直に見えるものを見る。純粋に見るから、おかしいものに対しては素直におかしいと言える。素直に見たものを、このHP上で伝えたい。
個人的な中国に対する思い
中国へは1985年にオーケストラの一員として上海と南京で演奏して以来、実に20年ぶりである。この20年間の中国は、名目GDPが9千億元から12兆元と十数倍に伸びるなど、その成長のすさまじさは言うまでもない。。
当時は、まだレジャーも少なく、我々の演奏会にも3,000人収容のホールがびっしり立ち見客で埋まったことを記憶している。バスは8円、ラーメンは30円ほどだった。
成長した20年後の中国をこの目で見ることができるのも楽しみだが、今回は前回行けなかったところばかりであるので、さらに興味深い。北京と地方の生活レベルの違いにも注目したい。
さて、中国に対してどのような気持ちで臨むか。
私のベクトルは、あくまで「日中友好」の方向でありたい。この方向を向きながら、ODAを眺めてみたい。
日本は、経済的にも軍事的にも、アメリカと良好な関係がなければやっていけないのは確かである。しかし、アングロサクソンのつながり、つまり最後にはイギリス以上との関係は結べないと思う。血には勝てないのだ。
日本は、環太平洋のつながりを大切にしながらも、中国、韓国との関係を特に大切にしなければならない時代が21世紀なのだと思う。
ただ、そのために中国に媚びるとかいうことではない。対等というよりはむしろ、互いに尊重した関係であることが重要だ。もちろんそのためには国としては越えなければならない壁がいくつもあることは事実である。しかし、民間レベルでは、その限りではない。地道な交流こそが、二国間の壁を低くしていく唯一の方法だろう。
また、歴史認識の問題は避けて通ることはできない。しかし、思いこみを排除し、事実を冷静に、科学的にとらえていくことが大切だと思う。
20年前の中国では、日本人は明らかに羨望のまなざしで見られていた。ホテルの周りには、柵越しにホテルの様子を見入る民衆の多くの姿があった。
今回はどうか・・・楽しみである。
中国人民元切り上げで、日本はどう変わるか?
長い目で見れば、日本が本来の姿に戻るチャンスだと思っている。
今の日本は、農産物を中国に頼り、工業製品も製造拠点を中国に移して生産している。第1次、第2次産業が空洞化している。ものを生み出さない国家が、そのまま永続するとは思えない。中国での人件費を含めた生産コストが上がり、日本でのものづくりが盛り返すことが最良の道である。そのためには、人民元切り上げは大きな一歩である。
さらに、これは若者の就業の範囲が広がり、ニートの問題の解決につながると思われる。
もともと、ニートは、現代の若者の社会性のなさの裏返しだ。
幼少期からガキ大将を先頭に群れをつくって遊んできた主に40歳代以上の人とは異なり、若者は小さな頃からゲームに親しみ、個人の中で完結できる遊びで過ごしてきた。そこでは、他人を傷つけたり傷つけられたりという学習を経験しないで大きくなってしまった。(もちろん、皆が皆そうではないが・・・・)要するに、人とかかわる力が弱いのである。
しかし、現代の主流である第三次産業とは、詰まるところ人を相手にした産業である。
それに対して、第一次産業、第二次産業は自然や物を相手にする産業である。
ニートが増えている原因は、こんなところにもあるのではないか。
東京は名古屋に比べて涼しい。同じ太平洋側でも、結構違う。
成田エクスプレスで成田空港へ向かう。成田エクスプレスに乗るのは、平成10年のオーストラリア以来だが、当時に比べて沿線の家がずいぶん増えた気がする。
成田空港第2ターミナルへ到着。成田エクセルホテル東急へ向かうために第26番バス乗り場へ。
成田空港からバス乗り場へ向かう光景は初めて見るもの。国際空港の周辺には、多くの関連施設があり、多くの人がかかわっていることを目の当たりにする。
成田空港は第2滑走路の延長が決まったらしい。ただ、そのすぐ先に道路が走るなど、航空会社からは危険視されている。成田空港開港に至るごたごたは、昭和史の一つになってしまったが、今でも問題は続いていることを実感する。
エクセルホテルの周囲は何もない。
 |
 |
 |
 |
| ここから乗車 |
ここかな? |
あ〜、ここなんだ・・・ |
みんなで食事 |
18時半より前日ミーティング。
何と、宿泊するホテルやコースが変更されている。事前に連絡がほしかったな・・・・
しかし、これも、ぎりぎりまでよりよいコースにしようという関係者の努力のたまもの。ありがたい。

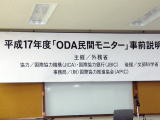 があり、会話を交わすだけでもおもしろい。そんなメンバーが、それぞれ感じたことをまとめる。行く前から、「あの人はどんな感想を持つのだろう。この人は、ODAをどうとらえるのだろう」などと考えると、今から楽しみである。それぞれ、異なる人生があり、当然見方・考え方が異なる。
があり、会話を交わすだけでもおもしろい。そんなメンバーが、それぞれ感じたことをまとめる。行く前から、「あの人はどんな感想を持つのだろう。この人は、ODAをどうとらえるのだろう」などと考えると、今から楽しみである。それぞれ、異なる人生があり、当然見方・考え方が異なる。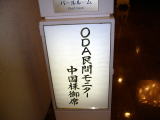 ろう。
ろう。


