|
|
|
|
|
古山恵一郎 〒430-0946 浜松市元城町109-12 tel: 053-453-0693 fax: 053-453-0698 e-mail: ask@tcp-ip.or.jp |
□ASK Inc. □住宅設計 ■まちづくり □台北の路地 □台東の街並 ■海岸公路 |

20170620
▼

台灣の海岸公路をバイクで走ってきた。公路(国道)11號というのが本名らしい。花蓮と台東を繋ぐので、花東公路とも言う。左岸公路という気宇壮大な呼び方もある。宇宙の彼方から地球を見たときに、太平洋の左岸を走っているからだそうだ。
花蓮市内から南を望むと、写真には入っていないが、右手に中央山脈が見える。そして正面が海岸山脈だ。いかにもユーラシアプレートとフィリピンプレートがぶつかっている、という壮大な景色だ。
駅前でバイクを借りる。店のお兄さんが検査官になって実技試験。店を出て駅の資材搬入口のようなところまで運転すると「ハイ結構です。店に戻ってください。」2日で1,200元。もう1日延長するかもしれないと言っておく。
橋を渡るといきなり市街地が消えて、海と山が迫っている。台湾では日本のような「都市」ではなく、中華文明の「城市」なので、集住地域と非集住地域の差が截然としている。花蓮近郊でこの差がゆるい近郊集落が見られるのは、稲作に親しんできたアミ族の住まい方なのかもしれない。

しばらく進むと東部海岸国家風景區花蓮遊客中心というのがあるので小休止。



これが今回借りた馬。日本で言うスクーターであります。バックパックがちょうど座席の前に収まり、脚で挟んで乗ることになります。

いざ出発。「海岸通り」と言っても伊勢正三が男の身勝手をイルカに歌わせるみみっちいものでなく、延長163kmでございます。






跳浪トンネルというのが、いかにもな名前。484mだけちょっとひんやり。




花蓮から20kmほど、芭崎休憩區というところで小休止。アミ族の娘、ではなくおばさんが色々と売っています。



前の週に台北などではかなりな豪雨があり、この辺りでも小さな崖崩れが。


漁村の近くに店があります。何を売っているのかと思ったら「飛魚の干物」を焼いて出していました。




最近のレジャーブームで「自然豊かな東台湾」というのが台湾の若者を引きつけているようです。



ふと気が付いたのはキロポストの旅。後からどこで撮ったかわかりやすいです。



豊濱郷です。漁港があるわけではありませんが、古くからの観光地のようです。
リッチな若者はSUVに自行車を積んで。そうでない高齢者はバイクで。


台東県でまず目に入るのは、誰にもよくわかる「人類発祥の地」であります。

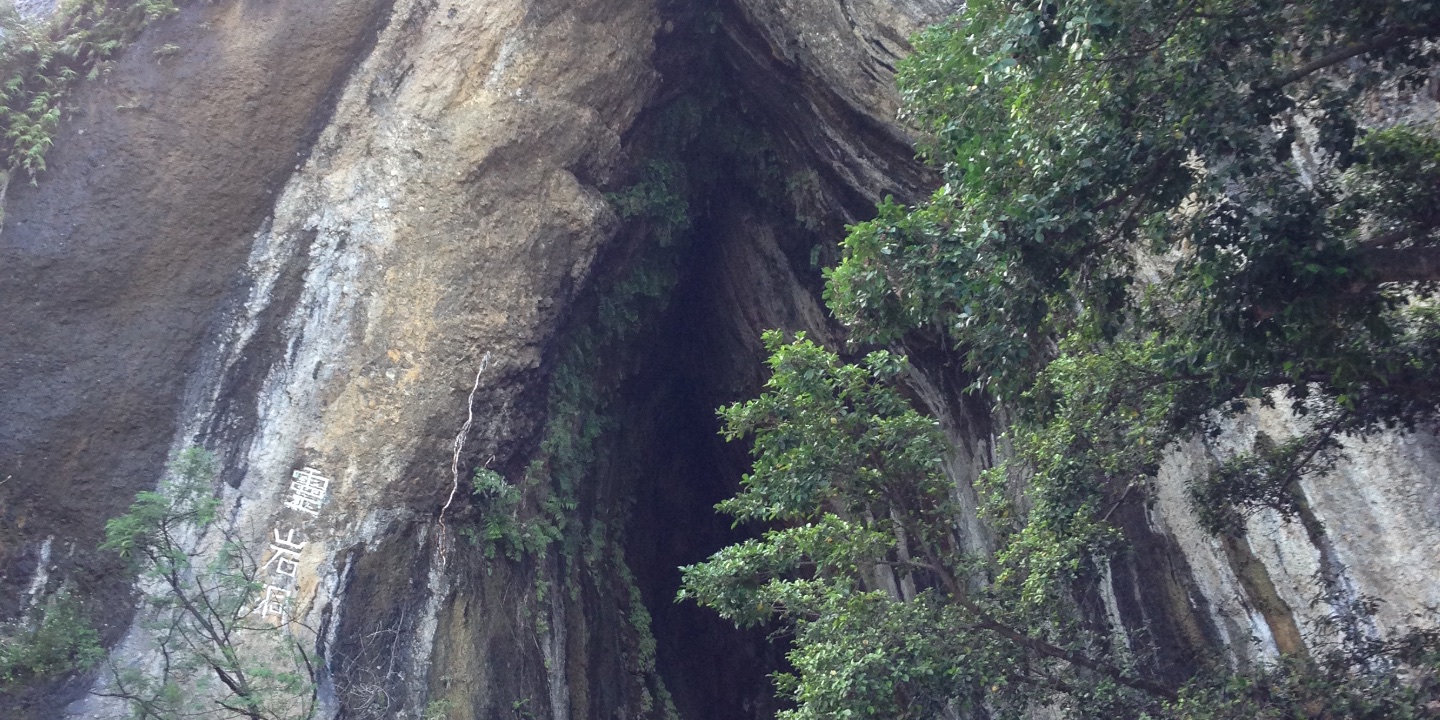

太平洋に向かって開いており、高さは30m程と女神様はなかなか壮大な方でございます。

3,000年前のもの、とされていたのが8,000年前から原住民族の聖地であったということになり、最近では15,000年前まで遡ると、どんどん古くなっています。

下の方では先日の豪雨で崩れたカスを片付けているのか、さらに30,000年前の人類の痕跡を探しているのでしょうか。

土産物屋では原住民族人の親爺が黙々とカゴを編んでいました。どうも「原住民は首刈族。」というのは原住民族人の伝統ではなく、四条河原に首を飾ったり、井伊直弼の首を殿様の墓前に供えたり、という人々の発想ではないかと思います。

などと考えるうち、雲行きが怪しく。

海沿いには田んぼだけでなく、先祖の村もあります。アミ族は海の民でもあるのでしょう。













おやこんなところでスピード違反の取り締まり、などと思っていたら、プスプスプスとエンスト。海に見とれているうちに燃料タンクが空です。
これは困ったと道端にいた元気な中学生に「ガソリンを分けてくれ。」と頼むと、中学生はピューっと家に走って行きました。

50m程歩いてスピード違反に聞くと困った顔。警察官は困った人を助けるのが仕事でなく、悪い奴をやっつけるのが仕事なのは知っています。中学生とその母がガソリンを持ってきてくれたので、
5分ほどでガソリンスタンドがあるので「やれやれ。」
「謝々。」
と100元出すと母が
「50元だよ。」
というが、半分はお礼にしました。







かくして午後6時半台東に到着。日本の市街地が際限もなく面的に広がってゆくのに対し、台湾の市街地は「城市」という住まい方の伝統に従って市街地と「城外」が截然と分かれています。一歩市街地の外に出るとオープンスペースが広がります。
















