
侾丂垽抦嫵堢戝妛晬懏柤屆壆彫妛峑幮夛壢暘壢夛彆尵儊儌
丂彆尵幰偲偟偰埶棅偝傟偨彆尵偺偨傔偵丄帠慜偵弨旛偟偰偍偄偨儊儌傪徯夘偟傑偡丅
丂摉擔偼丄庼嬈傪尒偰丄偙偺拞偐傜敳悎偟丄傑偨怴偨偵壛偊偰榖偟傑偟偨丅
戞俁擭俁慻丂幮夛壢丂丂抝侾俈柤丂彈俀侽柤丂寁俁俈柤
丂
彫妛峑幮夛壢戞俁妛擭媦傃戞係妛擭偺栚昗偲撪梕傛傝
(1)抧堟偺嶻嬈傗徚旓惗妶偺條巕丆恖乆偺寬峃側惗妶傗椙岲側惗妶娐嫬媦傃埨慡傪庣傞偨傔偺彅妶摦偵偮偄偰棟夝偱偒傞傛偆偵偟丆抧堟幮夛偺堦堳偲偟偰偺帺妎傪傕偮傛偆偵偡傞丅
(2)抧堟偺抧棟揑娐嫬丆恖乆偺惗妶偺曄壔傗抧堟偺敪揥偵恠偔偟偨愭恖偺摥偒偵偮偄偰棟夝偱偒傞傛偆偵偟丆抧堟幮夛偵懳偡傞屩傝偲垽忣傪堢偰傞傛偆偵偡傞丅
(3)抧堟偵偍偗傞幮夛揑帠徾傪娤嶡丆挷嵏偡傞偲偲傕偵丆抧恾傗奺庬偺嬶懱揑帒椏傪岠壥揑偵妶梡偟丆抧堟幮夛偺幮夛揑帠徾偺摿怓傗憡屳偺娭楢側偳偵偮偄偰峫偊傞椡丆挷傋偨偙偲傗峫偊偨偙偲傪昞尰偡傞椡傪堢偰傞傛偆偵偡傞丅丂丂丂仾
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仺丂斾妑巚峫丒娭楢巚峫
丂
亂丂姶丂憐丂亃
棟榑丂墶暥帤傗憿岅偑斆棓偡傞拞丄傢偐傝傗偡偄尵梩偱揱偊傛偆偲偟偰偄傞巔惃偑傛偄丅
丂丂丂幮夛壢偺墹摴偱偁傞栤戣夝寛揑側妛廗僗僞僀儖偱偁傞偙偲偵傕埨怱丅
丂丂丂丂嵟嬤丄抦幆傪岠棪傛偔揱偊傛偆偲偡傞庼嬈偑懡偄丅
丂丂丂幮夛壢偼丄帺暘偺惗妶乮幮夛乯傪夵慞偱偒傞恖娫偺堢惉傪偹傜偭偰偄傞丅
丂丂亖岞嫟偺惛恄偵婎偯偒丄庡懱揑偵幮夛偺宍惉偵嶲夋偟丄偦偺敪揥偵婑梌偡傞懺搙傪梴偆丅
丂丂丂丂丂偦偺偨傔偵偼丄栤戣夝寛偺応偑昁梫丅
亂丂揥奐偺帪娫丂亃
揥奐偑丄俆暘丄侾俆暘丄侾俆暘丄侾侽暘丂偵暘偐傟偰偄偨丅
丂俆暘偼乽偄偨偩偒傑偡丅乿乽抦傝偨偄丄峫偊偨乿偲巚偊偽傛偄偺偱丄僔儞僾儖仌僀儞僷僋僩偱傛偄丅
丂搑拞偼怘傋傞丅
丂嵟屻偺侾侽暘偼丄乽偛偪偦偆偝傑丅乿壗偑偍偄偟偐偭偨偺偐丄僐乕僸乕偱傕堸傒側偑傜怳傝曉傞悽奅丅
亂丂幮夛壢偼妶梡宆嫵壢丂亃
仜丂幮夛壢偼庼嬈偯偔傝偺帺桼搙偑懠偺嫵壢偵斾傋偰崅偄丅
丂備偊偵妶梡宆偺嫵壢偲偄偊傞丅偩偐傜偙偦丄愱栧揑側椡検偑昁梫丅
乽彫妛峑妛廗巜摫梫椞 幮夛壢丂夝愢乿
俹侾乣俹侾侽俈偺杮暥拞偵丄乽廗摼乿偑俉夞丄乽妶梡乿偑侾俋俁夞丄乽扵媶乿偑俀夞弌偰偔傞丅乽妶梡乿偼幮夛壢偑僟儞僩僣偵懡偄丅杮棃丄幮夛壢偼乽妶梡宆乿偺嫵壢丅乽扵媶乿偼帠幚忋丄僛儘丅
乽彫妛峑妛廗巜摫梫椞 崙岅壢丂夝愢乿乽廗摼乿偑侾侽夞丄乽妶梡乿係俉夞丄乽扵媶乿偑俀夞
乽彫妛峑妛廗巜摫梫椞 嶼悢壢丂夝愢乿廗摼俁亄侾丂妶梡丂俆俁夞亄俉俉丂扵媶丂俁亄侾
乽彫妛峑妛廗巜摫梫椞丂棟壢丂夝愢乿廗摼係丂妶梡丂俆俋丂丂丂 扵媶俈
丂
亂丂昡壙偑曄傢偭偨丂亃
昡壙偑曄傢偭偨丅
丂乽巚峫丒敾抐乿偑乽巚峫丒敾抐丒昞尰乿
丂乽媄擻丒昞尰乿偑乽媄擻乿
丂 偙傟偼丄尵岅妶摦偺廳帇偺寢壥丅
丂帒椏妶梡偺媄擻偼丄乽昞尰乿偑偲傟偨偺偱丄傛傝忣曬廂廤偺斾廳偑憹偡丅
丂峫偊偰敾抐偟偨偙偲傪丄抁偄尵梩偱昞尰偝偣偨偄丅
丂
亂丂惗妶壢偲幮夛壢丂亃
丂惗妶壢偲幮夛壢偼嬶懱偲拪徾
丂偁傞妛峑偱偼丄俁擭惗偱丂僌乕僌儖丂峲嬻幨恀偲俵俙俹傪暪梡丅僋儕僢僋偱抧恾偵曄傢傞丅帣摱偼棟夝偟偰偄偨丅峲嬻幨恀丂仺丂奊抧恾丂仺丂抧恾丂偼拪徾壔偺夁掱
丂惗妶壢丗抧堟偵偁傞帠徾偼丄偳偙偵壗偑偁傝丄帺暘偲偳偆娭傢偭偰偄傞偐
丂幮夛壢丗帠徾偐傜抧堟慡懱傪棟夝丄帇栰傪峀偘丄抧堟偵懳偡傞屩傝傗垽忣傪堢偰傞
丂
怴嫵堢壽掱丒幚巤偵岦偗偰偺嶲峫帒椏丂乽彫妛峑幮夛乿
乽屆偔偐傜偺寶憿暔乿偑壛偊傜傟丄乽曽埵傗庡側抧恾婰崋乿傪埖偆偙偲丅扨尦乽妛峑偺廃傝乿偼丄偙傟偐傜偺幮夛壢妛廗偺栚師揑側栶妱傪梌偊傜傟傞傕偺偱偁傝丄惗妶壢偲偺堘偄偼抧棟揑偵偲傜偊傞偙偲乮柺偲偟偰偲傜偊傞乯偙偲偵偁傞丅乽屆偔偐傜偺寶憿暔乿偼楌巎乮帪娫揑側尒曽乯偺抲偒愇偲偟偰挷傋偝偣傞傕偺
丂
亂丂峫偊偺嵞峔抸丂亃
峫偊偺嵞峔抸丂
丂懳棫傪挻偊偨崌堄宍惉丒桪愭弴埵傪媮傔偰偄傞丅
丂丂偦偺敾抐婎弨偼乽岠棪偲岞惓乿
暥晹壢妛徣偺惌嶔昡壙偺娤揰
丂 1丏昁梫惈丄 2丏岠棪惈丄 3丏桳岠惈丄 4丏岞暯惈丄 5丏桪愭惈丄 6丏憡摉惈丂
杮棃丄乽峫偊傪嵞峔抸乿仺丂懳棫傪挻偊偨崌堄宍惉
丂丂丂丂丂妶梡丂丂丂丂丂丂丂丂 桪愭弴埵傪晅偗傞丂偦偺婎弨丂岞暯丒岠棪
丂偦偺堄枴偱丄嵞峔抸偺応偑侾俇帪娫偺嵟屻偵偁傞偺偼柍棟偑側偄偐丠
丂
亂丂乽傒傫側偺壽戣乿偺帇揰丂亃
丂嘆丂巤愝丂嘇丂廧戭丂嘊丂岎捠丂偱傛偄偺偐丠丂懠偵傕弌偦偆偱偁傞丅
丂丂傂傚偭偲偟偰丄仜丂楌巎揑丂丒丂慜偵偼壗偑偁偭偨偺丠
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂側偤偙傫側偵峀偄偺丠
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂屆偔偐傜偁傞傕偺偼壗丠丂丂偑弌偨傜丠
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 1997擭丂嶰旽廳岺柤屆壆岺応偵僫僑儎僪乕儉
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 2006擭丂俰俿柤屆壆岺応偺愓抧偵僀僆儞
丂巜摫梫椞偵乽屆偔偐傜偺寶暔乿偑捛壛偝傟偨丂敧敠恄幮乮200m杒乯H11擭偵揝嬝丅
撿偵偼忋栰揤枮媨丄塱岝堾丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜丂帺慠丂丂丒丂栴揷愳丄壨愳晘丄拑壆儢嶁岞墍丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂戝岾乮偩偄偙偆乯岞墍丄丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜丂妛峑丂丂丒丂晬懏拞丄栴揷拞丄柤屆壆拞崅峑丄帄妛娰崅峑側偳
仜丂巤愝丂丂丒丂撶扟忋栰忩悈応乮柤屆壆巗嵟弶偺忩悈応丂戝惓俁擭乯
丂丂丂丂丂丂丒丂庣嶳帺塹戉丄嶰旽揹婡偺岺応丂1924擭丂娭搶戝恔嵭偺梻擭丂
丂妋偐丄戝岾乮偩偄偙偆乯媴応偑1981擭傑偱丄僫僑儎僪乕儉偺搶懁偵偁偭偨丅
丂俁偮偺帇揰傪丄俁偮偵傑偲傔傞壙抣偼偁偭偨偺偐丠
丂懡條側尒曽傪丄嫹偔偟偨偺偱偼側偄偐丠
丂
亂丂娤嶡椡丂亃
丂彫妛峑丗娤嶡丒帒椏妶梡偺媄擻丂丂拞妛峑丗帒椏妶梡偺媄擻
丂彫妛峑偺乽娤嶡乿偑廳梫
丂丂娤嶡偼丠乮乽夝愢乿P.20乯
丂丂丂侾丂偁傝偺傑傑偵丄俀丂悢傗検偵拝栚丄俁丂娤揰偵婎偯偄偰丄係丂懠偺帠徾偲懳斾
丂丂丂俆丂彅忦審偲娭楢偯偗偰
丒乽堘偄乿擇偮傪斾傋傞
丒乽曄壔乿堦偮偺曄壔傪斾傋傞
丒乽摿挜乿抦傪憤摦堳偡傞丅
丂
Q丂幚嵺偺尒妛偵偼丄偳傫側帇揰傪梌偊偨偺偐丠偦偺慜偵偳傟偩偗庬傪帾偄偨偺偐丠
丂丂傑偨偼丄惗妶壢偱偳偙傑偱尒妛偟偰偄傞偺偐丠
姶憐丗巜摫埬傪尒傞尷傝丄巕偳傕偨偪偺抧堟傊偺垽忣偑姶偠傜傟側偄偑乧丅
傑偪偺乽傂傒偮扵偟乿乽傑偪帺枬乿傪尒偮偗傞偲丄屩傝偲垽忣偵偮側偑傞丅嫵巘偑丄傑偪偑岲偒偐偳偆偐丠
丂
亂丂岺晇丒搘椡丂亃
仚丂幮夛壢偼丄恖乆偺乽岺晇乮抦宐乯傗搘椡乮娋乯乿偑僥乕儅丅戝慜採偱偁偭偰寢榑偱偼側偄丅
丂丂嫟捠帇揰偲尵偆偵偼埨堈偡偓側偄偐丠偡傋偰偵摉偰偼傑傞丅
丂丂偳傫側岺晇丒搘椡傪偟偰偄傞偐傪扵偭偰丄偦偺拞偱尨棟丒尨懃傪尒偮偗傞丅
丂
亂丂幮夛壢偼恖丂亃
仚丂幮夛壢偼恖傪偐傜傔偨偄丅婄偑尒偊傞幮夛壢偩丅俁夞偺朄懃偲偄偆偺偑偁傞丅俁夞弌夛偆偲丄丂怱棟揑嫍棧偑嬤偔側傞丅偦傟偑丄嫿搚傊偺垽忣偵偮側偑傞丅丂
丒尒妛偱愢柧傪暦偄偨恖偑偄傟偽丄偦偺婄幨恀傪揬偭偰忋庤偔棙梡偡傞丅
丂丂乽杒偵偼楅栘偝傫偑偄傞仜仜偑偁傞丅乿
丂
亂丂栚昗偺彂偒曽偵媈栤丂亃丂丂丂丂丂
仜丂乽杮帪偺栚昗乿偱偼丄庤抜偲栚揑傪崿摨偟偰偄傞丅丂
庼嬈偺杮幙偼妛椡偺岦忋
丂庼嬈慜偵斾傋偰丄偙偺帪娫偱岦忋偡傋偒偙偲偼壗偐丅偦傟傪偙偙偵彂偄偰傎偟偄丅
丂撪梕傪嬶懱揑偵彂偔傋偒丅
丒丂娭怱丒懺搙偺懳徾偼幮夛帠徾偱偁傝丄庼嬈偱偼側偄丅
丂
亂丂斾妑偲娭楢丂亃丂丂丂丂丂
幮夛揑巚峫偵偼俆偮偁傞偑
丂拞妛擭偺巚峫偼斾妑巚峫偲娭楢巚峫丅
丂丂斾妑巚峫丂摨偠僇僥僑儕乕偺拞偱嫟捠揰丒憡堘揰傪斾傋傞丂丂僇僽僩偲僋儚僈僞
丂丂娭楢巚峫丂堘偆僇僥僑儕乕偺傕偺偱偮側偑傝傪挷傋傞丂丂丂丂僋儚僈僞偲僋僰僊偺栘
丂
婭梫暥復拞偺乽娭楢偯偗傞乿偼娭楢巚峫偱偼側偄丅
丂丂丂偁偔傑偱傕幮夛帠徾偲幮夛帠徾傪娭楢偯偗傞偙偲丅
丂丂斾妑巚峫偼丄摿挜傪柧傜偐偵偱偒傞丅
丂
亂丂俁偮偺帇揰傪偳偆嵞峔抸偡傞偐丂亃丂丂丂丂丂
丒丂俁偮偺帇揰丄愒丂惵丄墿丂傪岎棳偝偣傞偲乽愒丄惵丄墿偑偁傝傑偟偨乿偵側傞偺偼偩傔丅扨側傞帠幚擣幆丅巼傗丂椢丄偩偄偩偄偵側偭偰乽娭楢偯偗偨偙偲偵側傞乿
丒丂娭楢偯偗傞偵偼曽朄偑偁傞丅
丂丂偦偙偵丄乽恾帵乿偲乽側偤丄偳偆偟偰乿偲偄偆乽敪栤乿偑搊応偡傞
巤愝
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偙偺慄傪峫偊傞丅愒偲惵側傜丄巼偺傛偆側摎偊傪丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 偦偟偰丄俁杮偺慄傪傑偲傔傞
廧傓丂丂丂丂丂岎捠
丂
亂 拵偺栚丒捁偺栚丂亃丂暘愅丒憤崌
拞妛擭偼憤崌偑擄偟偄丂仺丂拵偺栚傪抌偊偨偄丅
丂丂丂憤崌偼拪徾壔丂丂丂丂丂 娤嶡椡
嘆丂妛峑偺峑幧偺岦偒偼丠 桳悢偺暥嫵抧嬫丅
嘇丂崟斅偺曽妏偼寛傑偭偰偄傞丠
嘊丂恄幮偼偳偭偪岦偒丠丂偩偄偨偄撿岦偒丅搶戝帥偼丠撿岦偒
丂崫將偼丄搶懁偑垻宍乮岥傪偁偄偰偄傞乯偱惣懁偑欇宍偲偄偆偺偑懡偄丅
丂桋崙恄幮偼搶杒搶丅
丂岞擣栰媴婯懃偵偼乽杮椲偐傜搳庤斅傪宱偰擇椲偵岦偐偆慄偼丄搶杒搶偵岦偐偭偰偄傞偙偲傪棟憐偲偡傞乿偲彂偄偰偁傞丄偲丅
丂丂帺桼偺彈恄偼丄撿撿搶
嘋丂塹惎曻憲偺傾儞僥僫丂撿惣
丂丂偟偐偟丄僥儗價偺傾儞僥僫偼丄柤屆壆偼僥儗價搩偵岦偄偰偄傞丅丂丂
嘍丂挿曣帥乮偪傚偆傏偠乯
丂1179(帯彸3)擭偵嶳揷廳拤偑憂寶偟偨偍帥偱丄廳梫柍宍柉懎暥壔嵿偵巜掕偝傟偰偄傞丄懢晇偑愵巕傪帩偭偰廽帉傪彞偊丄嵥憼偨偪偑屰傪扏偄偰崌偄偺庤傪擖傟偨傝丄嶰枴慄側偳偺妝婍傪墘憈偡傞晳戜寍乽旜挘枩嵨乿偺敪徦偺抧丅
丂
亂 怳傝曉傝偺応丂亃
仜丂庼嬈偺杮幙偼丄妛椡偺岦忋丅
丂丂丂慜偲屻偱岦忋揑偵曄梕偟偰偄傞偙偲丅
丂丂丂崱擔偱丄壗傪偮偐傫偩偺偐丅帺暘偺尵梩偱怳傝曉傜偣偨偄丅儊僞擣抦傪偝偣偨偄丅丂丂
俀丂嫵巘椡傾僢僾僙儈僫乕丂愒嶁恀擇巵亅俀亅丂丂僽儘僌傛傝
丂慜夞偵懕偒傑偡丅
丂
椺偱徯夘偟偨俿孨偼丄壗偺偨傔偵僫僀僼傪帩偭偨偺偱偟傚偆偐丠
戝搒夛偐傜偺揮峑惗偱偄偠傔傗偐傜偐偄偺懳徾偵側偭偰偄偨斵偑丄僫僀僼傪尒偣偨偙偲偱拠娫偲偟偰庴偗擖傟傜傟丄斵帺恎偺嫃応強偑偱偒偨偺偱偡丅
埲屻丄庼嬈朩奞傪偡傞懁偵夞傝傑偟偨丅
尨場偲嫟偵丄斵偺栚揑偑尒偊偰偒傑偟偨丅
偦偙偱昁梫側偺偑乽桬婥偯偗乿側偺偱偡丅
 亅侾亅偱徯夘偟傑偟偨偑丄傾僪儔乕怱棟妛偱偼丄媄朄偲偟偰乽桬婥偯偗乿傪廳帇偟傑偡丅
亅侾亅偱徯夘偟傑偟偨偑丄傾僪儔乕怱棟妛偱偼丄媄朄偲偟偰乽桬婥偯偗乿傪廳帇偟傑偡丅
巕偳傕偨偪偺偝傑偞傑側栤戣峴摦偼丄桬婥傪偔偠偐傟偨忬懺偲峫偊傑偡丅
桬婥偯偗偵傛傝丄揔愗側峴摦偺堄梸偑惗傑傟丄揔愗側尵摦偑惗傑傟丄嫟摨懱偲偮側偑傞傛偆偵側傞偺偱偡丅

桬婥偯偗乮孹挳丄傾僒乕僔儑儞側偳乯偵傛傝丄愽嵼擻椡偑孈傝婲偙偝傟丄帺懜怱偵偮側偑傝丄嫟摨懱姶妎偑惗傑傟傞偺偱偡丅
俿孨偺応崌丄峔傢偢庼嬈傪巒傔偨偙偲偑揮婡偲側傝傑偟偨丅
晄揔愗側峴摦偵偼拲栚偟側偄偺偱偡丅
偦偺堦曽偱丄傢偢偐偵尒偣偨揔愗側峴摦偵懳偟偰拲栚偟丄斵偺嫃応強傪曄偊偰偄偔偺偱偡丅


丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
偙偆偟偰丄恖偲偮側偑傞曽朄傪嫵偊偰偄偒傑偡丅
 島墘偺拞偱丄愒嶁愭惗偼僆儁儔儞僩妛廗偺榖傪偝傟傑偟偨丅
島墘偺拞偱丄愒嶁愭惗偼僆儁儔儞僩妛廗偺榖傪偝傟傑偟偨丅
僆儁儔儞僩妛廗偲偼丠
僆儁儔儞僩偼乽巤偡乿偲偄偆偙偲偱偡丅
僆儁儔儞僩妛廗偼丄乽巤偡壗偐亖僆儁儔儞僩乿偵傛偭偰丄偁傞峴摦偑弌尰偡傞昿搙偑曄壔偡傞偙偲偱偡丅
傛偔丄敔偵擖偭偨僱僘儈偺幚尡偱愢柧偝傟偰偄傑偡丅
儗僶乕傪墴偡偲塧偑弌偰偔傞憰抲偺敔偵丄僱僘儈傪擖傟傑偡丅偨傑偨傑儗僶乕傪墴偟偨僱僘儈偼丄塧傪摼傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅偡傞偲丄儗僶乕墴偟峴摦偼丄彊乆偵憹偊偰偄偒傑偡丅妛廗偟偨偺偱偡丅
偙偺塧偺偙偲傪丄乽嫮壔巕乿偲屇傃傑偡丅
偡側傢偪丄乽桬婥偯偗乿偲偄偆嫮壔巕偵傛傝丄乽揔愗側峴摦乿傪憹傗偟偰偄偙偆偲偄偆傕偺偱偡丅
丂
妛媺偯偔傝偺恌抐偵Q-U傪妶梡偟偰偄傞偲偙傠偑憹偊偰偒傑偟偨丅
亀妝偟偄妛峑惗妶傪憲傞偨傔偺傾儞働乕僩亁偲偄偆傕偺偱丄懡偔偺僨乕僞偐傜棤晅偗傜傟偨桪傟傕偺偱偡丅
Q-U偺HP偐傜丄偦偺愢柧傪堷梡偟偰傒傑偡丅
丂
Q-U偱偑傢偐傞偙偲
巕偳傕屄恖偲丄妛媺廤抍偺忣曬偐傜丄晄搊峑丄偄偠傔丄妛媺曵夡側偳偺栤戣偵懳墳偡傞僨乕僞偑摼傜傟傑偡丅
丒晄搊峑偵側傞壜擻惈偺崅偄巕偳傕偼偄側偄偐
丒偄偠傔旐奞傪庴偗偰偄傞壜擻惈偺崅偄巕偳傕偼偄側偄偐
丒奺椞堟偱堄梸偑掅壓偟偰偄傞巕偳傕偼偄側偄偐
丒妛媺曵夡偵帄傞壜擻惈偼側偄偐
丒妛媺廤抍偺暤埻婥偼偳偆偐
埲忋偺傛偆側丄忣曬偑摼傜傟傑偡丅
丂
傾儞働乕僩偺寢壥傪廤栺偡傞偲丄師偺傛偆側昞偵昞偡偙偲偑偱偒傑偡丅
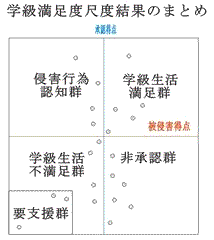 偦傟偧傟偺僇僥僑儕偺娙扨側愢柧偼壓婰偺捠傝偱偡丅
偦傟偧傟偺僇僥僑儕偺娙扨側愢柧偼壓婰偺捠傝偱偡丅
亙妛媺惗妶枮懌孮亜
妛媺撪偵帺暘偺嫃応強偑偁傝丄妛峑惗妶傪堄梸揑偵憲偭偰偄傞帣摱丒惗搆
亙旕彸擣孮亜
偄偠傔傗埆傆偞偗傪庴偗偰偼偄側偄偑丄妛媺撪偱擣傔傜傟傞偙偲偑彮側偄帣摱丒惗搆
亙怤奞峴堊擣抦孮亜
懠偺帣摱偲側傫傜偐偺僩儔僽儖偑偁傞壜擻惈偑崅偄帣摱丒惗搆
亙妛媺惗妶晄枮懌孮亜
懴偊傜傟側偄偄偠傔傗埆傆偞偗傪偆偗偰偄傞偐丄旕忢偵晄埨孹岦偑嫮偄帣摱丒惗搆丅摿偵梫巟墖孮偺帣摱丒惗搆偼偦偺孹岦偑偝傜偵嫮偔憗媫側巟墖偑昁梫丅
埲忋偑堷梡偱偡丅
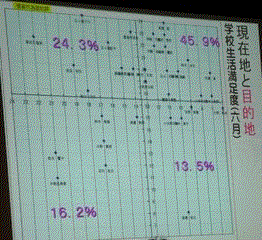 偍偍傛偦丄塃忋偵屌傑偭偰偄傟偽丄栤戣偑彮側偄僋儔僗偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅
偍偍傛偦丄塃忋偵屌傑偭偰偄傟偽丄栤戣偑彮側偄僋儔僗偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅
偝偰丄愒嶁愭惗偺僋儔僗偼丄嵟弶偼偳偆偱偁偭偨偐丠
丂
斾妑揑丄妛媺惗妶傊偺堄梸偼崅偄偑恖娫娭學偱僩儔僽儖傪帩偭偰偄傞巕傗旐奞幰堄幆偺嫮偄巕丄帺屓拞怱揑側巕偑懡偄偙偲偑傢偐傝傑偡丅
傑偨丄妛媺偑偍傕偟傠偔側偄巕傕彮側偔偁傝傑偣傫丅
丂
偙偺Q-U傪奐敪偟偨壨懞栁梇愭惗偼乽妛媺偯偔傝偱丄廤抍傕妛椡傕怢傃傞乿偲抐尵偟偰偄傑偡丅
偦偺乽廤抍偑怢傃傞乿偲偼壗偑怢傃傞偺偱偟傚偆偐丠
丂
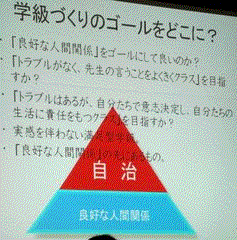 愒嶁愭惗偼師偺傛偆偵峫偊偰偄傑偡丅
愒嶁愭惗偼師偺傛偆偵峫偊偰偄傑偡丅
乽椙岲側恖娫娭學乿傪嶌傞偺偼戝愗偩偑丄偦傟偑僑乕儖偱偼側偄丅
僩儔僽儖偑婲偙偭偰傕丄帺暘偨偪偺椡偱夝寛偟偰偄偙偆偲偡傞乽帺帯乿傪栚巜偡傋偒偩偲丅
丂
乽嫵堢婎杮朄乿偺戞堦忦偵乽嫵堢偺栚揑乿偑偐偐傟偰偄傑偡丅
偦偙偵偼岞嫟偺惛恄偵婎偯偒丄庡懱揑偵幮夛偺宍惉偵嶲夋偟偲偁傝傑偡丅
乽椙岲側恖娫娭學乿偺愭偵偼丄乽幮夛偺宍惉幰乿偺堢惉偲偄偆僑乕儖偑偁傞偺偱偡丅
偱偼丄嬶懱揑偵偳偆偡傞偐丠
丂
廤抍偯偔傝偺僑乕儖傪乽帺帯乿偵抲偄偨愒嶁妛媺丅偦偺曽朄偑乽僋儔僗夛媍乿側偺偱偡丅
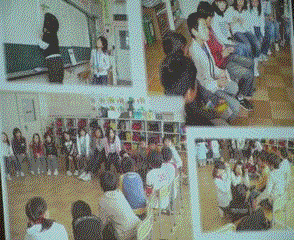 怴妛廗巜摫梫椞丂拞妛峑幮夛壢偵偼丄師偺傛偆偵彂偐傟偰偄傑偡丅乮堷梡乯
怴妛廗巜摫梫椞丂拞妛峑幮夛壢偵偼丄師偺傛偆偵彂偐傟偰偄傑偡丅乮堷梡乯
丂
岞柉揑暘栰偱偼丆尰戙幮夛偺棟夝傪堦憌怺傔傞偙偲傪廳帇偟偰丆恖娫偼杮棃幮夛揑懚嵼偱偁傞偙偲傪摜傑偊丆幮夛惗妶偵偍偗傞暔帠偺寛掕偺巇曽傗偒傑傝偺堄媊偵偮偄偰峫偊丆尰戙幮夛傪偲傜偊傞偨傔偺尒曽傗峫偊曽偺婎慴偲偟偰丆懳棫偲崌堄丆岠棪偲岞惓側偳偵偮偄偰棟夝偡傞妛廗傪庢傝擖傟偨丅
丂
偙傟偼丄嫵堢婎杮朄丂戞俀忦嶰丂偺師偺忦暥偑儀乕僗偵偁傝傑偡丅
丂
惓媊偲愑擟丄抝彈偺暯摍丄帺懠偺宧垽偲嫤椡傪廳傫偢傞偲偲傕偵丄岞嫟偺惛恄偵婎偯偒丄庡懱揑偵幮夛偺宍惉偵嶲夋偟丄偦偺敪揥偵婑梌偡傞懺搙傪梴偆偙偲丅
丂
偦偺庤朄偑懳榖偱偁傝丄壙抣娤傪嫟桳偟側偄恖偲嫟懚偡傞媄弍側偺偱偡丅
 偙偺嬶懱揑側幚慔偑乽僋儔僗夛媍乿側偺偱偡丅
偙偺嬶懱揑側幚慔偑乽僋儔僗夛媍乿側偺偱偡丅
丂
僋儔僗夛媍偼師偺棳傟偱峴偄傑偡丅
侾廡娫偟偐敍傝偑側偄偺偑桪傟傕偺偱偡丅
僋儔僗夛媍偱寛傑偭偨偙偲偼丄幚嵺偵傗偭偰傒偰丄侾廡娫屻偵偼尒捈偟偑峴傢傟傑偡丅
丂
偝傜偵丄僋儔僗偺栤戣偼懡悢寛偱丄屄恖偺栤戣偼屄恖偺敾抐偵埾偹傜傟傑偡丅
丂
丂


丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
偝偰丄偳傫側偙偲傪榖偟崌偆偺偱偟傚偆丅
椺偊偽丒丒丒
 巕偳傕傜偟偄丄偨傢偄傕側偄偙偲偱偡丅
巕偳傕傜偟偄丄偨傢偄傕側偄偙偲偱偡丅
偙偆偟偰丄傒傫側偱寛傔偰丄傒傫側偱幚慔偟丄傒傫側偱尒捈偡宱尡偑丄柉庡崙壠偺峔惉堳傪堢偰偰偄偔偺偱偡丅
丂
偝偰丄偙偆偟偰堢偰偨愒嶁妛媺偺Q-U偼偳偆側偭偨偺偱偟傚偆偐丠

偝偡偑偱偡丅
丂
偙傟傑偱丄愒嶁恀擇愭惗偺島墘撪梕傪徯夘偟偰偒傑偟偨丅
杮暔偼丄儐乕儌傾偨偭傉傝偱丄帪娫偑偁偭偲偄偆娫偵夁偓偰偄偒傑偡丅
嫽枴傪帩偨傟偨曽偼丄偤傂杮暔偺愒嶁愭惗偵怗傟偰偔偩偝偄丅
丂
丂
俁丂乽暯惉22擭搙偵偍偗傞巕偳傕庤摉偺巟媼偵娭偡傞朄棩乿摍偺巤峴偲妛峑媼怘旓偺枹擺栤戣傊偺懳墳偵偮偄偰
俆寧俀俀擔偵峴傢傟偨丄嬥梈宱嵪嫵堢尋媶夛丂丂愒曯 怣 島廗夛偺曬崘傪偟傑偡丅
偄偒側傝栤戣偱偡丅
丂
壖偵僩儓僞帺摦幵偺姅傪攦偭偨偲偟傑偡丅偦偺嬥偼偳偙傊偄偔丠
丂
傒側偝傫偳偆巚偄傑偡偐丠
壗恖偐偵暦偄偰傒偨傜丄傎偲傫偳偑乽僩儓僞帺摦幵乿偲偄偆摎偊偱偟偨丅
偟偐偟丄僩儓僞帺摦幵偵偼侾墌傕峴偒傑偣傫丅
僄僢丄側偤丠
偲巚偭偨恖偼丄愭傊恑傫偱偔偩偝偄丅
丂
偦傕偦傕婇嬈偑帒嬥傪廤傔傞偵偼偳偆偡傞偺偐丠
嬧峴偐傜偍嬥傪庁傝傑偡丅偨偩偟丄扴曐偑昁梫偲側傝傑偡丅
丂
 偦偙偱丄姅幃傪敪峴偟丄搳帒壠偐傜偺帒嬥傪廤傔傞偺偱偡丅
偦偙偱丄姅幃傪敪峴偟丄搳帒壠偐傜偺帒嬥傪廤傔傞偺偱偡丅
偦傟偑姅幃夛幮偱偡丅
偦偺拠夘傪峴偆偺偑丄徹寯夛幮偱偡丅
丂
傛偔丄乽姅幃傪岞奐偟丄峀偔帒嬥傪廤傔傞夛幮乿偲愢柧偝傟偰偄傑偡偑丄偦傟偼岆傝偱偡丅
慡崙偵侾俀侽枩幮偁傞拞偱丄姅幃傪忋応乮岞奐乯偟偰偄傞偺偼3,700幮偩偗偱偡丅
抦傜傟偨拞偱偼丄僒儞僩儕乕傗俰俿俛丆抾拞岺柋揦側偳偼旕忋応夛幮偱偡丅
丂
姅幃夛幮偺儊儕僢僩偼丠
 侾丂搳帒嬥妟傪彫偝偔偡傞丗懡偔偺恖偑搳帒偟傗偡偔偟傑偡丅
侾丂搳帒嬥妟傪彫偝偔偡傞丗懡偔偺恖偑搳帒偟傗偡偔偟傑偡丅
俀丂夛幮偑搢嶻偟偰傕丄搳帒偟偨嬥妟埲忋偺愑擟偼偁傝傑偣傫丅丗桳尷愑擟偲偄偄傑偡丅
俁丂偄偮偱傕攧傞偙偲偑偱偒傑偡丅
丂
姅庡偵偼偄傠偄傠側尃棙偑梌偊傜傟傑偡
姅幃夛幮偑丄弶傔偰丄傑偨偼捛壛偟偰姅幃傪敪峴偟偰尰嬥傪摼傞偺偑敪峴巗応偱偡丅偙偙偱姅傪攦偭偨偍嬥偼丄夛幮偵擖傝傑偡丅
偟偐偟丄姅幃偑忋応偝傟丄徹寯庢堷強乮棳捠巗応乯偱攦偭偨姅偺偍嬥偼扤偺強偵偼偄傞偐丠
傕偪傠傫丄攧偭偨恖偺傕偺偵側傞傢偗偱偡丅
丂
懕偒傑偡丅偙偺懕偒偼僽儘僌偱尒偰偔偩偝偄丅
俆丂栶棫偪倂倕倐摿廤丂
乮侾乯嫵怑堳摍偺慖嫇塣摦偺嬛巭摍偵偮偄偰乮捠抦乯
丂
乮俀乯帺揮幵偱USB僶僗僷儚乕丄USB懳墳偺僟僀僫儌
丂帺揮幵傪憜偄偱撪憼僶僢僥儕傪廩揹丄揹椡傪USB僶僗僷儚乕偲偟偰弌椡偱偒傞帺揮幵梡僟僀僫儌偑搊応丅僼儖廩揹偵偼丄帪懍15km偱2乣3帪娫憱傞昁梫偑偁傝丄偦偺屻乽実懷揹榖傪10暘娫廩揹偡傞偲5暘掱搙捠榖偱偒傞乿揹椡傪嫙媼偱偒傞偲偄偆丅
丂
乮俁乯戝婥拞擇巁壔扽慺擹搙偼夁嫀嵟崅
婥徾挕偑壏幒岠壥僈僗娤應傪幚巤偡傞崙撪娤應抧揰偵偍偄偰丄2009擭偺擭暯嬒戝婥拞擇巁壔扽慺擹搙偼夁嫀嵟崅偵丅傑偨丄2010擭4寧偺戝婥拞擇巁壔扽慺擹搙偼丄娤應奐巒埲棃偺嵟崅抣傪婰榐丅
丂
乮係乯彫拞妛峑偺僨僕僞儖嫵壢彂幚尰偵岦偗乽僨僕僞儖嫵壢彂嫵嵽嫤媍夛乿敪懌
彫拞妛惗丄崅峑惗丄戝妛惗丄堦斒嫵嵽側偳偺僨僕僞儖嫵壢彂幚尰偵岦偗僨僕僞儖嫵壢彂嫵嵽嫤媍夛偑敪懌丅(1)僨僕僞儖嫵壢彂丒嫵嵽偺梫審偺専摙丄(2)價僕僱僗儌僨儖丄晛媦曽嶔偺専摙丄(3)幚徹幚尡偺婇夋丒幚巤丄(4)偦偺傎偐偺壽戣惍棟丒専摙丒採尵傪峴側偆丅
丂
乮俆乯6,500嶜挻偺彂愋偑撉傔傞揹巕戄杮僒乕價僗
iPad偱彫愢丒幚梡彂丄幨恀廤側偳丄6,500嶜傪挻偊傞揹巕彂愋僐儞僥儞僣偑撉傔傞揹巕戄杮僒乕價僗偑僗僞乕僩丅iPad偩偗偱側偔丄僷僜僐儞傗懠偺忣曬抂枛偱傕摨偠嶌昳傪撉傓偙偲偑偱偒傞丅1嶜100 墌偱丄48帪娫乣柍婜尷偺墈棗壜擻丅
丂
乮侾乯旜杒崅懖嬈惗慱偄怳傝崬傔嵓媆懡敪乮垽抦乯
丂峕撿彁娗撪偱丄俆寧侾侾擔偐傜俇寧侾擔傑偱偵乽怳傝崬傔嵓媆乿偺旐奞傗枹悑帠審偑寁俁俀審憡師偄偱偄傞偙偲偑暘偐偭偨丅導棫旜杒崅峑偺懖嬈惗戭傪慱偭偨働乕僗偑懡偔丄摨彁偱拲堄傪屇傃偐偗偰偄傞丅 http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news2/08/20100603-OYT1T00047.htm?f=k丂
丂
乮俀乯嫵堳柶嫋丄柍椏偱峏怴島廗丂俉寧偐傜壀嶈巗乮垽抦乯
丂壀嶈巗嫵埾偼侾擔丄崙偑嶐擭搙偐傜巒傔偨乽嫵堳柶嫋峏怴惂搙乿偺島廗傪丄俉寧偐傜
巗偑撈帺偵慡妟柍椏偱幚巤偡傞曽恓傪柧傜偐偵偟偨丅巗媍夛堦斒幙栤偱峕懞椡嫵堢挿偑