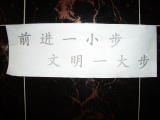![]() �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]() �@�@
�@�@![]() �@
�@
�V���Q�S���i���j
�@ �S�����N���B���\�n�[�h���B�e���r������Ƃm�g�j�ő告�o�̍ĕ���������Ă����B�������Ă���Ɠ��{�ɂ���̂ƕς��Ȃ��B
�k������A�B��
|
|
�@�z�e�����o��B���鏊�ɓ��{�����X���������B�����ł�����x�Ӗ���������̂Ŋy�����B�\�ӕ����͈̑傾�B�؍��ł͂����ς蕪����Ȃ������B |
|
|
�@��`�̃Z�L�����e�B�`�F�b�N�͂ƂĂ��������B�قڑS���������T�m�ň���������B�M�҂̓u���U�[�̃{�^���A�s����̓K���̋�̕�ݎ������������B�y�b�g�{�g���͂��������ӂ����J���ďL���������ł���B�����h���n���S�̃e���A�����Ėk���ŊJ�����Z�J�����c�̂��߂ł��낤�B |
|
|
�@�ȏオ�g���畷������ȓ��e���B
�₦�Ă��Ȃ��r�[��
 �@�@���Ńr�[���𒍕��B���܂����I�����ł́u�₽���r�[���v�Ƃ���Ȃ��Ə퉷�̃r�[�����o�Ă�������B
�@�@���Ńr�[���𒍕��B���܂����I�����ł́u�₽���r�[���v�Ƃ���Ȃ��Ə퉷�̃r�[�����o�Ă�������B
�@���������A�H��ł��y�b�g�{�g�����Ă��邪�A�قƂ�ǂ��퉷���B�g����ɂ��A�����l�͗₽�����͈݂̂Ɉ����Ǝv���Ă���B�퉷���X�^���_�[�h�B���ɂ́A�r�[����������l�����邻�����B�o���Ă������I
�@�l���Ă݂�A�������₷�Ƃ����s�ׂ��ґ�Ȃ��̂��B
�@���H����g�߂�̂́A�E�ۂƂ����傫�Ȗ�ڂ�����B�ޗ����ςāA�_�炩��������ʂ�����B�܂��A�₦���̂����߂�Ƃ�����ڂ��ʂ����B
�@����ł́A�u��₷�v�Ӗ��́H
�@�l���Ă݂�Ή����Ȃ��B�P�ɁA�������𖡂키���߂����ŁA�m���ɑ̂ɂ��悭�Ȃ��B����ɁA���߂����₷�����͂邩�ɃG�l���M�[�����������B
�@�݂Ȃ���A�����͗�₳�Ȃ��ň������I
�@�ł��A���͌��ł��B
����ĂȂ�
�@�X�F�R�O�̓����\�肪�A��`�O�̃o�X���ł������łɂP�O�F�T�O�B�����ł́A�u����ĂȂ��A������Ȃ��A���Ăɂ��Ȃ��A������߂Ȃ��v���s���̊�{�������ł���B
�@�m���ɁA���Ă̐l�����Ў���A�d����������Ă������Ȃ��Ă��A��������Ă�����������Ă������ɔ��f����Ȃ����オ�������B�o�ς̎��R���ʼn��P������邪�A�܂��A�����̋C�����c���Ă���̂�������Ȃ��B
�͓�Ȃɓ���
�@�͓���̏ȓs�A�A�B�ɓ��������B�ȐE���̂v�����낢��Ɖ�����Ă��ꂽ�B
|
|
|
|
 |
 |
|
�A�B��` |
�≑��ѓX |
�g�C���̌f�� |
�����̊X�� | �����̖��� |
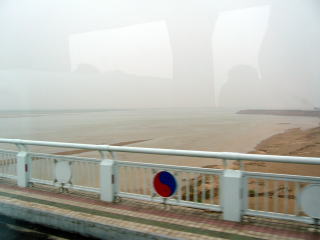 |
| �ԑ����猩������ |
�@�͓�Ȃ́A�����̂قڒ����B���z���͂��߂Ƃ��āA���Ă̓s���W�����Ă�����j�̂��鏊�ł���B
�@�A�B��`���牷���������r���Ɍ������͂́A�C���[�W�ʂ�Ԓ����āA�Y��ł������B�Ñ㕶������݁A�܂��A�����̔×����J��Ԃ��Ă������̑�͂��A����܂łɉ��l�̐l�����Ă����̂��낤���B
�@���H�́A�≑��ѓX�B���ؗ����̃o�C�L���O�ł���B
�@�����̃g�C���ł������낢�\�莆���������B���֊�̑O�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă������B
�@�u�O�i�ꏬ���@���������v
�@�v�킸�A�ɂ���Ƃ����Ă����B
�@�����̊X�̃��C���X�g���[�g�͓y�ŁA���ܑ��������B��ƒ��͐l���S���l�A���ɒ��w�Z���S����B�o�X�̎ԑ����猩�镗�i�́A�f�W�J���ŎB�肽�����̂���������B�k���ƈ���āA���Ă̒����炵����������B�X���痣���ƁA�n�������ȉƂ��������ԁB�ƂɎԂ͂Ȃ��A���]�ԂƂ��������o�C�N����ʎ�i���B��������ŁA���͂��^�y���Ă��č�����悤�ł���B�@
�����̍s���g�D�@�@����Ȍ�ɉ��x���o�Ă���ȁA���A���̈Ӗ���m�肽���l�́A���̃T�C�g���������������B
�@�����̒n���s�����x�@http://www.clair.or.jp/j/forum/c_report/html/cr209/�@�@�ڂ����m�肽������
�@�����̍s�����x�@http://www.cji.jp/China_chili/China_gov.htm�@�@�T���𗝉�����������
�����̋��琧�x
�@�@���ɏЉ�钆���̒��w�Z�𗝉����邽�߂ɁA���̃T�C�g���������������B
�@�@�����̋����@�@http://www.pekinshuho.com/2002-26/wh26-1.htm
 |
 |
 |
 |
 |
| �K�\�����X�^���h�͑傫�� | ��ʂ̃g�E�����R�V�� | �ŔƃX���[�K�� | ���B�x�O�̊X���� | �����K����R���N���[�g�� |
�����@��ƒ��@���w�Z�Z�ɍČ��v��
�@���悢��ŏ��̎��@�Č����B
�@���@���e�̏ڍׂ́A�����̕���������Web��ł����J�����̂ł�����ɏ��邪�A�\���m���Ƃ��āA���O�ɔz�t���ꂽ��������Љ�����B
|
�P�@������ƒ����w�Z�Z�ɍČ��v��(���̍�������������) |
�@�Q���Ɋw�Z�֓����B���j���ɂ�������炸�A��̗����ɐ��k��������āA����ƏΊ�ŏo�}���Ă��ꂽ�B��ł킩�������A�Ƃɓd�b������ȂǁA���������₷���q���W�߂�ꂽ�悤���B�Ƃ������Ƃ́A�Ƃɓd�b���Ȃ��q�������Ƃ������Ƃ��H
�@�~�n�ɓ���ƁA�U�N�O�ɓ��{�̎��������Ō��Ă��炵���Z�ɂ���������Ȃ��B����A����ɂ͂���̂����A�ǂ����Ă��z�Q�O�N�B���g�͂��ѕt���A���X�K���X�͂Ȃ��A�ē����ꂽ�������U����u�����̂����A�_�������̂͂Q�̂݁B�������A���ꂪ���̖������������Ō��Ă�ꂽ�Z�ɂ������B
�@�����Ђǂ��A���{�̏펯���猩��Ɗw�K���Ƃ��Ă͂��Ȃ���B���ɂ́A���{�̃A�j���̃V�[���Ȃǂ��\���Ă���B���͂ɂ́A�ё�}���N�X�Ȃǂ̏ё��������A�Ɛт�������Ă���B
�@���������������e�K�W�A�v�Q�S����B���k����������Έꋳ��������̐l���������邾���ł���B���������āA���݂͂P�N���X�U�O�`�U�T���B�������邪�A�����I�Ɏd�����Ȃ��B���{�̂悤�ɂS�O�l�w���ȂǂƂ����Ă����Ȃ��B
�@���E���͂U�T���B����́A�C�U��A���̐��b������l���܂܂�Ă���B���E���̂قƂ�ǂ͕~�n���ɉƑ�����݂Ŋ�h���Ă���A�E�������Z���Ȃ̂ł���B�^����̓o�X�P�b�g�S�[���̂݁A���Ȃ葐�ɕ����Ă���B�g�C���͉^���ꉡ�Ɉ���邾���炵���B���̃g�C���͑召���p�B���E�ǂ͂Ȃ��B
|
|
|
|
|
|
�����ɕ���ő劽�} |
�����̗l�q |
���^���� |
�ӂꂠ���^�C�� |
|
|
 |
|
|
|
�^����ƃo�X�P�b�g�S�[�� |
���ɂ�NARUTO�̊G |
���Ă�I���̓��ӋZ |
�E�������E���Z�� |
�@��c���ɂ́A���Ɂu�����l������F�D�v�Ə�����Ă���B�V�i�̃e�[�u���N���X���~����A������������A��̉��ƐΌ����u�����ȂǁA�ł������̊��҂����Ă����������B���}�̊ŔA�L�O�̐Δ�ȂǁA���{�ւ̊��ӂ̋C�������悭�\��Ă����B
�@�w�Z�Љ�̌�A�o�������ȏЉ�B�q�ǂ��B�̕\��͂��ł��B�����Ȃ�O���l�������̂����疳�����Ȃ��B�@
�@�q�ǂ��B�́A�V�F�S�O�`�P�V�F�O�O�̊ԁA�ߑO�͂S���ԁA�ߌ�R���Ԋw�K����B���H�́A�����͉Ƃɖ߂��ĐH�ׂ邻���ł���B�ł��Ƃ������q�͂U�q�B�ʂ��Ȃ������ł͂Ȃ��B�����̐l�����͌��ɂ���A���̒��ňٓ����邻���ł���B
 �@�����̌�ŁA�{���w�x�e���Ƃ����B�Ƃ���ǂ���Œc���Ǝq�ǂ��B�̌𗬂̗ւ��ł����B�����������A�ƂĂ��悢���͋C���B���ӋZ�̑��Ɍ����I����q�A���˂ł����Ă���R���r������B���̌��i�߂Ă���Q���҂̕\������������ł���B
�@�����̌�ŁA�{���w�x�e���Ƃ����B�Ƃ���ǂ���Œc���Ǝq�ǂ��B�̌𗬂̗ւ��ł����B�����������A�ƂĂ��悢���͋C���B���ӋZ�̑��Ɍ����I����q�A���˂ł����Ă���R���r������B���̌��i�߂Ă���Q���҂̕\������������ł���B
�@���^�������ĊJ�����B��قǂƂ͂����ĕς���ď_�炩���\��B�u�P�O�O���~�������牽���������H�v�Ƃ�������ɂ́A�u��]�w�Z�v�u���h�Ȋw�Z�v�u���H�v�u�g��҂̊w�Z�v��Ƃ������͔͓I�Ȉӌ���A�u�����͎��������炤�v�u�C�O���s�v�Ƃ������q�ǂ��炵���ӌ����o���B
�u�s���������́H�v�ƌ�������ɂ́A�u�������Ă��ꂽ���{�֍s�������v�Ƃ����ӌ����n�ߓ��{���ł������A�C�M���X��t�����X���������B
�@�u�����̖��́H�v�ɑ��ẮA�Ȋw�ҁA��ƉƁA���t�A�f��o�D�A�_�ƉȊw�ҁA���y�ƁA�����t�Ȃǂ�����A���ɂ͉���R�̕��m�Ɠ������q�������B
�@���t�W�c���O�����ŁA�u���{�͔\�͂�L�����Ƃ��Ă��邪�A�����ł͒m���Ώd���B���{����w�т����B�v�Ƃ����A�f���Ȉӌ������Ƃ��ł����B
���������Ƃ́E�E�E
�@�����ɂ͏��Ȃ��炸�V���b�N�������B���̗v���͂���������B
�@��́A�z���ȏ�̕n�����ł���B
�@�����ɏW�܂����Q�O���̎q�́A�d�b������ȂǘA���̎��₷���q�������ł���B���A�̗l�q�����Ă���ƁA�D�G�Ȏq�ǂ��B�ł���ɈႢ�Ȃ����A�C���^�[�l�b�g�o���̓[���ŁA�l�b�g���ɂȂ����Ƃ��킩��B�h���������S�����m���Ă���Ƃ��������ƁA�e���r�͕��y���Ă���̂��H�i����Œm�����̂�������Ȃ����E�E�E�j�@�w�Z�̔��i�͑S���Ȃ��B
�@����ɂ��Ă��A�ȓs����킸��90�L�����[�g���ł��̊w�K�����ƁA�����Ɨ��ꂽ�n��͂ǂ��Ȃ�̂��B
�@
�@��ڂ͂ƂĂ��U�N�O�Ɋ��������Ǝv���Ȃ��Z�����B�^����ً̋}�̋~�ς̂��߁A���z���ނ͔p�ނ��g�����̂ł��낤���A�f�l�ڂ��猩�Ă�������Â��B�����̌��z��ɂ͓K�����Ă���炵�����A�{���Ȃ����������p���������������ł��낤�B�܂��A�g�����ɂ���肪������B
�@���̍������������͂ŏo������z��1,000���~�B��������z�ȏ���o���K�v������B���̍Z�ɂ͂قږ��z�A�Q�疜�~�߂����̂ł��邪�A�����畨���̈��������Ƃ����Ă��A�s�����Ă����̂��낤�B�@
 �@�O�ڂ��q�ǂ��B�̋P�����ł���B���Ɍ㔼�̎��^�����ł́A�ǂ̎q�̖ڂ��P���Č������B�����̖��ɂ��Ď��M�������Č��A�w�K�ӗ~�ɂ��ӂ�A�����n��ւ̍v���ӗ~�������Ă����B
�@�O�ڂ��q�ǂ��B�̋P�����ł���B���Ɍ㔼�̎��^�����ł́A�ǂ̎q�̖ڂ��P���Č������B�����̖��ɂ��Ď��M�������Č��A�w�K�ӗ~�ɂ��ӂ�A�����n��ւ̍v���ӗ~�������Ă����B�@���{�ł͂ǂ��ł��낤�B�͂邩�ɖL���ŁA�b�܂ꂽ�w�K���̒��Ŋw�ԓ��{�̎q�ǂ��B�ɁA���ꂾ���̖�������ł��낤���B�P�����������Ă���̂��낤���B
�@����Ɍg�����̂Ƃ��āA�l��������ꂽ�B
�n�c�`�ɑ���]��
 |
| �w�Z�̃g�C���i���q�p�j |
�@���̍������������͂͋��z�������Ȃ����A�����Ă���l����Ԃ��Ăق������Ƃ��������邱�Ƃ��ł���B����̊炪������̂ŁA���ʂ������₷���B���̊w�Z�ł��A���҂Ԃ��l�X�̐��̐��ɂ��A���{�̂n�c�`�ɑ��銴�ӂ̋C�������\���Ɋ�����邱�Ƃ��ł����B���̈Ӗ��ł͗L�Ӌ`�ł��낤�B
�@�����A�����������������B���z���̃`�F�b�N�͂ł��Ă����̂��A�P�疜�~�Ƃ������x�z���݂����Ă��邱�Ƃ͓K���A���p�̎d���͓K���A���N���̏C�U��Ȃǂ̌o����ς����Ă��邩�Ȃǂł���B
�@�܂��A���炩�̌`�ŁA�l���p���I�ɌW��邱�Ƃ��ł��Ȃ����낤���Ǝv���B�w�Z�Ԍ𗬁A�s���E���𗬂ł��悢�B�l����݂��邱�Ƃł��L���ɂ͂��炭�Ǝv���B
Sofitel �z�e���ɂ�
�@�O���Ȃ̂j����Ƀz�e���ł��낢��Ƙb���B�O���Ȃ̊����Ƃ����ƁA�܂�ʼn_�̏�̐l�̂悤�Ȏ�����ɂ����C���[�W���������̂����A�j����͂��̂悤�Ȍ�����S�����������Ȃ��B�������A���H���R�Ƃ����b���Ԃ肩��A�ƂĂ��D�G�Ȑl�ł��邱�Ƃ͏\���Ɋ�������B
�x�̕��z
�@�n�c�`�͂��������x�̕��z�ł���B
�@���{�����Ōl���x���Ō��Ă݂�ƁA�ݐi�ېŐ��x�ɂ������ɉ����ĐŊz���ς��B����ɁA�Ꮚ���҂ɑ���x�����s���A�x�����z�����B�@�����̃��x���Ō��Ă��A�n����t�Ō�t�����x�ɂ��A�����̏��Ȃ������̂ɑ��Đŋ������z�����B�����ɑ��Đŋ����g���邱�Ƃɑ��ẮA�����̗����Ă���ƌ����悤�B
�@�����n�����x���ł݂��̂��A�n�c�`�Ȃ̂ł���B�������ɁA���ƊԂɂ����Ă��x�̕��z�͂����Ă悢�B����A�ނ��날���ē��R���B���ꂪ�������g����Ȃ�E�E�E
�@�����ɂ́A���������V�X�e���́A�܂��A�Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]() �@�@
�@�@![]() �@�@�@
�@�@�@


 �@ ���܂���炿���k�������A�U�N�Ԓ}�g��w�ɒʂ��Ă����B���Ƃ��Ɛe���ƌ����킯�ł͂Ȃ��������A���ł͒}�g�����̂ӂ邳�ƂƎv���ƁA���R�Ɛe���ɂȂ�B�l�ԂȂ�Ă���Ȃ��́B
�@ ���܂���炿���k�������A�U�N�Ԓ}�g��w�ɒʂ��Ă����B���Ƃ��Ɛe���ƌ����킯�ł͂Ȃ��������A���ł͒}�g�����̂ӂ邳�ƂƎv���ƁA���R�Ɛe���ɂȂ�B�l�ԂȂ�Ă���Ȃ��́B