
ハイタカ幼鳥 愛知県 11月 若杉撮影
前回のチゴハヤブサの記事の中で、地元の人と遠出していった人との関係を書きました。地元の人に敬意を表して …… というあたりはそのままですが、逆の場合、つまり自分自身の地元の観察では注意すべきことがあります。地元だからと言って地元の鳥に自分が一番詳しいということはまったくあり得ない話です。
2025年の秋は、ハイタカが愛知県に渡ってくるのが遅くて、「ハイタカがまだ来ない、10月20日を過ぎても私はまだハイタカを見ていない」と思っていた時、友人に「今年はハイタカの渡来が遅いですね。各地の渡り観察ポイントでもまだ0羽とか1羽しかカウントされていません。当地でもハイタカはまだでしょうね」などとメールを打ったところ、この友人は「昨日も今日も、私は〇〇池の上空でハイタカを見ました。幼鳥と思いますが、画像を添付します」と言って画像を送ってくれました。この池は私の自宅のすぐ近くにあるため池で、私のふだんの散歩圏内でもあるのですが、私とこの友人の一番の違いは、彼がほぼ休みなく、毎日一生懸命に観察・撮影をしていることです。これに対して私は彼よりもうんとこのため池に近いところに住んでいるとはいうものの、彼ほどの頻度では出かけていなくて、行っても彼ほど長い時間見ていないことです。自宅が近いか遠いか、「地元の人」かそうでないかではなく、熱心な観察者であるかどうかのほうが重要です。一生懸命な人にはかないません。

つまり謙虚に自然を観察して、人に対しても「自分は知らないことが多い」と考え、何か話をすると必ず誰からでも貴重な情報が得られることがあるという考えで接するべきと痛感します。ソクラテスの「無知の知」の話と同じで、知らないことを知らないと自覚する、自分は知らないことがいっぱいあるのだろうと思うと(実際そうですが)、さらに学び、探求しようとする意欲が生まれるものですね。自分が「知っている」と思い込んでいる人がいますが(一部の知識人や自分がいちばん一生懸命やっていると思いこんでいる人たち)は、もうそれで終わりでしょう。ましてや天狗になるなどということはあるべき姿の対極に位置することでしょう。
(Uploaded on 1 December 2025)
タカ類を観察していてタカが接近していることに気付くことが遅くなってしまうとタカは後ろ姿になって遠ざかったり、すぐに小さくなったり、あるいは逆にあまりにも近すぎて撮影や観察に対応することができなくなってしまいます。少しでも早く、可能ならば遠くからこちらに向かってくるところを発見する必要があります。一秒でも早く発見する必要があります。近くの樹木から突然現れてすぐに視界から消えてしまうような時には、0.1秒でも早く発見できるとよいです。
早期発見にこれといった絶対的な方法があるわけではないですが、いくつか考えてみます。試してみてください。いくつか組み合わせてやってみることもできます。
1 木々の隙間から見えることもある
四方八方に十分な視界が開けている時は考えなくてもよいことですが、時には視界の悪いところで観察せざるを得ないことがあります。そんな時は、タカが飛んできそうな方角にある木々の枝や葉の隙間も観察すると良いです。特に、ある方向にタカの巣があって近くによくとまる樹木があることが分かっている時などは、そちらからタカが低く飛んで木にとまる可能性が大きいです。繁殖期、私はこの方法をよく使って、けっこう頻繁に木々の枝や葉の隙間を見ています。けっこう役に立っています。
2 一羽が出ると他のタカも出やすい
渡りの時期でも営巣期でも、越冬期でも、いつでもどんな環境でも、一羽のタカが出現すると、それにつられるかのように他のタカが出現することがあります。頭上の高い位置のタカを撮影中は、時々後ろや前を見て、近くにタカが来ていないか確認する必要があります。さっきまでうんと遠くのタカを撮っていたのに、実はこんな近くに別のタカが来ていて旋回していたとは … と思うこともよくあります。撮影中はついつい撮っているタカに集中してしまうので、後ろから来たすぐ近くの別のタカになかなか気が付かない人が多いです。タカは一羽で生きているわけではなく、他の個体や他の種の鳥と複雑な関係(種間関係)を持ちながら生活しているので、一羽が出ると他の個体や種が出ることは当然でしょう。渡りの時はある時間に集中して飛ぶことが多く、集団で通過した後は一段落つくことが多いですが、その集中時は多くの種類、多くの個体が飛ぶものです。
3 逆方向にも飛ぶ
渡りのタカを観察する時は、おおよそ飛んでくる方向がはっきりしていますが、時にはそうでないことがあります。ハイタカなどは逆向きに渡っていく個体もいるので、正反対の方向にも着目する必要があります。ハイタカ以外の種でも低い谷を通り過ぎて、くるっと回って観察者の後ろで旋回上昇をし始めることがありますが、そんな時はかなり近くで汎翔し始めます。四六時中は無理としても、しばしば周囲をぐるりと見ることが必要です。海に出ていったサシバやハチクマが戻ってくることは頻繁にあります。繁殖期のタカでもあちらへ飛んでいったと思っていたらすぐに戻ってくることがよくあります。
4 遠くも近くも
頭上の真上を見る時も、尾根の上や木々の上を見る時(見上げ角の低い時)も、いずれも、遠くと近くに目のピントを合わせる必要があります。そうすれば見落としがなくなります。頭上を飛ぶタカは必ず高いところを飛んでいるわけではなく、高度が低いことがあります。近くの樹木の方向に見つけたタカは必ずしも高度が低いわけではなく、距離が近いわけでもないですね。
5 声にも注目
渡りの時や越冬期は鳴き声を聞くことが比較的少ないのですが、時々鳴くことがあります。他の個体や他の種と諍いになったりすると、普段あまり鳴き声を聞かない種でも鳴くことがありますので、声にも要注意です。もちろん、繁殖期では眼と同じくらいに耳を使うことが重要です。
6 変な飛び方に注意
タカや小鳥、カラスなどのタカ以外の鳥がすごく慌てたような飛び方をしたり、不自然な降下や急降下をしたりするときは、樹木の向こうなどの観察者からは見えないところに別の個体のタカや別の種のタカがいることが多いです。いつもとは違う飛び方をする鳥がいたら、別のタカに要注意です。
7 タカの行動や視線の先に注意
枝どまりのタカや飛翔中のタカの視線の先は重要です。じろっと見た方向に別のタカや獲物となる鳥がいることがよくあります。トビやクマタカがイヌワシの存在を教えてくれることも多くあります。ノスリが急降下したり、サシバが突然鳴き声を発した後すぐにイヌワシが天空から急降下してきたこともありました。タカの視線の先には、いろいろな意味で常に注意が必要です。タカの行動にも敏感になる必要があります。

8 他の鳥の気配に敏感になる
タカ以外の鳥の気配に敏感になる必要があります。特にカラス類はひときわ重要です。タカを探してくれるあなたのパートナーとして、カラスとは仲良くなっておいたほうが良いです。仲良くと言っても無理がありますから、感謝の気持ちだけでもあると良いです。私の場合は「カラス様、様(さま、さま)」というありがたい経験を数えきれないほどしました。タカの存在をカラスが教えてくれたということです。他の小鳥類もカラスとほぼ同じくらい重要です。ヒヨドリはタカに対して、よく鳴きます。メジロもかかなり大きな緊張気味の警戒声を出します。ここでは書ききれないので省略しますが、どんな小鳥もみんな、タカに対しては警戒し、鳴いたり急に移動したり、通常ではない飛び方をしたりします。時にラジオを聞きながら観察・撮影している人を見かけますが、大きな損をしています。
9 その他
太陽の位置によっては飛ぶタカの影の動きでタカの接近にいち早く気づくことがあります。そんな偶然は …… と思われるかもしれませんが、これはしばしばあります。
他の鳥たちの動きや気配ということでは、ため池などでの観察でカモなどの群れの動きを見ることもよいでしょう。それまで休息していた岸辺から離れて池の中央に泳ぎながらあるいは一部が飛んで移動を開始するとか、群れがある一定の方向ばかりを気にしだすとその方向の松の木にオオタカなどがとまっている可能性があります。群れが慌てるように飛んできたら後ろをタカが追いかけていたというようなこともよくあります。ありとあらゆる種類の鳥たちが、タカの存在と接近を教えてくれます。目の前のさまざまな様子を注意深く見るということに尽きますね。
(Uploaded on 27 October 2025)
オオタカやハヤブサなど、多くの鷹隼類はしばしば同じとまり場にとまっていることがあります。今とまっている木の枝に昨日もとまっていた、そういえばあの木にはよくとまるな…… ということをよく経験します。とまって、監視や獲物探し、休憩などに利用しています。観察する私たちからすると、あそこの枝か、ここの鉄塔の最上段のアームの上か、あちらの岩場か、どこかにとまっているだろうと思って探すと、そこにちゃんととまっていたりするので助かります。多くのタカにとって、このようなよく利用する特定のとまり場というものがあります。そのとまり場から直接飛び立つことがある一方で、そのとまり場から少しだけ、3~4歩くらい歩いてから飛び立つことも多いです。
【 オオタカの例 】
鉄塔にとまるオオタカはどこにとまってもそれなりにけっこう目立ちますが、時にはどうしてこんなところにとまるのかと思うほど入り組んだ、外から見つけにくいところにとまることがあります。下の画像では赤い矢印の先にとまっていますが、この鉄塔は大きくて、複雑に鉄骨が組み合わされていて、遠くからの確認では鉄骨の陰になっていて、ここにとまっていることはひじょうに分かりにくかったです。オオタカが一番よく見える位置まで移動して撮影してもこんな程度です。

人はカンカン照りの直射日光を避けて涼しい日陰に入ろうとしますが、鷹隼類は日射を避けようとすることは全然なく、猛暑日や強い日差しの中でも光を浴びて何十分間でも平気でとまっています。ヒナが大きくなりつつある繁殖期真っ最中のこの日も狩り目的でとまっていました。隠れるように隅にとまっていたのは人間に見つからないためではなくて、狙いとする獲物に悟られないように、見えないところ、見にくいところ、気づかれにくいところに意図してとまっていたのでしょう(推測)。特定の鳥を獲物にしようと一羽に狙いを定めたものの、どのタイミングで飛び出せばよいか待つ時間も必要です。この個体はこの後飛んで、別の鉄塔にとまり、そこで40分ほど獲物を探索して、最後、ドバト40羽ほどの群れを追いかけていきました。雑木林の向こうで高度を下げて見えなくなったので、狩りの成否は不明でした。
下の画像のような、もっと隠れたところにとまっていたこともあります。大きな鉄塔の、大きな碍子(ガイシ)の陰に隠れるようにしてとまっていました。でもよく見ると、足は水泳の飛び込みの時のように、指先と爪を鉄板の角に引っ掛けています(画像の黄色い矢印)。こうしていれば急に飛び出すことになっても踏ん張って、初速を大きくすることができます。
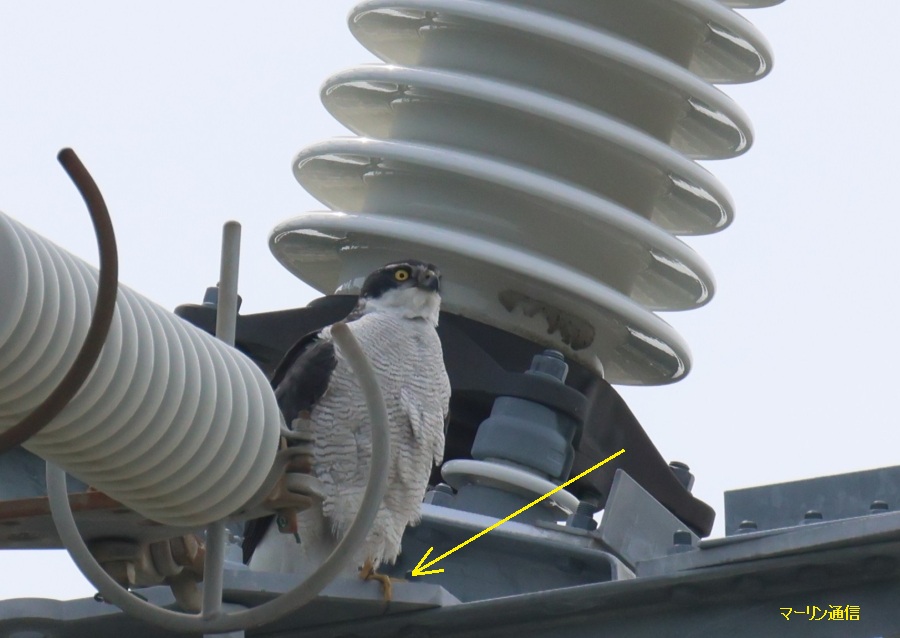
趾と爪の構造上、平たいところにとまると指の先が丸く盛り上がってしまい安定しませんから、わざと木の枝(ほぼ円柱状のもの)にとまったり、平面の場合はこういう隅っこにとまり趾と爪を前に垂らすことが多いです。ただ、この時は、3~4歩ほど歩いた後に鉄塔のアームと呼ばれる部分から飛び立ちました。飛び出しまでに十分な時間的余裕があったからなのか、より良い引っ掛かりのある部分があったからかもしれません。そのまま飛び出すとどこかに翼が当たってしまうような不都合があったのかもしれません。ゆっくりと飛び出しましたが、鉄塔の高い位置から落ちるように飛んだので高度が下がるにつれて速度はどんどん増していきました。最後は地上を歩いている鳥を狙いましたが、狩りは失敗しました。
【 ハヤブサの例 】
ハヤブサが鉄塔にとまる時も、オオタカと同じようなことが見られます。ちょうど水泳の飛び込みスタートの時といっしょで足の指をスタート台の角に引っ掛けるように合わせて、滑らずに力が入りやすくしています。最近の競泳選手のように、片足は台の一番前に当てて、もう片足は後ろの傾斜した部分にあてて飛び込むことは野外では無理でしょうが、そういうものがあればひょっとして利用するかもしれません(私は見たことがありません)。いつも休憩や巣として利用している岩場に、そういう趾を引っ掛けるところがなければ3歩とか4歩、歩いて行ってそこから飛び立ちます。あるいは足を引っかける部分があったとしても、そこから飛び立つと翼が岩や木に当たってしまうなどの何か別の不都合があれば歩いてから飛び立ちます。もちろん緊急時には足の筋肉を使って翼を閉じたままでポンと飛び出せば、飛び出した後から翼を開くことで難なく飛ぶことができます。
オオタカは巣から直接外へ飛び立つことができますが、ハヤブサは巣から何歩か歩いた後に飛び立つことが多いようです(歩かなくてもよい巣もあります)。
-----------
オオタカとハヤブサについて記述しましたが、他のどんな鷹隼類でも、ほぼ同じことが言えます。どの鷹隼類でも、平べったくて広いところにとまることは苦手で、木の枝にとまることや、隅っこにとまることが好きなようです。
ただし、すぐには飛び出しそうでないところにとまっていても、油断はできません。急に気分を変えて、くつろいでいた様子からきりっとした姿に瞬時に変わります。ほぐれてふんわりとかさが増したようになっていた羽毛が体に密着するように小さくなって、すぐに2~3歩歩いて飛び立ちやすいところからすっと飛び立ちます。この間わずか数秒以内ですから、とまり個体からは片時も目が離せません。私は飛び立ちの瞬間を撮影目的にはしていないですが、飛び立ちの瞬間が撮れば、その時は思い切り翼を開いていますので、風切や尾羽の一枚一枚のようすを確認することができます。どの羽に折れや傷みの欠損が見られるか、どの羽が旧羽でどの羽が新羽なのか、どこまで換羽が進行しているのかなど、その時の換羽状況がはっきりと分かります。通常の飛翔時にはあまり確認できない小翼羽4枚の換羽状況も分かることがあったり、大・中雨覆など隣りどうしの羽の重なりの上下位置関係が分かることがあったりしますので、なるべく飛び立ちの瞬間は撮影するようにしています。
(Uploaded on 5 July 2025)
鷹隼類の観察ではある定点を決めてそこで長時間待ちながら観察する方法と、徒歩あるいは車で移動しながら観察、探索する観察法があります。今日は「待つ」観察法について、シチュエーションを2つあげながら感じたことをエッセイ風に書いてみます(科学的な話ではないです)。
【 営巣期、巣から離れた所で待つ 】
オオタカの繁殖期に、巣から少し離れた地点に停めた車の中から、あるいはバックドアを上げて椅子に座って静かに観察するとします。もちろんオオタカへの影響はほぼゼロになるように気を付けながらの観察です。巣からの距離はどのくらい空けないといけないペアなのか、あるいはどのような配慮が必要な環境なのか、車内からの観察でなければダメな環境かそうでないかなど、いろいろ考えます。双眼鏡であまりじっくりと巣方向をのぞき込むことがないようにし、こちらからオオタカの存在が確認できなくても巣方向へ視線を向けないようにする必要がある時もあります。巣の近くで作業をしている農夫をオオタカが脅威と認識しないことが多いように、オオタカに観察者を無視してもらうようにする必要があるところかそうでないところかなども考えます。
こうして待っていると、1時間経ってもオオタカの出現がないことがあります。2時間待っても出現がないこともあります。場合によっては6時間、一度も姿が見えないことがあります。巣の近くにいる雌が時折り猛り鳴き(キャッキャッキャッ … )や高鳴き(フィアー、フィアー、 … )をすることはあっても、姿が一度も見えない時があります。こうなると、ひょっとして繁殖を中断してしまったのか、失敗したのか、観察の悪影響があったのかなど、さまざまなことが心配になってしまうことがあります。でも、何の変わりなく営巣活動を続けていることが多いです。
動きが「活発」な日は、たまたまオオタカの動くところを目の当たりにできただけのことです。あるいはヒナが小さくて、一日に10数回も獲物を運んでくるので観察しやすくて、動きがよく把握できただけという日もあります。
観察を始めて3分で雄が近くへ飛んで来て木の枝にとまったという場合もあるし、逆に3時間一回も姿が見えないこともあります。それは観察者のせいではなく、完全にオオタカの都合です。観察者は巣から見て北方に地点を置いていたけれど、オオタカが南の方へ狩りに出かけたとか、なかなか獲物が捕れなくて雌に獲物を運んでくることができなかっただけなのかもしれません。観察者が観察を始める前に、すでに大きな獲物を捕って自分は食べて雌にも獲物を運んだばかりなので、3時間ほど動きがなかった(休憩していた)ということもあるでしょう。観察者の観察力とは何の関係もなく、皆、オオタカの都合です。
もちろん、巣からの距離が長くなればなるほど姿を見る確率は(巣~観察者の)距離の2乗に反比例する程度で小さくなってきます。
開放的な環境で営巣するハヤブサやチョウゲンボウはオオタカと比べれば姿を見ることがたやすく、しかも、次の行動が手に取るように分かり、予測しやすく読みやすいですが、森の忍者ダカとも称されるオオタカは、環境にもよりますが、その動きがけっこう把握しづらいことが多いです。

【 開放的な環境で待つ 】
とある開放地で、あるいは目の前が開けている水辺で、一人で、毎日4時間ほどタカ待ち(オオタカ待ち)をするとします。その間ほとんどじっとしています。私は雨が強くなると家に帰ってしまうことが多いですが、小雨なら傘をさして雨を感じながら観察することもできます。寒風が吹きすさべばそれに適宜対処するだけです。季節によって待つ地点や観察対象が変わりますが、ほぼ一年中、毎日どこかで続けることができます。
できたら静かなところで一人で観察するとよいでしょう。極力、思考しないようにし、周りをしっかりと見て本質的な事柄に気づくことが大切です。この際、湧き出てくる妄想を瞬時に断ち切る努力が必要です。こういうことを続けている人はいつか哲学者になれます。さらに進む人は智者・覚者に近づけます。適切な指導者がいないと覚者にはなれませんが覚者に近づくことはできます。
「待つ」ということで、周りの変化が分かってきます。多くの場合、昨日いなかった鳥が今日やって来ていたり、昨日までいた鳥が今日はいなかったりします。鳥だけではなく、他の生命もみな同じです。自然の変化、時の変化、季節の移ろい、自分の心の変化と体の変化。気が付かないようでいて、刻一刻と太陽の高度が変化していくので、見える光景も刻々と変わります。目の前にいるカンムリカイツブリが昨日見た個体と同じ個体だったとしても、その個体は一日分の歳をとって一日進んだ時の中にいます。観察者も一日分の歳をとっています。植物のつぼみも、昨日のつぼみと今日のつぼみは違います。いつの間にかこんなことはすぐに分かるようになってきます。秋から冬へ(3か月間)、昨日と今日(一日間)、朝と昼(6時間)などの変化はすぐ分かると思いますが、この比較の時間(カッコの間隔)をさらにどんどんと縮めていって、一時間に、一分に、一秒に、そして一瞬へと短くしていく必要があります。
そうすると、これが一番大切なのですが、外の世界だけではなく自分の体と心の一瞬ごとの変化に気付くことができるようになります。さらに観察が進んだ人は、自分自身にも他の生命にも我がないということが自然と分かってくると思います。そして、生きるということも死ぬということも世間で言われているほど大げさなことではないんだということも分かってきます。「待つ」観察法は意外と効能があります。

(Uploaded on 15 June 2025)
タカは「高く飛ぶをもってタカという」と言われているようですが、気象条件の良いとき飛ぶタカは本当に高いところを飛んでいます。タカの渡りの観察においても、タカにとって渡りの条件が良い日は、もう肉眼だけでは見えないほどの高空を飛んで渡っていきます。山の端を双眼鏡で見てみたら、そこにサシバが10数羽見えた、双眼鏡を取ったら何も見えなかったということはよくあることです。今のところまだ視力に自信のある私ですが、肉眼だけではとても見えない高さを飛ぶタカを見かけることがよくあります。視力に自信のない方たちにとっては渡りの観察が苦痛になることもあるそうです。それほどの高空を飛ぶことが多いということです。

この春、ハイタカの渡りの観察をしていた時のことです。一羽単独でハイタカが眼下を飛んで私のいる方へ接近してきました。雌と思われる幼鳥で、どんどんこちらへ近づいてきましたが、かなり近くなる前に北へ逸れてしまい、北方の尾根で少し旋回上昇して、その後、風に流されたからか新しい上昇気流を見つけたからなのか、私の立っていた地点の上までやって来て、ここでさらに旋回上昇していきました。風があり日差しがあったから上昇気流が強かったようで、ハイタカはどんどん高空へ上がっていって、上がり過ぎて、14倍の防振双眼鏡で見ていても青空に溶けて見えなくなってしまいました。視力1.2で水晶体に濁りやゆがみがない目で、重くて大きな14倍の防振双眼鏡で見ていたのに見えなくなってはどうしようもありません。双眼鏡からスコープに目を移すことも可能でしょうが、一度双眼鏡から目を離すと二度と双眼鏡の視野に入れることさえも不可能なほど高くなっていたのでスコープに替えることはとてもできませんでした。お手上げでした。秋の渡りと違って春は秋以上にもやがかかったり春霞が強かったりしますので、春の渡り観察は秋の観察以上に見にくいことが多いです。
春や秋の渡りの観察は、おおよそ飛去方向が決まっていますから見失ったとしても大きな問題はありません。むしろ、高空へ上がることができるということは渡りの条件がかなり良いということの証でもあるので、タカたちにとって、とてもよいことなのでしょう。渡りのおおよその方向が決まっていますのでこれといった問題はなさそうです。
ところが、オオタカやクマタカ、イヌワシ等の繁殖調査や行動圏調査をしている時は高空へ上がった後どちらの方向へ飛んでいったかはかなり重要で、滑空時の飛去方向は大きなポイントになります。せっかく朝からその個体の位置を捕捉し続けて観察できていたとしても、ここで行方が分からなくなってしまうと一からやり直すことになってしまいます。再び広い範囲内でその個体がどこにいるのか見つけ直さざるを得なくなり、その日の振出しに戻ってしまいます。多くの時間がかかり、やっかいです。どんなタカも旋回上昇した後に必ず滑空しはじめてどちらかへ飛去するのですが、その飛んでいった方向を何としてでも捉えるようにしたいと思っています。でも、上がり過ぎて溶けて見えなくなってしまうので、そうなったら人間の力ではどうすることもできません。

旋回上昇の後のタカの行動はかなり興味深いことが多く、今までこの通信でもたくさん書いてきました。オオタカが高空まで上がっていった後にレースバトの群れに突っ込んだこと、オオタカがシラサギ(大きかったからダイサギか)の背中に突っかかっていったこと、イヌワシがノスリに突っ込んだこと、いろんなタカ類が自分の巣のある林に高空から突っ込んでいったこと、侵入個体よりも高いところまで上がって優位な位置について侵入個体を排除し始めたこと、繁殖初期にディスプレイ飛行を始めたこと、ただ単に移動するために遠くまで滑空していって尾根向こうで見えなくなったことなど、たくさんの観察例があります。旋回上昇が始まると、その後何かが必ずと言っていいほど起こり、見事な高速飛行、曲芸飛行などが見られることも多く、私はタカが高く上がっていくといつもわくわくします。
(Uploaded on 25 May 2025)
BIRDER 2025年3月号(2月15日発売)の特集は「街のハンター 生きざま事典」です。

タカ類5種(オオタカ、ハイタカ、ツミ、ミサゴ、トビ)、ハヤブサ類2種(ハヤブサ、チョウゲンボウ)とフクロウ類2種(フクロウ、アオバズク)の都会でのハンティングが中心です。
3月号の特集および鷹隼類関連の目次は次のようになっています。
・ 街なかは意外と暮らしやすい? 漫画=一日一種
・ イラスト図解 街のハンターたち 文=若杉 稔 イラスト=富士鷹なすび
- 街のハンターのプロフィール
- 街のハンターの見どころ 都市公園/ビル街/都市河川~海岸
・ 蒼鷹 浪速の空を翔る! 大阪ホークウォッチングガイド 文・写真=久下直哉
- 関西版 ハイタカ、オオタカと出会える公園
・ ツミとインコ 奇妙な鬼ごっこの理由 文・写真=高野 丈
・ サワラの葉っぱ サクラの花びら……!? 街暮らしのツミ 意外なグルメ
文・写真=井上茉優
・ ホテル子育て21年目!? 泉大津市のハヤブサ 文・写真・図=阪上幸男
・ 街のハンター 今昔物語
- カラスが鍵を握るオオタカの都心暮らし 文・図・写真=西海 功
- 街のハンターに追われるコアジサシ 文・写真=奴賀俊光
・ 猛禽天国パリ 古城で命を育むチョウゲンボウ 文=井田彰彦 写真=NHK
・ 鳥学会で発見! 高校生による街のハンター研究
- 人生の目標は生物と人間が共存共栄できる東京・日本・世界を作ること
文・写真=千葉美文(東京都立科学技術高校)
- 「先生の鬼!」 夏休み返上で仕上げたポスター発表
文・写真=群馬県立新田暁高等学校 文理総合系列 Project K
・ 野鳥アートカレンダー 水谷高英「美しき猛禽たち」 #03
ハイイロチュウヒ イラスト=水谷高英 (制作裏話も)
・ Field Report #171
大陸型チュウヒを追って 文・イラスト=水谷高英
このうちの、富士鷹なすびさんの素敵なイラストに若杉がテキストを書きました。そのページのレイアウトは以下のようになっています(すみません、いつものようにクリックしても画像は拡大されません)。
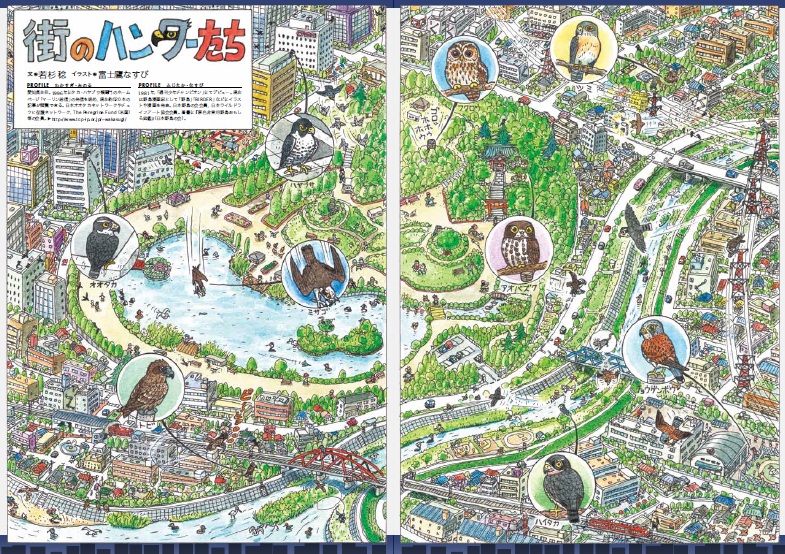
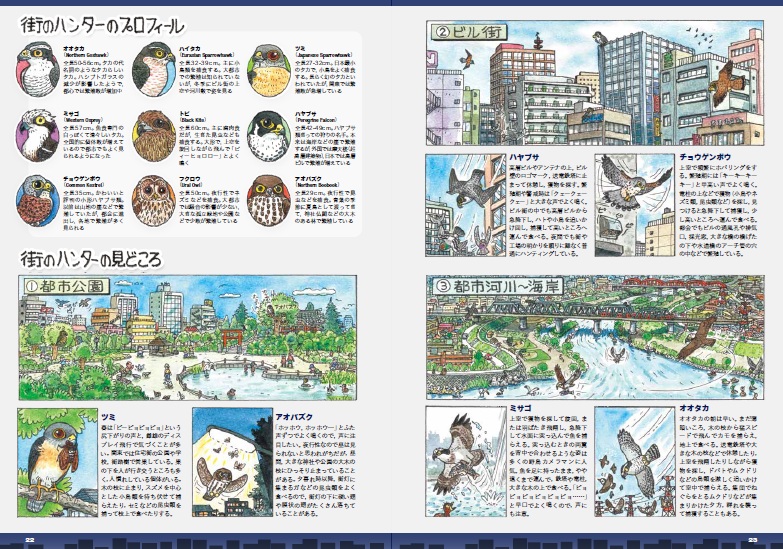
BIRDER 2025年3月号 20~23ページ「街のハンターたち」
筆者が今までに BIRDER 誌に書いた文章は、下記の通りです(すでに購入できなくなった号があります)。
1 1999年11月号の P.66 「Net で GO! GO! GO!」 マーリン通信の紹介
2 2010年 2月号の PP.76-77 「拝啓、薮内正幸様 ♯26」
3 2012年 9月号特集の導入 PP.8-9 「ハヤブサとはどんな鳥か」
4 2012年12月号特集の導入 PP.6-7 「冬のタカ観察の魅力とは?」
5 2013年 9月号特集の中 PP.20-21 「ハイタカ属とはどんなタカたちか?」
6 2014年 9月号特集の導入 PP.4-5 「夏鳥としてのサシバとハチクマ 観察の魅力」
7 2014年 9月号特集の中 PP.24-25 「サシバの幼鳥は何をしに日本へ来るのか?」
8 2016年 2月号特集の導入 PP.18-19 「水辺のワシタカ類 その観察の魅力」
9 2017年 1月号特集の中 PP.30-31 「ハヤブサ類との付き合いかた ~保全の過去・現在・未来~」
10 2017年12月号第2特集の中 PP.35-37 「オオタカ希少種解除 なぜ祝えないのか?」
11 2018年10月号特集の導入 PP.16-17 「空振りしないための タカの渡り観察の基礎知識」
12 2021年 9月号特集の中 PP.22-28 「”部位別” 渡るタカの見分け方ガイド サシバ・ハチクマ・ハイタカ属・ノスリ」
13 2021年 9月号特集の中 PP.34-35 「サシバ暗色型 観察ガイド」
14 2023年 2月号特集の中 P.29 「ヨシ原の覇者 チュウヒ & ハイイロチュウヒ」
15 2023年 2月号特集の中 P.30 「多彩な技を持つ高速ハンター コチョウゲンボウ」
16 2023年11月号特集の中 PP.20-23 「猛禽のハンティングを徹底解剖!」
17 2025年3月号特集の中 PP.20-23 「街のハンターたち」
(Uploaded on 15 February 2025)
人間が何かを理解しようとするとき、思考しやすいように対象を単純化して理解しようとしますが、不可能なことが多いです。自然界はかなり複雑にできています。単なる複雑さの問題よりも、時間とともに、今の自分の頭では考えられないような異次元の世界が目の前に次々と現れてくると言ったほうがよいでしょう。誰かがノーベル賞級の新しい世界を切り開いたとしても、その向こうにまた別の、誰も見たことがないような新しい世界がちゃんとあります。誰にも見えないような世界がどっしりとそこにあって、それには誰も気が付かないままずっと大昔から近くに存在している世界があります。形而上学の話ではなく、宗教の話でもなく、誰にも理解できない、まだ発見されていない現実の世界がここにあります。こういう世界を切り開いてきたのはほとんどが天才科学者であり、一部の思想家、文学者、東洋の哲学者だったりします。そういった人たちから莫大な恩恵を得ることができましたが、どんなことにも表と裏があって、恩恵以上の弊害もたくさん被っており、プラスとマイナスを考えると、どちらがよかったのか分からないです。個人的なことでも、「こんな考え方があったのか」「こういう世界もあるのか」「こんな生き方もあるんだ」などと、生きることがこれまで以上に楽になる方法も得られます。一方でその逆もたくさんあります。人生で何を選択すべきかはかなり重要なことです。
天体観測では、アマチュアが小さな望遠鏡でそれなりの楽しみを持ちつつ観察や撮影をすることができますが、遠くの天体や光の弱い天体、可視光線では見えないような天体では大きな特殊望遠鏡などの別の大々的な観測資材が必要になります。真理を突き詰めるためには量子力学や相対論、高度な数学、洞察力が必要ですし、一人で研究するわけではないのですらすらと論文が書けるような語学力や人付き合いも必要です。
鳥の観察はこういうものと比較すると楽そうでとても簡単なように見えます。誰でも気楽にバードウォッチングができますし、カメラを買えば誰でもそれなりの高画質の写真が簡単に撮れます。この辺りはアマチュアの天体観測に似ているところもありますが、実はアマチュアの趣味の鳥の観察もかなり難しいです。
それは、単に鳥を見るだけのことであっても、人間の「感受」や「概念構成」「認識」の在り方と深く結びついているからです。この通信に何度も書いてきたことですが、肉眼に入った光を脳の中でどう処理するかは、ほとんどがその人の思い込みや決めつけ、単純化しすぎること、錯覚、バイアス、肉眼の限界など、ありとあらゆることから影響を受けて、結果的に観察者が正しく認識することを阻害してしまいます。庭に来るメジロやヒヨドリを観察することは簡単なような気がしますが、これらの罠にかかって正しく観察できていないことがほとんどです。
例 1 オオタカがキジバトを追う
先日、こんな経験をしました。電線にとまっていたキジバトをオオタカ雄成鳥が捕獲しようとしました。キジバトは当然全速力で逃げ、オオタカも力いっぱい羽ばたいて追いかけました。両者の距離がだんだん縮まって、キジバトとオオタカが一点に結んだ(捕獲した)かのように見えましたが、数分後、オオタカが何も持たずに山から出てきたので狩りが失敗だったことが分かりました。どうしてあれだけ接近したのに捕れなかったのだろうかと考えてみました。最初キジバトとオオタカと私は下の図のAのような位置関係でしたが、キジバトが途中から(上から見て)右カーブして雑木林の方へ飛んでいきました。
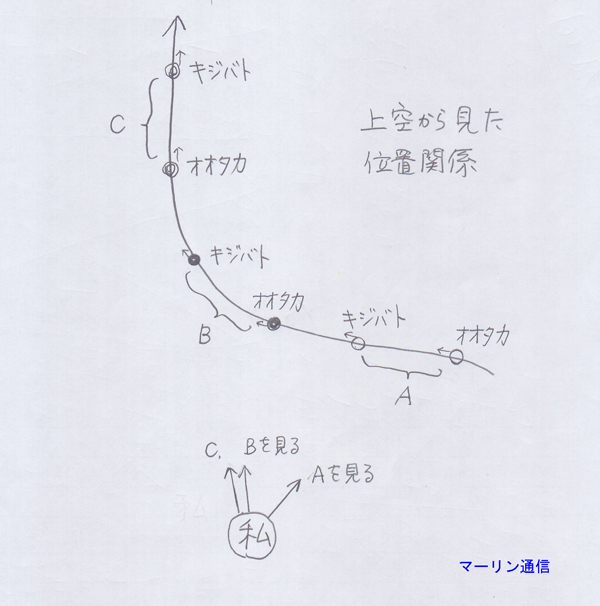
キジバトとオオタカの間の距離が同じでも、見ていた私からすると、Aのあたりでは十分に距離があるように見え、Bではキジバトとオオタカの距離はぐんぐん短くなっていくように見えて、最後Cのあたりからは二者が一点になったように見えるはずです。二者の距離がまったく変わっていなくても、あるいはキジバトがオオタカを引き離すような状況になっていたとしても、観察者からは逆に距離が縮まったかのように見えてしまいます。これも一種の錯覚なのでしょう。どんどん距離が縮まっていって一点に見えると誰もが「捕っただろう」→「捕った」→「捕ったに違いない」と思ってしまいます。
捕ったか捕れなかったかは現地まで行って確認しなければいけないです。カラスやヒヨドリなどの気配を参考にするか、山から出てくるまで待つか、そのうを膨らませた状態で出てくるまで待つか、あるいは繁殖期なら獲物を持って巣に帰ろうとするまで待つかなど、対処はいろいろあるでしょう。後になって先ほどの判断が間違っていたことが分かることもあります。
上で「失敗だった」と書きましたが、実際はハトの捕獲に成功したけれども、地面に降りたところでカラスに奪い取られてしまった可能性もあります。あるいは一度はハトを捕えたけれどもタカの爪がつるんとはずれて獲物が逃げてしまった可能性もあります。初めから悠々とハトが逃げ延びた可能性もあります。他にも考えてみれば可能性はいくつかあります。タカの近くで実際のようすを見ていなければ、どれがほんとうなのかは分からないはずです。でも、多くの場合、私も含めて、「たぶん捕っただろう」あるいは逆に「捕れなかった」などと決めつけてしまいがちです。
例 2 ハイタカがキジバトを捕獲した?
少し前のことですが、友人が「ハイタカがキジバトを捕った写真が撮れたよ」とのことで、写真を送ってくれました。その時点で私は「ハイタカがキジバトを捕ることはありうることだけど、それは稀なことだ。ひょっとしてハイタカではなくてツミではないのか?」と思いました。写真を見ると確かにハイタカがキジバトを持って飛んでいました。私は「うーん」と思いましたが、別の写真を見せてもらうと、ツミの幼鳥の後ろ姿が写っていて、キジバトを捕える瞬間が連写で何枚か写っていました。これでキジバトを捕らえたのはツミということがはっきりしました。
ではなぜハイタカがキジバトを持っていたのか、その時の状況をさらに聞くと、小さいタカのような鳥がキジバトを捕えた後すぐに池の対岸の地上に降りたそうです。そこへすぐに何か別の鳥が横から低くやって来て、池の対岸なので詳細はよく分からなかったけれどもタカがキジバトを持って飛び立ったということでした。つまりツミ(写真からは雌幼鳥)がキジバトを捕えた直後、池の対岸に降りて、そこへハイタカ(写真からは成鳥と思われる雌)が来てツミからキジバトを奪い取って、持って飛び立ったということでした。これでほぼ解明できました(この推論の中にもひょっとして間違いが含まれている可能性はあります)。
ハイタカがキジバトくらいの大きさの鳥を捕ることは少しもおかしくはないですが、多くのハイタカはそんなことはめったにせず、一方、ハイタカよりも気が強いツミはハイタカより小さな体ながらも自分より大きい鳥を捕獲しようとすることがよくあります。だから話を聞いていて、「何かおかしい」と思ったのです。現に野外では、ハイタカ雄はほとんどメジロくらいの大きさの鳥ばかりを捕り、ハイタカ雌はもう少し大きいけれども小鳥を捕るところを見るのがほとんどです(ハイタカがキジバトを捕ることを否定しているわけではありません)。
撮影者の名誉のために書き加えますが、この時の観察者は実に熱心な努力家で、長時間にわたりタカを待ち続けてじっくりと観察しています。それくらい熱心な有能な人であっても、やはり自然はそういう範疇の想定以上に複雑なので、誰にでも間違いは出てきます。100人が100人とも出てきます。全国的に有名な鳥見人でも種名を間違えてしまったり、行動に関して勘違いしてしまうことはよくあることです。
この2つの例のほかにも、チュウヒが魚を食べていたとしても、まさかミサゴのように急降下して水の中にドボンと飛び込んで生きた魚を捕えたか、あるいは水際にいた死んだ魚を食べていたのかは、一部を見ていただけでは判断できません。クマタカが大きなシカを食べていても、自分が仕留めた獲物なのか、猟師が捨てたシカを食べていたのかは、よくよく見てみないと分かりません。こんな例はいくつでもありますので、自分勝手に推論してそれをそのまま結論にしないようにしなくてはならないです。
------------- +
冒頭で書いた「新しい次元が開ける …… 」という例にはほど遠い例しか挙げられませんでしたが、天体の世界でも、身近な鳥の世界の観察でも、人間には見えない部分がたくさんあります。人はそれに対して無意識に勝手に何かを補ってしまい、「推測」としておくべきことを事実だと思い込み、自分勝手にストーリーを作って納得してしまうという特性があります。これは人間なら誰にでもあることです。人が、何から何までをその都度ゼロから考えていると、人間の脳はきっと疲れ果ててしまうでしょうから、バイアスにはバイアスなりの利点もあることが分かります。
そんなわけで、誰でも、正しく見ることと錯覚などを区別することは難しいことです。「写真に写っているから」ということも、その判断が正しいかどうかとは関係がないです。写真を見て自分の勝手なストーリーを作ってしまうことはごく普通の、誰にでもあることなので、ほんとうは「私はこの写真をこのように解釈した。違う解釈があるかもしれない」という謙虚さが大切だと思います。
天体と鳥の話を書きましたが、実は人生のあらゆることがらも、すべて同じです。眼、耳、鼻、舌、身体、心で感受した光や音や香り、味覚、固さ、暑さ、気などの刺激を脳がどう処理するかを考えると、(失礼な言い方に聞こえてしまうかもしれませんが)誰の脳の処理もほんとうにいい加減なのです。自分の都合のよいように解釈して、勝手に決めつけて、都合よく判断して、そして、訳も分からず怒ったり、欲を抱いたり、真実を見ようとしないものです。
話を戻します。私が写真を撮るのは自分の肉眼の性能とそこから得られる認識能力を高めることが目的です。私には芸術写真を撮ろうという気持ちはこれっぽっちもないので、いわゆるカレンダー写真、芸術写真などとは無縁ですが、撮った写真をなんとかして肉眼の能力以上に生かして、鳥の世界の真実に少しでも近づこうと工夫をしています。
肉眼の性能を補助する仕事は双眼鏡や望遠レンズにやってもらいます。そのためには(私の場合は)双眼鏡はやはり14×以上の防振双眼鏡でなければうまくいきません。カメラは、
〇 1秒を20分の1秒ごとに分割して見えるようにしてくれるもの、
〇 激しく動いているものを止めて見えるようにしてくれるもの、
〇 肉眼ではシルエットにしか見えない曇り空の鳥でも体下面の模様が縦斑か横斑か分かるようにしてくれるもの、
〇 高速で飛んでいる鳥でも細かな換羽状況(羽が新羽か旧羽か)や、小さな欠損があるかないかを手にとるように見せてくれるもの ……
などと割り切って、つまり人の認識能力を補助してくれるアイテム、助っ人のようなもの、眼の補助具として使っています。野鳥カメラマンの方が写真に持つイメージとはかなり異なったカメラの使い方をしています。
(Uploaded on 13 October 2024)
重複カウントというミスはタカ渡りの観察時だけでなく、一年中起こります。越冬中のハイタカの観察を例に挙げてみます。半日でハイタカの狩りを5回見たとします(最大では半日で20数回の日もありました)。それを「ハイタカ5羽」と記録することはないだろうと思いますが、では「ハイタカ5回」と記録すればいいのか、また、ハイタカは何個体いたと記録すればいいのでしょうか。これらを考える時、基本はやはり個体識別です。同一個体と確認できた一個体が狩りを5回繰り返したのなら「出現1個体、狩り5回」で間違いないです。個体識別を試みたが成鳥と幼鳥がいたことだけが確認できて、その2個体あるいは2個体以上が5回の狩りをしたのなら「最低2個体、狩り5回」となります。5回のうちの3回はどの個体なのか分からない時はこういう記録しかできないです。個体識別では体の色や鷹斑模様、個体の大きさなどではなく、高精細な画像を撮影して風切や尾羽などの欠損を確認することが一番間違いが少なくて、良いと思います。しかし、ピント、露出、大きさ(撮影個体までの距離の近さ)や光線の具合いがよく、ある程度うまく撮影できたとしても、いつでも、すべての個体を完全に高精細に撮影することはなかなか難しいです。距離があまりにもあったり(飛んだのが遠すぎたり)、出現した時間が短すぎたり、飛んだ角度が真横だったり(体下面や翼下面・上面の画像が撮れない)、あまりの逆光で写真にならないなど、いつもうまく撮れるとは限らないです。
みごとな高精細画像が撮影できたとしても、それが個体識別のためにベストな画像とは限らないです。種や亜種識別のための画像と同じで、見るべきポイント(その種の特徴的な部位の色や形)が写っていない画像はあまり役に立たないからです。そうすると、得られた情報はわずかで、かろうじて違いが分かり「2個体以上は出ていた」ということしか分からない時もあります。
ただ、ハイタカの場合は雄と雌で、あるいは成鳥と幼鳥でかなり色や模様が異なります。さらに幼鳥の場合は胸の斑が三角形であったり三日月形であったり縦に長く連なったり、また、横斑の間隔の粗さもかなり違ったりして、双眼鏡で見るだけでも違いが分かることがよくあります。雄成鳥の場合も下の画像のように喉と胸が真っ赤と言っていいほどに赤い個体からこのような赤みがまったくない個体までさまざまな個体がいますので、そういうあたりを中心に見てみると必ずしも高精細な画像が必要でない場合もあります。2羽同時に飛んだ時には大きさの比較ができて雌雄の判断ができることもよくありますので、識別の参考にはなります。また、小さな欠損を確認せざるをえない場合はやはりある程度の高精細さが必要ですが、大きな欠損は双眼鏡だけで確認できることがあります。

越冬地や繁殖地のハヤブサやオオタカについても同じようなことが言えます。ともに成鳥は体下面が横斑で、幼鳥は縦斑ですので、判断はすぐできます。成鳥や幼鳥が何回も出現したら模様や欠損状況などから個体識別をしなければいけなくなります。この辺りのことはハイタカの場合とほぼ同じです。何回出現したかという情報とともに、可能な限り、何個体の出現があったかが大事になってきます。
クマタカなどの観察や調査をするときも同じことが言えます。朝から見ているとなかなか出現がなく「今日は出ないのかな」と思う時間帯もありますが、出る時は一日に何度も出現します。今見ている個体が先ほど出た個体と同じか別か、あるいは夕方見た個体が午前中に出た個体と同じかどうかなどと、いちいち吟味する必要があります。大雑把に成鳥3、若鳥1、幼鳥1など、あるいは可能ならばそれらを雌雄で分けることはできますが、正確を期すにはやはりすべて画像を撮影して可能な限り高精細な画像から個体識別をする必要が出てきて、フィールドで夕方までにこの作業を完了させることはかなり難しいです。
うまくいかない時もあります。クマタカが頭上で同時に7羽出て旋回し始めるとします(私の今までの同時最高羽数が7羽です)。その日の観察個体数はこの時だけでも7個体で、その日一日で別の時刻の出現もあるので、7羽または7+羽となります。7羽もぐるぐると旋回し始めると、個体識別に使えるような角度の画像をもれなくしっかりと撮影することは困難で、入り乱れてきて、撮った個体とまだ撮ってない個体の区別さえできなくなることがあります。このように、個体識別をしっかりやろうとすればするほどもどかしく、判断できない個体が出てくるものです。先に出た個体と同一なのか異なる新たな個体かはカメラの液晶画面だけでは判断不能の場合があり、PCに画像を取り込んで拡大し、PC画面の左右を分割し、左側ウィンドウ1枚と右側ウィンドウ1枚で2個体を並べながら比較しないと無理になります。
限界もあります。いくらしっかりと個体識別用の撮影をしていても、山の端をすっと短時間かすめるように横切っただけの個体がその日の朝から今まで見てきた個体と同じか違うかという判断は本当に難しいです。繁殖エリア外のタカや、流浪しているタカ、移動中のタカに限って遠くの方をスーッと遠慮がちに通っていくのが通常ですから(これがタカ同士のトラブルを防ぐ知恵になります)、ますます個体数の把握が難しくなるものです。撮影に自信のある人でも撮れない角度を飛ぶ個体の識別写真は撮れないものです。ピントばっちりで高精細で、見事な画像であっても、個体識別ということに限って言うと何の役にも立たない画像があります。誰もがカレンダーの写真にしたいような画像でも、個体識別用としては0点の時があります。
たとえて言うと「この鳥はオジロビタキですか、ニシオジロビタキですか?」という質問の画像があなたの元に送られてきた時に、その画像に、下嘴の色が写っていないのは時には仕方がないとしても、喉の橙色部分の範囲がよく分からず、上尾筒の色が分かるように写っていなかったら、あなたならどう返信しますか。識別するために必要ないくつかの部位の特徴がどうなのかと分かっている人は、自分で同定できます。同定に必要な部位の写っていない画像を送ってくる人は識別ポイントが分からないということで、結局誰が見ても分からない写真ということが多いです。そういう方へは、この部位とこの部位の写っている画像はないですかと改めて聞くしかないだろうと思います。シギ類の識別で、腰や上尾筒の色、あるいは翼に帯があるかないかなど、種によって必要な情報が異なることと同じです。
したがって、結果的に重複カウントがないように完璧を目指すことは不可能ですが、観察数の書き方として「何羽」と書くか「何回」「何件」「何データ」と書くか、あるいは「何羽+」と書くか「何個体、何回」(もちろん雌雄も含めて)と書くかということになると思います。MA〇個体、FA〇個体、MY〇個体、FY〇個体、MJ〇個体、FJ〇個体でそれぞれに特徴を書くことができれば一番良いです。もちろん文章量がいくら多くなってもよい場合は観察した事実を事細かく書けば、より相手には伝わります。
ハイタカ、ハヤブサ、オオタカ、クマタカについて例を挙げましたが、これ以外の鷹隼類についてもまったく同じことが言えます。
(Uploaded on 10 February 2024)
タカの渡りを観察している時や、定点でタカ待ちをしている時、ちょくちょくすぐ近くの樹木の陰からハイタカやツミが出てきて、観察者に向かってきて、観察者の脇3~5メートルというたいそう近い距離を低く飛ぶことがあります。

ほぼすべてのカメラマンは「こんなのは撮れない。撮れっこない」「こういうのは見~て~る~だけ~」と言われますが、昨今のカメラ事情を考えると、ひょっとして今ならそれは撮れるかもしれないと思うことがあります。そのための必須項目として、
(1) 三脚は使用せず、手持ちで撮る。
(2) 座っていても立っていてもよいが、カメラは両手で常にホールドしている。
(3) 重くて大きなレンズは使用しない。
(4) カメラは瞬時にピントが来るような設定モードにしておく。
(5) 出現の予兆を少しでも早くつかむ。
細かく言うと、
(1) 三脚にレンズを載せると、(a) 三脚でレンズを支える支点と (b) カメラマンがファインダーを覗く目と (c) レンズの目玉の3点が一直線になってその先にタカが来ますから、すぐにはファインダーの中にタカを捉えることができません。一方、手持ちならカメラマンの目とレンズの目玉が一直線になってその先にタカが来ればよいので、一つ(aの支点が)省けます。そうすると即座にタカがファインダーの中に入ります。三脚を使っていると支点が動かないのでその代わりに人間が動いて腰を左右に動かしたり膝の曲げ伸ばしで高さを調節したりしないといけないのですが、それが必要なくなります。そうすると驚くほど早くタカをファインダーに捉えることができます。
(2) 目の前にタカが飛び出てきてからカメラを持ち上げるとその分時間が取られます。0 コンマ何秒でも時間を短くするにはカメラのシャッターに指を掛けっぱなしにしておくくらいが良いです。ファインダーを覗くまでの短時間にシャッター半押しか AF-ON ボタンを押します。
(3) 私は 100-400mmズームF5.6で狙います。ふだんはズームを200mmにしてあります。これならかなり近くてもけっこうファインダーにすぐに入ります。思ったよりもゆっくりと飛んだり、想定よりも距離があるときはズームインして400mmにして撮ります。200mmで撮ったタカもけっこう多くあります。タカが近ければ 100mmでも、いい写真になります。ファインダーに入らなければ結果はゼロですから、こういう時はとにかくタカをファインダー内に入れることです。昔は Nikon600mmF5.6 や Canon600mmF4 というレンズを使っていましたが、今はレンズとカメラの性能がすこぶるよくなったので、そんな重いレンズを使う必要がなくなりました(でも、比較すれば分解能はやはり違いますから、一本持っている意味はあります)。
(4) AF の設定はとにもかくにも「俊敏」に設定することです。「粘る」設定は必要ないです。メーカーによってはさまざまな便利な設定が他にも多くあって何かと役に立つこともありそうですが、この俊敏さを求めるためには俊敏さを阻害するような余分な設定はしないほうがよいです。また、AFの測距点の数は多いほうがよいので「全面」にしておきます。「動物優先」「瞳検出」機能があればもちろん使います。
こうすれば、すぐ近くに出現したタカが頭の上を通って後ろへ飛んで行っても、三脚とは違って頭の後ろまでも追いかけられます。瞬時にタカをファインダーに入れることができ、すぐにピントが来るようになります。「撮れっこない」と言われる近すぎるタカでも結構、撮れるものです。これができるようになると、中形や小形タカ類のハンティングの瞬間の素早い動きにも対応できるようになります。うまくいけば背面飛行やひねりを入れたスプリットS飛行なども撮れるようになってきます。
(5) 小鳥の動きと警戒声に注目するとよいでしょう。今までこのテーマでたくさん書いてきましたし、改めて書くとなるとかなりの量になるので省略します。
(1)~(5)ができるようになると次はタカの出現を待っている時の心の持ちようが大切になってきます。タカが突然出てきた時にびっくりして慌ててしまうとかなり時間のロスになります。いつでも出て来いというくらいの気持ちで待っていると、いざ出た時に余裕を持って対処できます。
でも、こうして、すぐ近くから飛び出してくるタカをずっと待ち続けて、スタンバイ状態で長時間過ごすことは心身ともにけっこう疲れるものです。うまくいけばみごとな画像が撮れますので、こういう待ち方は病みつきになり、やめられなくなりますが、長時間は気持ちが続きません。他の人からは「そんなに頑張らなくてもいいじゃないか」と言われて、「70歳を過ぎてもまだそんなことをしているの? 若い人でもそんなことはしないよ~」と呆れられて、私も「そりゃそうかもね …」と思ったりします。生活のために鳥を撮っているわけではないので、楽に鳥を撮って遊んでいればいいのですが、でも、何かに挑戦して疲れても、そこに充実感なり達成感があれば、やっぱり挑戦したくなります。
もちろん、撮れない写真もあります。雑木林を背にして開けた方向を見ている時に後ろの雑木林から私の脇2メートルほどを高度1メートルほどで突っ切っていったハイタカを撮ること、それは無理です。でも、そんなタカでも後ろ姿だけは撮ります。
突然の変化をしたタカの画像を1枚載せます。あまりに突然の出現で、しかもほとんど瞬時に見えなくなってしまったので、この個体がハンティング中にスプリットS飛行をしようとしている途中であったか、あるいはほかの個体(タカやカラスなど)と諍いがあって背面になって避けたか、あるいはこちら側が攻撃をしたのか、判断不能でした。

カメラとレンズの性能が昔(例えば私が鳥を撮り始めた48年前、一眼レフカメラを初めて購入した58年前)と比べると、格段に進歩しました。進歩どころか世の中が大きく変わったほどの変化です。今は誰にでも高精細で、ピントばっちりの鳥の写真がいとも簡単に撮れるようになりました。それほどのお金を出さなくても、そこそこの機材をそろえることができ、出現情報を聞いて珍鳥のいるところへ出かければ、そこには必ずと言っていいほどカメラマンが群がっていますので、その群中に入ればどんな珍鳥でも簡単に、苦労することもなく撮れてしまいます。そういう時代だからこそ、これからの鳥の写真は撮影者の眼力(鳥を観察する能力、行動を予測する能力)や眼の付け所、創造性の有無がそのまま素直に写真に表れてきます。
(Uploaded on 1 January 2024)
BIRDER 2023年11月号(10月16日発売)の特集は「モズからイヌワシまで ハンター列伝」です。タカ・ハヤブサ類7種とフクロウ類1種(コミミズク)のハンティングの他にモズやカワセミなどの記述もあります。

この特集で取り上げられている猛禽類は オオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、コチョウゲンボウ、コミミズク、イヌワシ、クマタカ、ミサゴです。
このうちの オオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、コチョウゲンボウ、コミミズクは若杉が原稿を書きました。これら5種はハンティング中(特にハンティング終盤)に見事な背面飛行を連発します。コミミズクも草丈の高い草地等においてはスプリットS飛行によく似た背面急降下飛行で着地し、着地と同時にネズミなどを捕らえます。紙面4ページで合計32コマの写真を使いましたが、多くが背面飛行をしている瞬間を連写したものなどで、いずれも狩りのようすをとらえたものです。また、ターン、ロール、スプリットS飛行 、インメルマンターンなどの解説図も付けました。
11月号の特集および関連の目次は次のようになっています。
・好みはタカそれぞれ 漫画=一日一種
・鳥界ハンターの真打ち、猛禽のハンティングを徹底解剖! 文・写真=若杉 稔
・イヌワシとクマタカ 雪国の山地を生きる「狩りの生態」 文・写真=石部 久
・猛禽類だけじゃない! 身近なハンターたち 文・写真=石田光史
・干潟の“意外な”大物ハンター、ハシボソガラス 文・写真=田仲謙介
・鳥ファーストな撮影術 かっこいいミサゴが撮りたい! 文・写真=佐藤 圭
・こんなもの、捕ってます! 日本野鳥の会神奈川支部の記録から 文・写真=秋山幸也
・我孫子市鳥の博物館 企画展「猛禽 ─タカ・フクロウ・ハヤブサ─」潜入レポート 文・写真=BIRDER
・[BIRDER Graphics]里山で暮らすクマタカ 文・写真=吉野俊幸
若杉が書いたページのレイアウトは以下のようになっています(すみません、いつものようにクリックしても画像は拡大されません)。

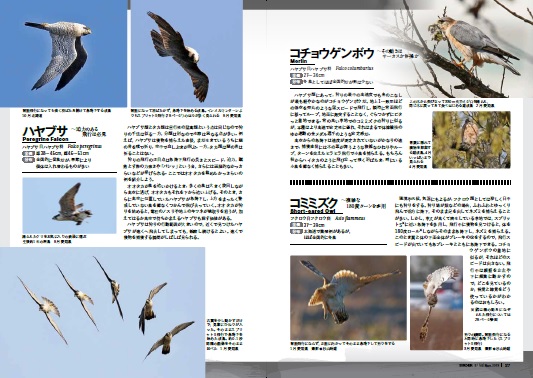
BIRDER 2023年11月号の20~23ページ
「猛禽のハンティングを徹底解剖!」
今までのBIRDER誌には掲載されなかった連続画像を3枚使いました。これはいわゆる合成写真とか合成加工写真といったものとは若干異なっていて、秒10コマの静止画像(約0.1秒間隔)をその進行方向に単純に何も加工せずに並べただけの「説明画像」です。一般には動画からコマを切り取ってつなげる場合が多いのですが、ここでは連写した静止画を並べました。背後に山や雲などの目印がないので相互の位置関係は100%正確ではないですが、おおよその位置はほぼ実際に近いと思われます。
正確を期すために、連続したコマのそれぞれの原画像(たとえばオオタカでは9枚を進行方向に並べましたがその9枚)、1枚当たりそれぞれ6MBくらいの画像データを全部、BIRDER編集部に提出してあります。明るさやシャープネスさえも含め何もいじっていないことが分かると思います。
筆者が今までに BIRDER 誌に書いた文章は、下記の通りです(すでに購入できなくなった号があります)。
1 BIRDER 1999年11月号の P.66 「Net で GO! GO! GO!」 マーリン通信の紹介
2 BIRDER 2010年 2月号の PP.76-77 「拝啓、薮内正幸様 ♯26」
3 BIRDER 2012年 9月号特集の導入 PP.8-9 「ハヤブサとはどんな鳥か」
4 BIRDER 2012年12月号特集の導入 PP.6-7 「冬のタカ観察の魅力とは?」
5 BIRDER 2013年 9月号特集の中 PP.20-21 「ハイタカ属とはどんなタカたちか?」
6 BIRDER 2014年 9月号特集の導入 PP.4-5 「夏鳥としてのサシバとハチクマ 観察の魅力」
7 BIRDER 2014年 9月号特集の中 PP.24-25 「サシバの幼鳥は何をしに日本へ来るのか?」
8 BIRDER 2016年 2月号特集の導入 PP.18-19 「水辺のワシタカ類 その観察の魅力」
9 BIRDER 2017年 1月号特集の中 PP.30-31 「ハヤブサ類との付き合いかた ~保全の過去・現在・未来~」
10 BIRDER 2017年12月号第2特集の中 PP.35-37 「オオタカ希少種解除 なぜ祝えないのか?」
11 BIRDER 2018年10月号特集の導入 PP.16-17 「空振りしないための タカの渡り観察の基礎知識」
12 BIRDER 2021年 9月号特集の中 PP.22-28 「”部位別” 渡るタカの見分け方ガイド サシバ・ハチクマ・ハイタカ属・ノスリ」
13 BIRDER 2021年 9月号特集の中 PP.34-35 「サシバ暗色型 観察ガイド」
14 BIRDER 2023年 2月号特集の中 P.29 「ヨシ原の覇者 チュウヒ & ハイイロチュウヒ」
15 BIRDER 2023年 2月号特集の中 P.30 「多彩な技を持つ高速ハンター コチョウゲンボウ」
16 BIRDER 2023年11月号特集の中 PP.20-23 「猛禽のハンティングを徹底解剖!」
(Uploaded on 16 October 2023)
営巣中のオオタカが巣の近くから飛んで少し離れた木の枝にとまったとします。この時、体の向きは巣とは反対側を向くことになるので巣を見るためにはクルンと180度回転して体の向きを変える必要があります。反対側を向いていては巣の監視はできないからです。狩りの目的で鉄塔や枝にとまった時も同じで、体の向きを180度変えることが多いです。こういう枝の上や鉄塔の上で体の向きを変えることはしょっちゅうやっていることで、私もほぼ毎日のように見かけます。
狩りの途中でも枝移りしたり、同じ枝の上で向きを変えたり、鉄塔の上でも小移りをしたり向きをしばしば変えたりしています。私が今年一番多く観察したオオタカFA(雌成鳥)は体の向きを変える時、いつでも(上から見て)右方向へ回転することに気が付きました。右足を軸足にして、右方向へ左足を回転させるので、この個体の利き足は左だということが分かりました。
人間の右利き・左利きはよく話題に出ます。聞くことが多い部位は手、耳、目、足で、利き手、利き耳、利き目、利き足などがあります。他にもあるかもしれません。利き手は鉛筆を持つ手、箸を持つ手です。利き耳は壁に空いた小さな穴から声を聞こうとするとしたらどちらの耳で聞くか(あまり多くはないことですが)という耳で、私の場合は、小さな声を真剣に聞こうとするとしたらつい右耳に掌を持ってくるので利き耳は右です。利き目はカメラのファインダーやスコープを覗く時にいつでも右目を使うので、利き目は右ということになるでしょう。利き足はサッカーボールを蹴るほうの足です。調べてみると、後ろから誰かに押された時につい先に出る足や、階段を上る時に無意識に第一歩を踏む足(これは私にはよく分かりません)が利き足だとも言われてますので、これも私は右です。
オオタカの場合、利き耳や利き目はどういうふうに調べたらいいか分かりませんが、利き手と利き足は調べられそうです。鳥類の場合は手が翼になっていますから、利き手はつまり「利き翼」のことになります。何かを翼でバサッとたたくなどの攻撃をするときに叩く翼が「利き翼」ということになるでしょう。鳥類の場合は左右のバランスというものがかなり重要なので、飛行中は左右の翼を同等に使っていると思われますが、急に向きを変える時や何か違った動きをしようとする時にはどちらかの翼だけを上にあげたり位置を変えたりします。その時の翼が利き翼ということになるでしょう。でもこれについては観察中に気を付けていますが、私はあまりたくさんデータをとっていなくて、個体ごとの正確な事は分かりません。
一方、足については先に書いたクルンと回転する時の軸足ではない方の足が利き足ということですので容易に調べられます。下の画像を見てください。巣の近くから出てきたオオタカFAが鉄塔の上の手すりのようなところにとまりました。向こう向きでは鉄塔の太い柱の方を向いてしまいますし、巣の方向とは反対なので、すぐに180度回転してこちらを見ました。その時に上から見て右へ回転したか、左へ回転したかによって軸足と利き足が判断できます。軸足でないほうが利き足です。この個体は右足が軸足になっています。左足がぐるっと動きますから利き足は左です。この個体がこの鉄塔のこの位置にとまって回転するところは頻繁に見ましたが、いつでも同じ方向へ回転しました。やはりタカにも利き足はあると考えて良さそうです。

ただ、反対側へ回転したこともありました。それは木の幹に近い枝にとまった時で、もし右回りするとなると、尾羽が幹に当たって回転しづらい時でした。だから反対側へ回転しただけだろうと思いました。
上の画像からも分かるように、軸足にはかなりの力がかかってしまいます。右足がすごく不自然な位置になっていて、かなり無理な回転をしているように見えませんか。こういうところを見ていると、よく軸足が折れずに(骨折せずに)回転できるものだと感心します。強い力がかからないようにするためと思うのですが、回転する時には趾の握りを緩めて(つまり人間で言うと手の指を開くようにして)、強い回転力がタカの跗蹠や脛、付け根にかからないようにしていることが分かります。そのためだと思うのですが、多くの場合回転中にバランスを崩しやすいので、両翼をうまく使って(実際は下の画像のようにどちらか片方の翼を主に使って)体全体のバランスを取っています。双眼鏡で観察していると、体のバランスを崩し、すぐに回復させていることがよく分かります。

(Uploaded on 1 August 2023)
タカ類が木の枝や鉄塔にとまっている時は、たいてい狩りの初期段階である獲物探索中のことが多いです。目立つ枯れ木や鉄塔にとまっていると、カラス類や他のタカ類によけいなちょっかいをかけられたり、あるいは自分が捕食される危険さえ出てくることがありますので、もしほんとうに休憩しようとするなら多くの場合はひっそりと目立たないところでゆったりと休憩します。一方で、それほど目立つ場所でなければ、あるいは状況が許せば目立つ場所であっても、ゆっくりと休憩しながら、もしも狩りのしやすい獲物(たやすく捕獲できそうな巣立ったばかりの幼鳥や弱っている鳥など)が現れたら突然飛び出してハンティングを始めることもありますので、正確に「これは休憩中である」とか「これは獲物探索中である」と断言することは難しいです。つまり獲物探索しながら休憩する場合(または休憩しながら獲物探索する場合)があるということです。相手(獲物)がどう出るか、周りの状況が次にどう変わるかはタカ本人にも予測ができないからです。

こういう状況を観察する時、獲物探索中のタカの「体の向き」と「頭の向き」はひじょうに重要です。タカの様子を見ていて、どちらを優先しようか迷うことがあります。それによって私の次の観察地点選定(タカが飛び立った後どこへ私が行くか)が大きく変わりますし、ハンティング位置を予測できれば、タカが狩りに飛び立つ前に先回りして狩りの行われそうな地点に行って狩りを近くで見ることができるからです。鉄塔にとまったタカが体を北向きにしていても、さかんに左の方ばかり(つまり西の方ばかり)を注視していると、このタカはどちらの方向へ飛び出していくのだろうかと思います。体の向いている北の方へ飛び出すか、頭が向いている(視線の先の)西の方へ飛び出すか、どちらでしょうか。今までの私の経験では、体の向きよりも頭の向き、つまり「見ている方向」が重要です。
その理由をいくつか考えてみます。
(1) 体の向きは風の強さによって決められてしまうことがあります。強風時のとまりはほとんどの場合に風上を向いています。もしも強風時に風下の方を向いていると体じゅうの羽毛がまくり上げられるように立ってしまいます。冬は体温が奪われますし、夏でもタカにとっては落ち着かない煩わしい状況になるでしょう。羽根が傷みやすく、飛び立ちもスムーズにはいかなくなります。もしも風上を向いてとまれば、体のほぼすべての羽はピタッと体に密着しています。ですから西の方に獲物がいて、飛び立つタイミングを図っている時でも、風上へ体を向けていたほうがよいことになります。ですから特に強風時は体の向きよりも頭の向きが重要になります。強風時でなくても、必ずというわけではありませんが、頭が向いている方向へ飛び出すことが多いです。
(2) 自分が目立たないような向き(白い胸や腹を見せるか、黒っぽい背中を見せるか)を考えてとまっているように思える時があります。背中を向けていれば相手からは目立たなくなります。突然体の向きを反対へくるっと変えて、その直後にハンティングに飛び立つことがありますから、あながち否定はできませんが、ただ、タカがそのことを考えてそうしているかどうかは疑問に思う時もあります。
(3) 光線の向き(順光か逆光か)が関係している時がありそうです。バックが晴れか曇りか(青空か雲か)も関係あるかもしれません。木の枝の伸び方によっては自分が飛び出しやすいようにわざと崖の方を向く時があります。フェイントではないと思いますが、崖の向きか崖の反対向きかという二者択一で選択せざるを得ない時には必然的に崖の方向を、あるいは反対側を向くという場合もあります。とまりの位置から見て、巣がどちらの方向にあるかによることもあります。
(4) 複合的な要因もあります。例えば「誇示どまり」をしながら、あわよくば獲物を探そうと思っている時は太陽の方向へお腹を向けています。また、「監視どまり」で、雌が抱卵中に雄が巣や営巣林を監視しながら同種の侵入個体やカラスなどを見ている時は巣の方向を向いていることが多いので、そういう時にあわよくば獲物を探そうと思っていると、体の向きは巣の方向ということになります。このように体の向きが必然的に決まっている時には体の向きよりも頭の向き(視線の先)が重要になってきます。
タカが木の枝、鉄塔、電柱、電線などにとまっているだけの時でも、観察者にはいろいろと考えるべきことがたくさんあります。一方で、タカはもっと柔軟に考えていて、そこまで考えていないかもしれませんが。
(Uploaded on 23 March 2023)
今までこの通信には失敗談をいっぱい書いてきました。誤判断、識別の間違い、個体の取り違えなどで、それらは推測や先入観、バイアスがかかっていたことなどが原因でした。今日の文章も書くにはあまりに恥ずかしいことなのですが、逆に考えるとこれは良い勉強になったなぁと思えることでもあり、ひょっとして誰かのお役に立つことがあるかもしれないと思い、あえて書くことにしました。
(1)
2022年10月中旬、北海道でのことです。私はあるタカ渡りポイントでハイタカを観察していました。朝のうちは仲間と一緒に見ていましたが、正午前に皆が山を下りていったので、午後は一人だけで見ていました。この日の観察のメインをハイタカに絞り、朝からハンティングシーンや急降下のようすを連写で撮りまくっていました。午後になってその日初めてのオオタカ成鳥が出ました。タカ類は何かが出現するとそれにつられるように一緒に他のタカ類も出てくるパターンが多いのですが、この時もハイタカ3羽が同時に出た直後にこのオオタカが出て、ハイタカとオオタカの計4羽が頭のすぐ上で同時に舞いはじめました。双眼鏡で見ていると、さらにその向こうにハヤブサらしき鳥も出ました。この地点のハヤブサは近くの営巣個体が頻繁に出現することが多くこの日も朝から何度も出ていたので、ある程度近い時や変わった行動以外はほとんど画像にしようと思いませんでした。この時もハイタカとオオタカのずっと奥の方(遠く高く)に出てきたので、それほどじっくりと見ることもなく、しかし「小さなハヤブサだなぁ」、「遠いとこんなに小さく見えるものなのか」と大きな違和感を持ちながらも、「ハヤブサはいつでも見えるから、今はオオタカとハイタカを見なくては……」と思い、それでこのハヤブサ類を見ることはやめました。
違和感を抱きながらもそのままにしてしまいました。ところが、山(と言っても低い山ですが)を下りて何人かの観察者がおられるところまで行くと、「何かよく分からない鳥を撮った」と言われる人がいました。時刻を聞くと私がハイタカ3羽とオオタカ1羽とこのハヤブサ類を観察した時刻と同じでした。画像を見せていただくと、それはなんとコチョウゲンボウ ForJでした。
久しぶりに秋の渡りのコチョウゲンボウを観察しながらも、十分に見ることなく、画像を撮ることもなく、惜しいことをしました。
(2)
それから一週間後の10月下旬、愛知県でのことです。私はある干拓地で鷹隼類を観察していました。電線にドバトが数十羽とまっていましたので、オオタカかハヤブサがこの群れに突っ込んでくるかもしれないと思い、しばらく待つことにしました。一時間ぐらい経ってドバトが増えてきて100羽を超えた頃、上空からハヤブサ類が垂直急降下に近いくらいの角度で降下してハトの群れに近づきました。ハトは当然ながら大きな音を立てて飛び立ち、逃げまどいましたがハヤブサはハトを追いかけずに上空で旋回を始めました。普通、こういう時のハヤブサはハトの群れを追い回したり、急上昇・急降下を繰り返したりしますが、このハヤブサはそういうことはしませんでした。双眼鏡では体下面が純白に見えなかったので幼鳥だろうと決め込んで、上空に上がってしまった後で撮った画像は小さくしか写っていませんでした。画像は眼鏡もルーペも使わず軽く確認しただけですが、胸や腹に縦斑があることだけを見て、「やはりハヤブサ幼鳥だ」と判断してしまいました。「ははぁ、今年生まれの幼鳥だから、まだ狩りに精通していないのだな」と勝手に解釈してしまい、双眼鏡も使わず肉眼だけで見ていました。

ところがハトがグルグルと旋回しながら飛び回っているその上をこのハヤブサはゆっくりした旋回をずっと続け、なんと5分間も旋回して南方へ飛去して行きました。普通ハヤブサはそんな長い間ハトの上で旋回し続けることはないですから、ここでも強い違和感がありました。あとで画像を拡大してルーペでチェックしたらハヤブサではなくてチゴハヤブサでした。ドバトの群れに急降下で突っ込むのはオオタカかハヤブサしかいないだろうと勝手に決め込んでいたのですが、今回突っ込んだ(ドバトをびっくりさせた)のはチゴハヤブサでした。
コチョウゲンボウをハヤブサと誤認し、その一週間後には今度はチゴハヤブサをハヤブサと誤認するというとんでもない失敗を連発してしまいました。「何か違和感を感じる」と思いながらも、いつも見ているハヤブサはそれほど珍しくもないと思ったからなのか、気が緩んでいました。そして、つくづく先入観を持つということ、バイアスがかかるということは危ないことだと実感し、「違和感」を放置することはよくないと感じました。
【コチョウゲンボウの件】
① 明らかに小さく見えたが「遠くを飛んでいるハヤブサは小さく見える」「このハヤブサはそもそも小さい個体かも」と推定してしまった。
② 今までこの通信でコチョウゲンボウはハヤブサとシルエットがそっくりで、大きさだけが小さいので、コチョウゲンボウという名前をやめて「コハヤブサ(小ハヤブサ、小隼)」にしようかと言っていたくらいなのに、ミスをした。こんなに小さなハヤブサがいるのかという違和感があったのなら、その違和感の後ろには必ず何かがあると思わなければいけなかったと痛感した。
③ 渡り途中のコチョウゲンボウを見る機会は少ないので、頭の中にコチョウゲンボウという選択肢がほとんどなかった。
④ ハヤブサはいつでも見られるなどと思わず、もっと大事にしなくてはと反省しました。
【チゴハヤブサの件】
① チゴハヤブサがドバトの群れに突っ込むという瞬間を今まで見たことがなかったので、想定外だった。
② ハトの群れに高空から急降下で突っ込むのは(愛知県では)オオタカかハヤブサしかないと決め込んでいた。
③ ハトの上を5分間も旋回し続けるというおかしなことを「違和感」と感じながらも「縦斑の幼鳥だからこういうことがあるかもしれない」と放置してしまった。違和感の先には必ず何かがあるはずなのに。
④ 愛知県で見るチゴハヤブサはほとんどが渡りの通過個体で、時にトンボを空中で捕えながら渡っていく程度というイメージしかなかった。
⑤ (ひょっとして)今回は、渡り途中に小鳥を捕えようとして急降下したところ、そこにドバトがいたので、ドバトが勝手にびっくりして騒ぎまくっただけだったのかもしれない。
【経験者が感じる違和感について】
まったくの初心者の方なら上のような違和感は持たないと思います。ある程度鳥を見てきた人、経験のある人は時々何らかの違和感を感じることがあります。なぜ違和感を持ったのか分からないまま終わってしまう、過ぎてしまうことがありますが、おそらくそれは何かしらの判断ミス(識別ミス)がそこにあったということが多いだろうと思います。経験を積めば積むほどその違和感というものは重要な情報を観察者に伝えています。違和感を放置せずとことん突き詰めることが大事です。
なお、この違和感は個体の入れ替わり時にも持つことがあります。
① ハイタカが木の枝から飛び立って向こう側へハンティングに行きました。ほどなくして手ぶらで戻ってきた個体はなんとなくやや大きく感じてしまいました。実はこの個体は雌幼鳥で、先の個体は雄成鳥だったということがありました。
② コチョウゲンボウ(幼鳥か雌)が電線から飛び立って狩りに行き、肉眼では見えないくらい遠くまで行ってしまいました。車でそちらへ見に行くと電柱の近くの電線にとまっていました。「ははぁ、狩りに失敗してここにとまっていたのか」と思ったものの、なんとなく色が違うかな?と違和感を感じ、双眼鏡でよく見たら、雄成鳥でした。
こういうことは観察時にはほとんど毎日のように経験することです。「違和感」の裏には大きな何かがあります。ベテランの人はこういう違和感を放置しないようにすることが大事で、初心者の方は早くこういう違和感が感じられるように経験を積むとよいだろうと思います。
本来は先入観を持たずに観察を続けられれば一番よいのですが、人間という生き物は先入観なしで生きているとすぐに疲れてしまいます。それを助けて軌道修正してくれる一つが違和感なのでしょうか。鳥の観察だけではなく、生活のあらゆるところで同じことが言えそうですが。
(Uploaded on 14 December 2022)
2022年秋、タカの渡り観察中に見たちょっと変わったタカを4例取り上げます。画像処理はいつも通り何もしていません(原画像のトリミングのみです)。
(1) サシバ部分暗色型
9月17日。この秋一番おもしろかった1例ですが、これについてはすでに書きましたので、興味ある方は下記のリンク先をごらんください。
結局、この秋見たサシバ暗色型は知多半島の渡り個体1羽だけでしたが、白樺峠でこの部分暗色型が見られてよかったです。なお、今年のサシバ(一般型)確認は初認が3月23日、終認が11月3日でともに成鳥でした。
(2) ノスリ
10月12日、変わった模様のノスリを見ました。たくさんのノスリが群れになっている時でも、通常の個体と比べて色彩や配色が変わった個体が混じっていることが多いので、いつでも双眼鏡(14倍防振双眼鏡)を使って一羽一羽確認することにしています。大陸から渡って来たのではないかと思われるような濃い鷹斑が体中にびっしり見られる個体とか、多くの部分でオレンジ色が濃い個体とか、異常なほど黒っぽいあるいは逆に白っぽい個体などを時々見かけます。時にはケアシノスリがノスリの群れになじめない状態で交じることもありますので遠くの個体でも必ずチェックしています。
今回のノスリはかなり遠かったのですが、双眼鏡で初めて見た時、頭や喉のあたりと腹部との間に非常にはっきりと区分されたような色の差があって(ジグザグのように区分けされていて)、あっと思うほどびっくりしました。遠かったのですが何とかカメラのAFが効いて、一応証拠写真程度のものが撮れました。下の画像です。こんな程度にしか写っていないですが、おおよそのことは伝わるのではないかと思います。写真がないと何も伝えられませんから、やはり写真は重要です。

(3) たぶんハイイロチュウヒ
10月13日に見たこの個体は上のノスリ以上に遠かったです。わたくしの頭の真上を通過して行きましたので、水平距離は0mに近いのですが高度がかなり高かったので小さくしか見えませんでした。最初、肉眼で気がついたときはゴマ粒ほどで、そもそもタカなのか何なのか分からなかったのですが、双眼鏡で見るとタカ類で、次列風切あたりを中心として黒い部分が非常に目立って、「なんだこれは!」と思うような個体でした。頭にパッと浮かんだのは ウスハイイロチュウヒ幼鳥ではないかということで、すぐにカメラに持ち替えて連写しようとしましたが、距離が遠かったのでオートフォーカスが効かず、マニュアルでピントを合わせました。かろうじて5枚ほど甘いながらもピントが来ていました。
よくよく画像を見てみると、翼先突出数が5枚ですから、それが4枚である ウスハイイロチュウヒではなさそうです。突出している4枚のとなりのP6が幾分長く見える個体もいるそうですが、それにしても今回の個体のP6はちょっと長すぎます。「残念!」と思ったのですが、ハイイロチュウヒにしては、双眼鏡で見た時の印象も撮影した画像を見ても、黒い部分が多く、(体下面+下中小雨覆)と(黒い部分)と(それ以外の部分)の配色が興味深く、見たことがない珍しい個体だということには変わりありませんでした。

(4) トビ
10月26日、岬の先端近くで9羽のトビが一緒に旋回したり、飛び回ったりしていました。私はいつもの習慣で、多くの人があまりじっくりと見もしないトビを双眼鏡で一羽一羽チェックしていました。当年生まれのトビ幼鳥は秋には多くの個体が頭部だけ成羽に換羽しますが、まだ幼羽のまま頭部に白い縦斑がたくさんある個体がいる一方で、すでに頭部すべてが成羽に換わっている個体もいて、それをチェックするのが目的です(私のタカ仲間がこれを一生懸命やっているので、私も)。トビの換羽は他のタカ類と比べると特別です。こうして一羽一羽見ていたときに他のトビと比べて(光線の角度とか光の具合だけではなさそうな)かなり黒い部分の多いトビがいました。トビの群れにハチクマ暗色型が1羽交じっているのかと思ったほど黒い部分が多かったです。「黒い部分は雨覆と、その先の……」などとついつい双眼鏡でじっくり見てしまったので、カメラに持ち替えた時は既に頭があちら向きになって、下の画像のような後ろ姿しか撮れなかったのですが、かろうじて黒っぽい部分はどこかという程度は写っていました。
その日のそれ以降も、その3日後にも同じ地点で出現したトビをすべてチェックしましたが、この個体は出現しませんでした。他のタカ類でもそうですが、たいていの場合チャンスは一回だけ、しかも撮影できる時間はほんの数秒以下(時に1秒未満)しかないということが多いです。証拠写真は重要ですが、かと言って多くの人がやっている「見るよりもまずは撮る」という気にはならないです。この辺りの選択はいつも微妙で、私はまず双眼鏡で見ることが多いので、シャッターチャンスをよく逃します。カメラマンよりもウォッチャーのようです。

一方で、ひょっとしてこのトビは私の見間違いだったという可能性もあります。もっとクリアーに撮影されていたら文句なしですが、やはり画像がよくありません。光の関係でそう見えてしまったのではないかということも完全には否定できないものです。画像は下雨覆部分が黒く写っていますが、肉眼で勘違いをした上に、画像でもだまされて、肉眼・画像の両方でこのように誤判断した可能性はありえます。バイアスがかかってしまうと客観的な証拠さえも流されて誤判断してしまうことがあるのと同じです。他の8羽のトビと比べて「若干黒味の強いトビ、黒っぽいトビ」だったことは間違いないですが、それを「かなり黒味が強いトビ、暗色のトビ」と認識してしまった(決めつけてしまった)可能性はあります。
(Uploaded on 21 November 2022)
干潟でシギの群れを見ていると突然何かにびっくりしたように舞い上がることがあります。たいていはハヤブサが接近してきたときですが、オオタカやチュウヒの場合もあります。ハイタカだった時もあります。昔の私は「何が来た? オオタカか? ハヤブサか?」「どこだ? どこに来ている?」と周りを探さなければならなかったのですが、ある時から観察方法を少し変えました。急降下してきたハヤブサやオオタカは、急降下する前は、どこかから移動してきているはずです。その前はどこかで旋回上昇していたはずです。そしてその前はどこかでとまっていたはずです。遠くでもいいので早くからとまり個体を見つけて、そのままその個体に付き合うという方法です。場合によっては何時間も同じ個体を見続けることもあります。
最近の私のメインの観察種はオオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、コチョウゲンボウ、チュウヒの5種です。この5種のうちチュウヒ以外はいずれも肉眼では見えないほど高いところから、急降下ハンティングをすることがあります。そこにタカがいるということを知らなければ誰の目にも見えないほどの高さからのハンティングです。3年ほど前までの私は両眼視力が2.0ほどあって、かなり自信を持って遠くにいる個体を見つけていましたが、そんな視力でも低いところを飛んでいる時から追跡し続けて見ていないと分からないほど高いところまで上がってからのハンティングです(チュウヒも同じようにかなりの高空まで旋回上昇しますが、目的は他のタカとは別です)。
オオタカは高空からの狩りを一年中します。樹木や鉄塔から飛び立った後、旋回上昇しながらどんどん高度を上げていきます。上昇気流をうまく捉えているのでしょう。早朝はあまり上がっていかないことからもそう考えられます。ただ、上昇気流がなさそうに見える曇天で無風の時でも難なく上がっていきますから、私が認識できないような上昇気流があったり、私が知らないような上昇するコツというものがあるのでしょう。旋回しながら上がっていって、ある所で若干位置を移動させたり時に高度を少し下げたりしながら体の向きを変えて徐々に移動します。上がると肉眼だけでは見えないくらいまで上がっていきます。どのあたりを飛んでいるのだろうか、どれくらいの高度だろうかが気になって双眼鏡から眼を離して肉眼で見ると、あまりにも小さくて分からないほどで、再び双眼鏡の視野に入れようとしてもなかなかすぐには入ってきません。特に今私が使っているキヤノンの14倍防振双眼鏡は(現時点では最高の機材と思うのですが)倍率が高い分だけ当然のこととして視野が狭いので、再キャッチは難しいです。それほど高いところまで上がっていくということです。
高空を飛んでいるタカをよく見ると、頭を左右に振ったり、下の方を注視していることが分かります。獲物を探索しています。捕獲対象が決まると徐々に高度を下げたり、あるいはそのまま一気に高度を下げて滑空します。急降下になることも多いです。急降下の時は正面から見ると両翼はほぼすぼめていたり、時にW型になり、横から見るとほぼ紡錘形になっています。どんどん高度を下げて獲物に近づくと両足をグイッと突き出します。意外と早いうちから足を出すこともありますが、そういう時は速すぎる速度を落とすために調整しているのかもしれません(地面に激突すると危険です)。そんな時のオオタカの足は長く、「足ってこんなに太くて長かったのか」と思うほど大きく前へ突き出します。足を出している時間が短くて、観察に慣れていない人には出したか出さなかったかが分からないこともあるほどです。


幼鳥も高空からの狩りの技術をすぐに習得するようで、冬の幼鳥も高空からのハンティングをよくやります。愛知県の例では、広い農耕地で、主にドバトやムクドリを捕えています。獲物となる鳥たちにとっては頭の上から猛烈なスピードで落ちてくるタカはかなりの脅威でしょう。直近まで迫られた時に瞬時に身を交わして逃げ延びるところをよく見ますが、あっさりととらえられる時もあります。獲物となる鳥たちの飛行技術、あるいは巣立ったばかりの幼鳥かどうか、体力、体調その他、いろんなことが影響しているのでしょう。
鳥にとって目に見えないほどの高空から急降下で突っ込んでくるオオタカはかなりの脅威になるでしょう。水中にいる魚が、突然空から水中に突っ込んでくるカワセミやヤマセミの嘴、あるいはミサゴの足の爪に捕らえられてしまうように、耕地にいるドバトやムクドリは急降下するオオタカに気が付かないので逃げ遅れることが多くあります。逆に考えると、ドバトやムクドリが群れになる理由がよく理解できます(誰かが早くにオオタカを見つけてくれます)。
急降下の狩りに失敗することが多いので、失敗も成功も合わせて今までに数100回の狩りを見てきましたが、角度が緩やかな時とほとんど鉛直な時など、実に様々です。私が見ているその時々での観察角度の違いもありますが、それを加味してもやはり様々な角度で急降下しています(同じ地点から何度もいろんな方向へいろんな角度で突っ込んでいきます)。メジロを捕えるところを見ることが多かったのですが、かなり高空で狩りを始めても、メジロが一気に高度を下げるように逃げていきますから、多くは地上近くで捕えます。時には不意打ちを食わせるように高空で一瞬にあっけなく捕ることもあります。

コチョウゲンボウについては、今までこの「マーリン通信」で何度も書いてきました。オオタカやハヤブサと同じように高所から急降下をしてハンティングをします。体が小さい鳥なので、高度が上がるとハヤブサやオオタカ以上に見にくいです。オオタカと違うところは急降下の角度です。石をそっと落とした時の角度、すなわち、ほとんど鉛直に落ちていきながら獲物に何回も成功するまでアタックします。小鳥にとってはまさに脅威となる狩りの方法です。こういう狩りを何度も見ていると、見るからに「小さなハヤブサ」という印象をもちます。標準和名を書き換えることが可能ならば「小さなチョウゲンボウ」という意味のコチョウゲンボウなどという名前をやめて「コハヤブサ」にしたいと常々思っています。現に仲間内ではコハヤブサという名前を勝手に使っています。対外的には(原稿書きなどでは)そういうわけにもいかないのでコチョウゲンボウと呼んでいます。コチョウゲンボウとチョウゲンボウは名前がよく似ていますが、狩りの能力に関しては大きな開きがあります。
オオタカとほぼ同じような急降下ハンティングをしますが、オオタカ以上にスピードコントロールがうまいようで、速い速度のまま獲物に突っ込んでいきます。私が心配する必要もないのでしょうが、地面に激突したらどうしようと思うほどです。高速でも身のこなしは自由自在に感じられます(高速だから自由にできるというのがほんとうでしょう)。体形はオオタカ以上に紡錘形になる傾向があります。
チュウヒもオオタカと同じようにかなり高いところまで上がっていきます。早朝は見ないですが、時間がたつと(たとえば9時を過ぎると)よく見るようになります。双眼鏡で見ても小さくて見えないほどまで上がって、ある時滑空に転じます。上の4種と違って、その高空から一気に急降下で獲物に突っかかるところは今まで一度も見たことがありませんが、高空から徐々に高度を下げてきて、それから獲物に突っかかるところは見たことがあります。
チュウヒが高く上がる主な目的は、遠くまで狩りに出かけることです。上昇気流を使って高度を稼げば省エネで飛行できます。サシバやハチクマの渡り時の飛行と同じです。ある時、雄がヒナのいる巣の近くでどんどん旋回上昇してから滑空し、7kmも離れたところへ行って、そこで860m飛んで狩りを成功させて、また獲物(小鳥)を足に持って6.82kmを延々と17分間もかかって巣まで一直線に運んできたことがあります。向かい風が強かったこともありますが、帰りは時速24kmほどのスピードでした(途中に旋回上昇をいれました)。遠いところでしたが、そこまで行けばそこに獲物が豊富にいることが分かっていたのでしょう(あるいはそこにオオヨシキリなどの巣内ビナがいることを知っていたのかもしれません)。
-------------------
チュウヒ以外の4種もチュウヒと同じように、遠くへ移動したいときに、同じように旋回上昇をして高度を上げて、その後に滑空して高度を下げ、遠方でハンティングを始めることがありました。
「しつこい人間に観察圧をかけられたオオタカが、嫌気が差して旋回上昇で高度を上げて、他所へ移動していく」ということを聞いたことがありますが、そう思うような時でも、やはり遠方で狩りを始めることが多いので、嫌気からの旋回上昇というものは(あるかもしれませんが)あまり多くはないように思います。もしも観察圧から嫌気がさしたのなら、その場から水平に飛んで避けることが多いようです。単純な思考で物事を決めつけることのないようにしなければと思っています。
(Uploaded on 10 July 2021)
鷹隼類が木の枝にとまる時、とまりやすい木や好んでとまる枝というものがあって、1本の同じ木の同じ枝に日によって違う種がとまることがよくあります。いつもノスリがよくとまっている枯れ木に今日はハイタカがとまっていたというようなことをよく経験します。鷹隼類に好まれる木にはそれなりの理由があって、たとえば
1 羽を逆立てるような強い北風を除けることができる
2 南側に面してぽかぽかと温かい
3 見晴らしが効いていて、狩りに出発しやすい
4 安定してとまっていられる
5 安全な場所に位置している
など、いろんな理由があるようです。ただ、温かいとか寒いとか、その他のこともみんな人間の思考から来ているだけかもしれませんので、これらの他にもっと本質的に重要な理由がある可能性があります。
さて、皆さんは観察中の個体(飛行中の個体あるいはとまり個体)が瞬時に別の個体に入れ替わってしまっていたという経験はありますか。私は幾度もあります。
【観察例 1】
ある日、木にとまっていたオオタカ成鳥を観察していました。動きがないまま長時間とまり続けていたので、コンビニで昼食を買って、元の位置で食べようとして戻ると、その同じ木の同じ枝の同じ位置にオオタカ幼鳥がとまっていました。一瞬「えっ」と思いましたが、別におかしなことではありません。ほんの10分ほどの間とはいっても10分経てば個体が入れ替わることはありえます。それに、観察者が動くとそれまで警戒心を持っていた鷹隼類が警戒心を解くことができるようになったわけで、観察者を意識することなく自由に動けますので、こういうことはしばしばあります。ほんとうはタカに警戒心を感じさせてはいけないのですが、実際はやむを得ない部分もあります。

この例はオオタカ成鳥から幼鳥への入れ替わりなので、入れ替わったことが明瞭で、すぐに分かりますが、成鳥から成鳥、幼鳥から幼鳥への入れ替わりはすぐに気が付かないこともありそうです。「何かちょっと変だな」「何か違和感があるな」と思った時は入れ替わりの可能性を考慮してみると良いでしょう。とにかく、入れ替わったことに早く気が付けば何のトラブルにもなりません。
とまる枝を共用するわけですから、もし力の強い種や強引にとまろうとする個体がいると、それまでそこにとまっていた個体ははじき出されるように飛び立っていくことになります。
【観察例 2】
ノスリがオオタカに入れ替わったことがあります。飛んでいたノスリが大きな茂った常緑広葉樹にとまるような感じの飛行で降下していきました。葉が茂っていたので見えなくなりましたが、見えなくなった直後に反対側からタカが出てきました。その時私は一瞬「なんだとまらなかったのか。反対側から出てきた」と思いましたが、ノスリは見るからに木の枝にとまるような感じの飛行をしていましたし、出てきた個体のシルエットにちょっとした違和感があったので、念のため双眼鏡で見てみたら出てきたのはノスリではなくてオオタカでした。遠かったので肉眼ではすぐにオオタカとは分からなかったです。
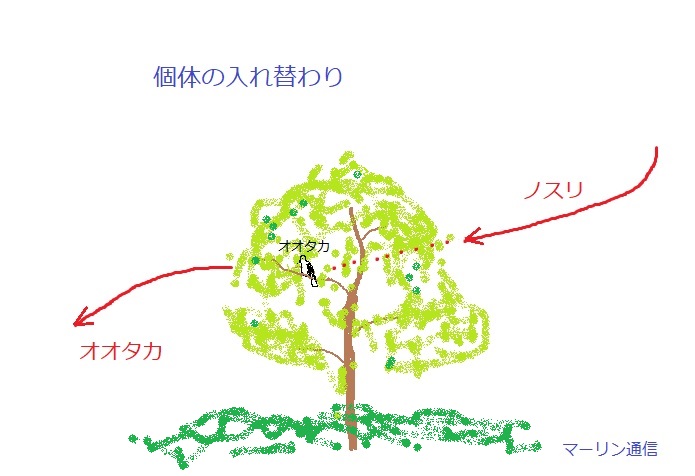
こういう瞬時の入れ替わりをよく経験しました。識別を誤ったのではないかと疑問に思うときもありましたが、よく見ていればそういうミスは防ぐことができます。
【観察例 その他】
ほかにもいくつか経験しました。ほんの短い時間ながらも、観察中の個体の姿が一瞬消えた時、あるいは見失ってしまった時です。すぐに再捕捉できたものの、その個体は前のものとは別個体だったということがよくありました。観察中の個体が草地や樹木の陰になった直後再び現れた時とか、たくさんのカラスと激しい突っかかりあいをしていた時、あるいはやや遠いところの個体を観察していた時などは、再捕捉した個体がほんとうに今まで見ていた個体と同じかどうか、個体の入れ替わりの可能性があったかなかったかをその都度考えたほうがよさそうです。
--------- 注意すべき点 ------------
オオタカ成鳥から幼鳥へ、ノスリからオオタカへの2例は、しっかりと見ていれば分かることで、2例とも特に問題はありません。問題は、同じ種の中でよく似た模様を持つことの多い♂から♀に、幼鳥から幼鳥に、成鳥から成鳥に入れ替わるときです。イヌワシ、クマタカ、オオタカなど、近ければあるいは長時間観察できれば雌雄の判断がある程度正確にできますが、ごく短時間現れただけですぐに姿が見られなくなった時は雌雄どちらなのか分からないことがあります。そんなときにとまり個体・飛翔個体の入れ替わりが発生したら、「今まで、見ていた個体の雌雄を間違えていたのか」あるいは「♂が♀に入れ替わってとまったのか」の判断ができなくなります。十分に鮮明な画像でなくても画像を比較することはかなり役に立ちますので、やはり撮影は欠かせません。判断に必要な角度からの画像が撮影できない場合もありますので、鷹隼類の調査中や研究中、あるいは趣味で観察中であっても、やはり「ぼんやりとタカを見ていてはいけない!」と痛感させられます。
(Uploaded on 14 March 2021)
下のような画像を持ってきた人から「この羽は何ですか」という質問を受けたことがあります。同じような質問を、タカの羽が写った画像を見せながら各羽の名称や説明をしている時にも受けたことがあります。また、ある日、鳥のイラストを熱心に描いている女性に羽についてレクチャーしていた時「これは何という羽ですか」と聞かれたので、逆に「あなたは何だと思いますか」と聞くと「うーん、下雨覆が伸びてきた個体ですか」と答えられたこともありました。このように、かなり長い間鳥を見てきたベテランと思われる人からも聞かれることがあり、またとんでもない答えを聞くこともあります。
問題の羽は左の画像の中央部分で、初列風切と下初列大雨覆の間に何枚かの羽があるように見えます。その羽らしき部分を赤く縁取ったものが右の画像です。


赤く縁取った羽のような形のものは一枚の羽ではなく、隣り合う初列風切2枚の重なった部分がまるでそれぞれ一枚の羽のように見えてしまっているだけです。反射光だけで写った画像ではたいていの場合、これは見えません。透過光の強さの差で一枚の羽のように見えてしまいます。
タカ類の外側初列風切は下の図のような形状をしています。例としてノスリの初列風切ですが、他のタカ類でもおおよそ同じような形です。羽軸を境に外側(翼先の側)は外弁と呼ばれ、外弁欠刻 emargination と言われる欠刻があります。反対側(体に近い側)は内弁と呼ばれ、内弁欠刻 notch と言われる欠刻があります。notch は辞書には「V 字形の刻み目、切り目、くぼみ、段」などと説明があります。
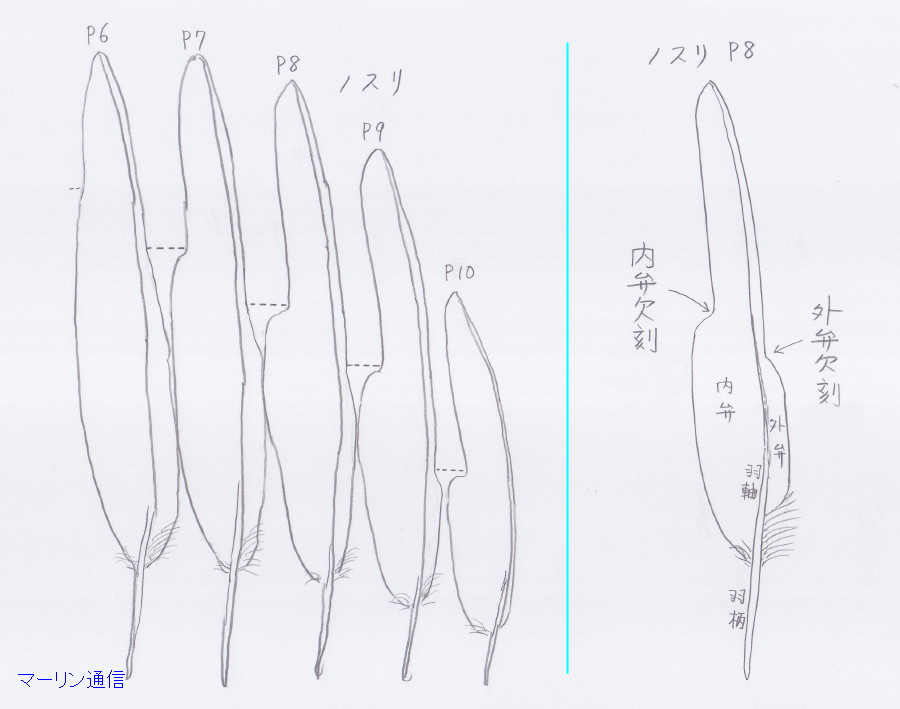
図の右のように、羽一枚だけを見ると欠刻の位置は内弁と外弁でかなりずれています。ところが、図の左のように、隣りどうしの羽を並べて欠刻(外弁欠刻と内弁欠刻)の位置を比べると図の破線でつないだように隣りどうしの欠刻がみごとに一致しています。隣りどうしの羽の外弁欠刻と内弁欠刻がピタッと絡まって固定されますので、2枚の羽の重なった部分の厚さが約2倍になり、他の部分よりも濃く透けて羽のように見えます。羽1枚だけの部分よりも2枚が重なった部分(一部は3枚重なっている)は透過光が弱くなるのでその部分がまるで羽のように見えてしまうというわけです。
翼を全開すると外側初列風切の羽と羽の間に隙間ができます。その辺りのことを翼先分離とか翼先突出などと呼びますが、翼先の羽が分離しても、翼全体の羽の重なり方(外側の羽ほど下に、内側の羽ほど上に位置する)が乱れては困るので、乱れないように互いに支えているのでしょう。
羽のように見えても実在しない(虚の)羽ですから、私は「虚羽(きょう)」と呼んでいます。高校の数学Ⅰで習う複素数の虚数単位iから連想して勝手に名前をつけました。鳥学会などの公認の学術用語ではないですが、自分では面白い命名だと思っています。いかがでしょうか。
今回紹介した種はノスリですが、他のタカでも虚羽は見られます。特に、トビ、ハチクマ、ノスリ、チュウヒなどではっきりしていて、画像をチェックするとよく写っていますが、もちろんオオタカなどのハイタカ属でも見られますし、やや見にくいもののイヌワシやクマタカなどの種でも見られます。ただし、光の当たり方がポイントで、反射光だけで写った画像では見えなくて、イヌワシのような黒っぽい羽では見にくく、高精細、クリアーな画像でないと見えません。
(Uploaded on 5 February 2021)
今まで雌雄成幼を♂♀のような記号や日本語で雄・雌・成鳥・幼鳥などと書いていましたが、今回は私がふだん使っている M,F,A,Y,J,U で記述します。これからはマーリン通信においてもなるべく M,F,A ……などを使っていく予定です。
M は Male で、♂(雄)
F は Female で、♀(雌)
A は Adult で、成鳥(全身が成羽のみ)
Y は Young で、若鳥(幼羽と成羽が混在している)
J は Juvenile で、幼鳥(全身が幼羽のみ)
U は Unknown で、不詳不明です。
組み合わせるので、例えば MA は♂成鳥、FJ は♀幼鳥、ForJ は雌か幼鳥(つまりMAではない個体)などとなります。M や F を記述せず単に A とする場合は♂か♀か判別しなかった(判別できなかった)時などです。U は種は識別しましたが、雌雄成幼が判断できなかった時とスルーして判断しなかった時に用います。
----------------
ここ数年の私は一年中、春も夏も秋も冬も、タカ類・ハヤブサ類のハンティングシーンを見ることに集中しています。彼らはどういう戦略で狩りを成功させているのか、翼や小翼、尾、体をどう使っているのか、種ごとのハンティングの違いは……など、知りたいことが山ほどあります。
この秋は愛知県に渡ってきて(だいたい10月20日ごろから)、その後、居ついたハイタカの狩りを中心に見ていました。獲物のほとんどはメジロで、時にカワラヒワやその他の小鳥を捕える瞬間を10数回見ましたが、至近距離ではなかったので、画像から獲物の種名は何とか分かるものの、しっかりとピントが来ていないものばかりでした。鷹隼類の渡来数は地域やポイントごとに異なると思いますが、私がよく行く地点(愛知県)の今冬のハイタカの数は多い年に比べればやや少ないように感じています。皆さんがお住いの都道府県ではいかがですか。
そんな中、2020年11月下旬、愛知県Y川の河口に近い干拓地へ行きましたが、やはりハンティングの様子に目が行ってしまいました。この日の観察は一人で、6:40~12:30の約6時間、天気は晴れ時々曇りで、ほぼ無風でした。ハイタカは出現がなかったですが、半日で鷹隼類9種が見られ、そのうちハイイロチュウヒ、コチョウゲンボウ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、チュウヒ、ミサゴの6種はハンティングのようすを見ることができました。オオタカとノスリは狩りを見ることができませんでした。印象に残った種の順に書きます。

クモの糸がそこかしこでかなり多かったです。種名等詳しくは分かりませんでしたが、バルーニングでしょう。

----------------
今年はCOVID-19の拡大で世界中の人々が思うようにいかない生活を強いられたと思います。「人類が生まれてこの方、いつの時代も大変な時代だった」ということを聞きます。これは世界史のトピックだけ、貴族の暮らしだけ、文化文明だけを追っていたのではなかなか分からないのですが、そこに生きた人々の生活をほんのわずかでも掘り下げて想像してみると、たしかにいつの時代でも苦しかったことがよく分かります。私が生まれるほんの7年前までは第二次世界大戦が行われていましたので、その後の時代は平和なような印象を受けますが、でも「生きづらい」時代だということは(たぶん)昔も今も同じでした。その原因は明らかにされていますが、原因が分かったからと言って「はい、それでは今日から別の生き方をしていきます」というのも難しいです。
おまけに歳をとってくると、むかし流行った「インベーダーゲーム」の最終盤のようになってきます。ゲームの最初のうちは誰でも簡単に気分良くインベーダーをやっつけることができますが、終盤になると敵機の数が一気に増えて、さらに相手の攻撃のスピードもぐんと増してきますので、人間業ではどう頑張っても最後は太刀打ちできないようにこのゲームはできています。100円玉一つで何時間でもゲームが続いてしまうとゲームセンターの人は困るし、遊んでいる人も飽きてくるので、当然終わる時が必要になり、そのためのからくりも必要です。ゲームを作った人はいろんなことがよく分かっていると思います。
(Uploaded on 20 December 2020)
バードウォッチングは気軽に始めることができる安全な趣味だと一般には思われていますが、けっこう危険な時もあります。鷹隼類の観察も同じで、一般の公園での鳥見などと比べると危ないことが多いです。昨日の私のへまを一つ。
タカ類の観察をするとき私は運動靴を履かず、たいていは長靴あるいはキャラバンシューズかトレッキングシューズを履きます。長靴は雨降りの日や泥の中、水辺近くを歩く時などで、これは一般的でしょう。キャラバンシューズを履くのは主に足首を保護することが目的です。急坂な登山道というほどの道は歩きませんが、ちょっとした坂のある登山道を歩いたり、起伏がある自然歩道を歩いたり、雑木林でもところによっては坂があったりしますので、やはりほぼ毎日キャラバンシューズを履く必要があります。
先日、この4年間履いていたお気に入りのトレゼータ製キャラバンシューズが傷んできたので、新しいものに買い替えました。履いていればすぐに慣れると思って気分よく履き始めたら、昨日、転倒しました。下の写真の黄色い矢印で示した左足のプルタブと同じく黄色い矢印の右足の靴ひものフックが絡んでしまいました。フックは片足で4個(左右に2個ずつ)ありますが、手を抜いて右足の下のフック2つを使わずにいました。一番左の画像のプルタブは危険だと思ってはさみで切ってしまった後ですが、元は一番右の画像のようにリング状になっていました。



さて問題はこのトラブルが私の年齢のせいではないかということです。ざっとで言うと、60~70%くらいはその可能性があると思います。歳ですから仕方がありません。残り30~40%は、若くても起こりうることと思うからです。体が倒れそうになると誰もが足を開いたり、ひざを曲げたりしてバランスを取るように対応すると思いますが、フックとプルタブが絡んでしまうと足は開けず、一瞬のことで何が起こったか分からなくなります。たとえて言うと両足の足首をロープできつく縛られてしまったような状態になります。さらにこの時はそれほど重い大口径レンズではないものの、キヤノンの100-400mmズームレンズと7DmarkⅡを両手で持っていて、とっさに「落とすとまずい!」と思ったのか、しっかりと持ったままでしたので、よけいに倒れやすかったのだと思います。

倒れたとはいっても幸いなことに草の上でしたので、痛みとか後遺症とかはまったくありませんでした。しかし、倒れたところの1メートル近くには大きな切り株があって、その脇に土管が置いてありましたので、頭が当たっていたらかなり危険でした。山の稜線を歩いている時だったらそのまま谷底へ落ちていきます。ニュースで谷底転落の死亡事故をよく耳にしますが、こういう些細なことが原因の場合もあるのでしょうか(登山の専門家に聞いてみたいです)。あるいは交通量の多い道路わきを歩いていて転倒し、車道側へ体が倒れたその瞬間に車が通りかかって死亡事故になることも考えられます。どんな小さなことにも気を付けないといけないですね。
こういう時に、何事も起こらずに擦り傷もなく済んでいく人と、その瞬間に死んでしまう人がいます。それぞれの人の業(ごう)をどのように理解・解釈すればよいのか、私には分かりません。
-------------------- +
タカ見、鳥見中の事故はかなり多いです。
〇 海岸の堤防から車が落ちてしまった
〇 急にタカが現れたので車から降りたら車が動いてしまった(エンジンがかかっていてPレンジに入れてなかったから)
〇 崖の上でバックしすぎて後輪2輪が脱輪し車が崖にぶら下がってしまった
〇 走行中に左に寄せすぎて脱輪した
〇 廃材に打ってあった釘を運動靴ごと踏んで足に刺さってしまった
〇 急坂を登っていて心臓発作が起きてしまった
〇 マダニに刺されて医者へ行かざるを得なくなった
〇 タカの渡り観察で紫外線を浴びすぎて上の瞼が腫れてしまった
〇 鳥の見過ぎで胃腸障害になった
〇 夏のアスファルト上での車内観察で熱中症になった
〇 行きかえりの交通事故
〇 氷点下の厳寒期に夜明け前から断崖絶壁に立って、翌日めまいになった
〇 上空ばかりをずっと見すぎて腰痛・首痛になった
これらはみんな、私が見聞きしたことや一部私が経験したことばかりで、おそらく全国各地で頻繁に起きていることでしょう。この他にも危ないことはきっといっぱいあるでしょう。私も68歳という年齢の割にかなりハードなタカ見(真冬の厳寒期でも、夜明け前から長時間におよぶタカ観察)を行っていますから、気を付けます。妻からは「深い山でなくても一人で山に入らないで、誰かを誘って出かけて……」と。そうですね、昨日は11月22日で「いい夫婦」の日でしたが、そんな日に死んでいては……。昨日は友人と2人で観察していましたが、転倒したところは一日中ほぼ誰も来ないところですので、もしも一人だけで頭を打って倒れていても、発見されるのは死んだ後です。
(Uploaded on 23 November 2020)
「タカ」の語源はいくつかの説があるようですが、一年中タカを見ていて一番もっともらしくて納得がいくのは「高い」「高く飛ぶ」説です。私に納得がいくからこの説が正しいというわけではないですが、実際、タカは高いところを飛んでいたり、高いところを渡っていくことが多いです。ハンティング中でも、高速を得るためにわざわざ旋回上昇して高く上がり、そこから急降下して必要なスピードを得ることが多いです。もっともタカ以外の鳥類もけっこう高いところを飛んでいることは多いですが、小さすぎて、双眼鏡のなかった時代には大きな群れでないと見おとされていた可能性があります。その点、タカ類は比較的大きいので、高くても分かる場合があるのでしょう。
タカの渡りなどで、よく聞く言葉があります。それは「タカが高すぎる」「遠すぎる」「かえってストレスになる」「最悪のコンディション」「見た気がしない」「いやになる」「気持ちがめげる」などです。確かに、そういうところを飛ぶことはよくありますが、「高い」ということは上昇気流をとらえやすくタカはいとも簡単に高空に達することができ、羽ばたかなくても楽に渡っていけるということ、「遠い」ということはいたるところに上昇気流があって観察ポイントの北側でも南側でもうんと遠くのほうでも、どこでもすいすいと渡っていけるということで、いずれもタカにとっては渡る条件が良いということです。もし翼を広げただけで1km上空まで難なく上がれたとすると、水平方向にはその10倍の10㎞くらいは羽ばたかなくても楽々移動できるようですし、風の向きが良ければさらに遠方までまったく羽ばたかずに移動できます。タカの気持ちを思うと、こういう日は「タカの渡る条件が良いんだ」と喜んでやって、タカに対して慈悲心を少し持てると良いなと思います。こういう心があれば(鳥にとって迷惑な)ストーカーじみたカメラマンになってしまうことはなくなります。こうなると観察者にはストレスが全くなくなり、こういう気象条件の時にはこういうふうにタカが渡っていく、こういう条件の日にはタカはあまり渡っていかない(渡れない、渡りにくい)ということがよく理解できるようになります。
私はできるかぎり「渡りをありのままに見る」ようにしています。タカが遠くを飛んでも近くを飛んでも、高く飛んでも低く飛んでも、あるいは(たぶん遠すぎて)タカがその一部の数しか見えなくても、ましてや写真が撮れても撮れなくても、それは、「タカがそこを選んでそこを飛んだから」というように観察します。無理にそう思い込まなくても客観的に見ているといつしか自然にそう思えるようになってきます。別の言葉で言うと、人間の意志とか希望(欲)、(撮影するとか数をたくさん記録するとかの)目的・目標をできるだけ取り払って、ただ客観的に、これっぽっちも主観を入れずに見るということです。こうなると、タカが渡るというエネルギーを直に感ずることができるようになり、渡り観察が今よりも数倍おもしろくなります。
------------------ +
さて、前置きが長くなりましたが、以下は遠いタカや高いタカを探す方法です。下の画像のようなところでタカを探すとします。
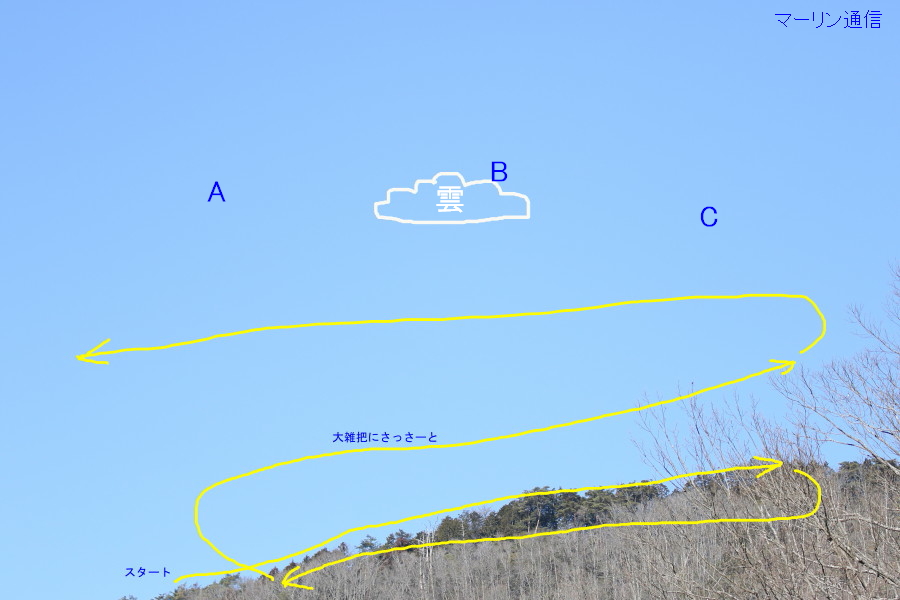
(1)
初めは写真の黄色い矢印のようにサッサーッと大雑把に見ます。空と林の境目をすーっと見て、林の木々をさらっと見て、空の低いところから順に上のほうへ右へ、左へ、右へとサーッと見ます。飛んでいるタカもとまっているタカもある程度近ければすぐに見つかります。スピードを上げて近づいているときは、双眼鏡で見るか、撮影するか、肉眼で楽しむか、いずれにしても早くに決めてすぐに対処できます。とまっているタカは空の色や樹木の色に溶け込んでいる時がありますが、どことなく色合いに違和感があって、何かがとまっているような印象を受けるものです。
(2)
次にゆっくりと探します。飛んでいるタカは図のA、B、Cなどを飛び飛びに見ていきます。ポイントはゆっくりとピントを合わせながら見ることです。肉眼で見るわけですから、若干目を細めないといけない時もありますし、時間をかけないといけない時もあります。
タカ渡りポイントでこの探し方を教えていると、たいていの人はA、B、Cの移動するスピードが速すぎます。うんとゆっくりと目を凝らしながら見ていきます。Aを一か所だけそのように見ていると、そのうちBもくっきりと見えてきます。そうこうするうちにCあたりではるか遠方を飛ぶツミが目に入ってきたりします。とにかくゆっくりと「何か飛んでいるはずだ」と思って時間をかけて見ることです。
なぜゆっくり見ることが大切かというと、遠くのタカは光の情報量が少ないからです。青空バックの白っぽいタカでも白い雲バックにポツンと黒っぽく見えるタカでも、遠いとそれだけ光が弱く情報量が少ないのです。速く視線を動かすと、たいてい見落とします。
とまっているタカも同じように「この木のてっぺん」「この木のあの枝」「この枯れ木のてっぺん」と納得しながら順々に丁寧に見ていきます。タカがバックの樹々に溶け込んでいるため、飛んでいる時と同じでやはり光の情報量が少なく、ゆっくりと見る必要性があります。
各地へタカを見に行きますが、「〇〇さんが来てくれると普段見られない珍しいタカ(例えば、愛知県でのタカ渡りでケアシノスリ、アカハラダカ、ハイイロチュウヒなど)が見えるし、いろんなタカを遠くで早いうちから発見してくれるので目の前に来るまでにカメラの準備ができて、ありがたい。今日もよろしく」と言われることがあります。初めのうちは「みんなお世辞がうまいなぁ」と思っていたのですが……(褒められた分のお返しは観察中にそれなりにしています)。私は偶然というか幸いというか、今も裸眼で左の視力が2.0、右が1.2~1.5で、眼鏡屋さんでの検査では、両眼ともに乱視がなく水晶体や硝子体に濁りがないと言われています(歳なので読書の時にはあまり強くないシニアグラスは必要です)。これは、今まで長い間、ほとんどテレビを見てこなかったことが一因とは思いますが、40数年間、遠くのタカにピントを合わせ続けてきたことも大きかっただろうと推測しています。
まとめると、
1 詳しく見る時は、アナログ的に連続して見るのではなく、飛び飛びにデジタル的に見る。
2 どこかに浮かぶ雲の端(写真のB)か遠い山のてっぺんに自分の目のピントを合わせ、目を凝らし、そのままゆっくりとずらしていく。慣れるまではゆっくりゆっくりと見ていく。たいていの人はこの「ずらすスピード」が速すぎます。
3 はるか遠方あるいは高空を小鳥が1羽飛んだように見えても、双眼鏡で確認するとタカだったということもある。
4 初めから「何も飛んでいるはずがない」と思わず、「何か飛んでいてもおかしくない」「何か飛んでいるはずだ」と思ったほうが良い。
3のようにして、それが間違っていてもいいです。昔、ミサゴの個体数がまだひじょうに少なかった時代、北陸地方へタカを見に行きました。海岸の崖に立っている枯れ木の枝にミサゴがとまっているように見えました。「珍しいミサゴだー」と喜んで、遠いので初めから友人にプロミナーを出してもらって覗いたらウミウでした。また、小さな黒い点が、双眼鏡で見れば、肉眼では絶対に識別できないほど遠くを飛ぶ飛行機だったこともあります。お祝い用のイベントバルーン(風船)だったこともあります。逆にその小さな点が、コウノトリであったりシロエリオオハムであったこともあります。仮に間違っても「あっ、飛行機でした」などと即座に訂正すれば笑って済みます(間違いをそのまま無理に通してしまうのは大間違いです)。
上の見方は時間がかかって面倒な印象を受けると思いますが、すぐ慣れて、慣れれば全く時間をかけずに遠くを飛ぶタカを今よりも容易に探すことができるようになります。
------------------ ++
偏光サングラスを使うと青空に溶け込んだ見にくいタカがくっきりと見えることがあります。ただし見る角度によって逆に見にくくなったり光量低下になったりしますので、時々首をかしげるようにしてグラスに入る光の角度を変えてやる必要があります。これもすぐ慣れますので、私としてはお勧めの方法です。
(Uploaded on 2 October 2020)
オオタカが鉄塔の上や目立つ木の枝にとまって、しきりに獲物を探索しているところを見かけます。こちら(観察者)が気が付かないだけで、木の葉に隠れて(獲物からは自身の姿が見えないようにして)獲物を狙っていることも多いです。首を動かしてキョロキョロと左右や周りを見たり、上空を見たり下の方をのぞき込んだりして何かを注視していることから獲物探索中と判断できます。狩りに飛び出すまでにけっこう長い時間がかかることがあります。獲物を見つけても狩りに適した瞬間(獲物が警戒心を緩めるまで、広いところやタカの近くへ移動するまでなど)が来るまで待っていますから、よけいに時間がかかります。
脱糞して体を前傾姿勢にすれば高い確率で飛び立ちますが、それまでの待ち時間がかなり長い時があります。脱糞せずに急に飛び出すこともよくあります。前傾姿勢になるまではいつ飛び立つか分からない時もあり、観察している私としてはずっと緊張して見続けることになります。ハンティングの決定的な瞬間が観察できなくても、最低限飛んでいった方向や入っていった森が分からないとその後の観察が続きません。せっかく今まで個体を捉え続けていたのにすべてが振り出しに戻ってしまいます(改めてタカを探さなくてはならず、ゼロからのスタートです)。飛び立つまで長時間待っている間に、カメラの液晶画面で露出のオーバーやアンダーをチェックしたり、届いたメールの差出人は誰かなと思ってごく短時間だけ目を離した隙に飛んでしまうことがちょくちょくあります。意図的にタカを凝視しないように気を付けながらタカから目をそらすようにさりげなく観察していても、タカはやはり見られていることが気になっていたのでしょう。観察者が目を離したわずかな隙を見て、スッと林に入ったり、下に降りたりするものです。観察者以上にタカは観察者をじっくりと観察しているからだろうと考えています。
さて、明らかに獲物探索中と思われる時であっても、時々羽繕いや伸びをしたり、それまではやや前傾姿勢だったのが体を垂直にし、羽毛をふっくらと膨らませたりし始めることがあります。そんな時、「なんだ、休憩モードに入ってしまった。狩りはお休みかな」と思うことがあります。休憩モードと獲物探索モードが瞬時に変わるようで、今はどちらなのか迷うことがあります。
しかし、見るからに休憩モードになっていても、脱糞し、前傾姿勢になって突然飛び立ち、羽ばたきと滑空で獲物の群れに突っ込んでいって、狩りが成功することがよくあります。
下の図をごらんください。初めオオタカは携帯電話基地局(携帯鉄塔)のAにとまって鉄塔の中央部分に体を向けていました。一番上のほうなので目立つところですが、中央向きにとまっていると飛び立つためには体の向きを逆にする必要がありますので、すぐに飛び立つことはできません。もちろん、それなりに周りが見えるところなのでどこに獲物がいるかなどは見ていたのでしょう。あるいは、獲物のほうに背を向けて相手を油断させようとしていたか、なんらかのカモフラージュの意図が多少はあったのかもしれません。長時間Aに向こう向きでとまっていました。40分くらい時間が経ったころ、アンテナのてっぺんBにひょこんと飛び移りました。移った後は頭の動きが盛んで、周りをキョロキョロと見ています。そして、体を前傾にして頭を少し上下させた後すぐに飛び立って、強いはばたきに時折滑空を交えてぐんぐんとスピードを上げて、870メートル離れた田の上にいたドバトの群れに突っ込みました。私は初めからドバトの群れの近くにいて「オオタカは体があちら向きだけど、一番てっぺんに近いところにとまっているので、待っていればこのハトの群れに突っ込むに違いない」と思って観察をしていましたが、鉄塔上のオオタカに私が気がついてから47分後にやっとハンティングで飛び出しました。幸いなことに一部始終を見ることができましたが、ドバトの群れのすぐ近くに人(私)がいることなどまったく気にしないみごとな一直線のハンティング飛行でした。
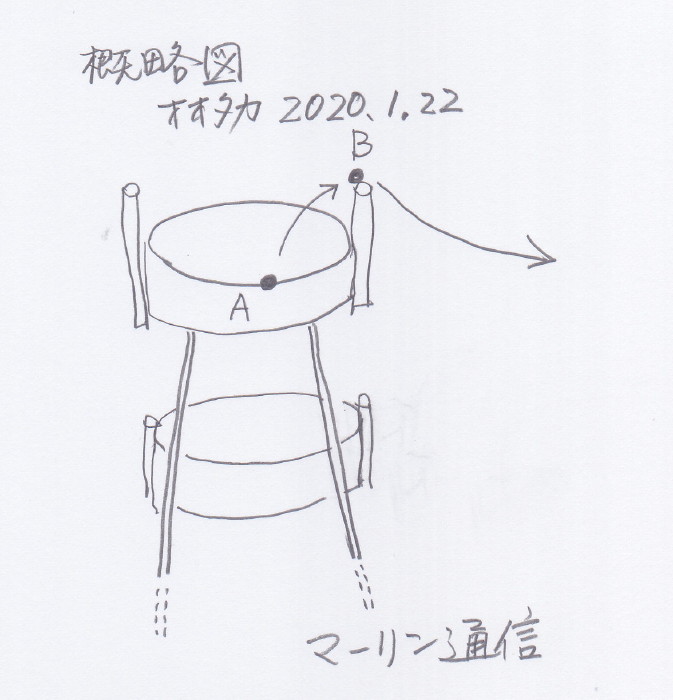
単純に「休憩中なのか、獲物探索中なのか」を区別することは難しいです。以前この通信で「電線上のコチョウゲンボウは狩りの真っ最中」という文章を載せました。実はオオタカも同じです。一般的に言うと猛禽類全体にもある程度当てはまります。鉄塔や目立つ木の枝の上にいるタカ類・ハヤブサ類は、そういうところにいるだけで狩りの真最中と思ってたいていは間違いないです。そうでないとしても、「休憩しながら、もしも獲物が現れて捕らえやすい状況になったら狩りをする」というつもりで休憩することもあります。紛らわしいのは監視木にとまっての監視中と、目立つ位置でのとまりディスプレイですが、状況を考えながらタカの頭の動きを見ているとある程度違いが分かります。
「休憩しながら獲物を探索している」、「獲物を探索中に休憩もしている」といったところが一番正確なような気がします。タカがほんとうに100%休憩したいのなら、鉄塔上の目立つところにはとまらずに、葉に隠れたような木の枝でカラスに邪魔されずに休むことが多いです。もちろん、オオタカのように葉に身を隠しながら獲物を探索することがありますので、逆は真ならずで、単純に考えることはよくないです。いずれにしても、オオタカが何を見ているか、その視線に注目することが一番大切です。
(Uploaded on 22 September 2020)
自分で撮影した一枚の画像、あるいは誰かから送ってもらった一枚の画像にだまされてしまったことはありませんか? だまされたというよりも勝手に勘違いしてしまったことはないですか?
写真を撮るには時間と資金と労力が必要です。つまり手間暇がかかります。撮影者には忍耐力が求められ、好きでないとやれません。しかし、画像は人間の肉眼では捉えきれない瞬間のようすを記録することができ、撮った後で尾羽の枚数を数えたり、換羽で伸長中の場合は長さを測ったり、肉眼では気が付かない風切の小さな欠損で個体識別をしたり、その個体独自の思わぬ特徴に気が付いたり……と、写真には写真でしか得られない情報がたくさんあります。タカの研究をするには、写真撮影は必須です。
でも、写真に写ったものを100%信じきっていると大きな判断ミスをすることがあります。今日は、つい錯覚してしまいそうな例と光線の加減によって誤判断を招きそうな例を紹介します。
【 例1 】 オオタカとツミの体の大きさ(錯視)
下の画像は有名なものなので今までにいろんなところでご覧になったと思います。垂直な部分の線分の長さが左のほうが右のものよりも長く見えてしまいますが、実は両者の長さは同じというものです。
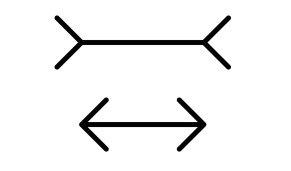
今度は下の画像を見てください。オオタカとツミが飛んでいます。ツミ幼鳥がオオタカ幼鳥にモビングしているところです。両者にほぼピントが合っていますから、カメラから2羽のタカまでの距離は、(多少違うかもしれませんが)ほぼ同じでしょう。2枚とも同じ縮尺です。毎秒10コマで撮影した連続する2コマですので、この2枚の画像の時間差は0.1秒ほどです。左はツミが、右はオオタカがそれぞれ翼を全開して、それぞれもう一方のタカは翼を閉じ気味にしています。

カメラの液晶でちらっと見ると、左の画像ではツミがかなり大きく見えてしまって、2羽が同じくらいの大きさのタカに見えます。右の画像ではツミがこんなに小さいのかと思うほど小さく見えていて、まるでワシとツミが並んでいるかのようです。同時に撮った他の画像から、オオタカは体の大きい♀で、ツミは体の小さい♂だろうと推定していますが、そうだとすると、なおさら違いが大きく表れているのかもしれません。PCの画面で見ればどうということはなく、間違えることはありませんが、カメラの小さな液晶画面で左側の画像だけ、あるいは右の画像だけを見ると一瞬ドキッとします。とてもツミの大きさには見えないでしょう。
【 例2 】 ミサゴの下大雨覆の模様
撮影したミサゴの画像を自宅のPCで確認中に、なんだこの模様は?と思ってしまいました。
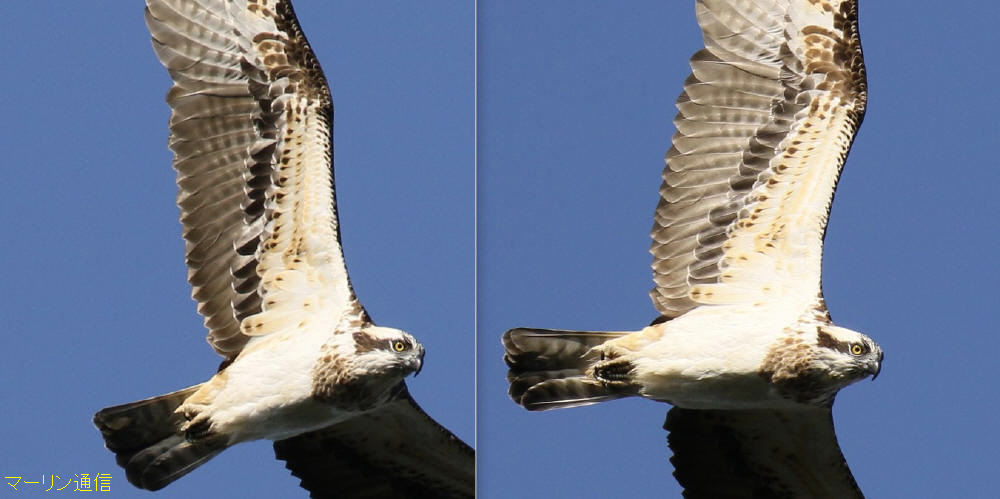
下大雨覆の一枚一枚が羽軸を境にして外弁だけが白っぽく(淡褐色)、内弁はみんな黒っぽく(濃褐色に)写っています。このミサゴは翼を広げたまま地上近くをゆっくりと飛びましたのでたくさん連写しました。左側の画像の前のコマも後ろのコマも確認しましたが、これ一枚だけではなく、10数枚全部が同じような模様に写っていました。そしてさらに画像を見ていくと、17枚目から右の画像のような模様の画像ばかりになりました。何らかの光線の加減で最初のうちの16枚だけが左のように写っていました。もし連写を10枚ちょっとでやめていたら、すべての画像が左のように写っていたわけで、「世の中には下大雨覆がこういう模様のミサゴもいるのかな? なんか変だけど16枚とも全部がそう写っているからそうなのかなぁ……」で終わっていた可能性があります。
例1は一枚の画像だけから、例2は枚数は多いものの一方向からだけの画像から判断したわけですが、それは危険です。
木の枝にとまるオオタカの一枚だけの画像を見て、頭がかなり大きくて、重心の位置や色合いなどから「この成鳥はオスだろう」と推定したものの、後で見るほかの画像(同じ個体を撮影した画像)や、後日追加で送信されてきた同個体の画像を見るとどう考えてもメスだろうということがありました。自分で勝手に間違えただけなのですが、つい画像のせいにしてしまうことがあります。やはり、一枚の画像だけで判断することは危ないです。
上記の2例以外にも雌雄の判断、年齢の推定、亜種、個体差など判断ミスを起こしてしまいそうな例を挙げていったらきりがありません。画像にだまされることは稀なことではなく、けっこう多いのです。日常茶飯のことと思って、せめて数枚の画像を見て、あるいは違った角度から撮った画像を何枚か見て判断すべきと思います。もしそのように画像を見ても何かおかしいなと思うときは判断をいったん保留にしたほうがよいでしょう。画像というものは慎重なうえにも慎重に見るべきで、その上でなお、「この写真は果たして真を写しているのだろうか」と思うくらいでちょうどよいでしょう。
(Uploaded on 3 September 2020)
去年一年間でタカ類・ハヤブサ類のハンティングを約380回見たと半年前の記事に書きました。こういう回数を数えることに何の意味もないことは私もよく分かっていますが、一日中いくら探し回ってもオオタカの姿が見られなかった40数年前と比べて、今はどんな状態なのかを実感したかっただけかもしれません。今年はいろいろな事情が昨年とは異なり、野外に出かける日数が少なくなってしまいましたが、この半年(1月~6月)間で観察できたハンティングの回数は157回でした。
157回の種ごとの内訳は、
1 オオタカ 102回
2 チュウヒ 21回
3 ハヤブサ 13回
4 その他 21回 でした。
「その他」は、ミサゴ6、ハイタカ6、ノスリ3、コチョウゲンボウ2、チョウゲンボウ2、ハイイロチュウヒ2回でした。
ミサゴは秋から冬にかけて海岸で見ていれば、狩りの観察回数はいくらでも増えると思います。同じようにノスリやチョウゲンボウも冬場農耕地で見ていればかなりの回数が見られると思いますが、ハイタカ属とハヤブサ類に比べると飛行の俊敏さが物足りないので、私はあまり熱心に見ていません。
私の主な観察種はオオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、コチョウゲンボウの4種です。この4種以外に見たいのはツミとハイイロチュウヒ、イヌワシ、クマタカなどですが、愛知県ではどれも生息数があまり多くないです。と言うよりも、2月~7月はオオタカの繁殖期の生態観察だけでも忙しすぎて、夏は換羽のようすの観察、秋から冬はハンティングの観察で忙しく、時々ハヤブサやコチョウゲンボウの観察に出かけると、すでに余った時間はありません。一人の人間が一年でまともに観察できる種はやはり一種しかない!のではないでしょうか。さまざまな野鳥の生態に詳しくないと林の中で潜むことの多いオオタカを(姿を見ずに、声も聞かずに)探すことはできないですが、オオタカの観察中に多くの鷹隼類やいろんな野鳥が出現しますので、楽しみはたくさんあります。
さて、問題はこれらのハンティングの対象種です。対象種が判明したものはたくさんありますが、不明というものもけっこうあります。最近の不明事例をいくつか紹介します。
2020年6月下旬のことです。携帯鉄塔にとまっていたオオタカ♀成鳥が飛び立って、力強く羽ばたいて私の頭上を通過し、520m先で身を翻して急降下しました。飛行中にすでにハシブトガラス2羽が激しく鳴きながら集まるように飛んでいきました。双眼鏡で見ていた私には、その林からキジバトが勢いよく飛び出すところが見えましたが、オオタカがそのキジバトを追いかけるところは見えなかったので、狙ったのがこのキジバトなのかどうかははっきりと分かりませんでした。キジバトがいた林にオオタカが突っ込んできたので慌てて逃げていっただけなのかもしれません。私の記録上は対象種不明にしてあります(キジバトは参考までに記録)。
こういうことはよく経験します。自宅近くを散歩中に目の前を横切るようにムクドリ10羽くらいとスズメ20数羽が田んぼから電線に飛び上がりました。こういう時は小鳥の後ろのほうを探すのが鉄則ですが、そちらを見ると、オオタカの成鳥(雌雄不明)が田の上を低く北の方へと飛んでいました。ハンティング中のような飛び方ではなかったので、飛んで移動中のオオタカにびっくりして、危険回避目的で飛んだだけ(除けただけ)だろうということが分かりました。上のキジバトも同じようなことだったかもしれません。
もう一例。
上とは別の地点で、2020年6月下旬のことです。この日は1羽のオオタカ♂成鳥を追跡していました。営巣林から出たオオタカは近くの松林に入った後、飛んで送電鉄塔や携帯鉄塔(基地局)のてっぺんにとまりました。離れて観察していましたが、また飛んで、旋回上昇をし始めました。どんどん高いところまで上昇していって、肉眼で見ていると点のようになり、少なくとも200m以上は上がったでしょう。そこで滑空に転じて、どんどんと遠ざかっていきました。飛んだ方向に思い当たるところがあるので友人と探索すると、木の枝にとまっていました。巣から直線距離でちょうど2.5kmのところでした。このとまり個体が追跡している個体と同じかどうかは、両翼の初列風切P9などの欠損のようす(欠けた部分の形)から判断しましたので、間違いはないです。とまった枝から下の画像のように今か今かとタイミングを見計らうようにしながら3回ハンティングしました。

3回のうち、2回はドバトを狙いました。2回とも追いかけるオオタカと逃げるドバトを見ることができましたが、狩りは失敗しました。問題は3回目です。同じ枝から飛んで、近くにある畑の上辺りで急降下するところまで見えました。すぐに何も持たずに急上昇し、同じ枝に戻ってくるところも見えました。畑の辺りは手前にある樹木のむこうで私からは見えませんので、何を狙ったのか不明です。ムクドリが激しく鳴いてその畑の辺りから出ていくところが見えましたが、オオタカがそのムクドリを狙ったかどうか、正確には分かりませんでした(ムクドリは参考までに記録)。
しばらくしたら、その枝から飛んで近くの林に入っていきました。私は車を移動させて近づきましたが、数分後に小さな獲物を持って私に向かって飛んできました。オオタカが目の前のすぐ近くにいるということと、狩りをしただろうということは分かっていました。しかし、運転席に座って少し油断していたので、助手席に置いてあったカメラを手に取り、車から出て、急いでカメラを構えて撮影しましたが、ごく短時間で向きを変えてしまい、下のようなどうしようもない画像しか撮れませんでした。小鳥だということは分かりますが、種名ははっきりしません。近くの林に入って行きましたが、その辺りのハシブトガラスの声やようすからその林で食べたようです。30分ほどで営巣林に戻ってきましたが、獲物持ちかどうか(全部食べてしまったのか、残りを搬入したのか)は不明でした。

こんなようなことばかりで、狩りの瞬間が木に隠れて見えないことが多いです。あるいは運良く撮影できても、種名が分かるほどクリアーに撮れなかったり、獲物が小さすぎて判断できなかったりします。また、巣にヒナがいるころのオオタカは獲物の羽毛をほぼ完全にむしり取って丸裸で、あるいはまるで肉のかたまりのようにしてから運んで来ますので、獲物を捕らえる瞬間を見るか、むしった後の羽毛を林内や畔まで拾いにいかない限りは種名の確定はできないです。
たった半年間でも、これに似たような観察が他にもいっぱいありました。逆に、追われている獲物の種名が分かった事例、目の前でハンティングに成功した瞬間が見られた事例や、獲物を運ぶところが見られた事例、獲物運びの画像から種名が判断できた事例もありました。下はチュウヒ♂成鳥がヒクイナの巣立ちビナを捕らえた直後の画像です。向こう向きに飛んだので(人がいると、たいていは向こう向きに逃げます)、獲物の一部しか見えていませんが、足が長くて赤いこと、趾も長いこと、(光が十分に当たった他の画像も)全身がほぼ真っ黒であること、下尾筒の辺りに白い斑点がくっきりとあること……などから運良く判断できました。チュウヒの頭が向こう向きなので一部の人からは「残念な写真だ。こちら向きだといいのに」と言われそうですが、私としてはこういうふうに種名が分かれば十分に満足です。

あるタカが鳥類を主に捕食しているか、あるいは齧歯類が中心なのか、昆虫類を多く捕っているのかということは大きな意味がありますが、その中でどんな種の鳥なのか、例えばヒバリなのかホオジロなのか、〇〇ネズミか△△ネズミかというようなことはそれほどは重要でないことが多いです。国や地域が変わればそこに生息する種も異なって、タカはその地域に生息している種しか捕らえることができないからです。アメリカ大陸のオオタカと日本のオオタカの獲物を比べてみるとよく分かります。
一方で、愛知県〇〇市の〇〇地区のオオタカが、冬は〇〇をよく捕らえ、ヒナが巣にいる繁殖期には△△の巣立ちしたばかりの幼鳥をよく捕らえ、その幼鳥が成長して飛翔力が増すとこんどは他の小鳥をよく捕らえるようになるとか、時期によって狩りの方法や生活様式がどのように変わっていくかというようなデータは欲しいです。また、どの程度の飛翔力のある獲物まで捕らえることができるか、体重何グラムくらいの獲物を多く捕っているか、哺乳類・鳥類・両生類・昆虫類など分類ごとの捕獲回数と総重量の内訳なども知りたいです。
(Uploaded on 4 July 2020)
ある人のブログのリンク先に「マーリン通信」が紹介してあり、その一言欄に「タカ類のハンティングの観察記録が多く見られます」とありました。今まで、タカの渡りをひんぱんに取り上げた時期や識別のことを多く書いた時期がありましたが、最近はタカ類のハンティングを多く書いています。去年(2019年)はタカ・ハヤブサ類のハンティング時の飛行技術を中心に見てみようと思い、狩りの観察を続けました。観察時のようすを鮮明に思い出すことができるように事細かく(時には、誰に会って何を話したかなども含め)記録を取っていますから、この正月休みに去年のハンティングの観察回数を数えてみたら、一年間で約380回の狩りを見ていました。
(今回の狩りの数え方)
鷹隼類はほぼ一日中狩りをしています。食べるために生きているわけではないですが、生きるためには食べざるを得ないので、一日中狩り中心の生活をしています。渡りの時期や夜間でなければ、その活動のほとんどは狩りに関係することばかりと言ってもよいでしょう。これは人間が生きるために仕事をしていることとよく似ていて、ほぼ同じです。
狩りは一般的には、「獲物の探索」から始まり、狩りしやすい瞬間まで待つ「待ち」の時間があり、「急降下・追跡」、「捕獲」、「獲物運搬」、「むしる・食べる」、「くちばし掃除」、「休息」などと続きます。運ばずに捕らえたその場で食べることもありますし、羽毛をむしってヒナがいる巣の近くにいる♀に渡すこともあります。これだけの一連の行動で狩りの回数は1回ですが、多くの場合獲物を捕らえることができなくて狩りは失敗します。うまく捕れなかった時も急降下や追跡が見られれば狩りの回数は1回としました。
獲物探索だけで、鉄塔や枝にとまって辺りを見回していた、凝視していたとか、飛びながらキョロキョロと頭を左右に向けて見ていただけで突っ込まなかった、あるいはそこまでしか観察できなかったという時があります。これもほんとうはハンティングの一部なのですが、これだけでは計上しませんでした。
計上しなかった理由は、探索だけでやめてしまうことが多くあるからです。また、樹木の枝や鉄塔上で休息しているように見える時も、実は隙あらば狩りをしようと思い、獲物が捕りやすいところまで来れば一瞬で狩りのモードに変わってしまうことがあります。つまり、休憩しながら狩りのチャンスを待っている時(逆に、狩りのチャンスを待ちながら休憩している時)がありますので、実際に追跡行動等をとるまでは数えませんでした。
以前、電線のような目立つところにとまっているコチョウゲンボウは狩りの最中だということを、コチョウゲンボウのフォルダーに書きましたが、これはコチョウゲンボウだけではなく他のすべての鷹隼類にもある程度共通しています。ほんとうに休憩したければどこからでも見えるような目立つところや高いところにはあまりとまらず、カラスにじゃまされないような静かで目立たないところにとまります。矛盾するような話ですが、実際に獲物を追跡し始めないと、よく分からない場合があります。追跡し始めれば、かなり正確な話になります(監視行動や誇示行動の時は似たようなとまり方に見えますが、それは違いがあります)。
ということで、鉄塔や枝で獲物を探索していても、それ以上の段階まで進んだ時だけ回数に入れました。追跡を始めさえすれば、途中でやめたかもしれない場合や見えなくなってしまった場合も狩りの回数に入れてあります。タカが両足を伸ばして獲物をつかむ瞬間が樹木に遮られて見えなかったとか、地上ぎりぎりまで追い詰めて草の陰で見えなかったという場合が多く、失敗も多いので最終段階までいかなくても回数は1回としました。
逆に言うと、オオタカがヒクイナを持って飛んでいたら狩りの全体が見えていなくても狩りが成功したので、それだけで狩り1回としました。地上でケリを食べていたところしか見えなくても、狩り1回にしました。ただ、ハトを捕らえたオオタカ♂成鳥が繁殖ペアではない(♂よりも体の大きな)♀成鳥に(冬の初め)獲物を捕られてしまったり、同じくオオタカ♂成鳥や♀幼鳥がノスリに獲物を横取りされてしまうことがあります(♀成鳥がノスリに獲物を横取りされたことは今のところまだ見たことがありません)ので、自分で捕ったものか横取りしたものかは念には念を入れて判断することが必要です。横取りは卑怯な方法かもしれませんが、それはそれで立派な狩りだと考えることもできます。
(さらに具体的に)
チュウヒやハイイロチュウヒが両翼をバンザイするように上げて両足を伸ばして地面やヨシ原に突っ込んだ時は獲物が見えなくても1回としました。両種とも、ヨシ原上空でキョロキョロしながら飛ぶような探索飛行だけでは計上しませんでした。狩りは多く見ましたが、繁殖期に獲物を持って巣に帰ってくるチュウヒばかりで(これもカエル類が多く)、ヨシ原で捕らえたネズミや鳥類をぶら下げて飛ぶところはあまり見えなかったです。以前、チュウヒが数百メートルにわたってヨシ原上でタシギを追いかけたことがありますが、タシギが私の立っていた脇を通っていったので、チュウヒは近寄れずあきらめたことがあります(愛知県の冬のヨシ原上空でしたのでこのジシギをタシギとしました)。
ノスリが電柱のてっぺんから急降下してネズミを捕らえたりバッタをつかんで上がってきた、あるいは地上で食べていれば狩り1回にしました。チョウゲンボウもほぼ同じで回数は多いです。
ミサゴが杭の上で水面を凝視しただけとか飛びながら頭を左右に動かし目をキョロキョロとしながら水面を見ただけでは1回に数えませんが、水面にザバッと突っ込めば失敗しても1回にしました。
トビが腐肉を食べている時は狩りには計上せず、(10月頃など)樹木の頂にとまっている生きたカマキリなどの大形昆虫を足で捕らえて食べる時は1回に計上しました。
ハヤブサは秋渡るヒヨドリの群れを海上で何度も急降下して攻撃しますが、陸地から飛び出していって陸地へ帰ってくるまでで狩りの回数は1回にしました。たいていは私からは遠すぎて、こういう狩りを見る回数は多いものの、近くで撮影できるのは獲物を持って帰ってくるところばかりです。陸上ではいろんな種の獲物が狙われますが、やはりドバトが多いです。ドバトの一群に何度も突っ込んでも回数は1回ですが、鉄塔にとまって一休みしてまた再開したり、上空で wait on した後で再開すればそれは2回目の狩りにしました。
ハイタカ好きな私はハイタカの狩りをよく見ましたが、小鳥や小鳥の小群に突っ込むものの失敗することが多かったです。失敗したら、枝にとまったり上空で待機するなどの仕切り直しをして、また別の小鳥や小鳥の群れを狙いますので、失敗が多い分だけ狩りの観察回数が増えました。ある日、高速度で急降下してメジロを捕らえましたが、捕獲の瞬間だけは樹木の陰になってしまい、足を伸ばしてつかみ捕るところは見えませんでした。捕った後、下の画像のようにすぐに浮上して(高度を上げて)、意気揚々と飛んで近くの雑木林に入っていきました(意気揚々というのは私の主観です)。このようによほど運良く観察できても、どこかの段階は観察者から見えないことが多いものです。


(もし観察回数を増やしたければ)
観察に出かける日数をもっと増やしたり、今は一日8時間止まりの観察時間を一日で10時間とか増やしたりすればさらに観察回数は増えると思います。生息数の多いノスリやチョウゲンボウが農耕地で獲物を探していても、ある程度の時間見たら観察をやめて、コチョウゲンボウはどこかにいないか…、ハヤブサは…と他種を探しに行ってしまいますので、そういうことをやめてノスリやチョウゲンボウが昆虫類を食べるところを朝から晩まで見続ければ狩りの観察回数は一年間で楽に500回を超えるでしょう。
(Uploaded on 18 January 2020)
オオタカやハイタカの行動や生態を観察中に写真を撮っていて、「しまった!」と思うことが時々あります。
たいていは、「しまった、こんな迫力のあるシーンはめったに見られない。写真なんか撮らずにもっとじっくりと見ればよかった」という場合が一番多いです。それはたいてい鷹隼類が近い時です。オオタカが私の20mほど先でハンティングした瞬間だとか、ハヤブサが上空から急降下してきて頭の上の低いところで獲物を蹴って急上昇に転じた時、ハイタカが私の存在に気が付かず(あるいは私を無視して)数mの距離をスーッと飛んだ時、オオタカがアクロバティックな背面飛行をした時、ハイタカが両足でメジロを捕らえた瞬間…などです。
写真を撮ればそれなりの満足のいくカットが撮れる時もありますし、ピントがぜんぜんこない時もあって、それはその時々で違いますが、いずれにしても肉眼でタカ類・ハヤブサ類のダイナミックな動きを見ていないことに変わりはありません。貴重な証拠写真あるいは他の誰も撮ったことのないような珍しい生態写真になる可能性もありますので、逆に「なぜ写真を撮らなかったのだろうか…」と思うこともあって一概に結論は出ませんが、「見ていない」ことは大きな損をしていることになります。「しまったー。あの時カメラなんか持たずにただ見ることだけに専念すればもっと感動的な体験ができたのに…」と思うからです。
私は小学生の頃からカメラに興味があって、昔有名だったアサヒペンタックスSPという一眼レフカメラと現像・プリントができる暗室など何もかもそろえたのは、もう50数年前のことです。以来ずっとカメラを持ってきましたが、やはり「肉眼」で鳥を見ることがいちばんの喜びです。どちらかというと私はカメラマンではなく、やはりウォッチャーです(このあたり、カメラマンとウォッチャーの定義と分類をしっかりしなくては議論できませんが、書き出すと長くなりますので今日はスルーします)。
心理学者の興味深い研究が新聞に載っていました。2015.11.1付けの朝日新聞に入っていたタブロイド判の GLOBE の7ページに下のような記事として紹介されていました。左下の4行分と右上のあたりです。私の実感としてもこれと同じで、「なるほどその通りだ」という内容です。「タカの写真を撮っている時、私はタカを見ていないのではないか?」というおぼろげな思いが「そうなんですよ!」とあぶり出されたようです。
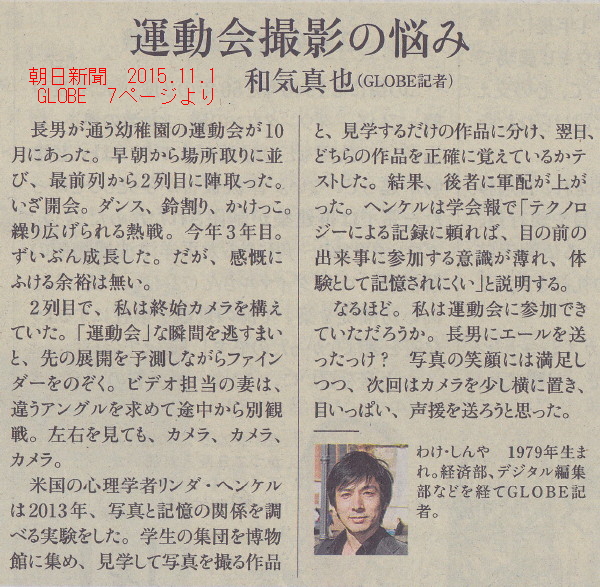
一方で、画像を撮らないと分からないことは多いです。個体識別、風切・尾羽の欠損、羽毛の乱れ、換羽のようす、風切・尾羽の新羽旧羽、鷹斑のようすなどいくら肉眼でじっくりと見ることができたとしても、画像を撮るとまた別の正確さが得られます。写真では風切や尾羽の鷹斑の太さを測ったりハイタカの体下面の横斑の本数を数えたりすることもできますし、画像をいつまでも見続けることや保存もできます。2枚以上の画像を並べて模様や色合いなど細かな差異のチェックもできます。
下の画像は、ハトを追うオオタカ♂成鳥です。高空でハトに近づき、追いかけながら徐々に高度を下げてきて、まさに捕獲直前ですが、ハトが急に背面飛行になったのでオオタカもわずか0.1秒後に背面飛行をしはじめました。この一連のハンティングのようすを毎秒10コマの高速連写で撮影しましたが、翼をどうすぼめたり広げたりしているか、尾羽は方向転換にどう使うか、どのタイミングで足を出すか、0.何秒間足を出しているのか、どのように足を伸ばして獲物をつかむかなど、さまざまなことが分かってきます。人間の視覚では把握できないスピードで繰り広げられる瞬間瞬間の動きを画像にすれば把握することができるのですから、どうしても写真を撮らないわけにはいきません。しかし、目の前で繰り広げられるここぞという決定的な瞬間はやはり肉眼だけでじっくりと見てみたい、そのほうが感動的でうれしい場合もある…という気持ちも別のところにあって、両者はまさにトレードオフの関係にあります。

下の写真は2月10日に撮ったオオタカ♀成鳥です。実はこのオオタカはしばしば見かけている個体で、狩りのようすや木どまり、カラスにちょっかいをかけられてうるさそうに飛んだり、けっこうさまざまなようすを何日も、何回も見ていたのですが、いくら双眼鏡で見続けても、あるいは下面からの飛翔写真を見ても(尾羽を閉じていることも多く)、尾羽の換羽状況はこの日まで分からないままでした。冬ですので「換羽は中断しているはずだ」、「去年の秋までにはたぶん換羽は終了しただろう」と思っていただけに、この画像を見た時にはびっくりしました。タカ類の尾羽の換羽順としては R5かR2 が最終ですから、12枚のうちの最後のころの換羽です。この時期までずれ込んだということでしょう。画像を撮らないと分からないことでした。

双眼鏡で、スコープで、あるいはカメラのファインダー越しにその瞬間を見ることはできますが、やはり「肉眼だけ」で目の前の空間の中のどの位置をどう飛んでどのように動いたかを把握しながら、そのスピード感や躍動感を実感することは、写真を撮りながらでは得られないものです。
(以下は以前にも似たようなことを書きましたが……)
ちょっと変わっているかもしれませんが、大きな口径のレンズを持っていて撮影技術と観察力のある人と一緒にタカ類を観察する時には、「撮影はお願いします。私は今日は肉眼で楽しませてもらいます。よろしく……」という時があります。これで嫌な顔をされる方は今まで一人もいらっしゃらなかったです。むしろ、初めての人は「変わってるねー。撮影しなくてもいいんですか」と言われ、お付き合いのある人は「えっ、今日は撮らないんですか」などと言われたりします。私は近くに来たタカを中心に400mmの短いレンズで撮っていますから、遠くを飛ぶ鷹隼類の雌雄成幼の判定や個体差などの確認はお任せして、私は十分に生態観察しながら肉眼で鷹隼類の飛行の醍醐味を味わっていますが、でもここぞという撮りたい時(タカが獲物を持って近くを飛んだ時、珍しい行動をしている時など)や証拠写真が必要な時には撮影もしています。ハイタカ属とハヤブサ類を中心に40数年間タカ類・ハヤブサ類ばかりを見てきましたが、最近ではけっこう至近距離でさまざまな生態や狩りの瞬間を見たり撮ったりできるようになってきました。
(Uploaded on 10 July 2019)
下の画像は4月28日に撮影したオオタカ♀幼鳥です。この画像からこの個体の換羽状況が分かりますか?

初列風切と次列風切を順番に見ていくと、両翼ともにP1とP2が脱落していることが分かります。2枚ずつ抜けているということは、P2は見えない可能性が高いですが、先に抜けたはずのP1が伸長中だろうということが想定されます。しかし、写真には写っていません。P1はあったとしてもまだ短く、これから伸びてくるところですので、隣の羽(この場合はS1とP3)に挟まれて隠れて見えないはずです。
こういう時は、同じ時に撮ったあるいは同じ日に撮った別の画像の中に、光が羽を透過しているようすが写っている画像がないか探すとよいです。下の画像は高速連写したもので、上の画像の約0.7秒ほど前のものです。

隣の羽の間に隠れている伸長中の羽は「反射光」からは通常写っていないことが多いです。1枚目の画像は反射光による画像ですが、羽の表面でほぼ全反射に近いくらい反射してしまいますので隠れた羽はまったく見えないですが、「透過光」なら隠れた羽でも見ることができます。たとえて言うとレントゲン写真のようなものです。または手のひらを太陽にかざした時のような見え方です。
同じ時に高速連写した22枚の中で新しいP1は6枚の画像に写っていました。上の右にある画像の赤い矢印をそれぞれ伸ばした交点あたりに半分くらい伸びたP1の先端が見えます。背面から入った光が透き通って透過してきますので、羽が1枚多い部分だけ黒くなっているのが分かります。
ヒナの時に体じゅうのすべての風切や尾羽などは一斉に伸びてきますから、幼鳥の風切は成鳥の風切に比べるとうんと薄くできています。そのため、ちょっとした光で羽が透き通って見えます。成鳥は幼鳥ほど透き通りませんが、それでも光が透過して伸長中の風切の存在が分かることは多いです。光が強い時はなおよく分かります。
高速連写については「無駄な連写」「撮影枚数が多すぎる」という印象を持つ時もありますが、連写することにより、光線の加減や翼の位置、写る角度が少しずつ異なりますのでそのうちの何枚かだけにしか写っていないものがあったり、数枚にしかピントが来ていない時があります。私がいつも連写にこだわって多くの枚数を撮影するのはそういう理由もあります。
(Uploaded on 1 June 2019)
キッチンにおいてあるステンレスポットを見た瞬間、私の目の前にコチョウゲンボウの姿・顔が浮かび上がりました。

このポットには上蓋の取り外し用に大きなつまみが左右対象に2つあって、それが大きく、丸くて黒く、わずかにキャッチライトもあり、可動部分がまぶたのようにも見えたので、このつまみ部分がちょうどハヤブサ類の黒っぽい(虹彩も瞳も黒っぽい)目に見えてしまいました。また、注ぎ口の先端が少しだけですが下にさがっていて、それが鷹隼類の嘴の先のように見え、上嘴と下嘴の境(会口線)もはっきりとしていますので、なおさら猛禽類に似ています。全体が黒く虹彩も黒っぽいのでノスリ成鳥やイヌワシ幼鳥・若鳥に見えてしまう方も、あるいは頭部が黒いので(虹彩は黄色ですが)クマタカ成鳥や Martial Eagle(アフリカに住むゴマバラワシ)成鳥に見えてしまう人もいらっしゃるのでは……。
実は「マーリン通信」の「コチョウゲンボウ」フォルダーにある 2011年3月9日付けの記事 NO.156の「グスタフ・マーラーとコチョウゲンボウ」でも、マーラーの顔とコチョウゲンボウがどうしても結びついてしまうというようなことを書きました。あの時は2者の共通点がはっきりと分かりましたが、今回、ハヤブサ類ということだけは理由が明白ですが、なぜそれが他の種ではなくコチョウゲンボウであるかということは私自身でも不明です。
さて、ポットをずっと見続ければこの現象はそのうち消えるか否定されるだろうと思っていましたが、見れば見るほど頭に焼き付いてきます。こういう類いの錯覚はシミュラクラ Simulacra 現象(類像現象)といって、ふだんよく見たり聞いたりしているものを、そこに存在していなくても思い浮かべるパレイドリア Pareidolia 現象というものの一つだそうです。ネット上にはこの種の画像が実にたくさん載っています。
ここで問題になるのは、何に見えるかということでしょう。自然に模様の付いた、あるいはありふれた傷の付いた同じカボチャを3人が見ても、一人はそれがかわいい孫の顔に見え、犬好きなもう一人には愛犬の顔に見え、昔、悪いことをしてしまった一人にはただのカボチャさえも昔の悪行(悪業)を思い起こさせるものになってしまうとか……、いろいろでしょう。ポットがハヤブサ類に見えてしまうとは、いささか鷹隼類の見過ぎかもしれません。
話が少しずれますが、これに関連して、画像を見る時に気を付けるべきことがあります。それは、ただ一枚の画像を見ただけで、すべてを判断してしまってはいけないということです。それがあまり精細な画像でないときはなおさらですし、逆に精細であるがゆえにだまされてしまう(間違った判断を正しいものだと思い込んでしまう)こともあります。遠くの木の枝にとまるオオタカ成鳥の正面の写真を1枚見て、この頭の大きさからすると絶対に♀だろうと思っても、横からの画像を見ると明らかに♂だったということはよく経験します。やはり、動く実物を見るか、画像なら違った角度のものを何枚か見ないと雌雄判断を見誤ることがあります。
タカ類の背中の色や風切の色についても、光線の角度で明るく見えたり黒っぽく見えたり、場合によっては一部分だけがあたかも新羽のようで他の羽は旧羽のように見えてしまうことがあります。やはり多くの場合、一枚の写真だけからの判断は危険!です。
(Uploaded on 2 April 2019)
2019年1月、愛知県内の農耕地4地点(下記のA~D地点)へ鷹隼類を見に行きました。4か所は比較的近いところにあります。干拓地や農耕地はどこも見晴らしのきくところが多いので、音もなく近づくタカ類や遠くを飛んでいるハヤブサ類、遠くの枝にとまっている鷹隼類を四六時中緊張して張り詰めたまま長時間一人で探し続けると疲れますので、タイトルのように鷹隼類以外の他の鳥に探してもらうとかなり楽です。
地点A(川の脇の農耕地)
この地点は以前この通信でも書いた地点で、グーグルMAPを見ていて「これはよさそうなところだな」と思ったところです。朝8:30ごろから観察を開始し、車の中に座ったまま農耕地にいるドバト20羽やハシボソガラス55羽の群れ、ムクドリ、カワラヒワ、スズメなどの小鳥の小群をぼんやりと見ていました。すると、距離がやや遠かったのですが、ムクドリ十数羽が通常よりも速いスピードで少し慌てたように斜め右上方に引っ張られるような変な飛び方をしていました。どうしたのかなと思ってムクドリの後方に目をやったら、民家の陰でそれまで見えていなかったオオタカ成鳥が見えてきました。このオオタカは強く羽ばたいてムクドリの群れを追いかけていました。すぐに、オオタカもムクドリも雑木林の上を越えて向こうへ行ってしまいました。
地点B(川の脇の農耕地)
次に行った地点の近くにある電線にスズメ約100羽、ムクドリ6羽がいましたので、しばらくこの群れに張り付くことにしました。すると、すべての小鳥が突然一斉に下の耕地へ降りたので周りを見回すように探すと北西方向からハイタカが接近中でした。かなり長い距離を低く滑空のまま飛んで、私の近くを通過し、東のほうにある社寺林に入っていきました。もしもスズメ等がいなかったら誰も(私も)ハイタカには気が付かなかっただろうと思われるほどの低い高度での滑空飛行でした。
地点C(林縁部にため池のあるところ)
次にため池の近くへ移動しました。しばらくホシハジロやキンクロハジロ等を見ていましたら、キジバトがしきりに飛んでヒヨドリが急に大声で鳴き騒ぎ始めました。何か来たかなと思ってあたりを注意していたらオオタカが「ピォー」と鳴きました。姿は現しませんでした。小さな池でいかにもオオタカがとまりやすいような大きな樹木やとまりやすい枝が池の周りにあるので、「これではオオタカに狙われたら逃げようがないな」と思いました。
そのころオオタカの声が聞こえてきた方向とは反対側の400~500mほど遠くの方でハシブトガラスらしきカラスが妙な飛び方をしました。短い急降下をして木の枝にとまります。また飛んで少し降下してまた木の枝にとまりました。よく分からなかったですが、きっとあの辺りの枝にも別のオオタカがとまっているだろうと思い、プロミナーで見たらノスリが向こう向きでとまっていました。私が予想したオオタカではなかったですが、カラスが変な飛び方をしなかったらこのノスリには気が付かなかったほど遠い距離でした。カラスはやはりタカ類の観察にはありがたい(私にとって好都合な)存在です。
地点D(農耕地の真ん中)
ふだんの私はあまり地点移動はせず、同じところで比較的長時間待っていることが多いのですが、この日はここで、はや4地点目です。休憩を兼ねて30分ほど車内で待っていたら、オオタカ成鳥が南のほうで旋回上昇しはじめ、かなり上がったところで急に北西方向へ急降下しました。私のいた地点へ向かってきたので雌雄成幼の識別で使っていた双眼鏡を車の助手席に置いてカメラに持ち換えようとしましたが、そのわずかな間にオオタカの姿を見失ってしまいました。オオタカはどこへ行ってしまったのでしょうか。すぐにハシブトガラス1羽(この時はたった1羽だけ)が来て近くの3階建ての建物の屋上で頭を激しく動かしながら大声で鳴き騒ぎ始めました。私もカラスが体を向けている方へ見に行こうとしましたが、民家が密集している地域だったので(民家周りでうろうろするのはよくないと思って)オオタカに近づくことはやめました。こんな短時間で見失うとは、ちょっと鈍くさかったです。
さらに30分ほど後、車の真ん前の田(地上)にいたムクドリ6羽、ハクセキレイ4羽、カワラヒワ2羽が慌てたように飛び立ったので周りを探しましたが、どこにも何も見当たらなかったです。「これは紛らわしい行動だな~」と思いながらも念のために車から出て上空を見たら、車の真上のかなり低いところにチョウゲンボウがいました。どんくさい話ですね! なんとか下の写真を撮りましたがすぐに遠くのほうへ行ってしまいました。車内から観察したほうがタカ類に警戒心を与えないのでよいのですが、車の中からの観察はやはり視界がよくないですから、こういう不審に思った時は可能であれば車から降りて死角になっている上空を見るべきですね。

この文章は、冬のある日の午前8:30~12:00の農耕地でのタカ観察について書いたものですが、基本的には繁殖期、越冬期、渡り期、ハンティング時などを問わず、また、広大な干拓地かうっそうと茂る森林内かなどの環境を問わず、鷹隼類以外の鳥類にタカ類・ハヤブサ類を探してもらうことが可能です。
(Uploaded on 1 March 2019)
「鷹隼類のハンティングシーンを見るには」というテーマで第1回は(1)~(11)、第2回は(12)、第3回は(13)~(14)を書きました。今回はその最終回の(15)です。
(15)気配を感じ、さまざまな変化に気を付けよう!
一番分かりやすいのは、ハシブトガラスでしょう。オオタカが出現すると、多くの場合ハシブトガラスがちょっかいをかけるようにモビングしてきます。オオタカがハンティングに成功し地上に降りたら、カラスがすぐに集まって上空で輪を描いたり鳴き騒いだりします。巣のある林の方向へ食料運びをしている時も鳴き叫びながらまとわりついてきます。これ以外の場合もしょっちゅうカラスは騒ぎます。逆に、ハシブトガラスがオオタカの巣の上空近くを飛ぶと、オオタカが排除するために飛び出すことも頻繁にあります。いずれにしても、タカ観察に関してハシブトガラスは注目度「大」です。ハシボソガラスもブトに準じます。

ハシブトガラスの他に気を付けるべきは、ヒヨドリ、ムクドリ、モズなどをはじめとしたさまざまな小鳥類あるいはその他の鳥類です。タカ類が近くにいると、いつもとは違う声で鳴くことが多いです。たとえば、ある時は大きな声で力を入れて声を伸ばしたり、短い声で激しく鳴いたり、音程がいつもと違ったりします。鳥種によって異なりますので一概にどういう声だとは書きにくいですが、少なくとも「ふだんとは違う鳴き方」、「何かを警戒しているような激しい鳴き方」「力の入っている鳴き方」ということが言えます。こういうふだんとは異なる鳴き声をする鳥に気が付いたら、近くにタカ類がいる、あるいは近くで仲間の鳥が捕獲された直後だというようなことが多いです。
でも、カラスや小鳥類に頼りすぎると失敗することもあります。オオタカ♀が抱卵中の時期、♂がハンティングに成功しました。ある程度自分で食べた後はきっと♀に残りを持っていくだろうと思い、巣のある林の近くで♀への食料運びを待つことにしました。ここの営巣林内に獲物を持って入る時はこのヒノキとあのヒノキの間から低い高度で入ることが多いということは分かっていました。獲物を捕ってもたいていはすぐには運んでこなくて、例えば20分後とか、60分後とかでこれも決まっているわけではありません。♂自身の空腹度や、巣でヒナが孵っているかどうか、♀だけに持っていくのかヒナにも持っていくのか、ヒナの大きさなど、さまざまな条件で異なってきます。したがって、いつでも「そろそろ来るか、いつ来るか、まだ来ない、自分で食べちゃったのか……」と思いながら長時間神経を使いながら集中して待つことになり、なかなかたいへんです。そうこうするうちに、疲れから思考が変わってしまい、「重そうに食料を運んでくればきっと何羽かのカラスが激しく鳴いて教えてくれるだろう。いや、教えてくれるはずだ」と思うようになりました。ところがその日、オオタカは何の音もなく、カラスもヒヨドリも鳴かずにそっと静かに食料を持って、私の目の前20mほどの所をスーッと入っていきました。もう2秒早く気が付けばうまくいったのですが、遅かったのでカメラを向ける時間的余裕もなく、じっくり見る心の準備もしていないうちに通過しました。肉眼で食料が見えたことだけでもよかったのですが、こういう思った通りにならないことはよくあります。いつでもカラスや小鳥類の気配が必ずあるとは限らないです。
次はタカ類の飛び方と行動の変化です。これは書くことが難しいですが、タカの飛び方をよく見ていると「いつもとはちょっと違うな」と分かるようになってきます。大事なことは疑問を持って、一つ一つの行動の理由を考えることです。例えば、ゆっくり飛んでいたタカが急に激しく羽ばたき始め猛スピードで飛んでいったら、誰でも「なぜ?」と思うでしょう。同じように、急に旋回上昇を始めた、急降下した、急旋回した、ぐるっと大きく向きを変えた、オオタカのようなあまりホバリングしないタカ類がホバリングを始めた、飛行中大きな声で鳴き始めた、というような注目すべき変化は書き切れないほどいくらでもあります。「なんだかおかしい!」と感じることが大事で、そういう時はたぶん何かが起こる時です。そして、それぞれの行動にはすべて理由があります。
4回にわたって15項目の注意点を書いてきました。これらすべてを満たさなくてもタカ類・ハヤブサ類のハンティングの瞬間を見ることは可能です。
下の4枚の画像はハヤブサ♀成鳥のハンティングのようすです。すべて同一個体です。1枚目は背面飛行の瞬間ですが、狩りの最中に背面飛行をする頻度はけっこう高いです。2、3枚目はハンティングの瞬間を秒10コマで連写した画像を並べたものです。4枚目は獲物を捕らえた直後、ほんの何秒も経たないうち(1、2秒後か?)に首の骨を折っている瞬間です。狩りの瞬間はそれぞれの鷹隼類の持つ最も優れた飛行能力をフル稼働させて飛行するわけですから、アクロバティックな見事な飛行シーンが多く見られます。撮影ができなくても、ハンティングの瞬間を見るだけで胸がすく思いがします。




(Uploaded on 16 May 2018)
「鷹隼類のハンティングシーンを見るには」というテーマで第1回は(1)~(11)、第2回は(12)を書きました。今回は第3回目で、「視線」についての2点です。
(13)タカと視線を合わせないようにする
鷹隼類が目の前に現れた、あるいは見ていたタカがハンティングしそうな状況になってきたとします。
タカ類・ハヤブサ類には非常に警戒心の強いものからややのんびりしたものまでさまざまな種がいます。さらに同じ種でも個体差があって、警戒心が強い個体や人をあまり警戒しない個体がいます。また、いつも観察の状況や環境は異なりますし、タカとの距離も常に異なります。双眼鏡で見続けていてもカメラで連写していても、目の前でごく普通にハンティングする時もありますから一概には言えませんが、警戒心の強いタカを相手にする時には一般的にいうと次のようにした方が無難です。
・双眼鏡で見続けることをやめる。プロミナーでじっくり見ることももちろんやめる。
・車の中にそっと入るか、樹木の陰にゆっくりと静かに隠れる。
・隠れるものがないような堤防の上では、壁の陰に入るか少なくとも身をかがめて観察する。手足の動きを見せないようにする。
・タカを注視しすぎることをやめる。ようすを見ながら、「見続ける」ことを控える。注視しなくても、慣れてくるとそれなりに見ることができます。
・カメラで高速連写をしすぎないようにする。
昔話で出てくる「種まき権兵衛さん」のようなふうになると良いです。以前からこの通信に何回も書いたような気がしますが、タカの巣から50mとか100mしか離れていないところで備中鍬で農作業している人には全然警戒しないのに、もっと離れたところからスコープで巣の方向を注視し続ける人にはひどく警戒するというようなことがよくあります。
(14)タカの視線に気を付けよう
ふだんからタカの視線に注意しておく必要があります。鷹隼類が飛んでいるとします。双眼鏡で見て、彼らの視線はどこを向いているのか常に気を付けるようにします。下のような観察者をギュッとにらむような写真を撮っていたり、こうさせるような観察をしていては、失敗です。

私が今、キヤノンの14倍の防振双眼鏡(Canon 14×32 IS)を使っている理由はタカ類の視線を認識できることが多いからです。双眼鏡の機動性を利用しながら、ほとんど双眼プロミナーの代わりができるほど性能が優れているということです。願わくば、20×50あるいは20×42くらいの口径の防振双眼鏡が欲しいです。
タカの視線を見ると、いろんなことが判断できます。視線といっても、いつでも瞳などの目の動きが見えるほど近くはなかなか飛ばないですし、近くても急な飛行をしていると瞳の向きまでは見えないことが多いです。しかし、目がはっきり見えない時でも頭をどちらに向けているかは分かると思います。左右をキョロキョロしているかいないか(獲物探索中か、他のタカが気になっているか)とか、じっと前を見据えたままで飛んでいる(目的地に向かってひたすら飛んでいる)か、下ばかりを見ながら(獲物を探索するように)飛んでいるか、観察者であるあなたの方を気にしながら(警戒して)飛んでいるかなどに気を使って観察します。慣れてくると、突然出現したオオタカやハヤブサでもどちらを向いて何を見ながら飛んでいるのか、どんな目的で飛んでいるのかがだんだんと分かるようになってきます。
練習として、ゆっくり飛んでいるトビやノスリを今まで以上にじっくりと見てみるのもよいでしょう。頭の動きをじっと見ていると、左右にキョロキョロしたり前と下を交互に見たりしていることがよく分かります。飛んでいたトビがこのような頭の動きをした後に、杉の木のてっぺん近くのカマキリ類を捕らえたりしています。頭を動かすということはつまり視線の先を変えながらじっくりと見ていたということです。
視線が分かるようになると、次の動きが予測できる場合が多くなります。いつでもこちらが予想したとおりにタカ類・ハヤブサ類が行動するわけではないですが、それなりに当たることがあります。
(Uploaded on 1 May 2018)
「鷹隼類のハンティングシーンを見るには」というテーマで前回(1)~(11)までを箇条書きで書きました。その続きの(12)~(15)を一回で同じように書こうと思いながら文章にし始めましたが、箇条書きでは微妙なことがうまく伝わるように書けなかったので、今回は日記風に書くことにしました。続きの(12)からです。
(12)獲物となる生き物の近くでハンティングを待とう!
2018年3月7日のことです。前夜、グーグルで航空写真を見ながら、「どこかに越冬ハイタカの観察によさそうな地点はないだろうか…」と思案していました。そして、行き着いたのが、ある川の近くの農耕地でした。ただ、そこにハイタカの獲物となる小鳥類がいるかいないかは実際に現地へ行ってみないと分からないことなので、「明日はあのあたりへ行こう」という程度にしておいて、現地に着いてから細かな観察位置などは決めることにして床につきました。
翌日、私としてはかなり遅い時刻の8時25分に家を出ました。川の近くのどの辺りでタカを見ようかと考えながら上流に向かって車を走らせていたら、あるところで電線にドバト10羽(後に25羽)とカワラヒワ40羽くらいがとまっていて、近くに果樹園がありましたので、ここならハンティングだけでなくタカ類のとまりも期待できると思い、「よし、今日はここにしよう!」と決めました。今まで一度も走ったことのない道、行ったこともない所でした。太陽を背に車をとめたのは9時ちょうどでした。
小鳥はカワラヒワの他に、ムクドリ10、スズメ20、ハクセキレイ、キジバト、ツグミなどがいました。
(9時30分)
電線にとまっていたドバトが一斉に飛び立ちました。車の後方を見るとオオタカ幼鳥が飛んでいました。小ぶりだったのでたぶん♂でしょう。ハトの群れに突っ込むようにハトと一緒に飛びましたが、どんどん右手奥方向へ飛んでいってすぐに後ろ姿になりました。そのまま一直線に飛去して、以後このオオタカは現れませんでした。
(9時40分)
田で食料を食べていたカワラヒワやスズメが慌てて飛び立ったので車の後ろを見たらハイタカ幼鳥が低空を飛んで近づいて来ました。カワラヒワ20羽ほどの群れを狙いましたが、捕れませんでした。ハイタカは未練があるようにゆっくりと旋回上昇しました。車の後ろ方向を飛んだので、車から降りようかどうしようか迷っているうちに高度を上げました。車から降りて写真を撮りましたが、ピントが十分ではないものの、頭の大きさと胸の斑から♂の幼鳥と推定しました。
車の後方からの接近が2回も続いたので、車の向きを変えようかとも思いましたが、こちら向きだからかえってよく突っ込んだのかもしれないので、そのままの向きで続けました。しかし、車の中にいては後ろからの接近に対応できないので、短時間なら……と思い、車外へ出ました。すると2分後に、
(9時52分)
ハイタカ♂成鳥が、激しくチチッと鳴くハクセキレイを追って果樹園から田の方へ、まさに至近距離で私の目の前を通過しました。私との距離は約10mで、ハイタカとハクセキレイの距離は最短時に約1m、地上からの高さは初め2mくらいでした。タカ類がこんなに頻繁に出現するとは予想してなかったのでカメラと双眼鏡を車の中に入れたままで外に立っていましたが、それがよかったのかもしれません。肉眼でもすぐに♂成鳥と分かるような近さでした。ハクセキレイは田の上で右方向へ急旋回しハイタカをうまく交わし、ハイタカはすぐに田の上の低いところを旋回し始めました。先のハイタカ幼鳥と同じように、(人間的な思考かもしれませんが…)捕れなかった獲物に未練があるかのような低空での旋回飛行でした。肉眼で下面のきれいなオレンジ色を楽しんだ後、カメラを出して旋回上昇中の姿を撮影しました。風切がすべてそろった美しい♂成鳥と思われる個体でした。

その後は1時間あまり何も出現しませんでした。出ないことがむしろ一般的ですので、「これが普通だ…」と思いながら、午後に用事があるから早めに帰ろうかと思って運転席でレンズをブロワーでシュッシュッとやり出したら……
(10時53分)
車のフロントガラスの正面から力強く羽ばたいて近づくハヤブサ類が見えました。真正面からの接近でシルエットが分かりにくくてしかも力強い羽ばたきだったので、最初はハヤブサだろうと思いました。一直線にこちらに向かってきます。よく見るとチョウゲンボウ♂成鳥でした。すぐに車から降りて撮ったのが下の画像です。私のすぐ近くを通過して、電柱にとまりました。とまる直前に10羽くらいのスズメがパラパラッと左右に飛び散りましたが、ハンティングしようと思っていたのかびっくりしたスズメが避けただけだったのかどちらかよく分からなかったです。

連続してのきれいな♂成鳥2種2個体はうれしかったです。
タカ類のハンティングを見るには、ある程度獲物がいるところで待つのがよいです。小鳥の群れがいてもハイタカやコチョウゲンボウがその群れに突っ込むとは限りませんし、雨降りの後で土手や畔にカエル類が多くいてもサシバは飛びつかないかもしれませんが、でも、初めから可能性がないと思ってしまうと何も見られません。
(Uploaded on 15 April 2018)
私は一年中、タカ類・ハヤブサ類を中心に見ていますが、出かけた日はほぼ毎回(毎日)のように鷹隼類の獲物探索・待ち・ハンティング・食料運びなど、何かしらの狩りに関するシーンを見ています。ここの「待ち」という言葉は私が勝手に作って使っている言葉なのであまり聞き慣れないと思いますが、鉄塔の上からあるいは飛翔しながらの探索中に見つけた獲物が捕らえやすい場所へ出てくるまで、あるいは捕らえやすい状況が生まれるまでしばらくの間監視しながらようすを見る、つまり鷹隼類がハンティングをスタートさせるまで「待つ」時間のことです。
ハイタカの狩りを見に行ったけれどハヤブサの狩りしか見られなかったとか、オオタカを見に行ったけれどもハイタカの狩りしか見えなかったということはよくあります。もちろん、サシバがカエル類を水田の畔で捕っただけとか、カナヘビを土手の上で捕っただけとか、ハチクマが食料を運んできたところしか見られなかったという日もあります。
これらを含めて、また「獲物探索」だけとか「待ち」だけとか、失敗した狩りも含めて、ほぼ毎回何かしらの狩りに関することを見ています。

私のふだんのタカ類・ハヤブサ類の観察方法を書いてみます。鷹隼類のハンティングを見るためのヒントになれば幸いです。主に愛知県での観察で、対象は小形~中形の猛禽類です。
(1) 夜明け前までには現着できるように朝早くに家を出る。日の出時刻が早い夏は守れないこともありますが、真冬の厳寒期でも、氷点下の朝でも、自宅から遠方の地点でも、ほとんどは夜明け前の現地到着です。
(2) 今日はここ、と決めた地点にできるだけ長く、できれば5時間は立ち続ける。繁殖期で悪影響が出る可能性のある時期は巣から十分な距離をとるとか、観察時間を短くするなどの注意をします。
(3) 朝から鷹隼類が一羽も出現しなくても、少なくとも2~3時間は同じ地点で粘ってみないと、ほんとうにそこにいないのか出現がないだけなのかは分からない。
(4) 鷹隼類はいつ出現するか分からないので、用足しや水分補給する時でも耳と目は気を抜かない。
(5) 朝早くの観察をしない時でも、夕方はよいことが起こるチャンスが多いので、夕方日が暮れる頃をねらってみる。
(6) 観察中にカメラの画像はできるだけチェックしない。鷹隼類は1羽が出た直後に連続して出現することが多いので、今撮ったばかりの画像をチェックし始める頃にちょうど次の別のタカ類が出ることが多いです。チェックするのは露出のオーバーかアンダーのみで短時間にする。
(7) 小鳥の群れが飛び立ったり急いで何らかの行動を起こした時は小鳥の群れを目で追わず、小鳥の後ろに注目する。タカ類が接近してきたり、追いかけていることが多いです。
(8) 他の人の情報に惑わされず、できるだけ観察ポイントは自分で納得のいく場所を自分で探す。
(9) 有名探鳥地はそれなりの良さがあるが、人が多いと自然な状態で狩りをすることが少なくなる。誰もいないところ、多くても2~3人までのほうがハンティングはよく見られることが私の経験上は多い。
(10) タカ類が出現しなくても、「きっとここにいるはずだ。出ないはずがない」と思う。
(11) 何か出た時に「キジバトだろう」、「カラスだろう」と思わずに、キジバトではなくハイタカかも…、カラスではなくサシバかも… と可能性のある鷹隼類を想定して、即対応する。
いくつかの項目には細かなコツがありますが、今までの「マーリン通信」の文章の中にそれとなく書いてきました。全部を守らなければハンティングが見られないわけではないですが、初歩的なことばかりですので、いくつかを実践すれば狩りを見ることができるはずです。
この記事の続きの(12)~(15)は次回に書く予定です。
--------------------- (以下、余談です)
上の11点はけっこうハードですので、体調には十分に気を付けてください。気温が氷点下の厳寒期に自宅から数十kmも離れたところへ週3回くらい、しかも夜明け前に現着して強風にさらされて立っていることはそれだけでけっこう疲れるものです。「そんなにハードな鳥見をしている人はあまりいないぞー」とよく言われます。
ある日、患者さんの数が少なくて暇そうだった年配の医師に上に書いた(1)~(4)の話をしていたら、こんなことを言われ、脅されました。
〇 そんなことをしていたら、(仮に)若くても自律神経のバランスを崩しやすいよ。
〇 腰痛とか首痛、目の感染症などになりやすいよ。
〇 行き帰りの交通事故に気を付けてくださいよ… 。
私も自分の歳のことを十分に考えないといけないことが最近身にしみてきました。無理はいけないですね。
(Uploaded on 1 April 2018)
私が野鳥の会に入った頃は、かなり安価な600mmF8というレンズを出たばかりのNikon FMに付けて使っていましたが、やはり画質は悪かったです。「安かろう悪かろう」でした。
1980年代に入った頃、50万円ほど出して、フォーカシングユニット付きではなくなった AI Nikkor ED 600mmF5.6S(IF)を買いました。これは良いレンズで実にシャープでした。重さ2.8kgで、Canonの旧型 EF600mm F4L IS USMの5.36kgと比べればちょうど半分ほどの重さしかなかったのですが、けもの道を歩き、薮こぎをし、斜面を登ることの多かった私にはやはり重かったです。そんなわけで2年ほど使って知人に譲りました。
その後は、Canon400mmF5.6などの短い単焦点レンズを使い続けました。Kodachrome64というISO感度64(当時ASA64)のスライドフィルムを使っていましたので、なにを撮影するにもけっこう苦労していました。もともと写真集を出すつもりはなかったので、無理せずにASA200か400のネガフィルムを使えばよかったですが、当時はほとんどの人がKodachrome64を使っていましたので、しっかり考えずに私もそれにならっていました。
デジタルの時代になって私でもきれいな写真が撮れるようになったので、一本くらい大きいレンズがあってもよいと思うようになり、100万円以上出して Canon EF600mmF4L IS Ⅱ USMを購入しました。使ってみたら、確かにイヌワシやクマタカ、シギ・チドリ類を撮るにはこれは最適のレンズでした。
ところが、このレンズは俊敏な飛行をする鷹隼類の撮影にはあまり向いていませんでした。私は小~中形のタカ類・ハヤブサ類を中心に観察しています。ハイタカ属のハイタカやオオタカ、ハヤブサ類が多いですが、これらはいずれも動きが素早く飛翔スピードもかなり速い時が多いです。突然出現することが多いので、レンズを瞬時に持つ必要があります。近くに来た時は角速度が急激に増大するので、レンズを激しく動かしたり、振り回したりしながら撮ることが自然と多くなります。やはり小回りがきいて、軽く、しかもシャープに撮れるレンズが好都合です。最近はほとんどの場合 Canon EF100-400mmF4.5-5.6L IS Ⅱ USM を使っています。条件にもよりますが、ロクヨンよりも良い写真が撮れることがあります。
今、「マーリン通信」の表紙に使っているチョウゲンボウの画像はこのレンズで撮ったものです。先月まで表紙に使っていたハイタカの画像や下のツミもこの100-400mmレンズで撮ったものです。私は野鳥カメラマンではないですし、プロでもないので、この程度撮れればもう十分に満足です。

もし600mmや800mmを使うとしても、三脚に据えて撮るよりは手持ちでの撮影の方がお薦めです。練習を積んだり、場数を踏んで上達してくれば三脚での撮影ができないことはないですが、小鷹の撮影の場合はやはり手持ちのほうがよく撮れます。
小さいレンズを使うようになってから他にも良いことがありました。タカ類だけではなく、他の鳥類も今までより逃げなくなりました。64は太くて大きな三脚と直径15cmもある大きくて光るガラスレンズで威圧感があるようで、鳥が驚いて逃げることがよくありましたが、今は三脚を使わないし、車の中から撮る時は窓を必要なだけ開けてレンズを窓の外にあまり出さずに車内から撮っていますから、威圧感はかなり小さいはずです。鳥は64ほどは逃げなくなりました。水田に入っていたヒバリシギもウズラシギも全然逃げません。少し待っていたら逆に近づいてきました。全くの偶然ですが、東海地方ではかなり珍しいクロツラヘラサギ成鳥夏羽をある干潟で700mほど先で見つけました。その後飛び立ったクロツラヘラサギはどんどんこちらに近づいてきて私の頭の上低いところを飛んで南へ飛去しました。もし大きい三脚と光り輝く前玉があったらたぶんそんなには近づいてこなかったような気がします(推測)。
サシバの群れの写真を撮っていた時に、縦に長い鷹柱ができたので、すぐにレンズを広角側にして鷹柱全体の写真を撮ることもできました。
さらに、このサイズですと大きな三脚もいらないし軽いので、飛行機に乗る時でも簡単に持ち運びができて、すごく楽です。
露出や構図、ホワイトバランスなどは後からある程度修正できますが、技術が進んでも、いまだにピントだけは後からでは手の施しようがありません。ですからピントには気を遣いますが、でもピントは実質的にはオートフォーカスでカメラ任せですので、真っ黒すぎず白飛びしない程度に適正露出のことだけを考えていれば、だいたいはよさそうです。写真集を出すこともないし、写真を販売する気もないので、まあ、小さい機材のほうが私にはいいかな……と思っています。
(Uploaded on 1 August 2017)
8月11日付の記事、「このチュウヒの初列風切の状態は?」の解説で、P4は欠損(欠落)と書いたところ、なぜ欠落していることが分かるのか?…という質問を複数いただきました。
まず、下の2枚の写真をご覧ください。一枚目がタカ目の鳥の例としてチュウヒを、二枚目はハヤブサ目の鳥の例としてハヤブサを挙げてみました。


いずれも十分に、いっぱいに羽を広げた時でないと確認しづらいのですが、初列風切の羽軸の向いている方向と次列風切の羽軸の向いている方向に微妙な違いがあることが分かります。次列風切は尺骨(人間でいうと腕時計の位置~肘までにある2本の骨のうちの1本)から生えていますが、初列風切は尺骨よりも先のほう、人間でいうと「てのひら」にあたる部分の骨から生えていますから、手首を少し動かすだけで初列風切と次列風切のお互いの向きは大きく変わってきます。2枚の写真のように力強く羽を広げた時は、隣接した初列風切と次列風切の羽軸の方向が明確に異なります。
(注意)
あくまでもその傾向にあるということで、翼の開きぐあいによっては判別しづらいことが多いです。一枚だけの写真から判断せずに、力いっぱい翼を開いた複数枚の写真、あるいは同じ個体で時期を変えての写真などを見ながら、常に慎重に判断する必要があります。
(Uploaded on 24 September 2016)
下の写真はチュウヒの♂成鳥です。繁殖個体で、愛知県で7月に撮影したものです。換羽のようすや欠損等の状態がよく分かります。
では、質問です。
このチュウヒの左翼初列風切はどういう状態になっているのでしょうか?
(解説は写真の下の方にあります)

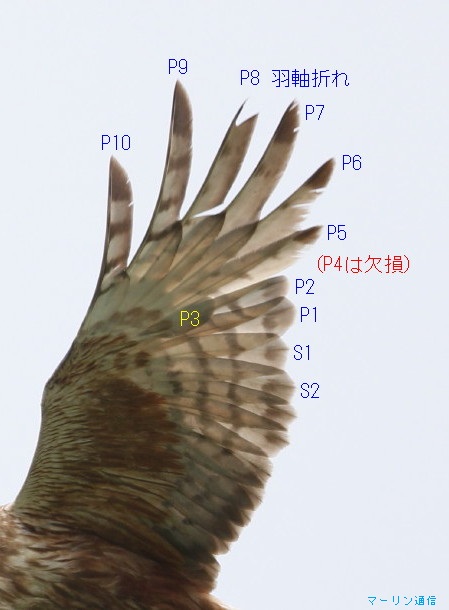
P1, P2は新羽、P3は伸長中、P4は欠落。P5~P10は旧羽か。
(Uploaded on 11 August 2016)
2014年5月1日付けの記事「鷹隼類観察の上達法(5) そんなはずがある!」の続編です。
ウミスズメ
1978年(昭和53年) 2月7日の朝、愛知県尾張旭市でのことです。私の自宅近くの中学生が、「こんな鳥を側溝で拾ったよ」と届けてくれました。見るとそれはウミスズメで、まだ生きていました。当地から海に一番近いところは名古屋市の堀川河口(伊勢湾)ですが、それでも約20kmあります。三河湾の一番近いところは衣浦港で、約40kmあります。一瞬びっくりしましたが、翼のある生きものですので、どこに現れても不思議ではありません。私たちが気づかなかったり識別できなかったりするだけで、実際は多くの海鳥が陸地の上空を飛んだり、山を越えたりしていることでしょう。もちろん海鳥が陸地やため池に降りることはかなり稀でしょうが、可能性ゼロではないです。
グンカンドリ
デジカメのないころの話です。ある人が山の中を歩いていてグンカンドリを見ました。他の人に言ってもなかなか信じてもらえなかったそうです。「オオ」か「コ」かはともかく、あの独特なシルエットは誰もまちがえようのないものですが…。観察者がふだん周りの人にどれだけ信用されているかの目安にもなりますね。私も海からかなり離れた山の中でシロハラトウゾクカモメを見たことがありますが、識別できる程度ではありましたが、証拠写真を撮っておいてよかったです。
コチョウゲンボウ
冬のある日のある山の中。ハイタカを観察中にハイタカが同時に3羽現れて、さかんに舞っていました。その時、双眼鏡でないと分からないほど遠くにぽつんとハヤブサ類が一羽見えました。「コチョウゲンボウの♂成鳥だ!」と私。すると、「オイ、オイ、ここは干拓地じゃないぞ」との声。幸いなことにその鳥は私たちの方へ飛んできて、近くの電線にとまりました。きれいな写真が撮れるほどの距離ではないのですが、比較的近い方でした。私はほっとしました。近くにとまったので、やれやれでした。近くに来なかったら誰にも信じてもらえなかったであろうと思ったからです。あとで、「若杉さんと鳥を見に来ると、いつも良いものが見られるね。ありがとう」と。そんなことはまったくないので、お世辞でしょうが…。
鷹渡りポイント
約44年前の1972年10月8日に、「伊良湖岬の鷹渡り」を発見したのは緒方清人さんです。江戸時代から「いらご鷹」は文献にも出ていて、ある意味有名でしたが、これは渡りのタカではなく、鷹狩りで使うオオタカの話です。渡り途中のオオタカ幼鳥を無双網で捕獲する「鷹打場」(たかうちば)というものが伊良湖岬の伊良湖ビューホテルのすぐ近くの宮山に江戸時代はあったのです。もし「そんなにたくさんのタカが渡るはずがない!」と決めつけていたら、つまり先入観があったらこんな大きな発見はできなかったことでしょう。
(Uploaded on 2 April 2016)
画像の整理法にはいろいろなやり方があるようです。人それぞれにやりやすい方法があって、どれがベストかは分かりません。ここでは、2015年の現時点で私のやっている方法を紹介します。PCやその他いろいろな環境が変わってくれば、当然、整理法も変わってきます。
1 データはDドライブに入れる
さまざまなアプリで作ったデータは、アプリのいいなりで保存すると一般的にはアプリソフトやウィンドウズソフトの入っているCドライブに保存されてしまいます。しかし、Cドライブに保存するといろいろな不都合がありますので、文書や画像、動画、PDFファイルなどはすべてDドライブに保存します。
私は、自宅の近くに日立の工場があるという事情もあって、最初にHITACHI B16 というパソコンを使い始めました。その後、いろいろな機種(デスクトップPCは、DESKPOWER、VAIO、VALUESTAR、ノートPCは日立FLORA、ThinkPad、VAIO、ASUSなど)を使いましたが、これまでにディレクトリー等の故障が計3回ありました。その都度OSを入れ直しましたが、もしCドライブにデータを入れていたらすべてのデータが消えていました。今の時代でも、やはり、データはウィンドウズファイルが入っているドライブとは別の、Dドライブに入れておいた方がよいでしょう。
もちろん、外付けのハードディスクあるいはクラウド上にバックアップを取っておくことは必須です。できたら2つ以上は取っておくとよいでしょう。私は持ち運びを考えて小型のポータブル式ハードディスクを2台使っています。机上のPCとノートパソコンと2台の外付けハードディスクの計4つです。4つ同時に壊れることは考えにくいです。それでも心配だからといって、DVDに焼いたり、USB FLASH MEMORYに保存したりして、それを自宅の離れや職場に置いておく人もいます。「もし自宅が火事になったらハードディスクもフラッシュメモリーも全部一緒に焼けてしまうから困るだろう」と言う人もいました。私にはそれほど貴重な写真はありませんので、そこまでのことはしていません。
旅先で資料が簡単に見られるように、ネット上の某クラウドのサービスも利用しています。ネットにつなぐ時はWi-Fiのアクセスポイントも利用しますが、パスワード不要のアクセスポイントはいろいろな心配がありますので、iPhoneのテザリングをよく使います。
また、外出先で時々コンパクトフラッシュの読み込みが必要になるので、iPad等は私には使えません。ごく一般的なノートパソコンとiPhoneを使い、ノートパソコンにはいろいろな画像や資料を入れて、iPhoneには瞬時に見られるような画像をいくつか入れて、両方を使い分けています。
2 SDカードの画像データは選択してからパソコンに取り込む
SDカード等の画像データは一気にはパソコンに取り込みません。SDカードやコンパクトフラッシュをそのままパソコンに差し込んで、あるいはカードリーダーを介して、あるいはカメラ本体とUSBケーブルでつないで、画像等をパソコンにコピーせずに閲覧します。パソコンに保存すべき画像の番号をメモに控えて、必要な画像のみをパソコンの該当のサブフォルダあるいはその下層のフォルダに直接コピーします。コピーがすんだら、パソコンでSDカードのデータを消去します。ほんとうはカメラで初期化したほうがよいでしょうが、画像ファイルのみの消去ならPCでもかまいません。
カメラで撮影した画像や動画のデータを最初から一気にパソコンに取り込んで、それから仕分けや消去などの処理をする方法もありますが、そうしない方がよいでしょう。いまのウィンドウズはデフラグや最適化はすべて自動的に実施されますが、PCのハードディスクは不必要な(やらなくてもよい)読み書きをできる限り少なくした方がよいと思っています。
3 フォルダはタカ類・ハヤブサ類1種ごとに作る
私のDドライブには、仕事関係やプライベートの他に、鷹隼類では次の3つのフォルダがあります。
「鷹隼類 画像」 … 他の方が撮影したタカ類・ハヤブサ類の画像
「鷹隼類 若杉撮影」 … 自分で撮影したタカ類・ハヤブサ類の画像
「鷹隼類 研究資料」 … 論文のPDFファイルやさまざまな資料
それぞれのフォルダには国内産のタカ類・ハヤブサ類全種の1種ごとのサブフォルダを作ります。さらにそのサブフォルダには、「ツミ MA」「ツミ FA」「ツミ J」「ツミ 繁殖」などのフォルダが作ってあります。サシバの場合は「サシバ 暗色型」などといったフォルダーも作ります。3層よりもフォルダの階層を深くするとかえって煩わしくなりますので、これ以上は深く・細かくしないほうがよいですが、ハチクマのMA・FA・Jの下層に暗色型・中間型・淡色型フォルダをそれぞれ作ったりすることはよいでしょう。逆に、MAとFAが正確に区別しにくい種は例えばまとめて「ノスリ A」としたり、♀成鳥と幼鳥がよく似ている種はまとめて「コチョウゲンボウ 非MA」などとしてもよいでしょう。他に、必要に応じて、ヨーロッパハチクマや、プレーリーファルコン、ラガーファルコンのフォルダも作ります。
特殊事情ですが、私はこの40年間、鷹隼類しか追っていないですので、タカ類・ハヤブサ類の観察中に撮影した一般鳥は、「鳥類 若杉撮影」というフォルダの中に目ごとあるいは「~類」と分けて入れます。ですから、多くの人がやっていらっしゃるような鳥類1種ずつにすべてフォルダを作って保存するという、かなりたいへんなことはしていません。
4 ファイル名には日付も入れる
1枚1枚の画像の名前は、例えば「ハイタカ 151012伊良湖若杉」のように、種名、全角スペース、撮影年月日、場所、撮影者名をいれます。同じ画像名が複数枚ある時は、下の5のような一括処理で、「ハイタカ 151012伊良湖若杉 (2)」と、半角スペース、半角カッコ数字を付けます。
5 できることは一括処理をする
いちいち細かなファイル名を入力するのはめんどうだと言われますが、できる限りのことをまとめて省力化すれば、ぜんぜんたいへんではないです。多くの単語登録をしておくとか、シフトキーを多用する、種名以外の部分のファイル名はコピーペーストする、あるいは一括でファイル名を変更するとか、できる限り入力の手間を省いてできるだけ一括処理します。便利な方法はいろいろありますし、ファイル名を換えるソフトもあります。
6 写真の比較はデスクトップの分割スナップを利用する
Win7からだったと思いますが、画面の左と右にウィンドウを簡単に分割できるようになっています。今は横長のデスクトップが主流ですので、画面の左右に2つの画像を並べるとすごく比較しやすいです。例えば20枚連写した同じような写真の中から一番ピンが来ている写真を残そうという場合には、便利です。Win10からは4隅に4分割することが簡単になりましたが、このスナップ機能はたまにしか使っていないです。
7 原画像は残すか、処理あるいはトリミングした画像のみを残すか、RAW+JPEGで撮影するか
画像処理やトリミングした画像のみを保存しておいて、原画像は捨ててしまうという人と、両方残しておく人と、原画像のみを残しておく人がいるようです。私は、原画像のみを残しておきます。トリミングはその時々で気分によってやり方が違ってきますし、発表する時々でトリミングに対する要求が異なるからです。例えば、縦1:横8くらいの細長い写真が必要な時がありますが、原画像を捨ててしまうとそれができなくなってしまいます。データ量がやや多いですが、やはり原画像を残しておきたくなります。
RAW撮影をするかしないかについては、判断が難しいです。これは人それぞれでしょう。私の場合、
① 画像処理はめったにしない。処理したとしてもライティングを少しいじる程度のこと。するのはほとんどトリミングのみ。
② RAW画像をPCの画面に表示する時に時間がかかる。
③ RAW画像は一枚ごとのデータ量がかなり多い。
④ RAW+JPEGで撮影すると、カメラのバッテリーがすぐに減っていく。
⑤ JPEGのみならば、毎秒10コマの高速モードで何10枚を連写しても何の不都合もなく撮影できる。
という理由から、JPEGのみで撮っています。たいした写真を撮っているわけではないですので、JPEGの画像のみで私は十分です。
8 同じような写真をたくさん保存しない
撮影した直後は、「これは残そう、これも残そう」と似たような写真をたくさん、ついつい残してしまいますが、結局後で捨てることが多いです。私は、そんなにたくさん残す必要はないと思います。上の6で書いたような方法で姿勢の異なるベストな写真を必要な分だけ残せばよいでしょう。ある人が、「虹彩の色が分からないようなタカの写真はいらない」、「(オオタカの)瞳と虹彩の区別が付かない写真なんていらない」と言っていましたが、よほどの珍鳥や珍しい生態の写真でなければ、これはある意味当たっていると思います。
9 時々、PCの中を掃除する
撮影した時には残しておいたけれども、改めて今見てみると不要な写真は多いものです。あの時よりもよい写真が撮れたとか、レンズを買い換えたのでクリアーな写真が増えてきたとかいう理由で、昔の写真でいらないものが出てきます。学術的に意味があったり、何かの証拠になるとか、自分の思い出になるとか、なんらかの意味があればぜひとも残すべきですが、多くの場合、いらないものです。いらないものはすぐに捨てましょう。すっきりさせれば、フォルダーの中身の表示時間は短くなりますし、検索にかかる時間も短くなります。同じような検索結果がたくさん出てくると煩わしいものですが、それもなくなります。
上の1~9すべて、人それぞれのやりやすい方法でやれば、それが一番よいです。
(Uploaded on 1 December 2015)
400mmのレンズにAPS-Cのカメラを付けて手持ち撮影をしていた知人が、最近、「このレンズには手ブレ補正機能( IS = Image Stabilizer ) が付いてないので、けっこう手ブレ写真が多い。手ブレを防ぐために三脚を使うことにしたんだけど、今度は飛ぶ鳥がすぐに画面内に入らなくなった。入っても、しっかりと追い続けられなくて…」と言ってました。
手持ちでの撮影と三脚を使用しての撮影は、考え方というか頭の使い方が異なりますので、意識を変えないとうまくいきません。長い間、試行錯誤を繰り返しやってみて、飛ぶ鳥を何千枚も撮れば、そのうちコツが分かってきて、いつの間にか追えるようになるでしょうが、考え方(意識)を変えれば、短い時間でできるようになります。
考え方のポイントは、次の2点です。
1 中心(支点)の位置
2 撮影者の動き
詳しく説明します。まず、下の絵を見比べてください。
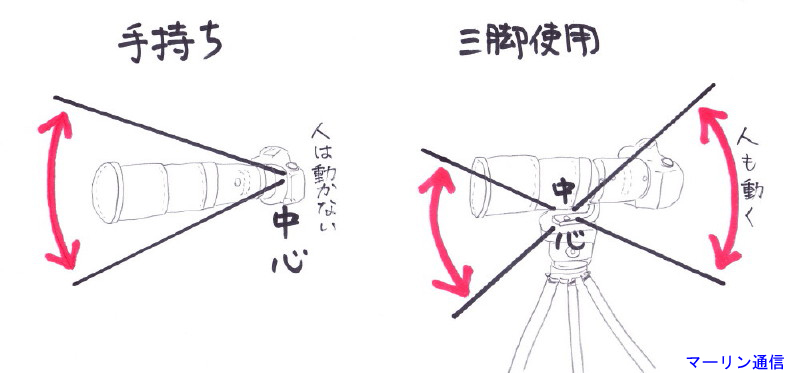
1 中心(支点)の位置を常に頭に入れる
手持ち撮影の場合は、カメラはほとんど動かず、レンズ全体を図の赤い矢印のように動かします。中心は、カメラの位置にあります。三脚使用の場合はレンズに付いている座金の位置が中心になります。レンズもカメラも矢印のように動きます。この「中心」の位置を常に意識する必要があります。
2 三脚使用の場合は、撮影者が小刻みに動く
手持ち撮影の場合、撮影者はカメラと一緒ですので、ほとんど動く必要がありません。これに対し、三脚使用の場合はカメラが動きますので、カメラと一緒に撮影者も右や左へ、上や下へと小刻みに動かなければなりません。具体的には、足を曲げたり伸ばしたり、左や右に体(重心)をずらしたりするという動きが必要になってきます。しかも、鳥が動く方向と真逆の方向へ体を動かす必要があります。
手持ち撮影の場合はレンズを支えるために両腕に力が必要です。重いレンズの手持ち撮影では、腰の力もかなり必要です。こんな時は椅子に座って撮影するほうがよいです。三脚使用の場合は、体を小刻みに動かすため、両足の力と斜めの体を支えるために腰の力が必要です。
-------
どちらの場合も右手人差し指はシャッターボタンにいって、右手全体でカメラを支えたり動かしたりしますが、左手は異なります。手持ち撮影の場合は、左手はレンズの重心より少し先の前玉近くに置くのが良いでしょう。一方、三脚使用の場合は、左手はレンズの座金の位置(中心)に軽く添えるように置いておくとよいでしょう。
三脚の高さは自分の身長や撮影対象に合わせて、日ごと、その都度調節します。三脚はやや丈夫目のものがいいでしょう。雲台はできる限りスムーズに動くために、ビデオ用雲台を使い、その都度動きの調整をします。動きは、軽すぎても重すぎてもよくないです。
手持ち撮影しかしないという方は、レンズに付いている三脚座を取り外すことをお薦めします。自分で簡単に取り外したり付けたりできるレンズが多いです。三脚座を取り外したほうが、じゃまな突起物がなくなり、さらに軽くなって、気分よく撮影ができます。
(Uploaded on 15 November 2015)
以下に述べることは100%正確な個体識別に使えるものではありませんが、個体識別の前段階で、「自分たちが継続観察している繁殖ペアとはちょっと違う個体だな」 と思えるような、そういうレベルのものです。つまり、個体識別の前段階でふるいにかけることに役立ちます。
まず、オオタカを例に述べます。幼鳥が春から夏にかけて全身の完全換羽を済ませると本来幼羽は残らないはずですが、実際はわずかに幼羽が残ります。どちらかというと、わずかですが幼羽が残ることが多いです。栄養状態等によっては幼羽がたくさん残ることがあります。残るのは風切や尾羽ではなく、主に脇腹の羽毛であったり下雨覆であったりします。この後さらに1年が経過した2度目の換羽後まで幼羽が残っているということは通常は考えられないですので、幼羽がわずかに残っている個体は「1歳の若鳥」と言ってよいでしょう。
換羽以外でも風切羽や体羽は変化していきます。メラニン色素を多く含んだ黒っぽい羽は紫外線等の影響その他で、羽色が白っぽくなっていきます。逆に、羽と羽、あるいは羽と空気との摩耗によって羽先の白い部分が削れて白っぽく見えていた胸が黒くなってくることもあります。このように、換羽によらなくても色が黒から白へ、あるいは逆に白から黒へと変化することがあるわけですので、注意が必要です。
いろいろな例
ここに書き出したらきりがないくらいいろいろな例があります。一番多い例は、いわゆる個体差です。猛禽類は小鳥類よりも体の大きい種が多いですので、個体差は小鳥類と比べるとよく目立ちます。また、大陸から渡ってきただろうと思われる個体のなかにはかなり特徴的な色や模様の個体がいます。
昭和6年に宮内省(いまは宮内庁だが当時は宮内省)式部職の編纂で発行された『放鷹』という分厚い本に、黒田長禮氏の論文「日本の鷹類に関する科学的考察 第4篇 鷹類に見らるる個體的趨異」が載っています。ここではツミ、ハイタカの個体差について言及され、さらに、「…之等を寫生してあらわさば千差萬別にして誠に面白き研究をなすことを得べしと信ず。…」と述べ、ノスリ、ハチクマ、サシバ、ハイタカ、ツミ、オオタカ、ハヤブサ、シロハヤブサ等を研究対象にするとよいとしています。この本の出版からすでに84年が経ちますが、デジタルカメラの写真技術が発達したおかげで、最近やっと個体差の研究が進んできました。
(ハチクマ) 個体差の激しさという点ではハチクマはまさにその典型例でしょう。濃いものから薄いものまで、また黒いもの、茶色いもの、白いものなど、あるいは色のほかに体下面の模様が異なるとか、翼などの斑の状態が異なるとか、これらのすべての組み合わせになりますので、かなりの数のバリエーションがあります。
(サシバ) 背面がかなり赤茶色い個体がいました。雄でしょうが、それにしてもかなり赤かったです。雌なのに眉斑がほとんどない個体や、雄なのに頭全体にグレー味がまったくない個体もいました。
(ノスリ) ノスリの成鳥と幼鳥は比較的よく似ているほうですが、それでも全体に黒っぽい個体や白っぽい個体、バフ色が強い個体、あるいは横斑がたくさん見られる個体がいます。
(オオタカ) 胸から腹、風切り羽、尾羽にほとんど横斑が見られず、アルビノではないのですがべったりと白く見える個体がいました。おそらく老鳥だろうと推測していますが、老化以外のほかの原因があるかもしれません。
(ハイタカ) 朝鮮半島経由で渡ってきたと思われるハイタカのなかには下面がかなり赤茶色の個体がいます。国内産も含め、幼鳥の胸の斑の様子は実にさまざまで、これだけで写真集ができるくらいです。
(コチョウゲンボウ) コチョウゲンボウなどのハヤブサ類は、正月前後から背中の羽や一部の風切羽、尾羽が通常換羽を始めます。換羽した部分以外の羽は幼羽ですので、自信を持って、幼鳥として観察することができます。
(ハヤブサ) 下胸の横斑が、雄と雌で全く入れ替わったように見えるハヤブサのペアがいました。こういうペアはけっこういます。両翼のP5だけが長く見える個体もいました。中央尾羽のみが長く見える個体もいました。オオハヤブサのように亜種がはっきりとわかる黒っぽい幼鳥個体もいました。ほかの亜種についても、斑の黒さ、腹の赤茶色、ハヤブサひげの太さや濃さ、胸の縦斑の太さや濃さなどに、さまざまな違いが見られます。
ほかのタカ類・ハヤブサ類について、1種類ごとに書き上げたらきりがないくらい個体差がたくさんあります。ここでは細かな記述は省略しますが、個体識別をするという時にはすべて役に立ちます。もちろん、これらだけで個体識別するのではなく、欠損等の他の識別ポイントと併用するような形で補助的に使うとよいでしょう。
(シリーズ「タカ類・ハヤブサ類の個体識別」は今回で終わります)
(Uploaded on 18 September 2015)
前回の続きで、5種類の欠損の内の「E 事故換羽による欠損」について、記述します。
E 事故換羽による欠損 (事故換羽欠損)
通常換羽に対して、事故換羽というものがあります。これは、Dの通常換羽とは違うときに、何らかのアクシデントによって羽が抜けてしまったものです。たとえば、ハシブトガラスに尾羽を1枚引っこ抜かれてしまったとか、他の猛禽類やほ乳類などに襲われて風切羽が抜けてしまったとか、ブッシュの中まで獲物を捕りに入って風切羽が抜けてしまったとか、いろいろな原因が考えられます。A~Cに書いたような途中で折れたり外れたりしたものではなく、羽全体が付け根から完全に抜けてしまった場合です。

この事故換羽欠損には3つの特徴があります。
〇 左右対称ではないです。事故で抜けたわけですので、左右対称になる可能性はかなり低いです。
〇 通常の換羽と同じように、抜けた後はすぐに伸び始め、新しい羽に替わります。1本だけでも生えてきます。
〇 幼鳥の時に更新される羽は、若鳥・成鳥の羽です。幼鳥の羽が生えてくるわけではありません。ですから、たとえば幼鳥が茶色っぽい羽で、成鳥が少し青みがかった羽という種の場合、全身茶色っぽい翼あるいは尾の中に、一枚だけ青っぽい羽が存在することになります。写真を撮れば、これは目立ちます。
もちろん、伸長中の羽は通常換羽の時と同じで、個体識別に利用できます。新しい羽がほかの羽と同じ長さになるまで、つまり伸びきるまで個体を追えます。
上に書いた幼鳥のように、一枚だけ違う色の羽の場合、ほかの羽が通常の換羽をして生え替わるまで、場合によっては何ヶ月もの長期間にわたって、個体識別に有効です。
下の写真は、真木広造さん著の「ワシタカ・ハヤブサ識別図鑑」の83ページに掲載されているハイタカの写真です。10月の撮影ですので、早めに体羽の換羽が始まったのではなく、何かの都合で抜けたと思われます。この写真のように、風切羽や尾羽以外の羽も事故で抜ければ新しい羽が生えてきます。幼鳥ですが、事故で抜けた後は成鳥と同じやや青っぽい羽が生えてきています。写真が1枚しか掲載されていないですので、光線の加減でこの腰羽一枚だけが違う色に見えているという可能性がゼロではありませんが…。
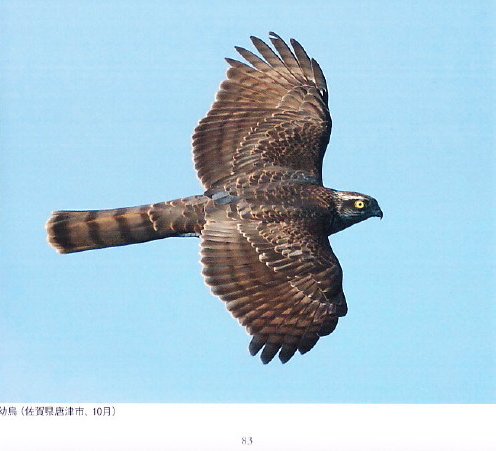
(Uploaded on 28 August 2015)
前回の続きで、5種類の欠損の内の「D 通常の換羽による欠損」について、記述します。
D 通常の換羽による欠損 (通常換羽欠損)
風切羽や尾羽の通常の換羽は、基本的には左右対称に規則正しく決まった順番に抜けていきます。大形の種以外は、多くは春から夏にかけて全身の羽を完全換羽します。このあたりのことについては、マーリン通信の記事No.284 「風切と尾羽 換羽順のわかりやすい表」 (左目次の「鷹隼類全般2」の2015年1月1日付)を、ごらんください。
左右対称ということについては、必ずしもそうでないものもいます。たとえばノスリなどは、左右対称ではない抜け方をするということが報告されていますが、多くの種において、左右対称に抜ける場合が多いです。私見ですが、ハヤブサやオオタカ・ハイタカなど、狩りのスピードが速いもの、すなわち敏捷で飛行能力が高いタカ類ほど左右対称性がしっかりとしているように思われます。ただ、トビの初列風切が左右対称に抜けているのに、クマタカの初列風切が左右対称ではなく、かなりばらばらに抜けている例もありますので、あまりおおざっぱに一概には言えません。
---(以下は、飼育個体での観察経験例です)---
ある日、知人の飼育しているオオタカを見にいったときのことです。朝方、タカ部屋をのぞきに行ったら、右の初列風切が一枚だけ地面に抜け落ちていました。いつもは左右対称なのに、右側だけという抜け方はおかしいなと思いました。ところがしばらくして再び見にいったら、地面に左の風切羽が落ちていました。野外で飛んでいるタカは抜ければすぐに抜け落ちるのですが、飼育個体では羽が抜けても翼を広げたりばさばさとさせなければ、あるいは飛行しなければ、そのまま抜け落ちずに翼にくっついていることがあります。
---(以上は、飼育個体での観察経験例です)---
猛烈なスピードで獲物に猛追するタカ類・ハヤブサ類にとっては、たとえ一枚でも左右対称でない羽の抜け方をした翼は飛ぶという点に関してはすごく困ることになると思われます。
野外観察した翌日に別の新たな羽が抜け落ちることはありますが、昨日までなかった羽が次の日に伸びて生えそろっていたということはありません。ですから、通常換羽欠損は個体識別にひじょうに有効ということが言えます。今飛んでいる個体が1時間前に現れた個体と同じ個体か、あるいは昨日の個体と同じ個体かという判断にはかなり役立ちます。何日か後には伸びかけで、半分くらいの長さまで長くなっていたということはありますので、羽の抜ける順番と伸びきるまでの日数さえ勘案しておけば、これほど有効な個体識別法はないと言えるでしょう。しかし、月に1回しか調査ができないような場合は、通常換羽以外の他の観点も合わせて考えていかないといけないです。

写真は6月に撮影したサシバの若鳥です。P5が伸び始め、P4がもう少しで伸びきるところです。両翼はきれいに左右対称になっています。P1の先端はあまりはっきりしませんが、P2~P4の先端は翼帯が太くて、新しい羽であることがよく分かります。尾羽は開いていないのではっきりとは分かりませんが、中央尾羽は脱落しています。
(Uploaded on 20 July 2015)
風切羽や尾羽の欠損は、羽が欠けた原因によって、次のA~Eの5つに分けられます (括弧内の名称は若杉が付けたものです)。
A 「羽軸」 が折れたことによる欠損 (羽軸折れ欠損)
B 羽軸から櫛の歯のように出ている 「羽枝」 が折れたことによる欠損 (羽枝折れ欠損)
C 羽枝から伸びている 「羽小枝」 の小鉤が一時的にはずれたことによる欠損 (羽小枝はずれ欠損)
D 通常の換羽による欠損 (通常換羽欠損)
E 事故換羽による欠損 (事故換羽欠損)
今回は、このうちのA~Cについて、つまり換羽以外の欠損について述べます。
A 「羽軸」 が折れたことによる欠損 (羽軸折れ欠損)

写真はクマタカですが、矢印の右翼P3のように、羽軸が途中で折れて羽の先のほうの一部がなくなってしまったものです。ブッシュに入って羽を傷めてしまったとか、何かに襲われて羽を傷めてしまったとか、いろいろな理由があります。羽軸に羽枝の生える方向がV型ですので、折れて切り取られたラインはたいてい「V」 の字になります。外弁が狭く、内弁が広い カタカナの「レ」 の字です。
この欠損は、次の通常換羽の時期が来るまで回復しえないものです。たとえばオオタカくらいの大きさのタカでは、通常の換羽期である春~夏ごろまで回復しないものです。ですから、個体識別という観点だけからいえば、かなり好都合な欠損です。もし10月に観察を開始した場合、翌年の春までの長期間にわたって、個体識別をしながら追い続けることができるわけです。クマタカの場合、さらに1年以上は換羽しませんので、もっと長い期間、識別に使えることになります。
B 羽軸から櫛の歯のように出ている 「羽枝」 が折れたことによる欠損 (羽枝折れ欠損)

羽毛の中心軸 (羽軸)から、櫛(くし)の歯のように、たくさんの羽枝というものが出ています。その羽枝が、羽軸のあたりから、あるいは羽枝の途中で折れて取れたものです。多くの場合、写真のような「コ」の字型に欠けています。木の枝に逆向きに引っかかってしまい、かなり幅広く、たとえば数cmにわたり「コ」の字型に欠けてしまうこともあります。
この欠損も上記のAと同じで、次の通常換羽の時期が来るまで回復しえない欠損です。Aと同じように、個体識別に長期間使えます。
C 羽枝から伸びている 「羽小枝」 の小鉤が一時的にはずれたことによる欠損 (羽小枝はずれ欠損)
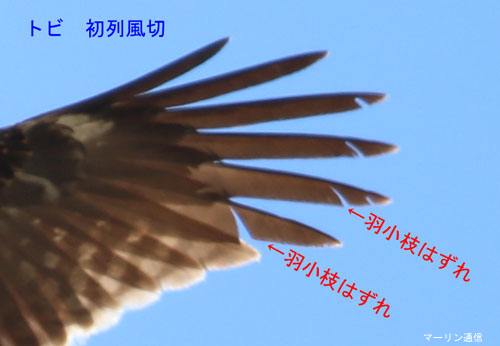
羽枝からさらに櫛の歯のように、孫のように派生しているものが、羽小枝です (親→子→孫のように、羽軸→羽枝→羽小枝というように枝分かれしています)。羽小枝には小鉤 (かぎ。カギカッコ「 」のカギ) がたくさんついていて、隣どうしの羽枝を結びつけています。この鉤のおかげでたくさんの羽枝が1枚の羽弁になるわけです。
この小鉤が一時的に外れると、上の写真のような細長い三角形状の欠損に見えます。単に鉤(hook、フック)が外れて間が開いただけですので、欠けたように見えるだけで何も欠けてはいません。タカがくちばしで羽をスーッと一回なぞるように羽づくろいすれば、簡単に羽枝と羽枝がくっついて、元に戻ります。ちなみに私たち(人間)が親指と人差し指で挟んで羽枝に沿ってなぞってやれば、簡単に元に戻ります。
ある観察の直後に、同じところが同じように三角形状に欠けて見えれば、個体識別に使ってもよいのですが、いつタカが羽づくろいをし、フックが元のように直っているのかが分からないですので、実質的には個体識別にはほとんど使えません。もちろん、翌日には使えないと思った方がよいでしょう。
(Uploaded on 1 July 2015)
タカ類・ハヤブサ類の繁殖ペアや越冬個体などを継続的に観察する時、一番必要になってくることは正確な個体識別です。今、目の前に出てきたタカが1時間前に現れたタカと同じ個体かどうか、または今出ている個体が昨日の朝に出た個体と同じかどうか、こういった判断が必要になることは多いです。いくら繁殖活動中といっても、他のエリアの個体が侵入してくることがありますし、さまよっている若鳥が今観察中のペアのエリアに入ってくることはいくらでもあります。ペアの片方がいつの間にか入れ替わっていたということもあります。ですから、しっかりした調査では正確な個体識別は絶対に避けて通れないものです。
今回から6回シリーズで、この個体識別について、書いていきます。
キーワードは、雌雄、幼羽・成羽、年齢、亜種、通常換羽、事故換羽、欠損、(黒っぽいか白っぽいか等の)色合い、(鷹斑等の)模様、虹彩色、(暗色型等の)型、(片足をぶら下げている等の)けがの状況、…です。その他にも個体識別に使えるものがたくさんあります。ただ、その特徴がいつまで有効なのか、たとえば、一週間程度なのか、抜けた後に生えてくる羽が伸びきるまでなのか、次回の春~夏の換羽時期までか、あるいは、ちょっとはずれただけのもののように嘴でなぞるまでのほんのわずかな時間だけのものなのか等、その項目ごとに異なります。この連載では、この有効期間についても触れていきます。
初回の今日は、幼羽と成羽について、ごく基本的なことを述べます。個体識別の前段階で有効です。
繁殖ペアの羽衣が雌雄ともに成羽で、エリアに入ってきた個体が幼羽である時などに、この個体識別の方法は簡単で有効です。
A 幼羽
幼羽の翼縁はきれいに揃っています。でこぼことしたところが一カ所もありません。下の写真は ノスリの幼鳥ですが、このように翼縁がきれいに揃っています。

羽縁がそろう理由は、純白だったヒナの体に風切や尾羽が生えてくる時、すべての羽が同じ時期に同じ速さで一斉に生えてくるからです。一枚一枚の風切や尾羽が時間差で順番に生えてくるわけではありません。全部の羽毛が一気に一斉に同じように生えてくるので、隣どうしの羽の長さが皆そろってくるというわけです。親から食料がもらえなかったとか、長雨がずっと続いたとか、よほどの理由があったとしても、すべての羽が同時に生えて伸びてくるので、伸びきった隣どうしの羽の長さに不自然な違いはなく、でこぼこは見られません。
B 成羽
ところが、下の写真はノスリの成鳥ですが、羽の長さに長短があるため、翼縁がでこぼことしています。

一回でも完全換羽を済ませた鳥、あるいは一部分の換羽を済ませている鳥、つまり成鳥や若鳥は、程度の差こそあれ、おおむねこのようになります。
翼縁がこうなる理由は、一枚一枚の羽が伸びてくる時期が違うということです。一枚が抜けて、ある程度伸びると、次に隣の羽が抜け落ち、時間差を置いて伸長してくるということの繰り返しですが、その時その時で、食べ物の量が違ったり、天気、ストレスなどさまざまなことが異なるので、どの羽もまったく同じようには伸びないのです。
小形のタカ類・ハヤブサ類は不揃いさやでこぼこが、あまり目立たないですが、写真を撮ってよく調べてみると、やはり翼縁はでこぼことしていて、不揃いになっています。大形のタカ類・ハヤブサ類は写真を撮らなくても、双眼鏡で見ただけでこのでこぼこがよく見えます。慣れてくれば、双眼鏡で翼縁を見るだけで、幼鳥と成鳥の識別は簡単にできるようになります。
尾羽についても風切羽と同じことが言えますが、尾羽は閉じて飛行することが多いですので、翼縁と比べて、個体識別には使いにくいです。しかし、尾羽を広げれば、双眼鏡だけでも成鳥・幼鳥の違いが明確に分かる時があります。また、写真で調べる時も、尾羽の先のでこぼこは成鳥・幼鳥の識別の役に立ちます。
成鳥同士のペアを観察中に幼羽の個体が観察されれば、少なくとも、「繁殖ペアのどちらでもない」 ということが言えますので、個体識別の前段階でふるいにかけることができます。
(Uploaded on 14 June 2015)
はじめに、ハイタカの狩りのようすを3つあげます。今年の3月に見たものばかりです。
事例 1
(2015年)3月上旬、用事があってある駐車場に車をとめ、車から降りて周りの景色を何気なく見ていました。このあたりは落葉樹が多く、ところどころにみかん畑や野菜畑があります。駐車場にハクセキレイが1羽やってきて、アスファルトの上をチョロチョロと歩いて私の近くに来ました。その歩き方を肉眼でしばらく見ていたら、突然、セグロセキレイのように「ジジッ」と鳴いて、足で地面を思いっきり蹴って北西方向へ力一杯飛び立ちました。どうしたんだろう? 車は来ていないし、人も来ていないし、犬も来ていないし…。飛び去った反対方向をパッと見ると、私に向かってツグミが一羽、体を45度くらい傾けて深く羽ばたきながら猛スピードで不自然な姿勢で飛んできました。「あっ、猛禽に追われてるんだ」と思った直後、みかん畑の上3メートルほどにハイタカが現れて、こちらに飛んできました。私にあと10メートルほどの距離になったところで、ほぼ90度左へスコーンと曲がって、畑のほうへ行ってしまいました。かなり近い距離でした。ハイタカは私の存在に気がついて、あわてて方向を変えたようです。ハクセキレイの飛び立ちの瞬間に、私が車の陰にでも隠れていたら、ハイタカがツグミを捕らえる瞬間が見られたのかもしれません。
事例 2
(2015年)3月中旬、山の中でタカを見ていました。高木の梢にいたエナガが、急に下の低木に降りてきました。エナガが地面近くの高さ50cmほどの低い木にとまるのは比較的珍しいものだなと思って見ていると、いつもはジュルジュルと鳴くエナガが、突然、「ティーティーティー」「ジージージー」と聞こえるような声で鳴いて、動きが急になってきました。私がぱっと上を向くと、ハイタカの♂成鳥が高度をどんどん下げているところでした。私がいたからでしょう、ハイタカは向きを変えて山の頂方向へと去って行きました。エナガがハイタカから身を守るために私を利用したのかどうかは分かりませんが、そんなこともあるような気がしました。
事例 3
同じく、(2015年)3月中旬、民家にほど近い果樹園の脇を歩いていたとき、果樹の間のあちらこちらから次々とツグミが「クェッ」と鳴きながら出てきました。それまでそんなに多くの姿は見えなかったけれども、こんなにいたる所にツグミがいたんだなと思いながら上空を見ると、ハイタカがやや高いところを舞っていました。ハイタカがよく行う急降下をして、果樹の上の低いところを通過して、少し高度を上げながら山のほうへと去って行きました。

ハイタカについて同じような観察記録を3つ書きましたが、小鳥の動きからハイタカなどの鷹隼類の存在を知ることができます。ハイタカのみではなく、他のタカ類についても同じようなことが言えます。タカが現れるとヒヨドリの鳴き声が警戒の鳴き声に変わることもよくあります。カラスの動きや鳴き声で鷹隼類の存在に気がつくこともよくあります。鷹隼類の存在を教えてくれるものはこの他にもたくさんあります。野鳥を観察していて、「あれ、変だな」、「何かいつもと違うな」と思ったときは近くに鷹隼類が来ていると考えたほうがよさそうです。
いずれにしても、少しでも早く鷹隼類の存在に気がつけば、それだけハンティングの瞬間が見られる可能性が高くなります。
(Uploaded on 2 April 2015)
鷹隼類が木の枝や鉄塔にとまっている時、それが休息であるのか、とまりディスプレイであるのか、ハンティング(獲物探索、待ち伏せ) であるのか、分かりにくい時があります。「ハンティングの瞬間を見るには(2)」 では、これらの見極めについて記述します。
(1) そのうの膨らみ
食料をたくさん食べたばかりでそのうが大きく膨らんでいる時は、「休息中」 の可能性が高いでしょう。しかし、そうでない場合もありました。秋のヒヨドリの渡りの時期に、こんな経験をしたことがあります。ヒヨドリを一羽食べたばかりの雌のハヤブサがそのうを膨らませて携帯電話会社の鉄塔にとまっていましたが、すぐに次のヒヨドリを捕りに飛び立ち、難なく捕らえて同じ鉄塔に戻ってきたのです。もちろん、すぐに食べました。そのうが多少膨らんでいても、狩りをすることはあります。
(2) とまっている場所
・ 繁殖エリアの中の最も高くてよく目立つヒノキ等のてっぺんに、太陽の方向におなかを向けている時、あるいは、そのあたりで最も目立つ枯れ木の枝や象徴的な鉄塔のてっぺんあたりにとまっている時は、とまりディスプレイの可能性が高いです。「目立ちすぎるほどのところにとまっているな」 というときほど、とまりディスプレイの可能性が大きいでしょう。
・ 足場がしっかりとしたところにとまっているかいないか。弱い枝やふらふらするような木のてっぺんに、風に揺られながらとまっている時は狩りの可能性が低いことが多いです。あるいは、足場のしっかりとした鉄塔や太い枝、電線にとまるにしても電柱に近い位置にある揺れない位置の電線か、あるいは飛び立つとふらふらしそうな電線の上(電柱と電柱の間の動きやすい電線の上)にいるかは一つの目安になります。
(3) とまっている時期、時間
なわばり宣言をしている繁殖期なのか、それとも越冬期なのかによって全然違ってきます。時間も食料を食べたすぐ後なのか、朝からまだ何も食べていない時なのかによっても違いがあります。
(4) とまっている時のようす
視線はどこにあるのか。頭を左右に動かしているか。キョロキョロしているか。体全体がスマートになっているか、ぶくっと膨らんでほぐれた状態になっているのか。とまっている時の方向が水田の方なのか山林の方向なのか、あるいは、風上方向なのか風下方向なのか、細かく状況を見る必要があります。
これらを総合的に見て判断する必要があります。
(チョウゲンボウの観察例)
先日(2015年2月)、愛知県の某河口にある干拓地へタカ類を見に行きました。田と田の間の道路を車でゆっくりと流していたら、電線にとまったチョウゲンボウを見つけました。私がチョウゲンボウに気づくのが遅く、あまりにチョウゲンボウの近くへ車を止めたので、すぐにエンジンを切って、車内でじっとすることにしました。チョウゲンボウのほうを見ないようにして目を合わせず、右手の指と指の間からちらっ、ちらっと観察しました。頭だけが青くなっていて、尾羽は一枚も換羽していない雄の幼鳥でした。
さて、このチョウゲンボウはなぜとまっていたのでしょうか。 2月で、越冬地へ来ている時ですので、とまりディスプレイではありません。では、休息中か獲物探索中か? しばらく観察することにしました。とまった場所は電柱のすぐ近くの電線の上。視線は下の水田の方向です。じっと見ています。そして、時折、あるところを注視します。という事は、どうも獲物探索中、ハンティング中と思われます。
電柱と電柱の真ん中の電線にとまると、いざ飛び立った時に反動で電線が動き、力が入らないのでスピードが出しにくいですが、電柱の近くの電線にとまると飛び立った時に電線が動かないので、力が出やすいようです。この時も電柱のすぐ近くの電線にとまっていましたので、狩りをする可能性は高いと思いました。
しばらくすると頭を上下にぴくぴくと動かしました。これは獲物を凝視し、獲物までの距離を測ったり、飛んでから獲物に到達するまでの時間を推定している時の行動です。そして、急に飛び立ち、俯角(ふかく。伏角とも)30度くらいで田の中に突っ込んでいきました。いともたやすくネズミを捕らえ、すぐにはじめにとまっていた一番近い電柱の隣の電柱のてっぺんに戻って食べ始めました。ハシボソガラスが1羽やってきてじゃまをし始めましたので、それを嫌って、北の方へ羽ばたいて200mほど移動しました。そこで、下の写真のように、電柱のてっぺんにとまって、誰にもじゃまされずにゆっくりと食べ尽くしました。私もじゃましないように、この写真はかなり遠くから撮ったものです。チョウゲンボウやノスリは比較的観察しやすく、他のタカ類には観察の難しい種もいますが、基本的な考え方はとにかくじっくりと行動を観察するということに尽きます。

次回、「ハンティングの瞬間を見るには (3)」 に続きます。
(Uploaded on 20 March 2015)
野鳥観察をしている人たちと話をすると、「猛禽類の狩りの瞬間は、なかなか見ることができない。私もタカ類のかっこいいところをもっと見てみたい」 とか、「あなたはよくそんなに迫力のあるハンティングシーンを見ることができますね」 と言われます。実は、タカ類・ハヤブサ類が毎日やっていることは 「休息」 と 「ハンティング」 が中心で、ほぼ一日の全部の時間をこれらに費やしていると言ってもよいほどです。年間を通しての大きな仕事は春や秋の渡り・移動と繁殖活動ですが、この間も、もちろん休息や狩りは必要です。ですから、タカ類・ハヤブサ類は、毎日、いつもいつもハンティングのことばかりを考えています。その気になって観察してみると、ほぼ一年中いつでもハンティングの瞬間は見られるということです。
鷹隼類の狩りの瞬間を見るためのコツを、3回シリーズで書いてみます。

(1) タカ類を驚かさない
タカ類が木の枝にとまっていた、あるいは、飛んできて近くの木の枝にとまったとします。車の中にいた場合は、車から出ずに、窓ガラスも開けず、視線をそらしタカと目を合わせないようにするとよいでしょう。また、絶対に大丈夫だという時以外は、写真は撮らないほうがよいでしょう。個体識別のためにどうしても写真が必要だとか、飛び立っても仕方ないからここのシーンだけはぜひ撮りたいという場合を除いて、写真は撮らないことです。車の外にいたなら、草かげに隠れるとか姿勢を低くして目をそらし、知らん顔をして、タカ類に「君には関心がないよ」というような態度で観察を続けるとよいでしょう。音を立てず、声を出さず、急な動きをしないとさらによい結果が出ます。これらは別に神経質すぎることではなく、また、必ずそうしなければいけないということでもありません。今まで私の近くに来たタカが、私が車から降りたために飛び立ってしまったとか、窓ガラスをおろしてレンズを出そうとしたために飛び立ってしまったとか、そういうことが過去にあったので、いろいろ試行錯誤してみたところ、上に書いたような方法が一番良かったという、そういう経験的な事実です。長時間にわたる調査圧とか観察圧とかではなく、たとえ短時間でも、タカが嫌がることをするとタカは飛んでいってしまう というそれだけのことです。観察者が石になりきると目の前でタカ類はごく自然な振る舞いをします。
このようにしてしばらく待っていると、たいていは飛び立ち、力強く羽ばたいて小鳥の群れに突っ込んだり、高度を少し上げた後に急降下して獲物を襲ったり、樹林帯の中へ猛スピードで入っていったりします。獲物を両足でつかむ瞬間が見られるかどうかはその時の現場近くの樹木の茂りぐあいとか見晴らしなどの環境にもよりますが、観察回数が多くなればチャンスは確実に増えます。
もちろん、タカが木の枝にとまってもすぐに狩りをするとは限りません。首を右や左に動かして周りをキョロキョロしたり、頭を上下に動かして獲物を注視したりすれば、飛び立つ瞬間が近いことが分かります。しかし、木の枝にとまった最初のうちは頭も目も動かさずに何くわぬ顔でじっと獲物が出てくるのを待ったり、獲物の様子をうかがっていることがありますので、こういう時は休息をしているのか狩りをしているのか、判断しづらい時があります。でも、そのうちに狩りをするだろうと思っていたほうが無難です。休息しているようにしか見えなくても、近くに小鳥がやってきたら急に狩りを始めることが多くあります。 (このあたりのことについては、次回書きます)
(2) 飛び立って 遠くへ飛去しても観察を続ける
タカ類が飛び立って羽ばたきながら去っていったり、旋回上昇して遠くの方へ飛去し始めたりすると、 「あーぁ、行っちゃった…」と思ってしまいがちですが、視界からタカが完全に見えなくなってしまうまであきらめず、双眼鏡で追い続けるとよいです。距離は離れてしまいますが、遠くの方で急降下して獲物を襲うところや、思いっきり羽ばたいてスピードを上げ、獲物に猛追して両足を前にグイッと出すようなダイナミックなシーンが見られたりします。
(3) 「小鳥類の観察法とは違う」 と思って観察する
タカ類の観察を小鳥類や水鳥類の観察と同じだと思ってしまうとうまくいかないことがあります。通常のバードウォッチングで小鳥類を観察する時の方法や水鳥類を観察する時の方法、秋のタカ渡りの観察をする時の方法は、みな違います。タカ類のハンティングを観察する方法も当然異なります。このあたりを意識するとよい結果が出るでしょう。つまり、対象あるいは目的によって観察の方法も変える必要があるということです。小鳥類の観察と比べれば若干きついかもしれませんが、これらは鷹隼類観察のコツです。
次回、「ハンティングの瞬間を見るには (2)」 に続きます。
(Uploaded on 12 March 2015)
どんな優秀な人でも、自分一人だけの力には限界というものがあります。もし、そう思わない人がいらっしゃいたら、例えば、遺伝子の研究を考えてみてください。たとえあなたがその分野ですばらしい成果をあげたとしても、「では、DNAを発見したのは……。それをさらに進めて発展させた個人・研究所・企業は……。簡単に分析できるように機械を製品化した企業は……。どこの大学にも設置できるように小型化し低価格にしていった企業は……。」 というように考えていくと、いかに多くの先人や団体・企業の力に依っているかということが分かると思います。また、もう一つの例ですが、アインシュタイン博士の相対性理論を考えてみてください。ご自分一人で考えていただけでは、一生かかっても自力で相対性理論にたどり着くことは困難でしょう。しかし、今の時代、世界中の何十億という人が相対性理論なしでは生きていけないほどの大きな恩恵を受けています。カーナビとか、スマホとか、パソコンとか…、これらはみな相対性理論なしではできなかったものばかりです。
タカの研究もこれと同じようなことが言えると思います。一人一人がゼロからスタートしていたのでは、何もできません。たとえば、日本にどういう種類のタカがいるかを調べることから研究を始めるとなると、これはけっこうたいへんなことです。ツミとエッサイ(ツミの♂の旧名)の違いや、この2つが同種であることを自分で発見することなど、それだけでもたいへんなことです。ハチクマの雌雄成幼の識別にしても、Kさんがしっかりやってくださったから、今こうして楽に研究がスタートできます。まず自分の力で雌雄成幼の違いを見つけてから研究に取り組むとなると、すごく時間がかかってたいへんです。
このように、今まで、科学はすべて先人の膨大な研究成果の上に自分の研究成果を少しだけ積み重ねることで、少しずつ進歩してきました。他の人が書いた論文を読ませてもらい、その上に自分の研究を少し積み重ねていく。先人の努力を、いかにして 「自分の土台」 にしていくのかが、これからの研究を進めていく若い人には大切だと思います。タカ類・ハヤブサ類の世界は、まだ分からないことが山ほどある、大きな金脈のような世界です。自分には何が分かっていて何が分からないのか、ここから始めて、先人の研究を土台にしてスタートすることは意義あることだと思います。
さて、話が少しそれますが、何をやっても、どんな世界にも、「上には上がいる」と言われます。これはほとんど普遍的なものでしょう。例えば、超一流の鳥学者になったとしても、その人とは違う感性の持ち主で、タカの心がある程度読める人がいたら、その点において彼はその人には勝てません。また、次元が1つ高い世界に生きる人もいます。われわれは4次元の時空間に生きていると言われますが、実際は、前後(1次元)・左右(1次元)にほぼ自由に動けて、時間という奇妙な一方通行のものに乗っているので、時間を0.5次元とすると、1+1+0.5 で、実質2.5次元の世界に生きているといえます。鳥は上下(1次元)にもまったく自由に動けますので、彼らは実質3.5次元の世界に生きています。人と鳥はこれだけでも大きく異なります。だから鳥よりもさらに1つ高い次元に生きている人は4.5次元の世界に生きることになります。たとえば、部屋の出入り口から出ようとして、からだが半分外に出た時点で、すでに反対側の窓から体の半分が部屋に入ってきているような、そんな考えのできる人、昔流行した言い方でいうと「ワープできる人」と言ってもいいでしょうか。4.5次元よりもさらに上の次元の人間は私の脳では考えることができないのですが、でも、世の中にはそういう世界に生きる人がきっといるんでしょうね。だから、違う感性で受け取るとか、違う次元の世界に生きるということを考えると、どんな時でも、「人は天狗になってはいけない」と思います。「常に人から学ぶ」、「誰からでも、どんな人からでも学ぶ」、「自分はたいした人間じゃない」と、(自尊感情を消す必要はないでしょうが)、これくらいに考えることが正解だろうと思います。
先人の得たものを勉強し、すべての周りの人から自分にない物や自分が持っていない感性や態度を学び、次元を超えたような人とも付き合う。研究がいくら進んでも、疑問点や分からないことが次から次と出てきて、一生かかっても研究すべきことはゼロにはなりません。今、分かっていることは、たぶんほんの1%未満。新しい概念が出てきたり、新しい次元に入っていくと、またゼロからのスタートです。一生やることがなくなることはなく、飽きることもないですので、人生はおもしろいものです。
(このシリーズ、終わります)
(Uploaded on 21 May 2014)
「ソウゲンワシが大都市の〇〇市近郊で出ました!」。 「ソウゲンワシがそんなところに来るはずないでしょう。何かのまちがいじゃないですか?」
… 「この時期(この季節)に、そんなタカやワシがここにいるはずがない!」 ということを、よく聞きます。頭の固いベテランの野鳥観察者が、経験年数の少ないバードウォッチャーにそう言っているところに居合わせたこともあります。でも、この件、100%の否定はできないはずです。あなたが思いもよらないタカがあなたの目の前に現れても、それは少しもおかしくはないです。もちろん、かご脱けではなくて。「愛知県にヤンバルクイナがいますか?」 とか、「ノグチゲラは出ますか?」 と聞かれると、それはちょっと困りますが、きょうは、こういうものとは少し次元のちがう話です。
「サシバがオオタカのヒナを捕って食べました!」。 「そんなものを食べるはずがないですよ。サシバの幼鳥とオオタカの幼鳥をまちがえたんじゃないですか?」
… オオタカがサシバの巣にいるヒナを捕ったという事例はいくつか報告があります。その逆の報告は今のところないようですが、可能性はゼロではないでしょう。
「イヌワシのヒナが1巣で2羽も巣立ちしましたよ!」。 「そんなはずがないですよ。日本では昔からイヌワシのヒナは1羽と決まっていますよ!」
… でも、2羽のこともあります。大きな巣であったり、親がたくさんの食料を運ぶことができたり、それなりの条件が整えば、2羽のヒナが巣立つこともあります。「決まっている」ということはどこにもありません。
「クマタカが名古屋市近郊の住宅地の近くのため池に来ています!」。 「まさか。クマタカはあまり繁殖地から離れないタカだから、こんな所までは飛んでこないですよ! それって、オジロワシかトビじゃないですか?」
… でも、2012年12月~2013年1月にかけて、名古屋市に隣接するベッドタウンの尾張旭市にクマタカが来ていました。2015年12月からも、第2回冬若鳥と思われる個体が来ていて、カワウやカモ類を捕食しています。こういうことは大都市近郊でも、十分にありうることです。ここには、近年、オオワシやオジロワシも来ています。カワウのコロニーが存在することが大きな要因と思っています。
「クマタカが海の上を飛んでいました!」。 「そんなはずがないです! クマタカは深い山の鳥なんです。ひょっとしたら、それは渡り途中のハチクマを見誤ったのではないですか?」
… いいえ、クマタカが海の上を飛んでもおかしくありません。伊良湖岬で記録されたタカ類・ハヤブサ類のリストにはクマタカが入っていませんが、伊良湖岬でクマタカを観察したという人がいます。残念ながら写真がないので、記録として残っていません。ひょっとして、その日の記録担当者に、「そんなはずがない!」 という barrier があったのかも…(推測)。
「渡りをしないとされる〇〇ワシや〇〇タカが500キロも移動しているそうですね!」。 「そんなはずがないです! 偉い先生が調べて、図鑑にも渡りはしないと記述してあるじゃないですか」
… でも、移動しています。特に、分散移動の場合は、かなりの長距離になります。偉い先生でも、何もかも分かっているわけではないでしょう。
「イヌワシが、名古屋市内にあるビルの上の広告塔にとまっていました!」。 「ハッハッハッ、イヌワシはそういうワシではなくて、深山幽谷に棲むワシですよ。トビか何かのまちがいではないですか?」
… イヌワシがめったに見られない愛知県ですが、イヌワシが名古屋市内に現れても、ちっともおかしくはないです。
「たくさんのイヌワシが、毎年、数100kmもの渡りをしているところがあるそうですね!」。 「嘘でしょう。イヌワシは定住性が高いワシですから、そんなはっきりとした渡りをするはずがないですよ」
… 日本の話ではないですが、北米ロッキー山脈では毎年、数多くのイヌワシが渡りをしています。
世の中には、けっこうとんちんかんなことばかり言う人がかなりいますので、人の言うことを何もかも信用していると、痛い目に遭うことがあります。そういう人からとんでもないデータが出てきた時は困りものです。このデータをどう扱っていいのか迷ってしまいます。しかも本気で強硬に言われたら、よけい困ってしまいます。そんな時は、ピンぼけでもいいから証拠写真があったらいいなと思います。
今回書いた内容は、これとは次元の違う話です。科学的な正確な話です。
頭の中にある「そんなはずがない!」 という概念は、再考の余地ありです。「そんなはずがある!」 と、考えたほうがよいでしょう。鳥類の飛行能力は、われわれ哺乳類には想像もできないくらいの「超能力」 でしょう。野鳥の世界、タカ類・ハヤブサ類の世界では、何が起こっても不思議ではなく、おかしくもないのです。頭をフレキシブルにして、100%の否定も100%の肯定も不合理だということを、私たちの世界の常識にしましょう。
(Uploaded on 1 May 2014)
「オオタカの抱卵日数は何日ですか?」 と聞かれたら、あなたはどう答えますか。私は「〇〇図鑑では〇〇日~〇〇日と書いてあります」、あるいは「〇〇さんの論文には約〇〇日と書いてあります」 と、答えます。というのも、自分の力でオオタカの抱卵日数を正確に調査したことがないからです。冷たい答え方にならないように、優しく返答しています。
さて、タカ類・ハヤブサ類の抱卵日数を正確に調べるには、どうしたらよいでしょうか。まず、目視観察だけでは十分でないということはすぐにお分かりと思います。最低限、ビデオカメラの設置が必要でしょう。
ここでひとつ、重要な前提条件? というか、先入観? というか、錯覚? があります。それは、「卵は生まれた順に孵化する」という暗黙の了解です。でも、これはいつでも正しいとは限りません。後から産まれた卵が先に孵化することは十分にあり得ます。さらに、別の問題点もあります。というのも、抱卵中のタカ類・ハヤブサ類も転卵といって、卵を頻繁に回転、移動させます。そうすると、どれが何番目に産まれた卵か分からなくなり、それを一つ一つ区別することはほんとうにたいへんなことになります。そのために、例えば、産んだ順に1,2,3,4などと番号をつけるざるをえないことになります。でも、字が小さかったりすると親鳥のおなかの下で、カメラではなかなか読めませんし、数字が下になったら読めません。結局、全部の卵に異なった色付けをしなければならないことになってしまいます。敏感で警戒心の強いタカに、こんなことをしてもいいのかどうか? そもそも、そんなことが可能かどうか? ということになって、なにかと悩ましいところです。
図鑑に書いてある抱卵日数は、みな、幅を持たせてあります。例えば、「37~41日」 などと書かれています。3つあるいは4つの卵にはばらつきもあるでしょうし、異なる巣ではデータが異なることもあるでしょう。地域によっても、その年の気候によっても、また、それぞれの個体によっても、みな日数は異なってくるはずです。だから、幅を持たせているのでしょう。うまく観察できたとしても、もちろん、「〇〇地方で、〇〇年に、この個体の産んだ卵は〇〇日で孵化しました」 としか言えないでしょう。
1卵目あるいは2卵目を産んだ後ですぐに抱卵を始めて、その後も卵を産み増しするタカや、(たとえば)6卵すべてを産んだ後ではじめて抱卵を開始するタカなど、抱卵の様式はかなり異なります。同じハイタカ属の中だけでさえも、大きな違いがあります。正確な抱卵日数を調べることは、たいへん難しいものですが、このような厳密さとか正確さをいつも意識しているかどうかは、ひじょうに重要なことです。
個体差、環境の違い、地域差、亜種の違いによる生態の差、その年の気温の傾向、外部からの観察圧や調査圧、その他考えなければいけない要素はたくさんあります。自分が(あなたが)得た一つのデータから勝手に類推して、「この種はこうだ」と、決めつけてしまうことは、危険です。違う年に、違う地域で、違う個体で、違う亜種で、びっくりするようなデータが得られるかもしれません。
正確さ、地域差、個体差、年による違いなどを常に頭に置いておくこと、そして、ひょっとして自分が(あなたが)このタカを観察していることによって観察圧がどの程度かかっているのかを常に意識していることは、ほんとうに大事なことだと思っています。
(Uploaded on 31 March 2014)
日本鳥類目録改訂第7版(2012)に掲載の鳥類は633種で、タカ類(タカ目ミサゴ科とタカ科の鳥)は26種、ハヤブサ類(ハヤブサ目ハヤブサ科の鳥)は8種です。このうちで、一人の人間が研究することのできる鳥は、最大で1種しかないと私は思っています。あれもこれもと見ることは必要ですが、集中して徹底的にしっかりと研究することのできる鳥は、やはり1種に限られます。
日本には、例えばハチクマを一生懸命に研究している人がいます。チュウヒに生涯を捧げた人もいます。同じように、クマタカに…、イヌワシに…、オオタカに…、サシバに…、ハヤブサに……と、きっとこのHPを見ていらっしゃる方なら、それぞれの研究者のお名前が頭に浮かんでくることと思います。
1種に絞っても、専門馬鹿になってしまうことは決してありません。高さ100メートルの山を築くためには、直径200メートル以上の広い裾野が必要なのと同じように、しっかりした研究には、その周りのもろもろの知識と研究が当然必要になってきます。裾野が広がれば、他の人が研究した他の種の鳥について、いっそう理解が深まり、他人の研究が自分の研究種にも大いに役立つものになってきます。
あれもこれも見ることはもちろん大切です。珍鳥と呼ばれる鳥を追いかけ回すことも、新しい視点が得られるため、良いでしょう。一年で何種類の鳥を見たかを記録することも、それはその方の自由です。たくさんの鳥を見たり研究したりすることの意味を否定することはまったくありません。
でも、タカのちょっとしたしぐさの意味、鳴き声のわずかな違い、タカが観察者のあなたをどう感じているか、どこに巣を架けたくなるのか、今からどこへ飛んでいきたいのか…。もちろん、私も十分には分かりません。しかし、一種に絞って観察を続けると、これらのこともある程度は分かってくることと思っています。
タカと会話ができるようなそんな深いレベルのことを考えたうえで、あえて言うならば、一人の人間が一生で研究することのできる鳥は、やはり最大で1種しかないと私は思っています。
「広く 浅く 見ること」 かつ ( or ではなく and です) 「1種のみを 徹底的に深く 見ること」 が大事でしょう。
(Uploaded on 1 February 2014)
前回の、「上達法(1) ♂・♀・成鳥・幼鳥 の識別」 の続きです。野外観察をしていても、写真を撮っていても、これは? と思うような個体が時々いるものです。種が分からない、年齢が分からないなどといった、悩ましい個体が必ずいます。そんな時に、あなたはどうしていますか。まあいいや、とスルーしてしまうのか。あるいは、誰か詳しい人に鑑定を依頼するのか。あるいは、分かるまで自分で徹底的に調べるのか…。上達法(2)の今回は、どんな方法でもいいから、とにかくスルーしないこと! ということがテーマです。
具体例として、ハイタカの雌雄成幼の識別の話にします。ハイタカ属の中で、オオタカやツミは成鳥か幼鳥かの識別が比較的簡単です。例えば、オオタカの体下面は成鳥が横斑、幼鳥が縦斑であり、それだけではっきりと区別できます。1歳か、2歳か、3歳かということは、正確には分からない時がありますが、でも0歳以外は、つまり1回でも換羽をすれば、すべて横斑ということに変わりがありません。また、ツミは幼鳥の胸にはっきりとした縦斑があること、あるいは雄成鳥の胸などに橙褐色味があり、虹彩が暗赤色であることなどから区別できます。また♂か♀かという点についても、体全体と比較して頭部が大きいか小さいかで、ある程度見分けがつきます。
これらに対してハイタカは、成鳥・幼鳥ともに体下面が横斑のものがほとんどです。ただ、幸いなことに、多くの幼鳥の胸には三日月型やブーメラン型、Vの字型、しずく型、(ツミの胸に似た)縦斑型などの粗い斑を持った個体が多く、それらが見られれば、高い確率ですぐに幼鳥と判断できます。また、胸から腹にかけてすべて横斑のみという幼鳥もたくさんいますが、その多くは比較的粗い横斑ですので、これも幼鳥であると判断できます。しかし、中にはけっこう横斑が密な幼鳥もいます。その場合は成鳥か幼鳥かの識別がたいへん難しくなってきます。
下の写真をごらんください。2013年秋の渡り途中のハイタカで、愛知県での撮影です。この個体は成鳥でしょうか、あるいは幼鳥でしょうか? 写真の下に、ヒントが書いてありますが、お時間がありましたら、それを見ずに、一度考えてみてください。

〇 「成鳥」 と思わせる点
・ 胸から腹にかけて、すべて細かな横斑である。
・ 次列風切と内側初列風切の最外側鷹斑 ( 「ハイタカ幼鳥斑」 と私は呼んでいます) が、まったく見られない。
※ 「ハイタカ幼鳥斑」 は、『バーダー』 2009年8月号の41ページに、伊関文隆さんが 「年齢線」 という名称で紹介しています。8,9,10月号のハイタカの記事はたいへん参考になります。
〇 「幼鳥」 と思わせる点
・ 次列風切の先端がひじょうにきれいに整っている。
・ 次列風切が長く、両翼の後縁が全体として数字の「3」の形をえがいている。
・ 尾羽の先端の両縁が、あまり角ばっていない。
これらの5点から考えると、成鳥とも幼鳥とも思えてしまいます。どちらでしょうか。背面の全体の色や羽縁の淡色の有無が分かるコマ、あるいは最外側尾羽(R6)以外の尾羽(R1~R5までの10枚)の横斑の太さが分かるコマがあればさらにはっきりとしてくるでしょうが、そういう写真が常に撮影できるとは限りません。この個体も高い上空を搏翔(はばたき飛翔)と滑翔(滑空)で一直線に飛んでいったので、尾を広げることはなく、もちろん背面はまったく見られませんでした。
…と、こんなような感じで、納得がいくまで追究してみるとおもしろいですよ。一部は人に聞いてもかまいません。本を見てもかまいません。どんな方法をとってもいいですが、よく分からないからといって、人に 「丸投げ」 したり、スルーしたりしないことです。分からないことを分からないままにしておかずに、自分の努力でとことん追究していくと、必ずや識別力が付くことと思います。
さて、上の写真のハイタカですが、この1枚の写真だけで断定はできないのですが、全体のシルエットのようすからたぶん♀幼鳥だろうと思っています。
(Uploaded on 14 January 2014)
2014年を迎えました。今年も皆さまに、タカ類・ハヤブサ類との素敵な出会いがあるよう願っています。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。今日から、タカ類・ハヤブサ類の識別と生態についてシリーズで書いていきます。今回は、その(1)で、♂成鳥(MA)・♀成鳥(FA)・♂幼鳥(MJ)・♀幼鳥(FJ)の識別力を身につける方法です。
今回紹介する識別の上達法
超望遠レンズ付きデジタル一眼カメラの撮影に堪能な人(A)とあなた(B)の2人で、あるいは3人以上で観察します。Aさんは双眼鏡を使わず、カメラで出現したタカ類・ハヤブサ類の写真を撮ることに専念します。あなたは写真を撮らず、双眼鏡だけで出たタカをじっくりと見ます。細かい部分までよく観察して、ある程度時間がたったら、あるいは見えなくなったら、「あれは、ハイタカの♀の幼鳥と思う」 などと言います。それを聞いて(A)の人は、「ピンポーン、当たりです」 とか、 「残念でした。♀ではなくて、♂の幼鳥でした」 などと言います。(A)の人が、タカ類・ハヤブサ類の識別にあまり詳しくない方なら、あなたがカメラの画像を見せてもらって、自分で、「うーん、残念。幼鳥ではなくて、♀の成鳥でしたね」 などと判定し、反省したりします。
注意点
(1) あなたはフィールドスコープや双眼プロミナーを使わず、手持ちの双眼鏡のみで観察をします。私は今はキヤノン12×36ISⅡという防振双眼鏡を使っています。
(2) デジカメ画像を見る時は、ディスプレイを小型ルーペでじっくりと見ます。換羽のようすや羽縁、翼縁、虹彩の色などもしっかりと見ます。ルーペはポケットの中に常時入れておきます。
(3) 幼鳥の♂か♀かの判定には、必ず複数の画像を見るようにします。体のプロポーションやシルエットが、見る角度によってかなり異なることがあるからです。
(4) 後ろ姿の写真も、何かと参考になります。人に見せたり、ネットにアップすることができないような写真も、識別には役立つことがありますので、後ろ姿の写真や見送り写真も撮影します。
「正解」の時、 「不正解」の時
「正解」の時 …
どの観点が一致していたか、2人で話をします。観点は幾種かの♂成鳥のように1つで十分な場合もありますし、3つか4つぐらい必要な時もあるでしょう。
「不正解」の時 …
たとえば (B)が「チゴハヤブサの♂の成鳥だと思う」 と言ったが、実際は 「♀の成鳥」 だったという時、その原因を探ります。双眼鏡ではすね毛の縦斑はなかなか見ることができないので仕方がないのか、あるいは、見えたはずなのに見逃してしまったのか、などが考えられます。
あるいは (B)が 「ノスリの幼鳥だ」 と言ったが、実際は 「♀の成鳥」 だったという時。虹彩の黄色が確認できたので幼鳥と判断してしまったが、ノスリの虹彩は2~3年たっても黄色いものや淡褐色のものがいるし、画像をよく見ると次列風切の翼端がわずかにでこぼこしていたので、やはり成鳥だった…とか。虹彩の色は、いろいろな場面でものすごく参考になりますが、しかし一方で、かなりの曲者です。気をつけなければいけないです。
その他の原因として、観察者の不注意だったのか、双眼鏡での観察の限界だったのか、気象条件が悪かったのか、タカ類・ハヤブサ類の出現角度・距離などの観察条件が悪すぎたのか、あるいは自分の識別力がまだまだ足りなかったのか…。その都度、一つ一つ反省していきます。
その他
・ (A)と(B)は、時々その役目を交代します。(A)さんが、写真を撮り続けたいなら、それはそれで別にかまいません。
・ ♂か♀か、成鳥か幼鳥か、どんな型(暗色型など)かを中心にして、可能ならば、年齢、亜種、個体差も観察します。
・ そのために、換羽の状況はどうか、欠損は左右対象なのか片側だけなのか、次列風切の翼縁は膨らんでいるかいないかなど、双眼鏡を見ながら一瞬にしてさまざまな項目をチェックします。
・ これらの訓練を繰り返していけば、あなたの 「識別力アップ」 は間違いなし! です。
では、問題です
下の写真を3秒ほど見て、すぐに目を離してください。写真はわざと小さくしてあります。
この個体はノスリですが、 「♂成鳥」、「♀成鳥」、「♂幼鳥」、「♀幼鳥」 の、どれでしょうか?
↓
↓ 答えは右端にあります。
↓
↓
↓
↓
↓
↓

(Uploaded on 1 January 2014)
冬の干拓地でのタカ類・ハヤブサ類の観察について、2013年2月16日付で「冬の干拓地 車での観察法」と題して書きました。ごく簡単にまとめると、
冬の干拓地を車で走行中、タカ類・ハヤブサ類を見つけても、
(1) 車を急停車させない。
(2) ガラス窓をすぐに下げない。
(3) 双眼鏡ですぐに見ない。
(4) ましてやカメラですぐには撮影しない。そして、大事なことは、
(5) 決してタカと目を合わせない。
ということです。私は最初の内のしばらくは下を向いているとか、センターピラーで目を隠すとか、中指と薬指の隙間からチラッと見る程度にしています。
以上のようなことを書きましたが、これらの注意点は、春の繁殖期のタカ類・ハヤブサ類の観察についてもほとんど同じことが言えます。
不注意に観察すると、あなたが観察した影響で、タカ類・ハヤブサ類は簡単に営巣を放棄してしまいます。特に、造巣期、産卵期や抱卵期は十分すぎるほどの注意が必要です。
では、どうしたらよいか。繁殖期に気をつけなければならないことはたくさんありますが、たとえば、
1 巣のある林の中へ入って行かない。ヒナが大きくなった頃に、入ってもごく短時間で戻る。
2 林の外からの観察でも、長時間にわたらないようにする。
3 できる限り、車内からの観察にする。でも、車を過信しない。
4 外のブラインドも過信しない。
5 対象のタカの警戒心についての個体差を見極める。初めは少し厳しめに考えておく。
6 現れたタカを双眼鏡やスコープでじっくりと見ない。
7 写真はなるべく撮らない。
8 定点観察では、長時間にわたり同じ場所で双眼鏡やスコープ、望遠レンズを使うことが多いが、知らず知らずのうちに繁殖に悪影響を与えてしまうことがある。
9 慣れないうちは、移動定点にする方がよい。
10 冬とおなじで、繁殖期でも、決してタカと目を合わせない。
11 農作業をする人のような感じで、タカに、「あんたには関心がないよ」というふうに思わせる行動をとる。つまり「無関心の関心」。
とにかく、細心の注意を払うことが必要です。できたら初めのうちは一人で行かずに、ベテランの人と一緒に観察を行うとよいでしょう。
(Uploaded on 6 July 2013)
寒風吹きすさぶ冬の干拓地でタカ類・ハヤブサ類を観察するには、やはり車がよいです。車をブラインドの代わりにするということです。半日車の中にいると運動不足になりますが、歩いて観察するよりもタカ類・ハヤブサ類は逃げません。
1 移動しない定点での観察
干拓地全体のようすをじっくりと把握したり、狩りの全体像をざっくりと見たりするためには、車を移動させない定点での観察がよいでしょう。車をとめる位置は、風向きや太陽光線を考えて決めることも大切ですが、干拓地全体が見渡せて、気持ちよく待てる場所が一番よいです。一般的には一つの干拓地のまとまりの南東の角あるいは南西の角で車を北向きにとめるとよいです。もちろんエンジンは切ります。ドアを開けるとティンティンと音がする車がほとんどですので、キーは抜いておきます。周りの音や鳥の鳴き声を聞くため、寒いですが窓ガラスはほんの少しでよいので開けておきます。こうして、最低でも1時間は待ちましょう。
2 車で移動しながらの観察
農作業をしている人や軽トラなどの作業車に迷惑をかけないよう気をつけて、また、田畑に自車が落ちたりしないように安全に回ることが大切です。スピードを出し過ぎたり、急にバックしたり、タカ類・ハヤブサ類を追いかけまわしたり、ましてや飛び立ちを撮影するためにクラクションを鳴らしてタカ類・ハヤブサ類を驚かせたりすることはよくありません。
タカ類・ハヤブサ類が近くの田に下りているところを発見したら、だいたい次のようにします。
① 距離が一番近い地点をやり過ごすように少し通り過ぎて、静かに止まり、エンジンを切ります。
② ウィンドウを下げず、ガラス越しに肉眼で見ます。この時、センターピラーで顔(目)を隠しながら、タカの方をちらっ、ちらっと見ます。タカと目を合わせないことが大切です。車でたまたま通った通勤の車を装うような感じで、「君には関心ないよ」と思わせます。
③ 少し経ってから双眼鏡で見ます。幼鳥か成鳥か、押さえている獲物は何かなどを観察します。
④ 時間が経って、逃げないだろうと思えてきたらキーをさして、ウィンドウを少し下げます。昔の車のような手動式の開閉はできませんので、静かにゆっくりと開けます(電動と手動と両方付いているとほんとうは嬉しいですが…)。タカの反応を見ながら少しずつ下げます。まだカメラのレンズは出しません。
⑤ タカが獲物をある程度食べて落ち着いたころにレンズをそっと出します。タカのほうから車を見ると、双眼鏡やスコープ、望遠レンズの奥にはあなたの「目」がしっかりと見えます。タカにとっては、ほんとうはこれは恐怖です。ですから、これくらい慎重に行動した方がいいです。
ただ、私はほとんどレンズは出しません。写真撮影もあまりしません。見るだけでも十分楽しいですし、タカ類・ハヤブサ類に無用な負荷をかけずに済みます。でも、余裕のある時や十分に遠い時は、時々写真を撮ります。
私は上の1と2を併用していますが、どちらかというと定点での観察が多いです。移動しながらの観察に疲れたら定点で、ということもあります。「定点ではなかなかタカ類・ハヤブサ類が見えない」と言う方もいますが、1時間くらいの間にはけっこうタカ類・ハヤブサ類が近づいてきたり、やや遠くの方で(あるいはやや近くで)ダイナミックな狩りをしたりするものです。待てば待つだけの価値はあります。さて、下の地図ですが、車ですべての道が通れて、水路が渡れるとしたら、あなたはどこを定点にし、どちら向きに車を置きますか。
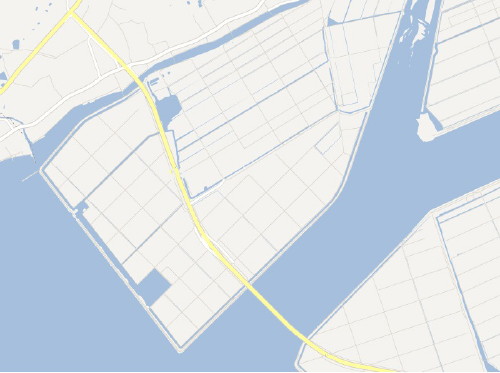
(Uploaded on 16 February 2013)
昔は、カーナビなどという便利なものはなかったので、珍しいタカが出たという情報が入ったら、地図とにらめっこでポイントの確認と自宅から現地までの走行経路を一生懸命に考えたものでした。いつしか地図が好きになり、暇があるといつのまにか地図を見ていたということもありました。北海道で車を借りたときも沖縄旅行に行ったときも、地図をたよりに走れば充分で、なんの不自由もありませんでした。
そういう理由もあって、カーナビが出始めたころ、私は購入や使用を躊躇していました。また、自分の「地図を読む力」が弱くなってしまうのではないかという危惧もありました。ところが、カーナビを使っても使わなくても、地図を読める人はいつまでも読めるし、読めない人はいつまでも読めないということがだんだん分かってきましたので、今はカーナビを使っています。使ってみればそれはそれでけっこう便利なものです。自車の位置が分かるという点がいちばんうれしいです。
ところで、あなたのカーナビの画面の上は進行方向ですか? それとも北ですか? 初期設定は自車の進行方向が画面の上になっていますので、そのまま使っていらっしゃる方が多いのではないかと思います。私も最初はそうしていました。ところが、ある日から画面の上を北に設定するようにしました。これはなかなか気分がいいものです。
画面の上が進行方向のままだと(もちろん利点もありますが)、
・ くねくねとした道を走ると、画面全体がくるんくるんとひんぱんに回転してしまう。
・ 自車の進行方向や地図の方角がひじょうに分かりにくい。
ところが、画面の上を北にすると、
・ 画面の回転がまったくない。ひじょうに見やすい。
・ 自車の進行方向がよく分かる。地図の方角はいつも画面の上が北。
・ 出発地から到着地までの走行経路のうち、どれくらい走行したのかが一目で分かりやすい。半分くらい走ったとか、あと 1/4 くらいで到着するとかがよく分かる。
・ 脳が刺激されて、なかなかいい感じです。
(Uploaded on 26 February 2012)
先週、2月7日に upload した 「コチョウゲンボウは小鳥にとって 脅威!」 に対して、4通のメールをいただきました。ありがとうございました。「コチョウゲンボウの写真はよく撮るんですが、なかなか狩りの全体は見ることがありません」、「獲物を食べているところやじっとしているところは、ときどき撮影できます。狩りの全体はあまり見たことがないです」などの内容がありました。狩りの全体を見ることが少ないのは、多くはきっと、写真撮影のせいだろうと思われます。土塊や木の枝にとまって獲物を探しているコチョウゲンボウを見つけたとき、すぐにカメラを出して撮影を始めると、コチョウゲンボウは必ず撮影者を警戒しはじめます。カメラのレンズの奥に撮影者の眼光がはっきりと見えて、タカにとっては恐怖にもなります(これは双眼鏡やフィールドスコープでも同じですが…)。できたら今いる場所を早く離れたいなと思うことでしょう。これではコチョウゲンボウが「ありのままの姿、自然の姿」を見せてくれるはずがありません。
このことは、物理学で有名なハイゼンベルクの「不確定性原理」に似ています。この原理は、電子などのひじょうに小さい粒子を観察するとき、当然電磁波などの光を当てなければいけないのですが、光の粒あるいは光の波を当てると、その光によって粒子の運動そのものが影響を受けますので、光を当てる前のほんとうの電子の様子を正確に観察することができないということを言っているものです。数式では下のように書かれます。
△χ△p≧ h/4π とか εqηp ≧ h/4π
h はプランク定数で、 6.626×10-34ジュール・秒、 △χ や εq は測定する電子などの位置の誤差、 △p や ηp は位置を測定したことによって電子などの運動量(=質量m×速さv)に生じてしまう乱れです。
2012年1月中旬の新聞各紙に、名古屋大学の小澤正直教授が 「小澤の不等式」として提唱していた数式がついに実験によって証明されたとして、大きく報道されましたね。その不等式は、
εqηp + σqηp + σpεq ≧ h/4π
です。これも各新聞に載りました。先の式と比べて2つの項が加わりました。学生時代に「常識」として習ってきたものが、実は正確ではなかった…ということになりましたが、光を当てると物質の位置に誤差が生じるということは確かです。ハイゼンベルクは1927年に不確定性原理を導いて、量子力学の確立に大きく寄与しました。そして、1932年に、なんと31歳という若さでノーベル物理学賞を受賞したドイツの天才ですが、まだ、古典力学から完全には離れられなかったということでしょうか。余談ですが、「ナチスはなぜ原爆を作ることができなかったのか」という話題になると、必ずハイゼンベルクの名前が出てきます。私には真実はよく分かりませんが…。
話が大きくそれてしまいましたが、コチョウゲンボウを観察するにあたって、「写真を撮る」という行為はコチョウゲンボウの状況・状態に大きな影響を与えてしまいます。撮った写真は不自然なものになりやすいですし、コチョウゲンボウはそわそわして逃げてしまいます。
これは何もコチョウゲンボウに限った話ではありません。雑誌やネット上で目にする多くのタカの生態写真は、タカがほぐれた状態ではありません。多少なりとも「警戒した」状態で撮影されているものが多いのです。その反対に、稀ではありますが、タカがほぐれた状態で撮影された写真を見せてもらうとなんだかうれしくなって、ほっとします。ほぐれたタカ、落ち着いたタカ、警戒していないタカは、たとえば、
〇 片足で立って、もう片足はおなかの羽毛の中に入っている(手袋を引いている)。
〇 体が直立に近くなっている。
〇 首が伸びていない。
〇 体中の羽毛がやや膨らんでいる。
〇 背中に白い部分(羽のうちの白い部分)がたくさん現れ、斑(まだら)のように白くなる。
などです。体が水平に近かったり、今にも飛びたちそうな状態とは全然違います。
私も多少は生態写真を撮影しますので、あまりほかの人に言える立場にはないのですが、でも、タカが緊張したような写真や迷惑そうな顔をしている写真、そわそわしている写真はできたら撮影したくないです。自分が撮った写真のタカがあなたを警戒しているのかどうか、分かりますか。
(Uploaded on 13 February 2012)
今新しく発売されるコンパクトデジタルカメラや家庭用ビデオカメラには、ほとんど手ぶれ防止機能( IS Image Stabilizer )が付いています。一眼レフカメラの超望遠レンズや他のレンズにも手ぶれ防止機能が付いているものが多くなってきました。将来的にはこれら以外のさまざまな機器にもIS機能が付いてくることになるでしょう。
ただ、双眼鏡の世界では、現在この機能はまだまだ稀なものです。ドイツのライカやカールツァイス、オーストリアのスワロフスキーなどの世界的に優れた最先端の光学性能を持つ双眼鏡にはまだ付いていません。でも、将来的にはきっとすべての双眼鏡に手ぶれ防止機能が付いてくることになると私は思っています。以前、「マーリン通信」に書きましたが、私は、当時の価格15万円ほどのライカの10×50 を長期間愛用していました。でも、ある時、手ぶれ防止機能のついた双眼鏡の性能の良さにほれこんでしまい、キヤノンの12×36ISⅡにしました。Ⅱですので、同じ12×36ISの後継機です。デザインや性能がよくなっています。レンズの性能、シャープさだけから言えば、この双眼鏡よりもライカのほうが優れていましたが、この双眼鏡のIS作動時は、飛んでいるタカの体の筋肉の動きまでもが実にリアルによく見え、生物の躍動感が伝わってきます。一度使い慣れてしまったら、IS双眼鏡でないといけなくなってしまいます。

キヤノンからは、12×36 ISⅡの他に、18×50 IS、15×50 IS、10×42 L IS、WP10×30 IS、8×25 IS が販売されています。私の個人的な思いとしては、もっともっと技術が進歩して、タカの渡り観察などでよく使われている自作の双眼プロミナーの代わりになるような、25×60、30×60 くらいの防振双眼鏡が発売されるといいなと思っています。きっと、手持ちで生き生きとした世界をとらえることができるようになることでしょう。
また、キヤノンの誇る世界的な技術力や一眼レフカメラEOSシリーズの膨大なEFレンズ群の性能の良さを考えると、今まで以上にクリアーで美しい見え味のIS双眼鏡が今後発売されるのではないかなと期待しています。
(さらに)
できたらフィールドスコープにも手ぶれ防止機能を付けてほしいものです。三脚に載せていても強風で像がぶれることがよくあります。これが止まればありがたいです。車の中でスコープを使うときは通常はエンジンを止めますが、止められないようなときにはエンジンの振動で車全体が揺れて、像が小刻みにぶれます。これも止まってくれるとありがたいです。
そこまでは…と思われる方は、電波時計を考えてみてください。福島県と佐賀県・福岡県境にある2つの標準電波送信所からの標準電波(JJY)を受信することで、年月日と曜日と時刻が自動的に正確に合わせられます。出始めのころは高価な時計だったのですが、今では千円台の目覚まし時計や腕時計、卓上カレンダーにもこの機能は当たり前のように付いています。双眼鏡やスコープのISも付くのが当たり前になってくることでしょう。
【2011年10月20日にニコンから防振VRスコープ( Nikon EDG 85 VR と 85-A VR)が発売されました。定価は35万円ほどです。うれしいニュースになりました】
(Uploaded on 20 November 2011)
以前は大きくて重いニコン600mmのレンズを使っていましたが、最近は使い勝手がよいので、Canon EF400mmF5.6を常用レンズとして使っています。三脚がない方が機動性がありますので、いつでも手持ち撮影です。樹木の幹や車のボディーなどに押し当てて少し固定することはありますが、手持ちのほうが慣れています。「どうして大きいレンズを使わないの?」と聞かれることがありますが、最近は、あの大きな巨砲に支配されてしまいそうで、ためらうのです。私は写真撮影が中心ではないですし、カレンダーのようなきれいな芸術写真を撮りたいわけではないですので、多少、ブレたりボケたりすることはあってもいいのかなと思っています(偶然、ピントが合ってしまう時もあります)。
45年ほど前のことですが、自宅のはなれの一室を改修整備して写真用の暗室にしました。フィルムの現像や焼き付けをしていました。もちろん当時は、白黒写真でした。カラー写真も出回り始めていましたが、ラボの処理でもまだまだ発色が良くなくて、私はモノクロ写真のほうが好きでした。
野鳥の写真を撮るようになってからは、もっぱらコダクローム64という、ISO感度が64と低く、ラチチュード(露出の許容度)のひじょうに狭いスライドフィルムを使っていました。感度がたいへん低いので、絞りはもちろん開放に決まっていました。これは譲れない条件でした。この頃の習慣が身についているからでしょうか、デジタルカメラの時代になってからも、絞り開放は当然のこととしていました。記念写真や旅行の写真など一般の写真を撮る時には、絞りは適度に絞るのは昔から常識で、開放で撮影することはなかったのですが、先のような事情があったので、野鳥の撮影には、最近までずっと開放のまま使っていました。そんなわけで、ピントの合わない写真を大量に撮っていましたが、最近、絞りとISO感度を見直して、f8、ISO800で撮ってみたら、今までよりもよくピントが合って、ノイズも思ったほど出ていないことが分かりました。下の写真は、最近、タカの渡り観察中に撮ったサンショウクイの群れです。

これからは、私はレンズを絞って使います。
(後日記)
Canonの技術者が書いているページを見ていたら、「長焦点の大口径レンズは絞り開放で最高の解像度が得られるように設計されている」 との記事を見つけました。新しいレンズではそうかもしれません。
(Uploaded on 2 October 2011)
Jerry Liguori著、『 Hawks at a Distance - Identification of Migrant Raptors -』 が、2011年4月、「全米10万人の鷹隼ファンにとっての決定版必携ガイド!」として出版されました。
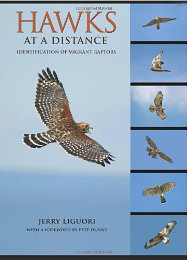
ペーパーバック版は、Amazonで1,475円です。洋書購入は、珍しく円高の恩恵を感じる一時です。21.6×15.7×1.5 cm、216ページ、英語です。出版社はPrinceton Univ. Press、ISBN-10:0691135592 です。全面カラー写真が19枚、カラー写真が558枚、モノクロ写真が shapes として896枚掲載されています。他にハードカバー版もあります。
北米で渡るタカ29種を扱っています。日本との共通種は、オオタカ、ハイイロチュウヒ、ケアシノスリ、コチョウゲンボウ、ハヤブサ、シロハヤブサ、ミサゴ、イヌワシの8種です。亜種に違いがありますので、体色などは当然違ってきますが、シルエットはほぼ同じです。この本の特徴は ”at a distance (遠く・やや遠く)”を飛んでいるタカの識別に重点を置いていることです。そのため、ひじょうに実戦的です。種の違いはありますが、日本でも考え方が役に立ちます。
数多い写真の中で、渡り途中のコチョウゲンボウの写真が気に入りました。下の写真です。日本では、なかなかこういう写真は撮れないですね。コチョウゲンボウは渡りの観察中にはあまり通過しないですから。私も自信を持ってコチョウゲンボウといえる渡りを観察したのは、今までにただ1回だけです。伊良湖岬の恋路ヶ浜駐車場前の民宿の屋上にいた時、斜めに猛スピードですっ飛んでいくところを見ました。この他にも各地で、「コチョウゲンボウ!?」と胸をときめかす個体がありましたが、みな、チョウゲンボウでした。チョウゲンボウも急降下したり、素早く飛んだりして、コチョウゲンボウとまぎらわしい場合が多いです。?のままの個体もいますが、何とも断言はできません。この本によると、コチョウゲンボウはチョウゲンボウに比べて、全体的に、より stocky(がっちりした・頑丈な)で、飛行中は、「fly with power, speed, and stability」で、はばたきは「with quick, forceful wing beats」と記述されています。

さて、この本には全29種のうち19種について、下の写真のようなあらゆる方向からのシルエット写真が付いています。この著者の5年前の前著『 Hawks from Every Angle: How to Identify Raptors in Flight 』 がここにも生かされているようです。
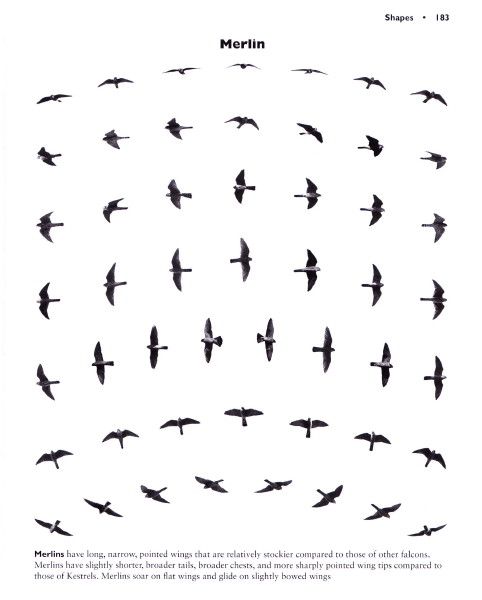
1,475円(送料無料)でこの内容ですから、購入価値は大きいですね。昔は50日かかって船便でイギリスから取り寄せ、代金を送るのに多額の手数料がかかる面倒な為替を作って郵送していたのが、今ではなつかしく感じられます。
(Uploaded on 1 August 2011)
冬のタカ類・ハヤブサ類を観察するのに最も適した時間帯はいつでしょうか。もちろん、十分に時間があれば夜明け前から日没後まで観察すればよいのですが、仕事や用事があって、それもなかなかできるものではありません。私の場合は、午前中だけ観察にいこうとか、夕方だけねぐら入りを見にいこうかということになります。

〇 河口の干拓地にて
まず、夜明け直後ですが、この時間帯はかなり期待できます。前日の日没前から14時間以上何も食べていないのですから、タカは空腹です。日の出前や朝一番はひじょうに動きが活発になり、オオタカなどが狩りをする瞬間が観察できるでしょう。
正午前後はどうでしょうか。私の見てきた範囲では、この時間帯もけっこう動きがあります。ハヤブサやコチョウゲンボウがよく狩りをしています。
日没前はどうでしょうか。私の経験では、この時間帯もひじょうに良いと思います。写真を撮るには光量不足だったり、色が赤っぽくなりますが、ねぐら入りするチュウヒ、ハイイロチュウヒ、コチョウゲンボウなどや、就塒前に獲物をとるタカなどがまさに入り乱れて飛び交うときがあります。この干拓地周辺に、こんなにたくさんのタカがいたんだなと何度も思うことがありました。
まとめると、河口の干拓地は、いつ行っても一日中、それなりの成果が期待できそうです。
〇 自宅近くの雑木林にて
2011年1月29日のことです。この日、午前中は自宅のガス給湯器が故障してその修繕に業者が来ることになっていましたので外出できませんでした。午後は2時すぎから仕事が入っていましたので、暇があったのはお昼前後のみでした。お昼ごはんを食べた後、運動不足を感じたので、時間的な余裕はなかったのですが自宅から車で2~3分で行ける雑木林を軽く歩くことにしました。午後1時20分から1時50分までのたった30分間だけでしたが、その間になんと5種類のタカに会えました。
ミサゴ1 ♀成鳥がため池の水面上の杭で魚を食べていました。
トビ4 上空飛翔していました。1羽は幼鳥。
ハイタカ2 成鳥1羽は水平に、紡錘形になって雑木林に突っ込んでいきました。
幼鳥1羽はカラスと対等バトルをしていました。
ノスリ1 飛翔中、翼をMの字にして急降下していきました。
オオタカ1 ♀幼鳥が1羽のハシボソガラスに執拗にモビングされていました。
この雑木林は、早朝や夕方はあまりタカが出ません。一番いいのは、午前11時頃~午後3時頃です。冬場はこのほかに、チョウゲンボウ、ツミ、オジロワシ、オオワシなどを見ましたが、皆11時すぎでした。「探鳥は早朝から!」というのは繁殖期の鳴禽類の観察などにはよくあてはまりますが、すべてにあてはまるわけではないですね。同じフィールドを、ある日は早朝に、ある日は午前中に、そして午後に、夕方に、夜に、というふうに行くといろいろ傾向が分かってきます。何かにつけ、決めつけはよくないですね。
(Uploaded on 17 February 2011)
「夜明け前に現地へ到着!」 これが私のホークウォッチングの基本です。例外もありますが、繁殖期・渡りの時期・越冬期、いずれも、夜が白々と明ける前に目的地に着くようにしています。なぜそうしているかというと、その時が、タカ類・ハヤブサ類の一番活発な時間で、いきいきとしたタカの生態が見られるからです。
朝が早いと就寝する時刻も早くなり、いつの間にか自然と、一年中、仕事の日も休みの日も早寝早起きが習慣になってしまいました。
〇 朝 食
夏場の、日の出がひじょうに早いときでも十分な朝食を自宅で食べて出かけます。ご飯に副食、そして常に3種類ほどのフルーツを食べます。朝食で体中の働きを覚ましてから車の運転をすることが、安全運転につながるものと思っています。
〇 昼 食 (4つの方法)
1 コンビニでおにぎりを買う
コンビニは、短時間で、サッサッとおにぎりを買うことができますので、もっとも手軽で、文字通り、非常に Convenience です。セブン-イレブンの日本第1号店が、東京都江東区豊洲にできたのが、昭和49年5月とのことです。

私は、愛知県にはまだほとんどコンビニがない昭和52年頃にホークウォッチングを始めましたので、最初の頃はコンビニを使うことができませんでした。コンビニが急成長しだしてからは、おにぎりを時々は買ったものでした。
ところがある時、買うことをやめました。その理由は、あまりおいしくない(まずい!)ということに気づいたからです。コンビニ食にはいつまでたっても添加物あるいは人工物がたくさん使われています。しかしながら、どうしてもコンビニを利用せざるを得ない時があります。そんな時はしかたがないので、値段の高い一個170円ほどのサケのおにぎりとあんぱん1個、バナナ1本を買います。弁当はめったに買いません。飲み物はできる限り自分で淹れたお茶か、水筒に入れた「サントリー 南アルプスの天然水」です。
2 自分でおにぎりを作る
ぜったいにお薦めはこれです。朝のあわただしい時におにぎりを作るのはたいへんだと思われるかもしれませんが、慣れてくると、意外と短時間で作ることができます。コンビニ食の添加物を思うとこれはやめられません。前の夜のうちに入れる具を用意しておいて、皿にのせたラップにご飯をのせて、そのままラップごと軽く握るだけです。具は、シャケ、塩昆布、梅干し、しそかつお、ふりかけが多いです。1つのおにぎりに、のりを2枚くらい巻くと風味が増してよいです。おにぎりについてはいろいろなウェブページがありますので参照してください。
3 レストラン・食堂・インターチェンジで食べる
これは、ごく稀にします。どちらかというと、一緒に行く人の好みや考え方に影響されます。そば屋さん、うなぎ屋さん…と、おいしいものを食べるときもありますが…
実は、ある時、こんなことがありました。
5人で、山間部へミサゴを見に行ったときのことです。日本では、ほとんどのミサゴは海岸部で営巣しています。今回、大陸のように、山間部の湖のほとりの樹木に営巣する可能性があるという情報で出かけたわけです。その日は、早朝からある干拓地で観察をして、その後、ミサゴ観察にいきました。楽しく話をしながらの走行中、お昼になったので、道路沿いの食堂で食べてから現地へ行きました。先に来ていた人が、「ついさっきまであの木の枝に止まっていたけど、飛んでいってしまったよ」と。すると、同乗してきた一人が、「食堂に寄ろうと、〇〇さんが言ったからだよ。バードウォッチングの時は、外でおにぎりを食べながら観察しなきゃダメだよ。時間の使い方が悪いよ」と。たしかに、なかなか出てこないワシやタカを見るときは、根気勝負ですね。じっくり構えて、時間をかけて、ただただ出現を待つのみというときもあります。そんなときには、やはり、おにぎりを食べながら、野外で、観察をしながらになるのは当然でしょう。
4 帰って自宅で食べる
私は今は、上の1~4のうち、もっぱら2です。自分でおにぎりを作っています。朝、ご飯が少なくておにぎりが作れなかったり、昼はみんなで楽しくやろうというときは、3もあります。特に、海岸部での観察のあとは美味しい魚介類が楽しみです。
(2015年11月追記 コンビニのおにぎりや弁当、おでんには今も甘味料のソルビット(ソルビトール)や品質保持のためにpH調整剤、グリシンという炊飯改良剤などがたくさん使われています。)
(Uploaded on 27 October 2010)
大きいもの、重いもの、かさばるものは基本的になるべく避けて、身軽に、楽しく鳥を見たいというのが私のコンセプトです。観察(ウォッチング)中心で、撮影は二の次です。のんびり、ゆっくり、長時間タカを見たいという人は参考にしてください。
タカ類の個体識別をしなければならない時は、やや大きいレンズも使用します。
双眼鏡
ライカの10×50を長期間愛用していましたが、ついに、手ぶれ防止機能のついた双眼鏡に負けてしまいました。今は、キヤノンの防振双眼鏡12×36ISⅡを使っています。ISは、イメージスタビライザーで手ぶれ防止機能のことです。レンズの性能、シャープさから言えば、ライカに勝るものはないのですが、この双眼鏡のIS作動時は、飛んでいるタカの体の筋肉の動きまでよく見え、躍動感が伝わって来ますので、使い始めたらもうやめられません。欲を言うと、双眼プロミナーの代わりになるような高倍率の、25×60、30×60くらいのIS双眼鏡が発売されることを願っています。
山登り等、補助的に軽いニコン10×25ASも使っています。
スコープ
ニコンED60mm(アングル・傾斜型)
コーワTSN-774(ストレート・直視型)
を使っています。諸外国、特にバードウォッチング先進国では、傾斜型の方がよく売れているそうで、私もかなりの間、傾斜型のみを使ってきました。練習を重ねて傾斜型で飛翔中のタカの動きを捉えることができるようになってきましたが、タカの渡りではストレートが見やすく、天頂付近を除けば楽です。
雲 台
スコープ用に、マンフロット社製の小型ビデオ雲台を使っています。動きが非常にスムーズですので見え味がシャープです。
大型三脚の雲台も、マンフロット社製のブリッジ型ビデオ雲台です。
車の中からの観察では、カーウィンドウ用雲台を使っていますが、これはなかなか便利です。
三 脚
スコープ用に、ジッツォ社製の中型ではありますががっしりしたものを使っています。
レンズ用には、ベルボン社製のカルマーニュN840を使っています。
旅行用あるいは手持ち時の補助用として、軽くて短くたためるが強度はある一脚を使用しています。
カメラ
キヤノンEOSシリーズを使っています。マニュアル(M、手動) で、撮っています。
レンズ
以前はニコンのニッコール600mmF5.6を使っていましたが、今はキヤノン製品を使っています。
デジスコ用カメラ
昔、一世を風靡した200万画素のソニーサイバーショットDSC P2をずっと使っていましたが、さすがに古くなり、今は キヤノンIXY31Sを使っています。アダプターで取り付ける方式ではなく、手持ちで、接眼部分にそっと持っていきピントを合わせて撮っています。アダプターがなくても十分に撮影できます。また、ホームページに載せる程度なら、大きい画素数もいらないです。
サングラス
双眼鏡もそうですが、目に関わるものは、安物はだめですね。バードウォッチャーにとって最も大切な「肉眼」を守るためにも、いい光学機器を使いたいものです。幸い今は左右ともに、1.5~2.0の視力がありますので、度の入っていないニコンのサングラスを使っています。
椅 子
渡り観察用の椅子は、折りたたんで円筒形のズック袋に入る椅子を使っています。リクライニングできるので、長時間待ち続ける渡り観察時に、楽な時間を過ごすことができます。他に、折りたたみの軽いキャンプ用椅子と踏み台としてホームセンター等で販売されている折りたたみ椅子を使いわけています。
乗用車
スバル フォレスター2000ccに乗っていましたが、2016年秋からは、SUBARU XVに替えました。選んだ基準としては、海外向けに大型化したフォレスターよりもわずかながら小型であることと、最低地上高が約20cm確保されていることです。
おにぎり
食中毒が心配な夏場を除いて、どんなに朝早くても、自分でおにぎりを作っていきます。具を工夫することで、コンビニのおにぎりよりもはるかに美味しく、健康に良いですよ。
(Uploaded on 13 August 2009、以後適時修正しています)
あなたが、今、観察中の、今、目の前にいるタカが何を考えているか? 今、双眼鏡で見ているタカが何を考えているのか、分かりますか?
こんなことを聞くと、きっと「自分以外の他の人が何を考えているのか分からないのに! ましてや、人間とは種が異なるタカが何を考えているのか人間に分かるはずがない! 思考回路も感じ方も人間とは違うんだから、そんなことが分かるはずがない!」と言われてしまいそうです。
では、そのタカはこのあとすぐ、次の瞬間、どんな行動をとるでしょうか? 例えば
(木の枝にとまっているなら)
飛び立ってしまうでしょうか? 片脚で立って、もう片一方の脚は腹の羽毛の中に入れて、リラックスするでしょうか?
(飛んでいるなら)
遠くへ行ってしまうでしょうか? 旋回して近くの枝にとまるでしょうか?
(食料を食べているなら)
観察者が近づいたことで、すぐに飛び立ってしまうでしょうか? 食料に執着があって、飛び立たずに食べ続けるでしょうか? 等
このあたりの質問になると、ものによっては、なんとか予測がつきそうです。つまり、タカが考えていることが多少は分かってきそうです。
タカが落ち着いてくると、まず、
(1) 体全体が、垂直に近くなってくる
(2) 羽毛をふくらませて、ブルブルッと、体中を振動させる(水に濡れた犬が、よくしますね)
(3) 片脚を曲げて、お腹の羽毛の中に完全に包み込む
(4) 首が短くなり、全体として丸くなる
(5) 背面の羽毛に白い部分が出てくる
(左目次の「鷹隼類全般」フォルダの「部分白化個体ではありません!」参照)
と、変化していきます。
逆に、緊張してくると、
(1) 体が水平に近くなってくる
(2) 体中の羽毛が体に張り付いて、体がスマートに見える
(3) 鋭く周りを見つめる
(4) フンをする こうなるとすぐに、飛び立つことが多いでしょう
こういうことが分かってくると、ある程度、次の行動の予測がついてきますよね。
下の写真を見てください。

写真は、冬のハヤブサです。午前8時37分に南から飛んできて、この鉄塔にとまりました。しばらくして、片脚でとまり、落ち着いてきました。しかし、脚はそのままで、周りをキョロキョロ見始めました。落ち着きなくキョロキョロとし始めましたが、体は垂直で、脚は片脚のままでした。このあと、しばらく、この鉄塔にとまっていました。
ところが、このハヤブサは、9時45分に、獲物を見つけて急降下し、猛スピードで耕地に突き刺さるように視界から消えていきました。水路から飛び上がったカモが数十羽見えましたが、獲物を捕ったその瞬間は見えませんでした。鉄塔にとまってから、68分後でした。ずっと、落ち着いてはいましたが、頭の中は獲物のことばかりで、目でキョロキョロと獲物を探し、どの方向へどう飛んでどう捕ろうかと考えていたことでしょう。風も読んでいたのでしょう。私もこれだけの時間、見続けて付き合うと、友達になったような感じです。何を捕まえて、どこでどのように食べているのかとハヤブサを探しましたが、残念ながら、見つかりませんでした。
私自身が何を考えているのか、自分でも自分のことがよく分からないですし、次から次へと考えが移り変わっていってしまうのに、タカの考えがはっきりと分かるはずはありません。しかし、タカも人間も同じ、脊椎動物の仲間です。同じように心臓があり、肺があり、肝臓・腎臓…、骨格、筋肉まで同じようにあって、目、鼻、口…、脳があるわけです。基本的には、かなりの部分で共通点があります。遺伝子配列もかなりの部分が同じでしょう。お互いに、理解できないはずがないと思っています。そのためには、注意力をとぎすまし、忍耐強く長時間観察し、お互い同じ仲間だと思う気持ちが必要と思います。
(Uploaded on 26 June 2005)
タカ類・ハヤブサ類の識別法と小鳥類の識別法は違いますよと、今までも何度か述べてきましたが、観察法もタカ類・ハヤブサ類と小鳥類とでは少し違います。ちょうど、小鳥類の観察法とシギ・チドリ類の観察法が違うようなものです。
小鳥類を中心に観察するとき、一般的には林道を歩いたり一定のラインを決めてそこを歩いて観察したりします。タカ類・ハヤブサ類を見ようとしてこのような歩き方をしても、なかなかタカ類・ハヤブサ類を見ることはできません。例外的な話ですが、以前、5月初旬に原生林の林道を歩いていて、運良く目の前の枝にツミがとまってこちらを向いたことがあります。幼鳥なのに虹彩が深紅で、ツミの♂は生まれて満1年にならないうちに虹彩が赤くなることがよく分かりました。でも、こんな運の良いことはそんなにしばしばありません。木が生い茂った林道を歩いていてタカ類・ハヤブサ類をたくさん見ることは、あまり期待できません。
私も昔は探鳥会に参加していたことがありますが、見晴らしのよい干拓地や秋の渡りの時期の探鳥会をのぞけば、このところあまり参加していません。それはタカがあまり見られないからです。
タカ類・ハヤブサ類の観察に一番適した場所は、見晴らしのよい定点です。遠くの山が見えるような所で、動かずに、少なくとも2~3時間は観察を続けるとよいでしょう。きっと、お目当てのタカが出てきます。すぐに現れなくても、そのうちきっと姿を現します。
今日、4月24日は、家の近くの定光寺というところで観察しました。ハイタカとノスリが出ただけでしたが、この地域ではそろそろ見納めになるタカたちです。名古屋市の隣の町ですが、遠く、石川県の白山連峰がくっきりと見えました。観察地の周りの新緑の萌え出るような薄緑色の葉とともに、実に新鮮でした。つい1週間前の日曜日(4月17日)に火事になった高座山の様子もよく見えます(下の写真)。地下に航空自衛隊の弾薬庫がある山なので、ニュースで火事のことを聞いたときはびっくりしました。

定点は、数カ所設定しておくとよいでしょう。今日はここにしよう、今日はどこにしようかなと思うことも、なかなかおもしろいですよ。もちろん、ハイタカのよく出る定点、クマタカの出るところ、〇〇の出るところというように、いくつかあると楽しめます。ため池のほとりのやや広くなっている見晴らしのよい地点も、違った意味でおもしろいですよ。
さて、定点でじっとしていると、タカがよく見えることの他にもよいことがいくつかあります。特に冬場は、いろんな小鳥類や水辺の鳥たちが、次から次と移動して、じっとしている私の近くへやってきます。こちらへ挨拶に来るような感じです。こちらが動けば逃げていってしまう小鳥たちも、じっとしていれば、かなり近くまで警戒せずに寄ってきます。双眼鏡がいらないほどの距離に、ルリビタキが5羽まとまってやってきたり(嘘みたいなほんとの話)、ベニマシコが群れて来たり……と。先ほどの、「ため池のほとりのやや広くなっている見晴らしのよい所」というのはこれがかなう所です。観察者が動かずじっとしていれば、ほんとうにいろんな鳥が手に取るほど近くまでやってくることがあります。鳥は追いかけ回したらダメです。警戒心を解いて向こうからこちらへ来させれば、自然なしぐさも見ることができます。
(Uploaded on 24 April 2005)
秋のタカの渡りにはまだ少し間がありますが、そろそろ識別の練習はいかがでしょうか。初心者の方は、下の例1のようなものを作っておくと、非常に役立ちます。例2は練習です。
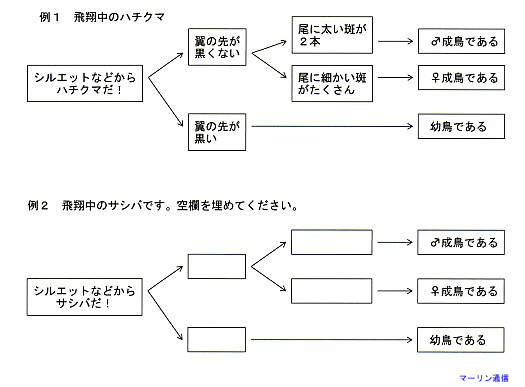
それぞれのタカでこれを作っておくと便利です。実力がつきます。
(各種の成鳥幼鳥雌雄の区別、ノスリ類3種の区別、ツミとハイタカの区別など)
アマツバメ類、ヒタキ類など、いろいろな他の鳥にも応用がききます。
( Uploaded on 7 July 2002)
タカ類・ハヤブサ類の見つけ方
・ 探鳥中は地面や木ばかり見ている人が多いようですが、小鳥類を発見するには最適です。しかし、タカ類・ハヤブサ類を見つけるには、ひんぱんに上空を見るとよいでしょう。
・ 山道をくねくねと歩いていると、次々と新しい景色が見えてきますが、新たに見えてくる遠くの枯れ木や止まりやすい木の枝をひんぱんに見るとよいでしょう。何かがとまっている可能性が大きいです。
・ あまり、鳴かないですが、タカの鳴き声にも耳を澄ましましょう。意外と鳴いていることがあります。
・ カラスが出てくると、「なんだ、カラスか」と言う人がいますが、カラスはすごく助けになります。カラスがタカの存在を鳴き声や飛翔によって教えてくれることが多いからです。
・ また、カケスやほかの小鳥が騒いでタカの存在を教えてくれることがあります。
・ 小鳥やハト、カモの群が急に飛び立つことがあります。その時は、必ず原因があります。あなたが近づいたからかもしれませんが、接近してきたタカに驚き、あわてて飛び立つこともよくあります。
・ トビが現れると、「なんだ、トビか」と言う人がいますが、トビは上昇気流の存在とその位置を私たちに教えてくれます。タカもトビの動きを見ていますので、トビが現れた後はタカも現れやすくなります。
・ 時間はいつ頃がよいか。難しいですが、一般には、夜明け直後の早朝と日没直前の夕方が、一番よいでしょう。昼前後は、動きが止まることが多いです。
タカ類・ハヤブサ類の識別が難しい理由と対策
タカ類・ハヤブサ類の識別が難しいと言われますが、ほかの仲間の識別も、本気でやってみると、なかなか難しいです。しかし、たとえば、シギ・チドリ類は、地上に下りているものをフィールドスコープで観察できることが多いですし、カモ類も、水面で、じっとしていることが多いですので、ある程度は、楽な面があります。タカ類・ハヤブサ類の識別が難しい理由を考えてみます。矢印の後は、そうするとよいかなという点です。
① 生態系の頂点に位置するため、個体数がかなり少なく、見る機会が少ない。一日、山を歩いても一羽もタカが出ないことがあります。出ても、トビとノスリだけだったということがよくあります。
→ 干拓地や渡りのポイントなど、タカの多いところへ観察に行って、多くのタカを見て、識別の訓練をする。
② 飛んでも一瞬しか見られないことが多く、じっくり観察できない。見やすい青空バックでゆっくり上空を低く飛ぶことは少ないですね。
→ 渡りのポイントへしばしば行って、識別の訓練をする。
③ 木に止まっても、たいていは遠く、それも近づけばすぐ飛び立ってしまう。近くの木にのんびりと止まっていることが少ない。
④ 識別が、飛翔中心になる。分かりやすいカモ類でも、飛翔のみで瞬時しか見られなかったら識別が難しいでしょう。
→ タカが出た瞬間に、どこを見るか、頭の中で整理しておきましょう。識別ポイントを常に意識する。
→ 双眼鏡はよいものを使い、しかも、使い分ける。私は、車の中からの観察や、渡りのポイントでの観察では、ライカ 10×50を使用しています。重いですが、よく見えます。Zeiss よりも気に入っています。山を歩いたり、写真撮影をしたりするときは、(あまり、性能がよくありませんが)、Nikon の軽いものを使っています。
⑤ 羽ばたき、急降下、ホバリング、ディスプレイの時は形が違って見えます。注意しましょう。
⑥ 風向きによって、シルエットは違って見えます。特に、強風時にはご注意を。
(Uploaded on 11 October 1999)
干拓地にはそれぞれの特徴や個性がありますが、ここでは愛知県の木曽川河口に広がる鍋田干拓を例に記述します。

(1) 夜明け前から日の出後1時間まで
私は鍋田干拓へ観察に行くときは、いつも夜明け前に現地へ到着するようにしています。「Early enough」 です。夜明け前後からの約1時間は、昼間の4~5時間ほどに匹敵する成果があるでしょう。どの鳥も人間に比べれば食べ物の消化吸収のサイクルが短く、朝は腹ペコですから、夜明けになるとまずは獲物をとりはじめるからです。冬場のこの時間は十分明るくなく、写真を撮るには不向きな時間ですが、観察にはベストタイムです。朝飯を食べたタカはひっそりとした場所に隠れて休憩し、あまり動かなくなります。私は10時ぐらいにはもう帰路につくことがあります。もちろん、それ以降の時刻にもタカは出現します。
(2) 獲物となる小鳥に注目し続ける
朝一番で、まずは小鳥の群れを見つけます。たとえば、カワラヒワ、ムクドリ、スズメなどの、20~200羽ほどの群れを見つけ、それに飽きずに付き合います。コチョウゲンボウ、チョウゲンボウ、ハイイロチュウヒなどが、必ずつっこんできます。
(3) 干拓地は獲物を捕るところ、ヨシ原はねぐら
朝一番に現れるタカは、おおよそヨシ原から現れて、耕地で獲物を捕ります。車の中から観察するなら、ヨシ原から少し離れてヨシ原の方に向かって車を前向きに止めるとタカがこちらに向かってくるので見やすいでしょう。
(4) 順光よりも逆光が良い時も多い
誰でも順光で鳥を見たいと思いますが、それはタカが獲物をねらうときもそうです。特に夜明け頃はそうです。従って良いチャンスを見たければ、逆光でタカを追うのも良いです。早くタカを発見でき、一部始終がよく見えます。
(5) 双眼鏡でしか見えなくなっても目を離さない
近くに現れたタカが、だんだん遠ざかっていくとそれで諦めてしまうことが多いのですが、しかし、双眼鏡で追うとかなり遠い所や高い所で小鳥を狙っていたり、実際に捕ったりすることが多くあります。
(6) 日没前後も良い
夕方薄暗くなり初め、写真を撮るには不向きな時間になった頃、多くのタカがすばらしく華麗な飛行を見せてくれます。この時間から約14時間、何も食べることができないので、その前に獲物を捕ろうとする小タカ、ねぐら入りするために移動するタカなど、日の出前後と同じようなすばらしい時間です。一日で、夜明け前後と日没前後の両方の観察はやや苦しいですね。
(7) 残念ながら 車の中からが良い
助手席のヘッドレストをはずし、ガラスをきれいにした車の中から観察するのが一番良さそうです。
(8) タカが獲物を捕ってもすぐに近づかない
獲物を捕った直後のタカは、他のタカやカラスに捕った獲物を取られないかと神経質になっていますので、人がすぐに近づくと逃げてしまいます。タカは獲物を捕ってしばらくしてから、おもむろにむしって食べ始めます。中形のタカでは、胸が食べた物でやや膨らみ始めた頃、小さいタカでは、小鳥を半分ほど食べた後なら、ゆっくりと近づけばある程度は近づくことが可能です。
できたら近づかないでください。
(9) タカの気持ちで観察すると良い
自分がタカになったつもりでタカを観察すると、本当の姿を見せてくれるものです。これはなかなか難しいことですが…。
(Uploaded on 30 October 1996)