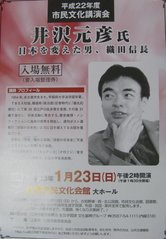1 愛教大での集中講義感想紹介
4日間、90分15コマの授業が終了しました。学生の感想を一部紹介します。
【初日後】
(前半略)今までに授業の仕方、子どもの引きつけ方について学んだことはなかったので、今日の授業は目新しいことばかりでした。小ネタを作ったり、言い回しを工夫して子どもが自分から動くような授業を作るために、自分は全く勉強していないことに気づきました。
今日の授業では、社会科という限定がなく、授業や児童生徒への対応を学ぶことが出来た。また、授業の合間の先生の一口ポイントは、これから役に立つことばかりであった。(中略)授業は子どもにとってわかりやすく、考えることが出来ることを忘れてはならない。そのためには、まず教師が教材研究(日常的)の面で、教師自身が疑問に感じたり、児童生徒なら気になる部分を事前に見つけらることが重要だと思う。加えて、子どもの様子や特長を常に敏感にキャッチできるアンテナを張っておくことも大切だと思う。
社会科だけでなく、他の授業でも使える授業の技術を学ぶことが出来ました。教師というのは、いつも児童の目線に立って授業を構成していかなければいけません。どこで児童がだらけてしまうのか、どうしたら全員参加が出来るような発問が出来るのかを常に考えていくべきだと改めて思いました。(以下略)
模擬授業では、大学生ながら驚いたり笑ったりと、すごく楽しんで授業を受けることが出来ました。好奇心をくすぐられたり、自分でも自分の目が輝いていることが分かりました。
子どもを楽しませるためには、やはり授業を進める側も楽しまなくてはいけないと改めて気づきました。(中略)今日1日だけで、本当にたくさんの技(子どものコントロールの方法やクラスの雰囲気作り、授業の進め方)を得ることが出来ました。あと3日の講義がすごく楽しみです。
【最終日後】
「すごくたくさんのことを学べた。普段の大学の授業では教えてもらったことのないような、授業の工夫や方法、アドバイスなど、中身が詰まった4日間だった。」
「何度も受けた模擬授業が本当に面白かった。たくさん驚いて何回も『へぇ〜』とうなってしまった。」
「子どもだって1人の人間なのだから、教師はおごってはいけないといったことも学んだ。」
「教師という職はとても面白いものだと改めてこの授業で感じました」
「今まで、実際の授業の仕方や工夫、教材研究について学んだことがなかったので、今回の授業は現場をイメージできる内容になっていて新鮮味がありました。
授業を進めていく中で、生徒の理解度を確認したり、指示の仕方の工夫、使い分けは、授業の雰囲気を変える大事な要素だと学びました。」
「心構えから技術、考え方まで学べて、教育大の理想の講義だと強く感じました」
「4日間の集中講義では、教材から指導案や指導方法など、幅広いことを学んだ。
1つ目は、教材は、教材研究すればするほど深いものだと感じた。(略)
2つ目は、学び合いの重要性である。(略)
3つ目は、指導案における導入の重要性を改めて実感することができた。(略)」
私自身も、たいへん勉強になった4日間でした。
貴重な機会を与えていただいた愛知教育大学と学生のみなさんに感謝いたします。
2 拙稿紹介 PRから見る産業界ウォッチング Vol.1〜Vol.12
愛教大集中講義で使用た10年前の『社会科教育』(明治図書)の連載です。
社楽での紹介は(たぶん)3回目です。
3 日本地図を描こう
愛教大集中講義で使用しました。
次の用紙を配布します。(北海道と九州の一部しかありません)

「その間を描いてください」
これだけです。
多くの人は、北から細かく描きすぎて中国・四国が描けなくなってしまう、湾曲しないでまっすぐになってしまうなどの傾向が見られました。
みなさんもやってみてください。
次の用紙を配布します。(北海道と九州の一部しかありません)

「その間を描いてください」
これだけです。
多くの人は、北から細かく描きすぎて中国・四国が描けなくなってしまう、湾曲しないでまっすぐになってしまうなどの傾向が見られました。
みなさんもやってみてください。
4 社会科は情報が命
(1)米中韓メディア“日本語版”リンク
*一部記事が有料なものや、無料会員登録が必要なものもあります。
【アメリカ】
「ウォール・ストリート・ジャーナル」
(トップ) http://jp.wsj.com/
「CNN」 http://www.cnn.co.jp/
「ブルームバーグ」 http://www.bloomberg.co.jp/
【中国】
「人民日報」(トップ) http://j.peopledaily.com.cn/home.html
「新華社新華網ニュース」 http://www.xinhua.jp/
「チャイナネット」 http://japanese.china.org.cn/
「中国国際放送局」 http://japanese.cri.cn/
【韓国(三大紙)】
「中央日報」(トップ) http://japanese.joins.com/
「朝鮮日報」(トップ) http://www.chosunonline.com/
「東亜日報」(トップ) http://japan.donga.com/
【日本語で読む中東メディア】
最新と言ってもよい中東各紙の論調や記事を、日本語訳で読むことができます。
(※)次のURLから、サイト左側「条件検索」の「ジャンル」内、「コラム」をチェックし検索しますと、社説の和訳文を読むことができます。
【世界の新聞は何を言っているか?】
「世界日報」の若干過去の記事ですが、米・英・仏・独・露・豪・中・韓・印・他、アジア諸国・中近東等の主要新聞論調の表題が、日本語で見ることができます。
(ただし本文購読は有料です)
【世界のビジネスニュース「通商弘報」】
日本貿易振興機構(ジェトロ)http://www.jetro.go.jp/biznews/
【ニュース海外トピックス】
「Infoseek楽天」http://news.www.infoseek.co.jp/topics/world/
【ニュースダイジェスト】
【タイの地元新聞を読む】http://thaina.seesaa.net/
【シオンとの架け橋】(イスラエルニュース)
【その他、日本語による海外情報サイト】
「ロイター」 http://jp.reuters.com/
「U.S. FrontLine(アメリカ)」 http://www.usfl.com/
「羅府新報(ロサンゼルス)」 http://rafu.com/news/category/japanese/
「ハワイ報知」(音が出ます) http://www3.shizuokaonline.com/hawaii/
「ル・モンド・ディプロマティーク(フランス)」 http://www.diplo.jp/
「スペインニュース・コム」 http://www.spainnews.com/news/
「スイスインフォ」 http://www.swissinfo.ch/jpn/index.html
「ポートフォリオ・オランダ」 http://www.portfolio.nl/
「ポートフォリオ・ベルギー」 http://www.portfolio.nl/benews
「JSN(ロシア経済情報ナビ)」 http://www.jsn.co.jp/
「25today(オーストラリア)」 http://top.25today.com/
「香港ポスト」 http://www.hkpost.com.hk/
「朝鮮新報(朝鮮総連機関紙)」 http://www.korea-np.co.jp/sinboj/
「まにら新聞(フィリピン)」 http://www.manila-shimbun.com/index.html
「バンコク週報(タイ)」 http://www.bangkokshuho.com/
「南国新聞(マレーシア)」 http://www.nangoku.com.my/
「星日報(シンガポール)」 http://www.shinnichi.com.sg/
「じゃかるた新聞(インドネシア)」 http://www.jakartashimbun.com/
「ベトナムニュース」 http://www.thewatch.com/
「カンボジアウォッチニュース」 http://www.cambodiawatch.net/cwnews/
「ブルネイ友好協会」 http://www.jbfa.or.jp/
「インド新聞」 http://indonews.jp/
「サンパウロ新聞(ブラジル)」 http://www.saopauloshimbun.com/index.php/
【Newseum「Today’s Front Pages」】(英語、及び現地語表記)
世界各国の新聞のトップページが、新聞紙のレイアウトそのままに閲覧できます。その数なんと、50〜70カ国・500〜700紙。日によって変動はあります。
PDFで閲覧でき、拡大表示・印刷も可能です。また、当該新聞サイトへのリンクも張られております。
【OpinionSource「Today’s Newsletters」】(英語表記)
米・英・中・中東・印など主要紙の、最新といってもよい社説が掲載されております。
5 役立ちWeb特集
(1)元号と天皇
(2)コラム:「〜を聴く」シリーズ 沼津交響楽団
(3)「日本人の海外留学者数」について
(4)地図タイル・ランキング
インターネット地図サイトは、表示を速くさせるために、地図画像をタイル状に分割して表示している。見られた回数が多い地図タイルを集計したランキングが登場。思いもよらない場所がみられているかも。
(1) 《知能観は変わった》 筑波大学名誉教授 辰野千尋
知能は、簡単に言えば「物事を識別し、処理する能力」である。この能力を調べるのが知能検査である。知能は遺伝と環境の相互作用の影響を受けて発達するが、研究者の立場や時代の思潮により、遺伝重視か環境重視かに傾斜し、知能検査の考え方にも影響した。
知能検査を最初に体系化したのは、フランスの心理学者アルフレッド・ビネー(1905)だといわれ、その検査は学校教育で広く活用されたが、それ以後今日まで、知能は遺伝か、環境かの論争を中心に知能検査についても「素質検査か否か」の論争が続いた。米国では60年ごろまでは、知能は生得的能力として考え、知能検査で測定される知能指数は生涯にわたって不変であると考えられた。そこで、知能検査で優劣のレッテルを貼ることは差別、選別することになり、知能指数が低いと、教師も子供も「どうせ駄目だ」と宿命論的態度を持つようになると考え、知能検査に対する激しい反対運動が生じた。もちろん、これに反対する立場も現れたが、大勢は変わらず、学校での使用は減少した。事情はわが国でも同じであった。
ところが、1970年代以降になると、認知心理学などの影響を受け、知能検査の再検討が行われ、その役割が再認識されるようになった。すなわち、知能は環境や教育の影響を受けて開発され、形成された能力であり、知能検査はこの能力を測定するものと考えられるようになった。そこで、生得的能力と考えられやすい知能の代わりに適性という言葉が使われ、知能検査の代わりに学業適性検査、学習能力検査、学校能力検査、認知能力検査などの言葉が使われ、知能指数の代わりに学校能力指数などの言葉が使われるようになった。
検査の結果は、現在の学習能力の尺度であり、将来の学習の成功を予測するものと考えられるようになった。従って、このような知能観の変化を考えると、知能検査を学業適性検査、認知能力検査として学習指導に生かしていくことが大事である。
時事通信「内外教育」メールマガジン 2010/12/24 第326号 より
☆★☆ コメント ☆★☆
よく分かります。
目的が分かっていること、結果に対処できることが大切です。
☆★☆ コメント ☆★☆
よく分かります。
目的が分かっていること、結果に対処できることが大切です。