�i�P�j�m��Ȃ��ᑹ����I�ʔ��@���u���@�@�@2011�N 7��11���@�@�@��585��
���@�@���N�C�Y�@��259��@�y���z
�@�u�v���o�C�_�[�̖@�I�ӔC?�v
�@A����́A�Ƃ���C���^�[�l�b�g�f���Ɏ����𒆏�������e�̏������݂��݂��A�Ђǂ������܂����B
�@�����ŁA������ׂ��@�I���u����낤�ƍl���A�v���o�C�_�[D�ɓ��Y���e���������҂̏����J������悤�ɋ��߂܂����B
�@�v���o�C�_�[D�͊J������@�I�`�����ł��傤��?
�@�@1. ����
�@�@2. ����Ȃ�
�@
�@�͍Ō�ɁB�܂��͗\�z���Ă݂܂��傤�I
�@
�i�Q�j�w���㗴�A���Z�o�ς̐��Ƃ����ɕ����x
�p�F���{�o�ς̐��ނ������w�W�A���l�Ƃ́H
�`�F���@�^�Ǐ��v�@�@�F�M�B��w�o�ϊw������
�@�m���ɁA��������"����"�Ƃ������t���A���m�Ȓ�`�Ȃ��Ɏg���Ă����Ǝv���܂��B���̔w�i�ɂ́A�P�X�W�O�N��A�킪����"���E�̍H��"�̒n�ʂɂ��������Ƃ��A�ƂĂ�������ۂƂ��Ďc���Ă��邱�Ƃ�����̂ł��傤�B���ɁA"���E�̍H��"�̒n�ʂ͒����Ɉڂ��Ă��܂��܂����B�J���͂��L�x�ő��ΓI�Ɉ����Ȓ����́A���Ă킪���ōs���Ă����A�Z���u���[�i�g���^�̐����Ɓj�𒆐S�Ɋ����Ȍo�ϊ������s���Ă��܂��B
�@
�@�܂��A�؍����p�Ȃǂ��������l�Ɍo�ϊ��������������A�킪���̐����ƒ��S�̎Y�Ƃ����������݂Ƃ��Đ������Ă��܂��B���ɂh�s�֘A�̐��i�⎩���ԂȂǂɂ��ẮA�킪���́A�����̏����ɋ}���ɒǂ��グ���Ă���A�����̕���ŁA���Ă̋����͂��ێ����邱�Ƃ�����Ȃ��Ă��܂��B����������ڂ̓�����ɂ���ƁA�ǂ����Ă�"����"�Ƃ������t���g�������Ȃ��Ă��܂��܂��B
�@
�@�����A����A�A�Z���u���[���S�ł������킪���̊�Ƃ́A��v���f�ނ╔�ށA����ɂ͕��i�Ȃǂ̕���ŁA�ˑR�Ƃ��āA���E�̎�v�Ȓn�ʂ��߂Ă��镪�������܂��B���N�R���̑�k�Ђɂ���āA�킪���̐����Ƃ͑傫�ȒɎ���܂����B����ɔ����A�����ԕ��i�Ȃǂ������̕���ŃT�v���C�`�F�[�������f����܂����B�킪���̃T�v���C�`�F�[�������f���ꂽ���Ƃɂ���ĉe�������̂́A�킪����Ƃ����ł͂���܂���ł����B
�@
�@�Ƃ��Ɏ����ԂɎg����}�C�R���ƌĂ�镔�i�ɂ��ẮA����̕���ł킪����Ƃ������V�F�A�������Ă������Ƃ�����A���E�I�ɐ��Y�����Ƀ}�C�i�X�̉e�����o�܂����B���ɂ��A�h�b�`�b�v�̊�Սނ̂悤�Ȏ�v���ނɂ��Ă��A�킪���̊�Ƃ������V�F�A�������Ă������߁A���̉e���͐��E�I�ɍL�������悤�ł��B
�@
�@����ɂ��āA�č��̂���G���́A�k�Ђ̔����ɂ���āA�킪����Ƃ���v�f�ނ╔�ނȂǂ̕���ŁA�����ɏd�v�ȃ|�W�V�������߂Ă��������Ċm�F���ꂽ�Ƃ������W�L�����f�ڂ��Ă��܂����B�Ƃ������Ƃ́A���{��Ƃ̌o�c�헪�Ƃ��āA���ΓI�ɍ����l����ɂ���ċ����͂��������A�Z���u���[�̕��삩��A�����Z�p�͂�����f�ނ╔�ނȂǂ̕���Ƀ^�[�Q�b�g���V�t�g�����Ƃ��l�����܂��B
�@
�@���̏؋��Ƃ��āA�k�Ђ̑O�܂ŁA�킪���������ɖf�Վ��x�̍������҂��ł������Ƃ�����킩��܂��B�Ƃ������Ƃ́A�h�s���i�Ɋ؍����������Ȃ�������A���邢�́A�ߗ��i���~�����}�[��o���O���f�b�V������A������Ă��邩��ƌ����āA�����ɁA�킪���o�ς����ނ��Ă���ƌ��_���邱�Ƃ͓���Ǝv���܂��B
�@
�@�o�ς����ނ��Ă��邩�ۂ��̊�́A��͂�f�c�o����v�ȃ����N�}�[���ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃ����̂́A�f�c�o�́A���̍��łǂꂾ���̕t�����l���ׂ��ݏo�������������w�W�ł��邽�߁A���Y���̌o�ς��������Ă���̂��A���邢�͐��ނ�H���Ă���̂���[�I�ɕ\���w�W�ƍl�����邩��ł��B�����A�f�c�o�Ƃ����ꍇ�A�����ϓ����l���Ȃ����ڃx�[�X�̕����A�������̎����ɋ߂��Ǝv���܂��B�������̊��o�ɋ߂Â���̂ł���A�����x�[�X�ł͂Ȃ��A���ڃx�[�X�̕����K��������܂���B
�@
�@�f�c�o�������X����H��Ƃ������Ƃ́A��Ƃ������̋����͂������A���S�ׂ̖̂����t�����l����������Ă���Ƃ������Ƃ�������͂��ł��B�f�c�o����������ƁA��{�I�Ɏ������̂������������邱�ƂɂȂ�܂�����A�������������߂邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@
�@�t�ɁA�f�c�o����������Ƃ������Ƃ́A���S�̂Ő��ݏo���t�����l����������킯�ł�����A��ʓI�ɁA��Ǝ��v�⎄�����̂����������邱�Ƃ��z�肳��܂��B�����ԁA���������������ƁA���������𗎂Ƃ��K�v���o�Ă��܂��B���̂悤�ȏ�Ԃ́A�܂��ɍ��̌o�ϗ͂����ނ���A��̃v���Z�X�ƍl�����܂��B
�@
�i�R�jJMM [Japan Mail Media] �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@No.643 Saturday Edition
���@�wfrom �X�P�P/�t�r�`���|�[�g�x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��T�Q�Q��
�u�{�[�C���O�V�W�V�͂ǂ����ē��{���łȂ��̂��H�v
�@
�@�{�[�C���O�̐V����@�u�h���[�����C�i�[�V�W�V�v�̎����@���H�c�ɔ��A���T�͉��R�A�L���A�ɒO�A��A�����Ȃǂ֔��ŏA�q�܂ł̌����Ȃǂ��s���Ă��܂��B���̐V�^�@�́A�S���{��A���u���[���`���O�E�J�X�^�}�[�i�����グ�p�[�g�i�[�Ƃ��Ă̍w���ҁj�v�ɂȂ��Ă��܂�����A���̔͐��ɂ��̐V�^�@�̐��E�ɑ���u����I�ځv�Ƃ����Ӗ�����������킯�ł��B
�@
�@����Ȃ킯�ŁA�₩�Șb��ɂȂ��Ă���̂ł����A���͋���Ȉ�a������������܂���ł����B�����Ԃ𒆐S�Ƃ����u�A���p�@��v�����r�W�l�X�Ƃ����̂́A���{�̂��ƌ|�ɈႢ����܂���B�ɂ�������炸�A���݂��̂V�W�V�N���X��X�ɂV�S�V?�W��R�W�O�Ƃ���������@�N���X���܂߂������p���q�@�����r�W�l�X�Ƃ����Y�Ƃɂ����āA���{�͂����܂ʼn������̕��i���[�J�[�ɗ��܂��Ă���̂ł��B
�@
�@���̑���ɐ��E���������Ă���̂́A�{�[�C���O�ƃG�A�o�X�̓�僉�C�o���Ђ����ł����āA�o�����킹��ΔN�Ԃ̔��オ�P�O���~�߂����鋐��Y�Ƃɓ��{�͐H�����߂Ă��Ȃ��̂ł��B
�@
�@���i���[�J�[�ɗ��܂��Ă���Ɛ\���܂������A����̂V�W�V�̏ꍇ�ł́A�@�̂ɗʎY�@�Ƃ��Ă͎j�㏉�ƂȂ�Y�f�@�ۂ��g�p����Ă���̂ł����A���ꂪ�������ł��邱�Ƃ�M���ɎO�H�d�H�A�x�m�d�H�A���d�H�Ȃǂ��Q�����Ă���A�S�̂ɐ�߂��u���C�h�E�C���E�W���p���v�̔䗦�͂R�O���ȏ��ƌ����Ă��܂��B
�@
�@���̂��Ƃŏ\���Ɍւ�Ɏv���Ƃ����_��������̂ł����A�o�ό��ʂƂ��Ă͍ŏI�g�ݗ��Ă����āA�@�̑����グ�ɂł���ŏI���[�J�[�ƁA�����I�ȕ��i�̔[���Ǝ҂Ƃ��Ă͓V�ƒn�قǂ̈Ⴂ������̂ł��B���̊������a���Ƃ����̂́A�ǂ����Ă��������n�ʂɊÂĂ���̂��Ƃ������Ƃł��B
�@
�@���̂��ƂɊւ��ẮA�F�X�ȗ��R������Ă����悤�ł��B
�@
�@��́A���Ƃ������p�ł����Ă��A�q��@�̐����Z�p�Ƃ����̂͌R���Y�ƂƖ��ڂɊW������A�������̍��̂��u�쎝�v���Ă��܂������{�͗��j�I�Ɂu���l�v������Ƃ��Ă����Ƃ������ł��B���x���Ƃ������Ƃ�����܂����A���������u��C�v�͈ȑO�͂������̂��Ǝv���܂��B
�@�ł����A���͂�������Ȏ���ł͂Ȃ��Ǝv���̂ł��B���ƌ����Ă������{�̌R���O���̎��т�������ێЉ�ɂ́A���̂悤�ȋ^�O�͂Ȃ��A�]���ē��{�����l�����闝�R���Ȃ��悤�Ɏv������ł��B
�@
�@�����@�ł����Ă��A�R���Z�p�J���̗\�Z�����{����o������J�����\�ɂȂ�A����ȍl����������܂��B�m�����{�[�C���O�̂V�S�V�́A�����͌R�̗A���@�������v�}���]�p���ꂽ���̂ł����A�G�A�o�X��A�R�W�O�ɂ́A�������R�p�o�[�W�����̎o���@������܂��B
�@
�@�ł����A�Ⴆ����̂V�W�V�̂悤�ȍ��������ړI�̒��^�@�́A���������v�f�͔����ł����A���������A�����J�̉F���q��\�Z�̓X�y�[�X�V���g�����~�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��قǍ����������ŁA�R�̍q��W�̌����J������ׂ��Ă��܂��B���B�������\��������A�R�p�̋Z�p�J���\�Z�ɗ��炸�ɖ����@���J�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ƃ����_�ŁA���{�̃n���f�B�͏��Ȃ��Ȃ��Ă���ƍl�����܂��B
�@
�@��s�@�ɂ͍��x�Ȉ��S�������߂��܂��B���ɏ��p�^�s���ɑS�����̂��N��������Ȕ����ӔC���������A�����ꐻ����̌��ׂ������ł���Ƃ����悤�ȏꍇ�ɂ́A���[�J�[�̐ӔC������Ȃ��̂ƂȂ�܂��B���̓_�ŁA���{��Ƃ͖@��ł̘_��������̎������邵�A���ۂɍ��ۊԂ̖@�I�����Ɏア�̂ŁA�ŏI���[�J�[�ł͂Ȃ��A���i���[�J�[�Ƃ��čs�����Ă��������u���S�v�Ƃ�������������悤�ł��B
�@
�@���̓_�ɂ��Ă��A�����͔����b�ł��B�m���ɍ��ۖ@���Ƃ����͎̂�Ԃł���A�C�U�@�쓬���ƂȂ�Ύ��Ȏ咣��r�点�Ȃ��m�b�Ǝ��v�͂����߂��܂��B�ł����A���̃��X�N�Ƃ������Ƃł͕��i���[�J�[������������ł��B
�@
�@����́u�s�s�`���v��������܂��A���Ă̖f�Օ����̊W�ŁA���{�̓A�����J�Ɏ����Ԃ̗A�o��F�߂Ă��炤����ɁA�{�[�C���O��A�ȑO�̓��b�L�[�h�i���͖����@����P�ށj��A�_�O���X�i���݂̓{�[�C���O�ɋz��������Łj�ȂǁA�A�����J���������Ă����q��@�r�W�l�X�́u�����v���Ă����Ƃ�����������܂��B
�@����܂��^�U�̂قǂ͂Ƃ������A���͏͕ς���Ă��܂��B�����ԂɊւ��ẮA�e�ЂƂ��k�Ăł̌��n���Y���ɑ剻���Ă��܂��B����ȏ�i�߂�A�ٗp�m�ۂ̐ӔC�Ƃ������Ƃł͓��{��Ƃł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����x���܂ŗ��Ă���킯�ł��B����ŁA���[���b�p����́uEU�����ЌR�v�Ƃ����ׂ��G�A�o�X���{�[�C���O�ɒ��킵�Ă��Ă���킯�ł��B
�@�����������A���{���傫�Ȗ����@�̍ŏI���[�J�[�������Ƃ́A�Ⴆ�A�����J�̕��i���[�J�[�ɂ̓����b�g�ɂȂ�悤�ȋ��ƊW�͉\�ł���A���{���q��@�r�W�l�X�ɖ{�i�Q�����邱�Ƃ��A���̂܂܃A�����J�̉��ւ́u�����v�ɂȂ鎞��ł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�@�Ƃɂ����A�v�����o�Ǝ��̊�p���A�����ă~�X�⌇�ׂւ̕q���ȃ��������������������J���͂���������Ȃ��܂܁A���S�̂̋����͂��ቺ����Ƃ��������Ƃ����̂́A�{��̑Ώۂł���ȑO�ɉ��Ƃ��ܑ̂Ȃ��b�ł��B�q��Y�ƂƂ����̂́A���̃M���b�v�߂�傫�ȃ`�����X�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@
�@�J���͂̊��p�����łȂ��A��K�͂ȍq��@�r�W�l�X�Ƃ����̂͗l�X�Ȍ`�œ��{�Љ�ɂ����e����^����悤�Ɏv���܂��B�Ⴆ�A�o�c�ɑ���l�����ł��B�����p���^�@�̊J���Ƃ����̂́A����v���W�F�N�g�ł��B�ł�����A�]���̓��{�I�o�c�ɂ������u����������ő傫����Ă�v�Ƃ������@�_�͎g���܂���B
�@
�@�q��@�Ƃ����̂͑�ςɕ��G�ȋ@�B�ł���A�������������x�����߂��邱�Ƃ���A�ŏ�����A�������[�_�[�V�b�v���A�������莑���Ɛl�ނB���āu�����x�̍��������v�v���s�����Ƃ����߂��܂��B���������o�c�����������A���͂܂���R���̎c���Ă��鍑�ۉ�v��iIFRS�j�̏d�v���Ȃǂ���������Ă䂭�̂ł͂Ǝv���܂��B
�@
�@�����܂ł́A�V�W�V�����@�Ƃ����j���[�X�ɂ������āA���^�@�����r�W�l�X�̂��ƂR�ƈӎ����Ă��b���Ă��܂����B�m���ɂ��̃J�e�S���ɂ��ẮA�G�A�o�X���R�T�O�Ƃ������f���̊J�����}���Ȃǃz�b�g�Ȏs��ł���̂͊ԈႢ����܂���B�ł����A���̉��̏��^�@�s����傫�ȉ\��������̂ł��B
�@�����ɂ́A�{�[�C���O�̂V�R�V�Ƃ����������̂悤�ȃq�b�g���i������̂ł����A���ꂪ�T�C�N���̏I�����}�����钆�A�J�e�S�����̂̎s��ɂ͂܂��܂��\���͂��邩��ł��B
�@
�@������ɂ��Ă��A���^�@�ƒ��^�@�Ƃ�������ȃr�W�l�X�`�����X�ɁA���{�o�ς͒��킵�čs���Ȃ����R�͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�����{�́u�A���p�@��v�r�W�l�X�́A�܂����D�Ƃ��֎Ԃ𐬌������A���̎��Ɏ����Ԃő傫�Ȑ��������݂܂����B���̐����̂��邤���ɁA�{�i�I�ɍq��Y�Ƃֈڍs���Ă䂭�A���ꂪ���R�Ȏ��Ԋ��o������ł��B
�@
�@���ƌ����Ă��A����̍q��@�ɋ��߂��Ă���̂́A�K�͂⑬�x�ł͂Ȃ��A�����܂ł������ƈ��S�������S�ł��B���̓�̉��l���������镶���Ɛl�ނ������Ă�����{�ɂ́A�����S�ō������ȍq��@������Ă䂭���ƂɁA�ނ���l�ޓI�ȐӔC������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���[�W���i���E�W�F�b�g���ǂ��ł����A�����Ƃ����Ɛ�i�ނׂ��ł��B
�@
�@
�i�S�j�����w���E���Z���t�p�j���[�X�}�K�W���x�i�����l�l�j����Q�W�W�X����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�P�N�V���@�U���F���j�����s
���u���ȂŎg����͌^����낤�I�v�i�V�j�����h��(�������j
���G�l���M�[�֘A�͌^
�@���q�͔��d���Ɋւ��Ă͑O��Љ�܂����B����́A���q�͈ȊO�ł��B
�@���}�ʐ^�ԍ��́A
�@�i�P�j�@���͔��d

�@�{�����_���̃y�[�p�N���t�g�i�ʐ^�P�j����肵�܂����B�ȑO�A�l�b�g�Ŕ������A�ǂ����Ă��~���������̂ł��̎�|���{�����_���̎��������ĂɃ��[�������Ƃ���A���ʂɂ��������܂����B��͂�~�����Ǝv�����Ƃ��́A�_�����g�ōs�����邱�Ƃ��厖�Ƃ������Ƃ��킩��܂����B
�@���̃��f�����g�債�đ傫�ȕ����쐬���_���̖͌^�ƃZ�b�g�ɂ��Đ��͔��d�������悤���Ǝv���Ă��܂��B
�@
�@�i�Q�j�@�Η͔��d
�@�Η͔��d���̖͌^�Ƃ����̂́A�܂��������Ă��܂���B�y�[�p�[�N���t�g�ł���Ȃ�~�����̂ł����E�E�E�B�����Ŏ������肵���̂́A�Η͔��d�̔R���ł��B�Ζ����{�i�ʐ^�Q�j�ɖ{���̐ΒY�ł��B
�@�Ζ����{�͓��{�Ζ��A���L��ہiTEL:03-3279-3816�j�ɘA�����ē��肵�܂����B�ΒY�͗��Ȃ̂l�k�Ŋ�]�҂����Ă����̂ł��������܂����B
�@�`�����X�͂����ȂƂ���ɂ�����̂ł��B
�@�����āA���q�͌^�����܂����B
�@�V�R�K�X�i���^���E�G�^���E�v���p���E�u�^���E�y���^���j���q�͌^�i�ʐ^�R�j�A�ΒY�̕��q�͌^�i�ʐ^�S�j�A���ꂩ�痘�p����邩������Ȃ����^���n�C�h���[�h�̕��q�͌^�i�ʐ^�T�j�܂��A�S���͌^�ɃK�X�^���N�z���_�[��Ζ��^���N�A���łɃK�\�����X�^���h�܂ł���܂��B�K�X�z���_�[��
http://www.1999.co.jp/search.asp?Typ1_c=104&scope=�@

0&scope2=0&itkey=%83K%83X%83z%83%8B%83_%81%5B
�K�X���^��ł���D�̃y�[�p�[�N���t�g������܂��B
�@�k�m�f�D�̂[�p�[�N���t�g�̃_�E�����[�h��
�i�R�j�@���͔��d
�@���ԁi�ʐ^�U�j�͓����̉Ȋw�Z�p�قōw���������̂ł��B�܂��̔����Ă���Ǝv���܂��B
�i�S�j�@���d�ݔ��@
�@�ϓd����S���Ȃǂ͓S���͌^�ɂ���܂��B���������܂������A���͂�����ƌ�����܂���B���Ƃ̑q�ɂ̂ǂ����ɂ��܂��Ă���̂ł����E�E�E
�@�S����http://www.1999.co.jp/search.asp?Typ1_c=104&scope=0&scope2=0&itkey=%93S%93%83�@
�@�@�@�@���ɁA�o���U�C�S���̃y�[�p�[�N���t�g�̃_�E�����[�h��
�@�@�@�@�d�C�̏I���_���d�����i�̃y�[�p�[�N���t�g�̃_�E�����[�h��
�@�@�@�@���Ȃ̎����Ŏg�����d�����[�^�[������삵�܂����B�i�ʐ^�V�j
�i�T�j�@�����
�@�@�@�@�@�y�[�p�[�N���t�g�ł����낢��Ƃ���܂��B
�@�@�@�@�@��_���Y�f�̔Z�x���z�̒n���V�����܂��B�_�E�����[�h���
�@�@�@�@�@�n���̊C���ʂ̉��x���z���킩��n���V�ł��B�_�E�����[�h���
�@�@�@�@�@�I�]���j��ɊW���镪�q�͌^�����܂����B�i�ʐ^�W�j
�@
�@����́A�V���֘A�͌^�i�P�j�ł��B
�@
�@
�@
�i�P�j�m��Ȃ��ᑹ����I�ʔ��@���u���@�@�@2011�N 7��11���@�@�@��585��
���@�@���N�C�Y�@��259��@�y���z
�@�u�v���o�C�_�[�̖@�I�ӔC?�v
�@
�i�P�j����
�@1. ����
�@
�@�ō��ٕ���22�N4��8�������́A�C���^�[�l�b�g�̌f���ɒ���������e���������܂ꂽ�l���A����������̌l����������悤�ڑ��Ǝ҂̃v���o�C�_�[�ɋ��߂邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����ɂ��āA�u�f���̊Ǘ��҂����łȂ��A�v���o�C�_�[�ɂ��l�������߂邱�Ƃ��ł���v�|�̔��f�������܂����B
�@���������āA�{��ł�A����̓v���o�C�_�[D�ɏ��̊J�������߂邱�Ƃ��\�ł���A���̗��Ԃ��Ƃ���D�͓��Y�����J������@�I�ӔC���Ƃ����܂��B

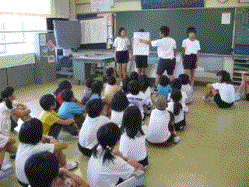 �܂����A���̐�A�����d�˂邱�ƂŐi�����Ă����̂ł��傤�B
�܂����A���̐�A�����d�˂邱�ƂŐi�����Ă����̂ł��傤�B
 �w�K���J�T
�w�K���J�T

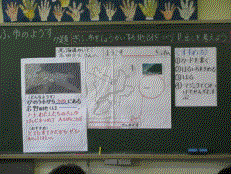 �Љ�͊s�̂悤�����R�N���������Ă��܂��B
�Љ�͊s�̂悤�����R�N���������Ă��܂��B
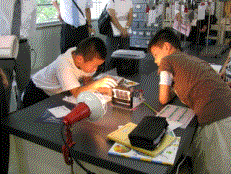
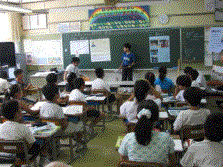
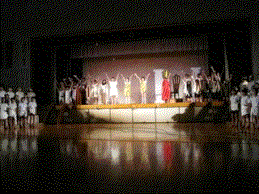
 �@�{�����_���̃y�[�p�N���t�g�i�ʐ^�P�j����肵�܂����B�ȑO�A�l�b�g�Ŕ������A�ǂ����Ă��~���������̂ł��̎�|���{�����_���̎��������ĂɃ��[�������Ƃ���A���ʂɂ��������܂����B��͂�~�����Ǝv�����Ƃ��́A�_�����g�ōs�����邱�Ƃ��厖�Ƃ������Ƃ��킩��܂����B
�@�{�����_���̃y�[�p�N���t�g�i�ʐ^�P�j����肵�܂����B�ȑO�A�l�b�g�Ŕ������A�ǂ����Ă��~���������̂ł��̎�|���{�����_���̎��������ĂɃ��[�������Ƃ���A���ʂɂ��������܂����B��͂�~�����Ǝv�����Ƃ��́A�_�����g�ōs�����邱�Ƃ��厖�Ƃ������Ƃ��킩��܂����B
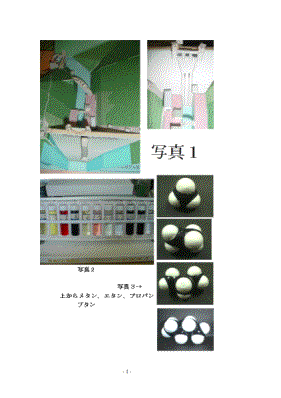 �܂��B�_�E�����[�h�͂��Ă���̂ł����A�܂�����Ă��܂���B�ł��A���͔��d��������̂ɂȂ��Ȃ��������ނɂȂ�Ǝv���܂��B �_�E�����[�h��@�@ �@
�܂��B�_�E�����[�h�͂��Ă���̂ł����A�܂�����Ă��܂���B�ł��A���͔��d��������̂ɂȂ��Ȃ��������ނɂȂ�Ǝv���܂��B �_�E�����[�h��@�@ �@ 0&scope2=0&itkey=%83K%83X%83z%83%8B%83_%81%5B
0&scope2=0&itkey=%83K%83X%83z%83%8B%83_%81%5B