1 平成25年度北方四島交流訪問事業報告
プレゼンと資料で報告しました。
その内容は、ブログ「あなたも社楽人」におおよそ書いてあることです。
2 授業に役立つ金融経済セミナー
プレゼンと資料で報告しました。
その内容は、ブログ「あなたも社楽人」におおよそ書いてあることです。
8月16日に、ウインクあいちでおこなわれた、授業に役立つ金融経済セミナーに参加しました。
講義1は、「日本経済の現状と展望〜アベノミクスと金融政策〜」
株式会社東海東京調査センター 専務取締役 チーフグローバルストラジスト 中井 裕幸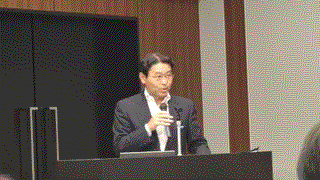 氏の講義でした。
氏の講義でした。
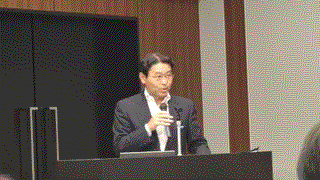 氏の講義でした。
氏の講義でした。 日本が明るくなる話を、いくつかの事例を元に教えていただきました。
安部さんが首相に、黒田さんが日銀総裁になったのは奇跡だそうで、苦しい時代を切り抜けられる可能性があります。
東京でのオリンピック開催が決まり、日本は大きく変わるかもしれないと予言されました。
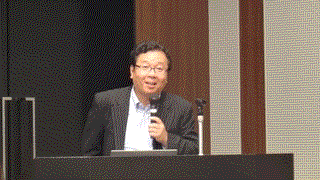 講義2は、「地域活性化の手法としての6次産業化」
講義2は、「地域活性化の手法としての6次産業化」 野村アグリプランニング&アドバイザリー株式会社 取締役社長 西澤 隆 氏
農業の6次産業化を進めよう。
1次産業が2次・3次もやりましょう。生産者が加工・販売をすればいい。作っているだけでは儲からない。違う付加価値を見いだして、雇用を生みだそうという話でした。
ちょうど翌日に行った、丹葉フィールドワークのテーマだったので、興味深く聞くことができました。
午後からは、三菱電機 名古屋製作所の見学でした。
三菱電機 名古屋製作所は、JR駅と、イオン・ナゴヤドームとの間に広がる、10万坪の敷地にあります。
ナゴヤドーム7個分以上の敷地です。
この中に、関連会社を含めると、約5千人が働いています。
製品は、簡単に言えば、機械を作るための機械を作っています。ハイテクと人力の両面を見ることができました。ぜひ、HPをご覧ください。
3 平成25年度 第3回教師力アップセミナー 岡野 昇 先生
9月7日に大口中学校で行われた三重大学教授 岡野 昇 先生の講演紹介します。
テーマは、「身体技法を通したワークショップ形式による学び愛を中心とする授業づくり」です。
体育の先生というよりは、学びの共同体研究会スーパーバイザーとしてのお話でした。
一言でいうと、授業で生徒指導的なことを求めない。子供を変えようとするのではなく、環境を変えようとすれば子供はよくなる、ということでした。
たとえば、まじめでなく、協調性のなかったタロウ君。
見方を変えて、ゆとりのある、かかわりを求める子ととらえると、こちらの対応が変わり、それがタロウ君にとってよかった。
今回のポイントは次の点です。
授業をつくる(授業デザイン)ということの意味
○ 子供を変えてみようとするのではなく、私たちの見方を変えてみる。
ex.リレーの基本はバトンを正確に渡すことではなく、スピードを渡すこと
○ 個体主義的アプローチからの脱却
・子どもを周りとの環境の中で見ていかないといけない。
○ 環境を変えることにより子供が変わる
ex.「今、なぜ椅子にもたれていますか?」→「リラックスした状態で聞きたいから。」
「それは個人主義的な考え方。答えはここに背もたれがあるから。もし、肘掛けがあったら肘をかける。」
・我々は環境に動かされている動物。主体的に動いているようで、実は環境を受動的にキャッチしてそれに答えて動いている(アフォーダンス理論)。
・授業を1つの環境と見た時、その環境を変えると子どもが変わる。
○ 固定観念とはある観念が固定されている
・どんな観念がどんなふうに固定化されているのか。変えてみると生きてくるものがあるかもしれない。
○ 気づく、離れてみる
○ Design = de + sign
(出る) (形)
・デザインとは、形から離れること。構想すること。どんな形か
内容は、ここをご覧ください。http://www2.schoolweb.ne.jp/swas/index.php?id=school55&frame=weblog&type=1&column_id=668380&category_id=11952