シーズンオフ企画決定!若い先生に声をかけてください。


次回予告
特別企画第一弾!
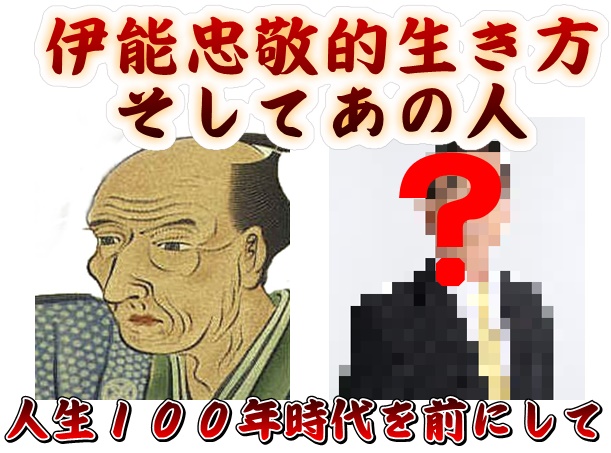 これからの日本人の課題が「人生100年時代をいかに生きるか」
これからの日本人の課題が「人生100年時代をいかに生きるか」 信長の時代の人生50年、戦後の人生80年が、人生100年時代へと突入します。
そのような中で、私たちはどう生きていけばよいのか、先人の行き方をヒントに、自分の将来の生き方を、模擬授業形式で、みんなで考えてみましょう。
当日は、布袋北学供で組合の執行委員会もあります。駐車は、縦列で行い、満車の場合は、
交通児童遊園、旧HONDA跡地も可能です。
これは、7月10日に行われた、学校におけるICT環境整備の在り方に関する有識者会議(第7回)の配付資料です。
平成29年3月13日 効果的なICT活用検討チームがまとめた一部抜粋です。
(教育用コンピュータでできること)
教育用コンピュータは,様々な機能を持つ。各学習者に1台ずつ配布して, その機能を生かした学習が試みられている(図参照)。
(1) 個別のドリル学習 計算練習や漢字練習,単語練習などは,出てきた問題に解答すれば,即座 に採点されるようなシステムを用いると効率的に実施できる。これは従来か ら,紙の教材で行ってきたことである。しかし,紙でできないものが自動採 点による IKR(Immediate Knowledge of Results:即座に結果を返すこと) である。 協働的に練習を行うような学習も考えられる。例えば,学習者を教科リー ダーに分け,授業の初めに学習内容と関連するフラッシュカード型の教材を 一斉配布する。各学習者は,それを使って3分程度繰り返し練習して,知識 の定着を図る。教材は,リーダーが作成し,教師の了承をもらっておく。教 師との打ち合わせ時に柔軟に問題を変更でき,印刷の必要がなく,一瞬で全 員に配布することができることが,紙では実現できないスピードを生み出 す。
(2) 試行錯誤する 教育用コンピュータの教材に,指定された時刻に時計を合わせる教材があ る。自分で色々試してみて確かめる。学習用の時計は「お道具箱」に入って いるが,デジタル教材は多様なものを準備できる。しかも,IKR が可能であ る。コンピュータ教室があれば,同様の教材を実行可能ではあるが,通常の 授業の一部に少しだけ行うような学習のために,コンピュータ教室を予約し 移動するのは非効率的である。
(3) 写真撮影する 教育用コンピュータ(タブレットPC)を一人1台持つということは,全 員がカメラを持っているということである。一人一人が観察に行った時に, 対象を撮影してくることができる。従来は,現場でスケッチをしてきたが, スケッチと写真では,その後の使い方が異なってくる。写真であれば,教室 で再度観察し直すことができる。
(4) 念入りに見る 教育用コンピュータ(タブレットPC)には,画面を拡大するピンチアウ トという機能がある。写真や画像資料の細部を,その機能を使って念入りに 見ることで,各学習者の気付きが根拠をもつ。(3)でみたように,一人ひと りが現地で撮影した写真を,詳しく観察して学び直すことが可能になる。
(5) 録音・録画と再視聴 教育用コンピュータ(タブレットPC)には,通常ビデオ撮影する機能も 付いている。英語の発音や詩の朗読などを自分で録音し,それを自分で聞い てふり返り,改善するような学習が可能になる。かつて LL 教室で行われて いたことを,より高度化してできるのである。また,実験の様子を録画し て,後から再視聴しながら現象を詳しく観察し直すことも可能である。
(6) 調べる 教育用コンピュータは,インターネットにもつながる。何かについて調べ る学習は,図書室などでも行える。しかし,一人に1つ,資料があたるよう に準備するのは難しい。インターネットであれば,すべての学習者が自分に 必要な情報を閲覧することが可能である。また,複数の学年が同時に図書館 を使うのは難しいが,そのような問題も起こらない。
(7) 分析する 調べ学習で情報を集めた後は,情報を整理して分析する。それは,例えば 数値の観測データを表に整理したり,グラフ化して傾向を見つけたりするこ とである。グラフを描くのは,手書きでもできるし,それが重要なこともあ る。しかし,大量のデータを扱ったり,さまざまなグラフ表現を試したりす ることが,教育用コンピュータを用いることで容易になる。また,実践して いるその場で,同時進行でデータを処理することもできる。
(8) 考える 思考を促す方法として,シンキングツール(思考ツール)が注目されてい る。従来,これは紙の台紙と付箋紙で実施してきた。しかし,シンキングツ ールのアプリケーションが出てきており、アイデアの書き消し,修正,移動 などが容易にできるようになっている。また,文字がテキストデータに変換 されるため,アイデアを書き出したあとの共有場面などで相互理解を図りや すい。
この後、各学年、各教科での使用例が数多く載っています。
2 新学習指導要領のポイント 小学校・中学校社会科編
教育出版教育研究所 教育情報シリーズ174
こうしたコンパクトにまとまっているものは役に立ちます。別紙で紹介しました。
3 サントリー山崎蒸溜所
 京都の南西、天王山の麓、山崎。
京都の南西、天王山の麓、山崎。
1923年、鳥井信治郎はウイスキーづくりにおいて重要な“良質な水”と“自然環境”にこだわり、数ある候補地の中からこの山崎の地を選び蒸留所を建てました。
ウィスキーは、麦芽を煮て、その煮汁を発酵させ、そのアルコールを蒸発し液化したものが原酒。それを樽に詰めて寝かせたものを、ブレンドし、水を加え、43度ぐらいにしたものを瓶詰めします。
 山崎蒸溜所におけるウイスキーづくりの特長は、多彩な原酒のつくり分けにあります。例えば、発酵工程における木桶発酵槽とステンレス発酵槽の使い分け、蒸溜工程における大きさや形状の異なる蒸溜釜の使い分け、 貯蔵(熟成)工程における様々な樽の使い分けなど、仕込から発酵、蒸溜、そして貯蔵(熟成)に至るまでの全ての工程で 多彩な原酒のつくり分けは行われているのです。だからこそ、いろいろなブレンドで、他品種のウィスキーを作ることができるのです。原酒の熟成状況をチェックし、製品の特長にあったものを厳選して組み合わせを決定していくのがブレンダー。 多いときには1日に数百種類のテイスティングを行い、樽ごとの原酒のピークを見極めながら、どのタイミングでどの原酒を使用するべきかを判断します。
山崎蒸溜所におけるウイスキーづくりの特長は、多彩な原酒のつくり分けにあります。例えば、発酵工程における木桶発酵槽とステンレス発酵槽の使い分け、蒸溜工程における大きさや形状の異なる蒸溜釜の使い分け、 貯蔵(熟成)工程における様々な樽の使い分けなど、仕込から発酵、蒸溜、そして貯蔵(熟成)に至るまでの全ての工程で 多彩な原酒のつくり分けは行われているのです。だからこそ、いろいろなブレンドで、他品種のウィスキーを作ることができるのです。原酒の熟成状況をチェックし、製品の特長にあったものを厳選して組み合わせを決定していくのがブレンダー。 多いときには1日に数百種類のテイスティングを行い、樽ごとの原酒のピークを見極めながら、どのタイミングでどの原酒を使用するべきかを判断します。
 ここでは、有料で、工場見学の後にテイスティングを体験できます。
ここでは、有料で、工場見学の後にテイスティングを体験できます。
一番左のグラスがホワイトオーク樽原酒、2番目はワイン樽原酒、3番目が山崎で、一番右は好きな飲み方(実際はハイボール)で飲むものです。
その方法や、色、香り、味覚の判断の仕方を教えてもらいました。
〒618-0001大阪府三島郡島本町山崎5-2-1

4 京都鉄道博物館
平成28年4月29日、鉄道の歴史を通して日本の近代化のあゆみを体感できる「京都鉄道博物館」が開業しました。
実物資料を中心に収蔵資料をテーマごとにわかりやすく展示されています。実物車両に触れる体験展示はとてもうれしい展示です。
 実際に動くSL、大ジオラマ、車両を上から見たり下から見たり、パンタグラフや信号機、自動改札の中身など幅広く見ることができます。
実際に動くSL、大ジオラマ、車両を上から見たり下から見たり、パンタグラフや信号機、自動改札の中身など幅広く見ることができます。
鉄ちゃんでなくてもお勧めです。
京都市下京区観喜寺町 0570-080-462
5 MM紹介
メールマガジン「教師教育を考える会」49号 2017年12月12日発行
教師としての私の成長物語 熊本大学教職大学院准教授 前田 康裕
1 自己紹介 ( 略 )
2 私自身の教師としての成長
(1)1年目~10年目 教育技術への傾倒
初任教師時代は苦しみの連続でした。授業が成立しなかったからです。特に国語の時間は、何をどう話し合わせればいいのかが分からず、子どもたちが退屈しているのを感じる毎日でした。通勤するたびに胃が痛くなるほど悩んでいたのです。
ちょうどその頃に出会ったのが教育技術の法則化運動でした。尊敬している有田和正先生も参加している運動だと聞いて、躊躇せずに参加したことを今でも覚えています。それから、向山洋一先生、野口芳宏先生といった日本を代表する教育実践家を知ることになり大きく影響を受けていきました。
教育技術の法則化運動は、その当時から批判も多くありました。管理職から直接注意を受けたこともありましたが、私自身はこの運動に没頭していくことになります。当時の法則化運動に賛同する教師たちは、積極的に法則化論文を書き全国的な研究会に参加する積極派と、法則化シリーズとして刊行された出版物を追試するだけの消極派に別れていました。
私自身は積極派として活躍の場を見出し、法則化シリーズの書籍も出版しました。「完成された教育技術は存在しない」といった法則化の理念や「21世紀になったら解散する」という潔さに共感を覚えていたからです。漫画やイラストといった私の強みを見出してくれたのは向山洋一先生でした。
様々な批判を浴びながらも法則化運動に参加したことは、そのあとの自分の人生に大きな影響を与えました。その一つ目は、自分の授業を記録し法則化論文にまとめていくというプロセスで省察が習慣化されたことです。二つ目は、ビジネス書を含めた様々な書籍を読むことが習慣化されたことです。三つ目は、深澤久先生、横山験也先生、福山憲市先生といった後の教育界のリーダーとなる多くの教師と知り合いになれたことです。
この時期は、まさに学び続ける教師としての土台をつくった時期だったように感じます。
(2)11年目~20年目 授業観の大転換
教師になって11年目に熊本大学教育学部附属小学校に赴任。その頃、私の教育観を大きく変えた出来事がありました。それは、プロジェクト学習との出会いです。サンフランシスコでプロジェクト学習の教員向け研修会があるということを聞き、思い切って参加することにしました。山の中にある研修場にはたくさんのコンピュータが置いてあり、そこで私は、アメリカ人の教師たちと協働しながら日本の文化を伝えるデジタル教材を作成したのです。それは、今までの指示・発問を中心とした教師主導型の授業とは全く異なるものでした。
学習者の側に立って授業を考察すると、仲間の存在が非常に重要になってくることに気づきました。仲間の知識や技能、一緒に学習を楽しむという人間性が学習に大きく作用します。このような協働して作り上げていく学習を浴びるように経験したことは、私の授業観を大きく変えることになりました。いわゆる社会的構成主義に基づいた授業観です。
ちょうどその頃、日本では総合的な学習が始まろうとしている時でした。指示・発問を中心とした教師主導型の授業を決して否定するものではありませんが、そのやり方では総合的な学習は成立しません。その頃出会ったのが、NHKの放送番組で見た三宅貴久子先生の授業実践でした。子どもたちを学習へと導いていく三宅先生の教師のあり方に大きく影響を受け、やがて私は総合的な学習の専科教員となり、5年間、ICTを活用したプロジェクト学習を推進していく役割を担うことになっていきます。
授業観の大幅な転換によって、私は学習理論に興味を持つようになり、岐阜大学の大学院に進学することにしました。岐阜大学教授の益子典文先生に師事し、学会に通うようになり、実践知と理論知をむすびつけていく面白さを実感するようになったのがこの頃です。その頃に出会ったのが、中川一史先生、堀田龍也先生、木原俊行先生といった日本のICT教育を牽引していく研究者の先生方です。
この時期は、実践から理論を導くことに大きな価値を見出していった時期だったと言えましょう。
(3)21年目~30年目 教師教育への目覚め
附属小学校を出てすぐに赴任した学校では、校長先生から「少人数指導の国語科専科となって国語の学力を向上させてほしい。」と言われました。初任教師のときに苦しんだ国語科の専科教員になることには大きな抵抗がありましたが、これもまた何かの試練だと考えて引き受けることにしました。
その頃、日本ではPISA型読解力が話題になっていました。そこで私は、そうした学力を向上させるために、ICTを活用したプロジェクト学習を国語科でも推進していくことにしたのです。翌年度からスタートした全国学力テストの結果、特にB問題が良好だったので、学力を向上させていく方略をつかんだ時期でもありました。
5年後、私は熊本市教育センターの指導主事となり、ICT関連の研修やICT関連の管理・運営を担当することになりました。後に、熊本市教師塾「きらり」の主査となり、教職経験4年目から10年目までの若手教師の力量形成を図るための研修を企画していくことになります。「きらり」では、塾生はその専門性に応じて師範とよばれる力量の高い教師とペアになります。塾生は師範の授業を見学し、師範の教育技術だけではなく、それを支える教育理念についても学ぶことができます。そのようなシステムを教育センターの職員と協働して作りました。また、その特別講師として真っ先に招聘したのが、有田和正先生と野口芳宏先生です。意欲溢れる若い教師たちが一流の実践家と出会うことによって、教師人生を豊かなものにしていくと私は信じていたからです。
この時期は、後輩の育成に全力を挙げることで、教師教育にやりがいを感じるようになった時期です。
(4)31年目~32年目 カリキュラムの重要性への気づき
熊本市教育センターを出て、私は初めての教頭職を務めることになります。しかし、授業や研修ができないばかりか、事務仕事やクレーム対応に追われることになり、次第に大きなストレスが溜まっていくようになっていきました。また、土日や夜間に開催される地域の会合や行事が、私にとってはわずらわしく感じられました。今まで培ってきた授業研究の知識が生かされないからです。
しかし、2016年4月に起こった熊本地震によって、そのストレスは吹き飛ぶことになります。地域の方々が結束して避難所を開設し多くの被災者のお世話をしている様子を見て、大きく感動したからです。地域の行事は人と人とがつながってコミュニティーを形成するために大きな役割を果たしていたことに気づき、自分の考えが間違っていたことを痛感しました。それから私は地域の行事に積極的に参加し、地域の方々の考えや取り組みから学ぶようになり、こうした人々の働きを教育に生かそうと考えるようになりました。ありがたいことに、当時の6学年の先生方が、地域の取組を総合的な学習として発展させてくれました。
日本の教師は1時間の授業研究には非常に熱心に取り組むけれど、学校全体のカリキュラムにはあまり興味関心を持たないという傾向があります。今まで1時間の授業をどう組み立てるか、あるいは1単元の授業をどう構成するかといったことに囚われていた自分をおおいに反省しました。
この時期は、よりよい社会をつくるための教育には、私一人ではなく教師集団も家庭も地域も一体となって取り組む必要があることを実感した時期でした。まさにカリキュラム・マネジメントの重要性が理解できたのです。
3 今、考えていること
今、私自身考えていることは、これからの人生をどう生きるかということです。
松尾芭蕉の言葉で「古人の跡を求めず、古人の求めたるところを求めよ」というものがあります。「昔の偉人たちが残した結果を真似るのではなく、偉人たちが何を求めようとしたかという志を求めなさい。」という意味だと捉えています。
(以下略)
人は強みでこそ成果を挙げると言ったのはドラッカーです。自分の強みを生かし、人生を楽しみながら教師教育の仕事に携わりたい、そのことが自己実現であり、自分の人生を豊かにしていくものだと考えています。