次回は、第501回11月15日(木)です。

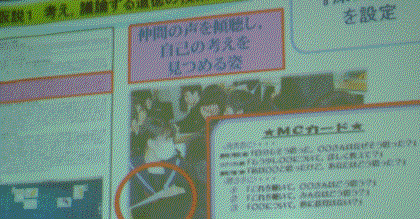 研究としての優れものは、「MCカード」。グループ討議の司会者用のマニュアルである。グループ討議は、とてもよい雰囲気であり全員が参加していた。実際には、別所学級ではもうMCカードが不要なレベルで、話し合いは成立していた。
研究としての優れものは、「MCカード」。グループ討議の司会者用のマニュアルである。グループ討議は、とてもよい雰囲気であり全員が参加していた。実際には、別所学級ではもうMCカードが不要なレベルで、話し合いは成立していた。
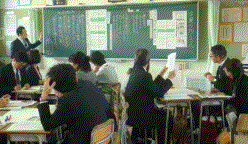 その後は全体会で研究発表会があった。研究理論はシンプルで、好感がもてる。公立学校の研究はこれぐらいが良いのではないかと思う。
その後は全体会で研究発表会があった。研究理論はシンプルで、好感がもてる。公立学校の研究はこれぐらいが良いのではないかと思う。
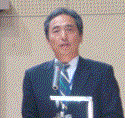
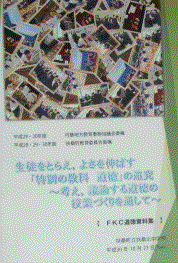 私はこの話は小学校高学年ぐらいがよいと思っている。思春期にある中学生はこの手の話は照れくさい。だから意見が出にくい。
私はこの話は小学校高学年ぐらいがよいと思っている。思春期にある中学生はこの手の話は照れくさい。だから意見が出にくい。
2 平成30年度 岩倉南部中学校 研究発表会参加報告
 この夏、本校の現職教育の講師としてお招きした、愛知教育大学の 磯部 征尊 先生 が主宰する研究会です。
この夏、本校の現職教育の講師としてお招きした、愛知教育大学の 磯部 征尊 先生 が主宰する研究会です。
6 教師力アップセミナー 横山浩之先生
 いつも、短い言葉でずばっと教えてくださる横山節は今回も健在。
いつも、短い言葉でずばっと教えてくださる横山節は今回も健在。
7 千代田区立麹町中学校

1 平成30年度 扶桑町立扶桑北中学校 研究発表会 参観報告(10月23日)
13時からは公開授業。全体をざっと見た後、3年2組へ行く。担任の別所先生が、以前社会科でとてもよい授業をされていたからである。
教材は、オー・ヘンリーの代表作「賢者の贈り物」内容項目B(6)思いやり、感謝。TV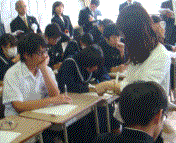
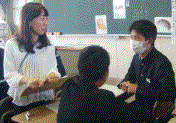 のCMにもなった、髪を売って夫のために時計の鎖を買った妻と、時計を売って妻のために櫛を買った夫のすれ違いを小説にしたものであまりにも有名。ヘンリーは物語の結末で、「この一見愚かな行き違いは、しかし、最も賢明な行為であった」としていたが、さて中学生はどう考えるか?
のCMにもなった、髪を売って夫のために時計の鎖を買った妻と、時計を売って妻のために櫛を買った夫のすれ違いを小説にしたものであまりにも有名。ヘンリーは物語の結末で、「この一見愚かな行き違いは、しかし、最も賢明な行為であった」としていたが、さて中学生はどう考えるか?
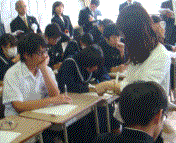
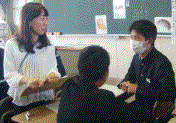 のCMにもなった、髪を売って夫のために時計の鎖を買った妻と、時計を売って妻のために櫛を買った夫のすれ違いを小説にしたものであまりにも有名。ヘンリーは物語の結末で、「この一見愚かな行き違いは、しかし、最も賢明な行為であった」としていたが、さて中学生はどう考えるか?
のCMにもなった、髪を売って夫のために時計の鎖を買った妻と、時計を売って妻のために櫛を買った夫のすれ違いを小説にしたものであまりにも有名。ヘンリーは物語の結末で、「この一見愚かな行き違いは、しかし、最も賢明な行為であった」としていたが、さて中学生はどう考えるか?
教室はコの字型。コの字型では教師が机間指導しにくいのが欠点だが、扶桑北中のコの字は 教師が入るスペースが作ってある。
教師が入るスペースが作ってある。
 教師が入るスペースが作ってある。
教師が入るスペースが作ってある。
別所先生のすごさは、短時間に生徒のノートから考えを把握し、座席表にメモ。そして意図的指名で「○○さん、○○さん、○○さん、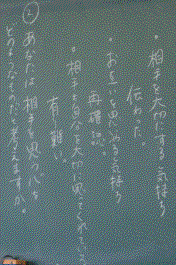 ○○さん、発表してください。」と指名をして授業を作っていくところ。私も見取りは速い方だが、さらに速い気がする。それを板書に構造化しながらまとめていく。
○○さん、発表してください。」と指名をして授業を作っていくところ。私も見取りは速い方だが、さらに速い気がする。それを板書に構造化しながらまとめていく。
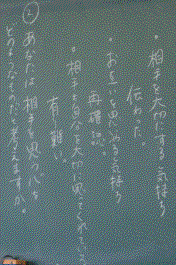 ○○さん、発表してください。」と指名をして授業を作っていくところ。私も見取りは速い方だが、さらに速い気がする。それを板書に構造化しながらまとめていく。
○○さん、発表してください。」と指名をして授業を作っていくところ。私も見取りは速い方だが、さらに速い気がする。それを板書に構造化しながらまとめていく。
後半の主発問は「この話から、あなたが考える「思いやりの心」とはどのようなものだろう。」の予定であった。しかし、実際には、「相手を大切に思う気持ちはどのようなものだと考えますか?」と発問された。これは、私も答え方に困った。生徒のワークシートもあまり書けていない。主発問は十分吟味しなければならないことを痛感する。
また、教室の雰囲気はとてもよいのだが、意見があまり繋がっていない気がした。自分の発信が主で、他者の意見を受信して自分なりに受け止め直したものとはあまり思えない。
改善点としては、意図的指名を連続で指名しないで、「○○さん」と一人をあてたら、次に「今の意見も踏まえて・・誰か・・○○さん」としていれば自ずから繋がるようになる。
小学校なら「○○さんと似ていて」「○○さんと違って」などの話形も他者の話を聴かせる基本である。
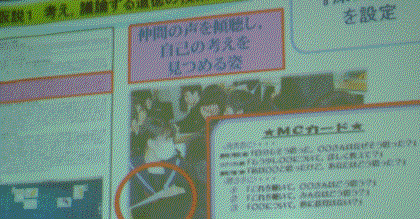 研究としての優れものは、「MCカード」。グループ討議の司会者用のマニュアルである。グループ討議は、とてもよい雰囲気であり全員が参加していた。実際には、別所学級ではもうMCカードが不要なレベルで、話し合いは成立していた。
研究としての優れものは、「MCカード」。グループ討議の司会者用のマニュアルである。グループ討議は、とてもよい雰囲気であり全員が参加していた。実際には、別所学級ではもうMCカードが不要なレベルで、話し合いは成立していた。
そして授業のバトンリレー。学年4クラスが順に改良しながらリレーしていく。これはすばらしい!道徳は学年全体で取り組んだ方が効果的である。参考にしたい。
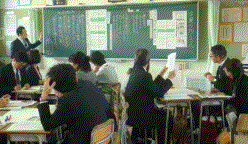 その後は全体会で研究発表会があった。研究理論はシンプルで、好感がもてる。公立学校の研究はこれぐらいが良いのではないかと思う。
その後は全体会で研究発表会があった。研究理論はシンプルで、好感がもてる。公立学校の研究はこれぐらいが良いのではないかと思う。
午後からは「道徳を語る会」。各教室で、残された板書を見ながら、授業者の意図の説明があった。
続いて、4人グループで、授業のよいところ、改善したらよいところを付箋紙に書いて話し合いが始まった。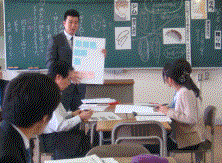
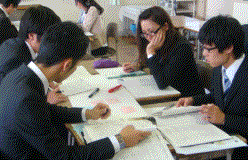 初対面の人とも話し合いができるのは、さすが大人である。その後はグループごとに発表。研究協議としては、全員が参加できるという点で、この方法がベ
初対面の人とも話し合いができるのは、さすが大人である。その後はグループごとに発表。研究協議としては、全員が参加できるという点で、この方法がベ ターなのではないかと思う。
ターなのではないかと思う。
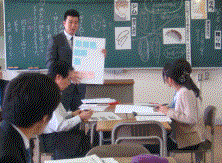
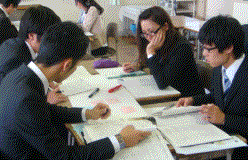 初対面の人とも話し合いができるのは、さすが大人である。その後はグループごとに発表。研究協議としては、全員が参加できるという点で、この方法がベ
初対面の人とも話し合いができるのは、さすが大人である。その後はグループごとに発表。研究協議としては、全員が参加できるという点で、この方法がベ ターなのではないかと思う。
ターなのではないかと思う。
その後は、京都産業大学の柴原弘志先生の講演である。扶桑北中学校には7回目の訪問である。
柴原弘志先生は、平成13年から文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官。道徳としては一般的な話で、新しい道徳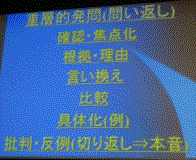 科に至る裏話のようなものは少なかった。
科に至る裏話のようなものは少なかった。
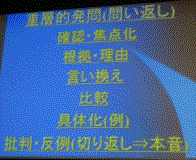 科に至る裏話のようなものは少なかった。
科に至る裏話のようなものは少なかった。
全体としては傾聴と問い返しを大切にし、話し合った結果を可視化するといういつもの話は理解されたと思う。
なかでも、柴原先生の問い返しの基本である、確認・焦点化、根拠・理由、言い換え、比較、具体化(例)、批判・反例(切り返し→本音)は参考になる。
教師が切り返すことで、子どもも切り返す視点で話を聴くようになる。すなわち他者の意見を聴き、関わる思考をするようになる。ぜひ取り入れていきたい。
別所先生の授業に戻る。
最後は、「相手が負担に考えるやさしさは、本当にやさしいとは言えない」という話になっていった。
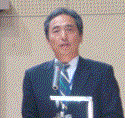
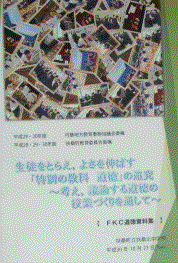 私はこの話は小学校高学年ぐらいがよいと思っている。思春期にある中学生はこの手の話は照れくさい。だから意見が出にくい。
私はこの話は小学校高学年ぐらいがよいと思っている。思春期にある中学生はこの手の話は照れくさい。だから意見が出にくい。
とはいえ、別所先生の授業力は確かだ。子どもの乗せ方、全員参加の手立てもできてる。
最後の中村校長先生のあいさつもすばらしいものであった。
また、別冊の「FKC道徳資料集」は圧巻である。教育情報の集積で、宝物になる。
扶桑北中学校の生徒のみなさん、先生方、お疲れ様でした。ありがとうございました。
2 平成30年度 岩倉南部中学校 研究発表会参加報告
10月30日に行われた研究発表会の様子を別紙で紹介しました。お疲れ様でした。
3 平成30年度 岐阜市立長良東小学校 校内拡大研究会 参観報告
10月20日に愛教大・真島先生と行ってきました。別紙で紹介しました。
4 平成30年度 岐阜市立長良小学校 第40回 研究発表会 参観報告
10月27日に行ってきました。別紙で紹介しました。
5 平成30年度 第3回学級力向上研究会(中部部会)
 この夏、本校の現職教育の講師としてお招きした、愛知教育大学の 磯部 征尊 先生 が主宰する研究会です。
この夏、本校の現職教育の講師としてお招きした、愛知教育大学の 磯部 征尊 先生 が主宰する研究会です。
「学級力」を高めるために取り組んだ実践について、一宮、関、名古屋、西宮、広島の先生による発表を聞きました。
それぞれ、学校規模や環境、発達段階(小2から中3まで)も異なるので、興味深く聞くことができました。
特に、荒れた学校を「学級力」で立て直した広島の先生の実践はすばらしく、これから取り組んでいく学校には貴重な先例になることでしょう。
最後の指導・助言を私が努めました。
その後は、多くの参加者と懇親を深めました。
6 教師力アップセミナー 横山浩之先生
10月28日には教師力アップセミナーを開催しました。講師は、今回で4回目の横山浩之先生です。福島県立医科大学 医学部 小児科学の教授です。
テーマは自立を目指す特別支援教育とは? 就労を目指した特別支援教育の在り方について
 いつも、短い言葉でずばっと教えてくださる横山節は今回も健在。
いつも、短い言葉でずばっと教えてくださる横山節は今回も健在。
ADHDや自閉スペクトラム症、知的障害の子ども達の特徴、コンサータ・ストラテラ・インチュ二ブの違い、そして今回のメイン「通常学級における特別支援教育」についてお話をしていただきました。
一人の発達障害の児童から学級崩壊状態になった事例から、その対処法を教えていただきました。
そのコツは、「学級経営を個別指導に優先させる」ことです。
詳しいことは、ぜひ横山先生の著書をご覧ください。
7 千代田区立麹町中学校
最近何かと話題の名門公立中「千代田区立麹町中学校」の挑戦を紹介します。
校長 工藤勇一先生がリードする「麹中メソッド」の柱は主に二つ、
1 社会で必要とされる学び方の習得を支援する
2 個性・特性を伸ばす機会を支援する
さらにこれを実践する中でキーワードとなるのは、次8つの言葉です。
・様々な場面で言葉や技能を使いこなす ・信頼できる知識や情報を収集し、有効に活用する
・感情をコントロールする ・将来を見通して計画的に行動する
・ルールを踏まえて、建設的に主張する ・他者の立場で物事を考える
・目標を達成するために他者と協働する ・意見の対立や理解の相違を解決する
そして、固定的学級担任なし、「心の教育」から「行動の教育」、「麹中塾」とサークル活動、5ミリ方眼のA4ノート、能率手帳、ツアー企画取材旅行、定期テスト廃止、宿題廃止、制服廃止 などの手を打っていったのです。
《参考》私立のような公立中「千代田区立麹町中学校」の挑戦
公立中学が挑む教育改革 http://wedge.ismedia.jp/category/kojimachi
岐阜市立研修校秋の発表会
11月 2日(金)陽南中学校
11月 3日(土)長良中学校、長良西小学校
11月 9日(金)東長良中学校
11月10日(土)加納中学校
11月17日(土)加納小学校
教師力アップセミナー今年度予定
第6回 1月12日(土)10:00~12:00 白石範孝 論理的に思考させる国語の授業づくり
第7回 2月17日(日)10:00~12:00 佐々木昭弘 理科授業の基礎・基本