次回は、第502回11月29日(木)です。
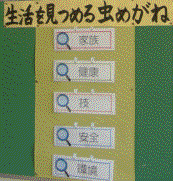 左は長良小学校の家庭科で、「虫めがね」としていました。
左は長良小学校の家庭科で、「虫めがね」としていました。
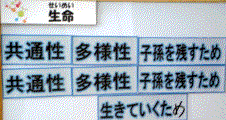 左は長良中の理科室。生物単元での「見方」です。確かに、この4つがあればおおかた説明がつきます。
左は長良中の理科室。生物単元での「見方」です。確かに、この4つがあればおおかた説明がつきます。
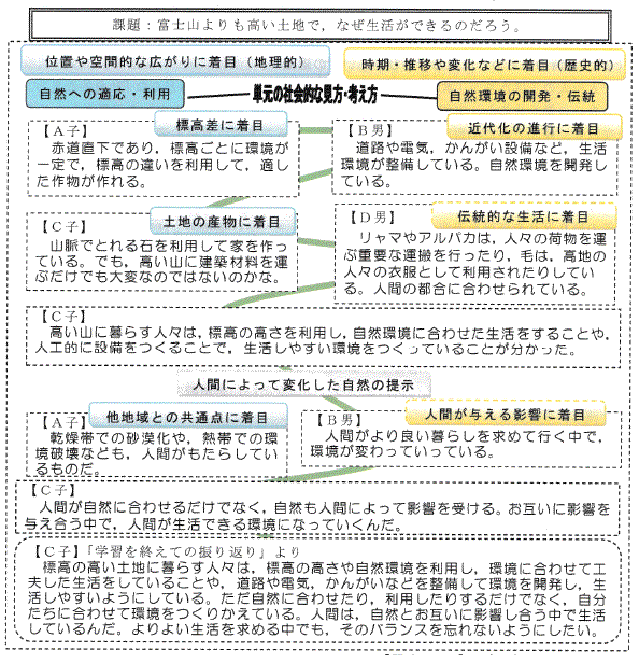 2 平成30年度 岐阜市立長良中学校 中間報告会
2 平成30年度 岐阜市立長良中学校 中間報告会
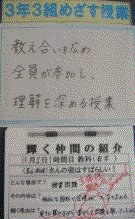
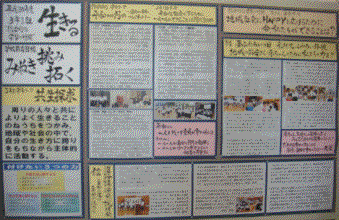 廊下の掲示では、生徒が学びを作っていることがわかります。東長良中学校のように、目指す授業や輝く仲間が紹介されています。
廊下の掲示では、生徒が学びを作っていることがわかります。東長良中学校のように、目指す授業や輝く仲間が紹介されています。
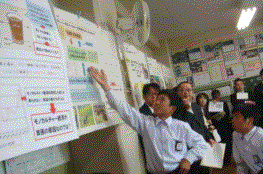 社会科ではアフリカ州の授業を参観しました。
社会科ではアフリカ州の授業を参観しました。
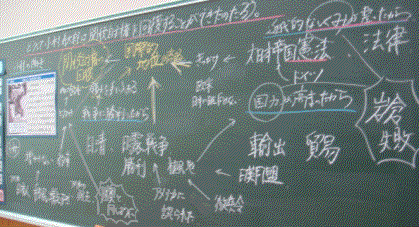
 膨大な資料を読み取り、駆使しながら
膨大な資料を読み取り、駆使しながら

 算数が始まる前には、一人一台のパソコンでドリル形式の問題を解いていました。正解すると赤い○が出て、次への意欲を刺激しています。
算数が始まる前には、一人一台のパソコンでドリル形式の問題を解いていました。正解すると赤い○が出て、次への意欲を刺激しています。
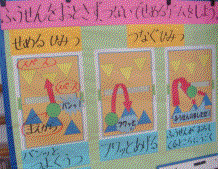 1年生の体育「風船バレーボール」は発達段階に合っているユニークな取組です。「せめるひみつ」「つなぐひみつ」を「バシッ」「フワッと」「うごく」のキーワードで押さえていきます。
1年生の体育「風船バレーボール」は発達段階に合っているユニークな取組です。「せめるひみつ」「つなぐひみつ」を「バシッ」「フワッと」「うごく」のキーワードで押さえていきます。
4 平成30年度 岐阜市立加納中学校中間研究報告会 参観報告
 加納小・加納中は、道徳や特別活動にも力を入れている学校ですが、秋には教科指導の発表を行っています。春は特別活動を公開しています。
加納小・加納中は、道徳や特別活動にも力を入れている学校ですが、秋には教科指導の発表を行っています。春は特別活動を公開しています。
 合唱もさすがに上手で、高音も下がりません。ハーモニーもしっかり響いています。
合唱もさすがに上手で、高音も下がりません。ハーモニーもしっかり響いています。
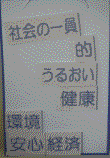
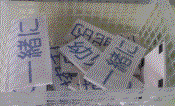 他の教室でも教科の「見方・考え方」が意識されていました。丹葉と同じように、見方カードが準備されている教科もありました。考えることは同じです。
他の教室でも教科の「見方・考え方」が意識されていました。丹葉と同じように、見方カードが準備されている教科もありました。考えることは同じです。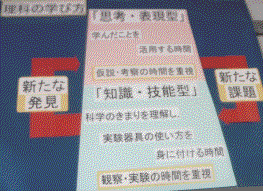
5 布袋ぶらりん日和

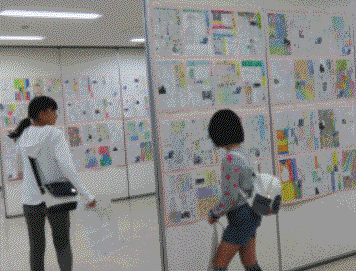


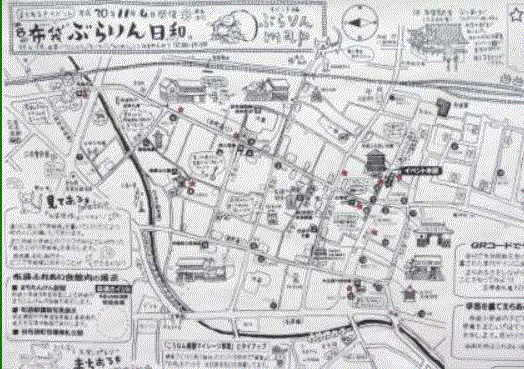 今年で8回目になる、まちづくりイベントです。布袋のまちにあるポイントを巡り歩きながら、いろいろな店で食べ歩きや買い物ができます。ボランティアは数百人。多くの人で作り上げています。
今年で8回目になる、まちづくりイベントです。布袋のまちにあるポイントを巡り歩きながら、いろいろな店で食べ歩きや買い物ができます。ボランティアは数百人。多くの人で作り上げています。


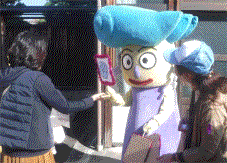

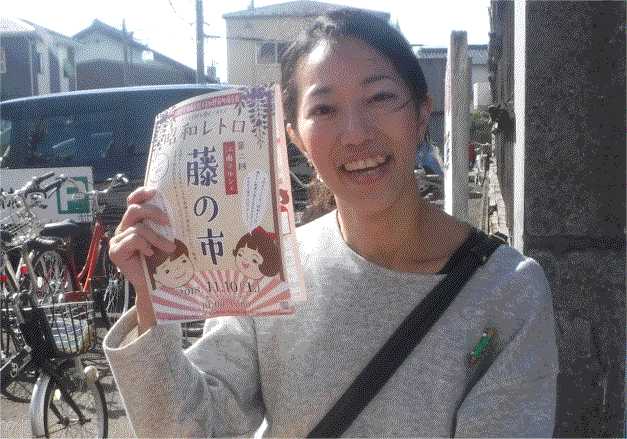 こちらは古知野の愛栄
こちらは古知野の愛栄 通り
通り を舞台にしたまちづくりイベントで、11月17日に行われました。リーダーは私の教え子で主婦です。主婦仲間でこれだけのイベントを作り上げるエネルギーには驚嘆します。布袋小のHPでも紹介し、多くの親子を見かけました。
を舞台にしたまちづくりイベントで、11月17日に行われました。リーダーは私の教え子で主婦です。主婦仲間でこれだけのイベントを作り上げるエネルギーには驚嘆します。布袋小のHPでも紹介し、多くの親子を見かけました。
 |
 |
|---|
シーズンオフシリーズの講師を募集します。
1月10日(木)資料集部会リハーサル
1月17日(木)土井 江戸幕府なぜ長く続いた?-家康・秀忠の知恵に学ぶ-
1月31日(木)
2月13日(水)
2月28日(木)
3月14日(木)
1 「見方」について
今回の研究対象である「見方」は、『学習指導要領 総則 解説編』の次の文が定義に該当します。時々読み返しましょう。(P.4)
3 指導計画の作成と内容の取扱い」において,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進めることを示した。
その際,以下の6点に留意して取り組むことが重要である。
オ 深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせることが重要になること。各教科等の「見方・考え方」は,「どのような視点で物事を捉え,どのような考え方で思考していくのか」というその教科等ならではの物事を捉える視点や考え方である。各教科等を学ぶ本質的な意義の中核をなすものであり,教科等の学習と社会をつなぐものであるこ とから,児童生徒が学習や人生において「見方・考え方」を自在に働かせることができるようにすることにこそ,教師の専門性が発揮されることが求められること。
とから,児童生徒が学習や人生において「見方・考え方」を自在に働かせることができるようにすることにこそ,教師の専門性が発揮されることが求められること。
 とから,児童生徒が学習や人生において「見方・考え方」を自在に働かせることができるようにすることにこそ,教師の専門性が発揮されることが求められること。
とから,児童生徒が学習や人生において「見方・考え方」を自在に働かせることができるようにすることにこそ,教師の専門性が発揮されることが求められること。
最後の文は特に大切で、「児童生徒が学習や人生において自在に働かせる」ことができなければなりません。すなわち、児童生徒レベルの概念であり、決して教師サイドの抽象的なものではないのです。
左は長良西小学校の家庭科の授業で「生活のカギ」と表現しています。「使いやすさ」「美しさ」など、わかりやすいカギです。
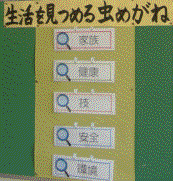 左は長良小学校の家庭科で、「虫めがね」としていました。
左は長良小学校の家庭科で、「虫めがね」としていました。
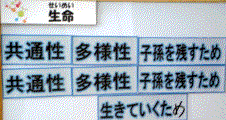 左は長良中の理科室。生物単元での「見方」です。確かに、この4つがあればおおかた説明がつきます。
左は長良中の理科室。生物単元での「見方」です。確かに、この4つがあればおおかた説明がつきます。
別紙資料は、「挿絵読解の視点」
「統計・グラフ読み取り10箇条」です。いずれも深い学びのためのものです。
次の資料は、長良中学校社会科部のレジメ(P.6)の資料です。
「アンデスの人が富士山よりも高い土地で、なぜ生活できるのだろう」という課題について、C子が他の生徒の見方・考え方とふれる中で、段階的に考えが広がり、深まっていることが読み取れます。ここでの水色部分・黄色部分が「見方」であり、その見方により考えた内容が書かれています。(なお、「見方」・「考え方」は分離できない場合もあり、常に無理に分ける必要はないと考えています。)
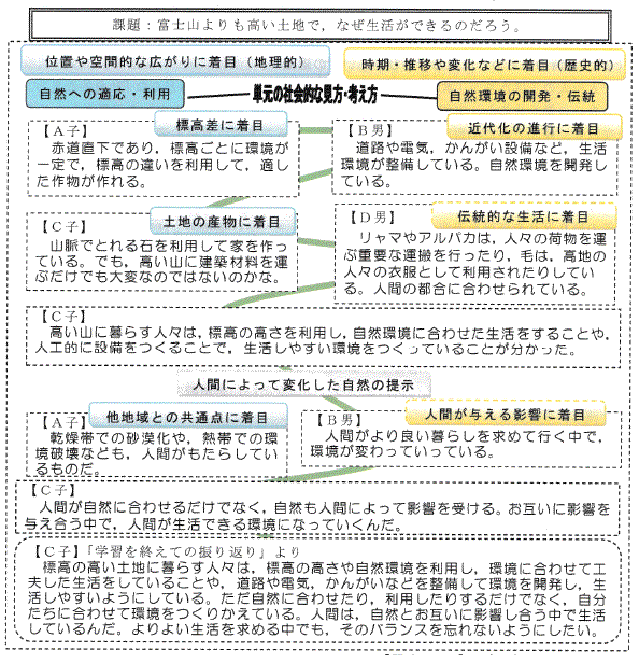 2 平成30年度 岐阜市立長良中学校 中間報告会
2 平成30年度 岐阜市立長良中学校 中間報告会
「生活をきり拓く子」を育てる学習指導
~子供が「見方・考え方」を働かせ、深い学びを通して「つけたい力」を身につける指導の在り方~
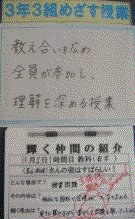
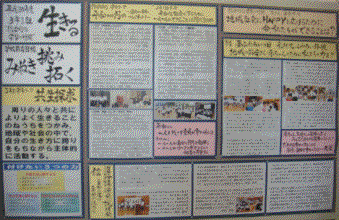 廊下の掲示では、生徒が学びを作っていることがわかります。東長良中学校のように、目指す授業や輝く仲間が紹介されています。
廊下の掲示では、生徒が学びを作っていることがわかります。東長良中学校のように、目指す授業や輝く仲間が紹介されています。
学級経営とそれに伴う総合的な学習の紹介もよく錬られています。これだけのものを構成し、表現する力はすばらしい。
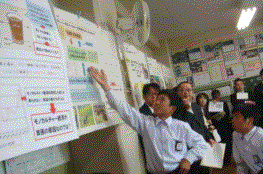 社会科ではアフリカ州の授業を参観しました。
社会科ではアフリカ州の授業を参観しました。
コートジボワールの一人の人の生き方を通して、アフリカが抱える問題を浮き彫りにしていきます。教材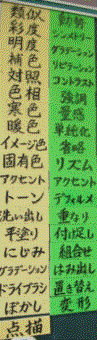 研究の深さには驚かされます。
研究の深さには驚かされます。
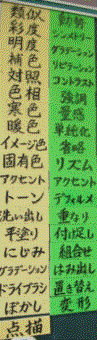 研究の深さには驚かされます。
研究の深さには驚かされます。
それにしても、一人一人の発言が長い!(野口先生に言わせれば「長すぎる。端的に言え」と叱られそう)そして、みんながよく聞いています。誰で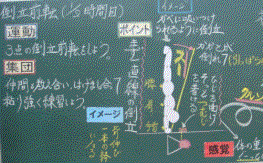
 も話せるのもすごい。
も話せるのもすごい。
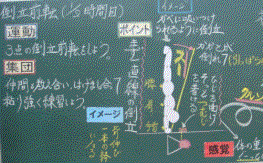
 も話せるのもすごい。
も話せるのもすごい。
倒立前転では、木の人形を使って、仲間にアドバイスをしていました。
右は美術室の掲示。これも「見方」になりうる言葉でしょう。
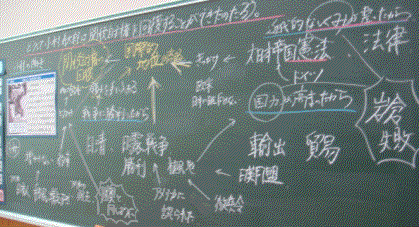
3 平成30年度 岐阜市立長良西小学校 中間研究発表会 参観報告
『社会を創造する子』を目指して ~既知で創り出す授業を通して~
6年生の社会科の授業は直接見てはいませんが、板書や掲示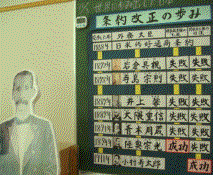 資料、子供たちのノートを見る限り、とてもレベルの高い授業が行われたことがわかります。
資料、子供たちのノートを見る限り、とてもレベルの高い授業が行われたことがわかります。
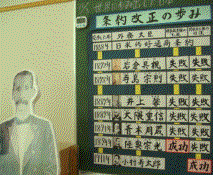 資料、子供たちのノートを見る限り、とてもレベルの高い授業が行われたことがわかります。
資料、子供たちのノートを見る限り、とてもレベルの高い授業が行われたことがわかります。
 膨大な資料を読み取り、駆使しながら
膨大な資料を読み取り、駆使しながら
論を組み立てています。中学校レベル、またはそれ以上かもしれません。
別紙で単元構成表と本時の展開を紹介します。

 算数が始まる前には、一人一台のパソコンでドリル形式の問題を解いていました。正解すると赤い○が出て、次への意欲を刺激しています。
算数が始まる前には、一人一台のパソコンでドリル形式の問題を解いていました。正解すると赤い○が出て、次への意欲を刺激しています。
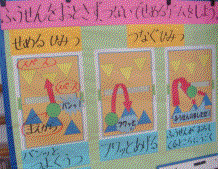 1年生の体育「風船バレーボール」は発達段階に合っているユニークな取組です。「せめるひみつ」「つなぐひみつ」を「バシッ」「フワッと」「うごく」のキーワードで押さえていきます。
1年生の体育「風船バレーボール」は発達段階に合っているユニークな取組です。「せめるひみつ」「つなぐひみつ」を「バシッ」「フワッと」「うごく」のキーワードで押さえていきます。
その他、多くの参考になる情報を得ることができました。。
4 平成30年度 岐阜市立加納中学校中間研究報告会 参観報告
11月10日(土)に行われた会に、午前の前半に参加しました
テーマは「社会で生きる力の育成~見方・考え方を働かせながら、自分の考えを広げ深める教科指導~」です。
 加納小・加納中は、道徳や特別活動にも力を入れている学校ですが、秋には教科指導の発表を行っています。春は特別活動を公開しています。
加納小・加納中は、道徳や特別活動にも力を入れている学校ですが、秋には教科指導の発表を行っています。春は特別活動を公開しています。
まず全校の教室や掲示物等を見て回りましたが、学 級経営・学年経営、生徒会活動などへの力の入れ方の強さを随所に感じました。左は学年の掲示です。右は丸太を彫り込
級経営・学年経営、生徒会活動などへの力の入れ方の強さを随所に感じました。左は学年の掲示です。右は丸太を彫り込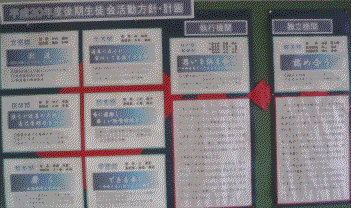 んでいます。
んでいます。
 級経営・学年経営、生徒会活動などへの力の入れ方の強さを随所に感じました。左は学年の掲示です。右は丸太を彫り込
級経営・学年経営、生徒会活動などへの力の入れ方の強さを随所に感じました。左は学年の掲示です。右は丸太を彫り込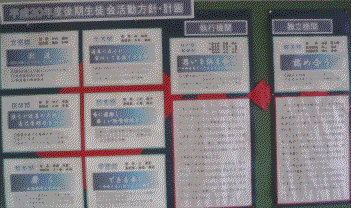 んでいます。
んでいます。
左が生徒会の掲示です。
このほか、「地域補導委員会の方々のお言葉」「部活動連絡」「歴代生徒会長」など、見応えがありました。
さらに、生徒による学び方チェックも充実しており、参観者に、学び方や授業への参加態度への感想尋ねてきます。こ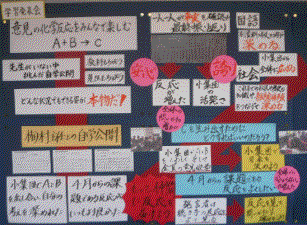 のあたりは東長良中学校のよいところを取り入れています。笑顔でのあいさつもできており、申し分ありません。
のあたりは東長良中学校のよいところを取り入れています。笑顔でのあいさつもできており、申し分ありません。
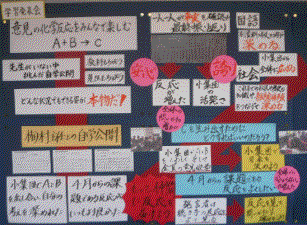 のあたりは東長良中学校のよいところを取り入れています。笑顔でのあいさつもできており、申し分ありません。
のあたりは東長良中学校のよいところを取り入れています。笑顔でのあいさつもできており、申し分ありません。
左は学年の方針を受け手の学級の掲示です。
 合唱もさすがに上手で、高音も下がりません。ハーモニーもしっかり響いています。
合唱もさすがに上手で、高音も下がりません。ハーモニーもしっかり響いています。
さすがに加納小・茜部小の卒業生です。
社会科の授業は、松平定信と田沼意次の比較、議院内閣制と大統領制の比較を検討する授業でした。歴史を参観しましたが、話し合いにより深まっていく姿が見られました。
実際には、田沼政治=わいろ政治というのは、現在ではかなり否定されています。その根拠が田沼政治を批判した松平定信の関係者によるものばかりだからです。明治政府が田沼を見本にしているものが多く、田沼の先見性が再評価されています。ここでは「農業・商業」「自由・規制」「開国・鎖国」が「見方」です。別紙をご覧ください。
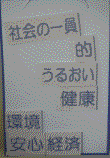
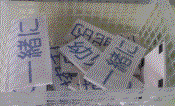 他の教室でも教科の「見方・考え方」が意識されていました。丹葉と同じように、見方カードが準備されている教科もありました。考えることは同じです。
他の教室でも教科の「見方・考え方」が意識されていました。丹葉と同じように、見方カードが準備されている教科もありました。考えることは同じです。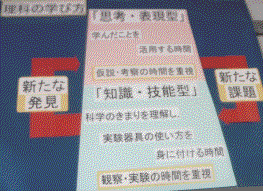
右は理科の学び方。見て納得の内容です。 下は技術/家庭科の学び方。教科の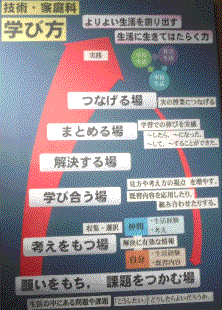 特長がよく表現されています。
特長がよく表現されています。
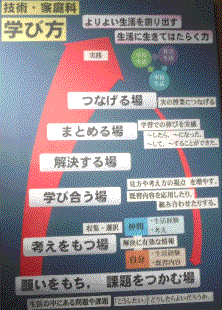 特長がよく表現されています。
特長がよく表現されています。
右下は、ロッカーの整頓方法。やはり、こうした見えるかは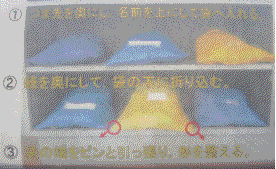 大切です。実際のロッカーは下の通り。見事です。これを生徒が作ったのなら、さらにすばらしい!
大切です。実際のロッカーは下の通り。見事です。これを生徒が作ったのなら、さらにすばらしい!
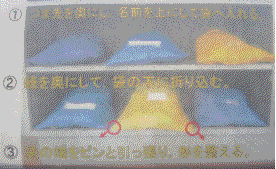 大切です。実際のロッカーは下の通り。見事です。これを生徒が作ったのなら、さらにすばらしい!
大切です。実際のロッカーは下の通り。見事です。これを生徒が作ったのなら、さらにすばらしい!
本当は自習も見たかったのです が、今回は見ることができませんでした。掲示物を見ると生徒による「自学」の文字が多く、かなりの自信がありそうです。
が、今回は見ることができませんでした。掲示物を見ると生徒による「自学」の文字が多く、かなりの自信がありそうです。
 が、今回は見ることができませんでした。掲示物を見ると生徒による「自学」の文字が多く、かなりの自信がありそうです。
が、今回は見ることができませんでした。掲示物を見ると生徒による「自学」の文字が多く、かなりの自信がありそうです。
一時期は東長良化しましたが、そのよいところを取り入れ、高いレベルを維持し続けている,すばらしい学校でした。
5 布袋ぶらりん日和
11月4日(日)に行われた地域のイベントです。
今年は悪天候により、千人ほどの参加者でしたが、昨年は多くの人で賑わいました。住民による手作りのまちづくりには敬意を表します。布袋小学校の児童や布袋中生徒も活躍していました。
6 江南マルシェ 藤の市


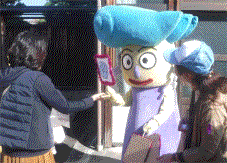

 通り
通り を舞台にしたまちづくりイベントで、11月17日に行われました。リーダーは私の教え子で主婦です。主婦仲間でこれだけのイベントを作り上げるエネルギーには驚嘆します。布袋小のHPでも紹介し、多くの親子を見かけました。
を舞台にしたまちづくりイベントで、11月17日に行われました。リーダーは私の教え子で主婦です。主婦仲間でこれだけのイベントを作り上げるエネルギーには驚嘆します。布袋小のHPでも紹介し、多くの親子を見かけました。
各地域で、このようなまちづくりイベントが行われ、発展することを願っています。そこから地域のコミュニティが生まれるのです。
岐阜市立研修校秋の発表会
11月17日(土)加納小学校
教師力アップセミナー今年度予定
第6回 1月12日(土)10:00~12:00 白石範孝 論理的に思考させる国語の授業づくり
第7回 2月17日(日)10:00~12:00 佐々木昭弘 理科授業の基礎・基本