次回は、第507回2月13日()高橋先生による模擬授業です。
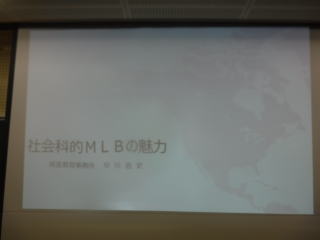 |
 |
 |
 |
 |
|---|
シーズンオフシリーズの講師を紹介します。
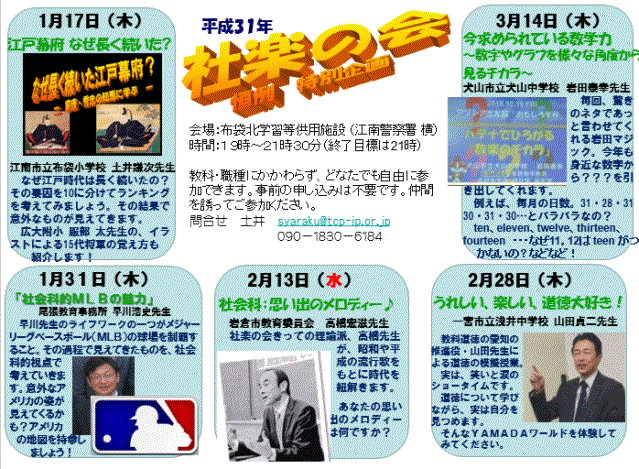

 教務主任が、毎日このブログの名言を印刷して職員に配付しています。
教務主任が、毎日このブログの名言を印刷して職員に配付しています。
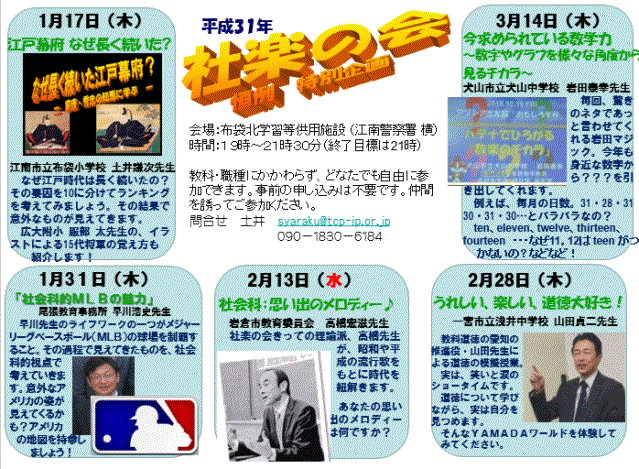
1 模擬授業「社会科的MLBの魅力」
早川先生によるこだわりの授業でメジャーリーグを社会科の視点で斬っていきました。
30球団中、13のホーム球場に訪れた早川先生の、行ったものにしかわからない魅力を教えていただきました。
また、実際にホームチームへの応援の仕方も体験しました。
感じたことは、ヨーロッパの人がサッカーが好きなように、アメリカ人が根っから野球が好きだということ。
ベースビールと野球は違う。球場も含めて、ベースボールはおおざっぱ。野球は武士道に通じる緻密さがある。
アメリカ全土に、冷帯から熱帯、乾燥帯まで、いろいろな気候帯に球場があり、個性が豊かなこと。
イギリスから独立し、西部を開拓して国をつくっていった愛国心と郷土愛が、ベースボールの根底にあること。
まだまだ、いろいろと感じるところがありました。
社会認識が大きく広がる授業でした。
30球団中、13のホーム球場に訪れた早川先生の、行ったものにしかわからない魅力を教えていただきました。
また、実際にホームチームへの応援の仕方も体験しました。
感じたことは、ヨーロッパの人がサッカーが好きなように、アメリカ人が根っから野球が好きだということ。
ベースビールと野球は違う。球場も含めて、ベースボールはおおざっぱ。野球は武士道に通じる緻密さがある。
アメリカ全土に、冷帯から熱帯、乾燥帯まで、いろいろな気候帯に球場があり、個性が豊かなこと。
イギリスから独立し、西部を開拓して国をつくっていった愛国心と郷土愛が、ベースボールの根底にあること。
まだまだ、いろいろと感じるところがありました。
社会認識が大きく広がる授業でした。
2 「自衛隊DVDコレクション」第1号

DVDの内容は、他社(バナプル)の旧作のパッケージ替えです。
バナプルhttp://www.banaple.co.jp/ 2006年から発売されているシリーズの12作目です。
3 犬山城を歩く~愛知観光 歴史と文学の旅/左大臣光永
愛知県の犬山城を歩きます。木曽川のほとりにたたずむ犬山城は李白の詩になぞらえて「白帝城」と呼ばれました。徳川家康と羽柴秀吉の間で戦われた「小牧・長久手の合戦」の時、羽柴秀吉が拠点としました。今も城下町の風情がただよいます。
音声と写真でお楽しみください。
左大臣光永さんのメルマガを長い間購読しています。
4 文部科学省関係資料
(1)中央教育審議会(第121回) 配付資料
資料1-1 2018年度文部科学省第2次補正予算案 (PDF:155KB)
資料1-2 2019年度文部科学関係予算(案)のポイント (PDF:12930KB)
資料1-3 2019年度文部科学関係税制改正要望事項の結果(概要) (PDF:790KB)
資料2-1 教育再生実行会議第十一次提言中間報告概要 (PDF:243KB)
資料2-2 教育再生実行会議第十一次提言中間報告 (PDF:795KB)
資料3-1 「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申素案)」に関する意見募集の結果について (PDF:318KB)
資料3-2 新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申(案)) (PDF:990KB)
資料3-3 「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン(案)」に関する意見募集に寄せられた御意見等について (PDF:270KB)
資料3-4 公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン(案) (PDF:118KB)
資料4-1 第9期中央教育審議会の主な答申、報告等について (PDF:246KB)
資料4-2 教育振興基本計画部会の審議の状況について (PDF:242KB)
資料5 生涯学習分科会の審議の状況について (PDF:619KB)
資料6 初等中等教育分科会の審議の状況について (PDF:1104KB)
資料7 大学分科会の審議の状況について (PDF:4751KB)
資料7参考資料 2040年を見据えた大学院教育のあるべき姿(審議まとめ要旨) (PDF:262KB)
資料7参考資料 2040年を見据えた大学院教育のあるべき姿(審議まとめ) (PDF:436KB)
(2)主権者教育推進会議(第2・3回) 配付資料 公民の授業に関係します。
第2回
(資料1)主権者教育推進会議(第1回)における主な意見等
(資料2)新しい学習指導要領における主な記述等 (PDF:2911KB)
(資料3)ヒアリング団体の発表資料 (PDF:2462KB)
第3回
(資料1)主権者教育推進会議(第2回まで)における主な意見等
(資料2)新しい学習指導要領における主な記述等 (PDF:2358KB)
(資料3)OECDにおけるAgencyに関する議論について (PDF:1152KB)
(資料4)ヒアリング団体の発表資料 (PDF:125KB)
(3)新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合 的な方策について(答申)
併せて、ガイドラインも確定しました。
5 森川正樹の“教師の笑顔向上”ブログ
 教務主任が、毎日このブログの名言を印刷して職員に配付しています。
教務主任が、毎日このブログの名言を印刷して職員に配付しています。
授業における<間(ま)>2018年12月23日
「間」は奥が深い。
これをコントロールできるようになると授業が圧倒的に変わると思っています。
「間」は<かかわり>を生むからです。
仲間とのかかわり。
教材とのかかわり。
そして付け加えるなら、「間」を生み出すには一方で圧倒的な活動が必要だ、ということです。
圧倒的に考える。
圧倒的に書く。
圧倒的に話す。
これがあるから、「間」が生きる。
「間」を生かすために、「工夫」をする。
「間」を生むために、「思考させる場面」を意識する。
「真」ということを軸に授業を組み立ててみると色々なことが見えてきます。
「教室」は自分の人生が出る場所2018年09月30日 テーマ:自分磨き
やさしいのと、馴れ馴れしいのは違う。
面白いとふざけているのは違う。
些細なことで人は人を傷つけている。
人にかける言葉にちょっと気をつかえたり、ちょっとした礼儀をわきまえていたり、些細な声や、少ない側の気持ちに心を寄せられる大人になりたい。
迎合することが人付き合いではないし、おべんちゃらを言うことが上手な生き方ではない。
拒否すべき事は拒否すべきだし、「え?ちょっとそれは違うんじゃないの?」と言えること。
んなことを考えていたら、そういったことが背景になって、私たち教師は子どもに接しているのだろうと思った。
子どもに出ているのだろう・・・と。
自分の生き方が直接、瞬時に多くの子どもたちに伝わる、伝わってしまう、という仕事なんだね。私たちの<教師>という仕事は。
優しく、心穏やかな大人でいることですね。
子どもたちに相対するんだから。
6 第196回国会 安倍内閣総理大臣 施政方針演説 教育部分
このブログでは、施政方針演説の教育部分を毎回切り取っています。
【教育無償化】
我が国の持続的な成長にとって最大の課題は、少子高齢化です。平成の30年間で、出生率は1.57から1.26まで落ち込み、逆に、高齢化率は10%から30%へと上昇しました。
世界で最も速いスピードで少子高齢化が進む我が国にあって、もはや、これまでの政策の延長線上では対応できない。次元の異なる政策が必要です。
子どもを産みたい、育てたい。そう願う皆さんの希望をかなえることができれば、出生率は1.8まで押し上がります。しかし、子どもたちの教育にかかる負担が、その大きな制約となってきました。
これを社会全体で分かち合うことで、子どもたちを産み、育てやすい日本へと、大きく転換していく。そのことによって、「希望出生率1.8」の実現を目指します。
10月から3歳から5歳まで全ての子どもたちの幼児教育を無償化いたします。小学校・中学校9年間の普通教育無償化以来、実に70年ぶりの大改革であります。
待機児童ゼロの目標は、必ず実現いたします。今年度も17万人分の保育の受け皿を整備します。保育士の皆さんの更なる処遇改善を行います。自治体の裁量を拡大するなどにより、学童保育の充実を進めます。
来年4月から、公立高校だけでなく、私立高校も実質無償化を実現します。真に必要な子どもたちの高等教育も無償化し、生活費をカバーするために十分な給付型奨学金を支給します。
家庭の経済事情にかかわらず、子どもたちの誰もが、自らの意欲と努力によって明るい未来をつかみ取ることができる。そうした社会を創り上げてこそ、アベノミクスは完成いたします。
子どもたちこそ、この国の未来そのものであります。
多くの幼い命が、今も、虐待によって奪われている現実があります。僅か5歳の女の子が、死の間際につづったノートには、日本全体が大きなショックを受けました。
子どもたちの命を守るのは、私たち大人全員の責任です。
あのような悲劇を二度と繰り返してはなりません。何よりも子どもたちの命を守ることを最優先に、児童相談所の体制を抜本的に拡充し、自治体の取り組みを警察が全面的にバックアップすることで、児童虐待の根絶に向けて総力を挙げてまいります。
(中略)
来年から全ての小学校でプログラミングを必修とします。中学校、高校でも、順次、情報処理の授業を充実し、必修化することで、子どもたちの誰もが、人工知能などのイノベーションを使いこなすリテラシーを身に付けられるようにします。
ほとんど厚労省関係ばかりで、文科省関係はプログラミング教育のみでした。
こうして毎回教育部分を切り取って比較すると、それぞれの政権の教育への思いがわかります。
教師力アップセミナー今年度予定
第7回 2月17日(日)10:00~12:00 佐々木昭弘 理科授業の基礎・基本
