次回は、第515回7月4日()です。
理論を紹介します。
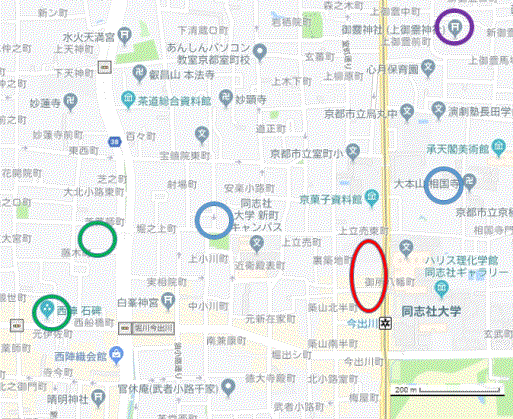 6月14日(金)アソシア志友館関西おもしろ学校で授業をしてきました。会場が西陣産業会館だったので、2時間ほど前に到着し、応仁の乱の舞台を歩いてきました。
6月14日(金)アソシア志友館関西おもしろ学校で授業をしてきました。会場が西陣産業会館だったので、2時間ほど前に到着し、応仁の乱の舞台を歩いてきました。
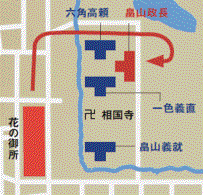
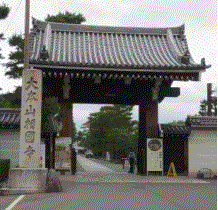 細川勝元・畠山政長・足利義視vs.山名宗全・畠山義就・足利義尚という図式の中で、文正2年1月18日、上御霊神社に陣を敷いた畠山政長を、畠山義就が攻撃、政長は自害を装って細川勝元邸に逃亡。これによって宗全は将軍邸(室町亭)を占拠し、細
細川勝元・畠山政長・足利義視vs.山名宗全・畠山義就・足利義尚という図式の中で、文正2年1月18日、上御霊神社に陣を敷いた畠山政長を、畠山義就が攻撃、政長は自害を装って細川勝元邸に逃亡。これによって宗全は将軍邸(室町亭)を占拠し、細 川は幕府中枢から追われるこ
川は幕府中枢から追われるこ とになりましたが退去せず、都において戦いが行なわれることになりました。 同年10月には、東軍の要地・相国寺を西軍が占領しました。その後、畠山政長らを相国寺に向かわせる。政長は相国寺内
とになりましたが退去せず、都において戦いが行なわれることになりました。 同年10月には、東軍の要地・相国寺を西軍が占領しました。その後、畠山政長らを相国寺に向かわせる。政長は相国寺内
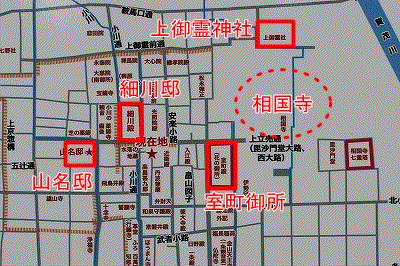 に陣取る一色義直、六角高頼軍を急襲し、両軍を混乱に陥れ、相国寺の奪還に成功。
に陣取る一色義直、六角高頼軍を急襲し、両軍を混乱に陥れ、相国寺の奪還に成功。
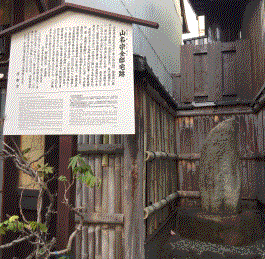
 応仁の乱の軍勢数は、大幅な誇張ではないかというのが今回の感想です。呉座 勇一氏『応仁の乱』ではどうなっているのかな?
応仁の乱の軍勢数は、大幅な誇張ではないかというのが今回の感想です。呉座 勇一氏『応仁の乱』ではどうなっているのかな?
3 アソシア志友館・関西おもしろ学校 参考動画
(1)歴史秘話ヒストリア ワシはコレで天下をとりました 徳川家康の読書愛 https://www.youtube.com/watch?v=NfAb8fFZ5O8
(2)知恵泉「二代目はつらいよ 偉大な先代を持ったら 徳川秀忠」
(3)その時歴史が動いた 「徳川四天王に学べ 組織のためにいかに生きるか」
(4)そのとき歴史は動いた「大坂の陣 豊臣家滅亡す 徳川家康 非情の天下取り」
(5)歴史ミステリー「家康はなぜ江戸を選んだのか?」
(6)歴史ドキュメント ゼロワン 江戸、東京の誕生

 戦国魂は戦国時代・戦国武将をプロデュースする企画集団です。各自治体の地域活性化や企業コラボレーション、ものづくり、観光などの支援で社会に貢献します。
戦国魂は戦国時代・戦国武将をプロデュースする企画集団です。各自治体の地域活性化や企業コラボレーション、ものづくり、観光などの支援で社会に貢献します。
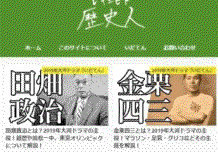 歴史関係サイトとしては比較的歴史は新しく、これから期待のサイトです。
歴史関係サイトとしては比較的歴史は新しく、これから期待のサイトです。
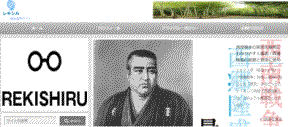
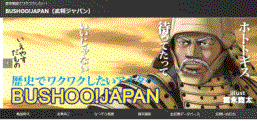 (6) BUSHOO!JAPAN(武将ジャパン)
(6) BUSHOO!JAPAN(武将ジャパン)
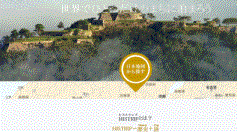

(8)歴史研究所-裏辺研究所
5 トゥキュディデスの罠とは
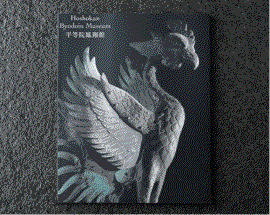
歴史倶楽部
 |
 |
 |
|---|
社楽の会 今年度 開催予定 すべて木曜日
| 510回 4/25 | 511回 5/9 | 512回 5/23 | 513回 6/6 | 514回 6/20 | 515回 7/4回 |
| 516回 9/5 | 517回 9/19 | 518回 10/3 | 519回 10/17 | 520回 10/31 | 521回 11/14 |
| 522回 11/28 | 523回 12/12 | 524回1/9リハ | 525回1/16 1 | 526回1/302 | 527回2/133 |
| 528回2/274 | 529回3/125 | 丹葉地区研修会 1/11 | 愛社研冬期研修会 1/18 | ||
1 岐阜大学教育学部附属小学校 研究中間報告より
理論を紹介します。
テーマ 学びを深める児童の育成-「見通す力」「柔軟に表す力」「学びを捉える力」を育む-
学びを深める児童の姿とは
一人一人が学習意欲をもって学びに向かい、『もの・こと・ひと』と学び、納得できる内容をつくりだし、自己の変容を自覚しながら学び続ける姿
そのために必要な3つの資質・能力;「見通す力」「柔軟に表す力」「学びを捉える力」
① 見通す力とは
・ 児童が課題解決や目的達成の価値を知ること
・ 児童が課題解決や目的達成までの見通しを持つこと
・ 教師が物理的な側面(教室環境や学習用具など)や対人的な側面(なかまとの関わり方 や交流の仕組みなど)から学習環境を整えること
② 柔軟に表す力とは
・ 導入または展開時に、「『何を』『どのように』学ぶのか」を確かめること
・ 見方・考え方を働かせるようにするための、意図的な働きかけを行うこと
・ 単元や題材を通して見方・考え方を働かせるような計画を立てること
③ 学びを捉える力とは
・ 学習活動後の確かめの方法に工夫を入れること
・ 活動中、活動の合間に自己の変容を自覚できるように、意図的に働きかけたり、価値づ けたりすること
・ 授業とそれ以外の教育活動(日常生活を含む)の関連性を整理して結びつけること
・ 何をめざせば良いのか(評価基準)と何をすれば良いのか(学習方法)を児童と教師の 間で共通理解しておくこと
2 応仁の乱の舞台を歩く
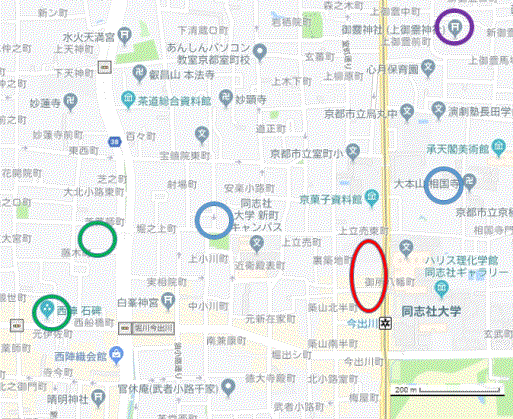 6月14日(金)アソシア志友館関西おもしろ学校で授業をしてきました。会場が西陣産業会館だったので、2時間ほど前に到着し、応仁の乱の舞台を歩いてきました。
6月14日(金)アソシア志友館関西おもしろ学校で授業をしてきました。会場が西陣産業会館だったので、2時間ほど前に到着し、応仁の乱の舞台を歩いてきました。
応仁の乱の直接の原因は、畠山氏の家督相続争い。管領・畠山持国は甥の政長を養子にしましたが、その後、実子・義就が生まれ、家督争いに発展しました。
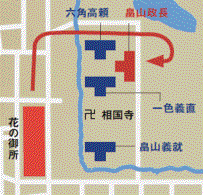
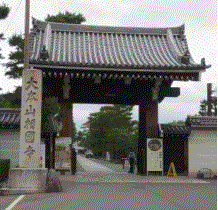 細川勝元・畠山政長・足利義視vs.山名宗全・畠山義就・足利義尚という図式の中で、文正2年1月18日、上御霊神社に陣を敷いた畠山政長を、畠山義就が攻撃、政長は自害を装って細川勝元邸に逃亡。これによって宗全は将軍邸(室町亭)を占拠し、細
細川勝元・畠山政長・足利義視vs.山名宗全・畠山義就・足利義尚という図式の中で、文正2年1月18日、上御霊神社に陣を敷いた畠山政長を、畠山義就が攻撃、政長は自害を装って細川勝元邸に逃亡。これによって宗全は将軍邸(室町亭)を占拠し、細 川は幕府中枢から追われるこ
川は幕府中枢から追われるこ とになりましたが退去せず、都において戦いが行なわれることになりました。 同年10月には、東軍の要地・相国寺を西軍が占領しました。その後、畠山政長らを相国寺に向かわせる。政長は相国寺内
とになりましたが退去せず、都において戦いが行なわれることになりました。 同年10月には、東軍の要地・相国寺を西軍が占領しました。その後、畠山政長らを相国寺に向かわせる。政長は相国寺内
結局、痛み分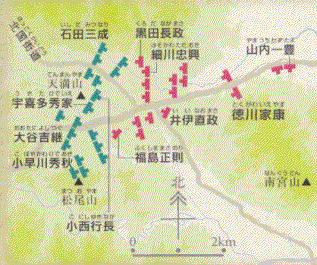 け。いたずらに死者が出ただけ。
け。いたずらに死者が出ただけ。
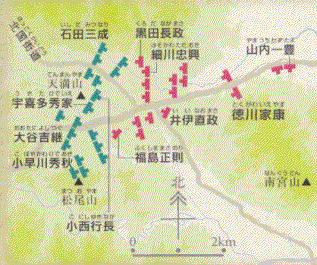 け。いたずらに死者が出ただけ。
け。いたずらに死者が出ただけ。
<歩いてみて気づいたこと>
西陣と東陣があまりにも近く、しかも当時も家が並んでいたはず。
同年5月20日、山名宗全が評定を開き、五辻通大宮東に本陣をおいた頃の兵力は、『応仁記』によれば東軍が16万、西軍が11万以上であったと記されています。両軍の本陣は、わずか数百m。そこに20万人以上?
片や、関ヶ原の戦いでは、西軍10万、東軍7万の軍勢。しかも当時は荒れ地、もしくは耕作地。
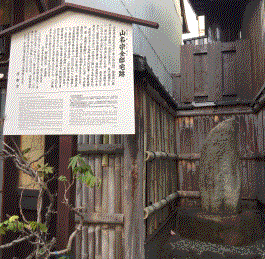
3 アソシア志友館・関西おもしろ学校 参考動画
(1)歴史秘話ヒストリア ワシはコレで天下をとりました 徳川家康の読書愛 https://www.youtube.com/watch?v=NfAb8fFZ5O8
(2)知恵泉「二代目はつらいよ 偉大な先代を持ったら 徳川秀忠」
(3)その時歴史が動いた 「徳川四天王に学べ 組織のためにいかに生きるか」
(4)そのとき歴史は動いた「大坂の陣 豊臣家滅亡す 徳川家康 非情の天下取り」
(5)歴史ミステリー「家康はなぜ江戸を選んだのか?」
(6)歴史ドキュメント ゼロワン 江戸、東京の誕生

4 歴史ポータルサイト
(1)歴人マガジン https://rekijin.com/
歴史ファンはもちろん、まだその楽しさを知らない人にも歴史を楽しんでもらいたい。
歴人マガジンはそんな思いから「歴史をもっと楽しくするメディア」として誕生しました。
歴史の楽しみ方はまさに十人十色。歴人マガジンは時代や国を問わずに、様々な切り口で歴史をテーマにした情報をお届けしていきます。
 戦国魂は戦国時代・戦国武将をプロデュースする企画集団です。各自治体の地域活性化や企業コラボレーション、ものづくり、観光などの支援で社会に貢献します。
戦国魂は戦国時代・戦国武将をプロデュースする企画集団です。各自治体の地域活性化や企業コラボレーション、ものづくり、観光などの支援で社会に貢献します。
(3)歴ログ -世界史専門ブログ- https://reki.hatenablog.com/
おもしろい世界史のネタをまとめています。
(4)歴史人(レキシビト) https://history-men.com/
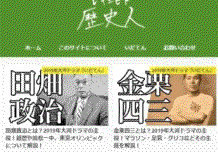 歴史関係サイトとしては比較的歴史は新しく、これから期待のサイトです。
歴史関係サイトとしては比較的歴史は新しく、これから期待のサイトです。
大河ドラマ関係に、特に力を入れています。
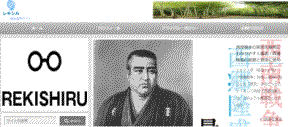
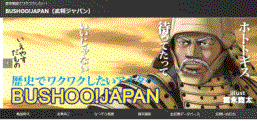 (6) BUSHOO!JAPAN(武将ジャパン)
(6) BUSHOO!JAPAN(武将ジャパン)
歴史戦国でワクワクしたい!
(7)HISTRIP https://histrip.jp/
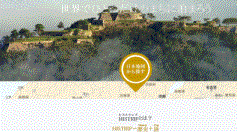
日本中に存在する特有の伝統文化や奥深い歴史残る数々のまち。
実際にひとつずつ訪れ、その土地にしかない魅力をあつめた、まだ見ぬ日本と出会える歴史旅専門サイトです。

(8)歴史研究所-裏辺研究所
(9)歴史人公式ホームページ
エンターテイメント歴史マガジンのHP。おもしろいネタが満載です。
5 トゥキュディデスの罠とは
覇権国が、その地位を維持するための高い負担に耐えかねて、自ら覇権国の地位を降りる形で覇権国の交代が実現するケースよりも、覇権国同士の軍事的対立が覇権国の交代をもたらすケースの方が、歴史的に見ればより一般的なのではないか。こうした見方を米国の政治学者グレハム・アリソンは「ツゥキジデスの罠(The Thucydides Trap)」として警告する。ツゥキジデスは古代ギリシアの歴史家で、その著書「戦史」のなかで、海上交易を抑える経済大国としてアテナイが台頭し、陸上における軍事的覇権を事実上握るスパルタの間で対立が生じて、長年にわたる戦争、ペロポネソス戦争が勃発したことを記述している。
そこから、急速に台頭する大国が既成の支配的な大国とライバル関係に発展する際に、当初はお互いに望まなかった軍事的な対立に、いずれは及んでしまうという様子を、ツゥキジデスの罠と表現している。
ハーバード大学のベルファー・センターの研究によると、過去500年にわたる新興国とその挑戦を受ける覇権国との関係を示す16の事例で、実に12件までが戦争に至ったと分析している。また、20世紀に日本が台頭した際の日露戦争、太平洋戦争などもこれにあたるという。戦争を回避できた事例でも、覇権国が国際システムやルールの改変などの大きな代償を強いられたとされる。 「覇権安定論とツゥキジデスの罠」より一部引用
・中国の新興はトゥキュディデスの罠か? https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/53254
・米中戦争勃発の可能性は「16分の12」だ! 500年間のケース分析は警告する
・覇権争いの序章としての米中貿易戦争/論座
・トゥキディデスの罠ということ/教育コラムマガジン
・アメリカの国際政治の底流に流れる「トゥキディデスの罠」とは何か
・米中覇権闘争とツキディデスの罠 http://jein.jp/jifs/scientific-topics/1656-topic80.html
・覇権安定論とツゥキジデスの罠
・「トゥキュディデスの罠」にかかった習近平
6 第2回(123回)教師力アップセミナー 川上 康則 先生
テーマ「通常学級における発達につまずきがある子どもの輝かせ方」
資料を紹介しました。
7 資料紹介
図録『平等院鳳翔館』
持ち歩く年表 -幕末クロノロジー
応仁の乱
持ち歩く年表 -幕末クロノロジー
応仁の乱
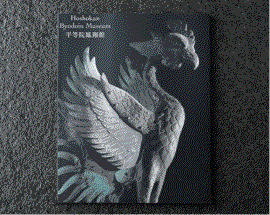
歴史倶楽部
● 全長5m70cm大容量の幕末絵巻!(裏表合計)
各種データも充実した、持ち歩く幕末維新年表!
ペリー来航前年から戊辰戦争終結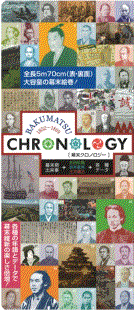 までの18年間の社会動向と松陰・龍馬・歳三のの年表を併せて掲載。
までの18年間の社会動向と松陰・龍馬・歳三のの年表を併せて掲載。
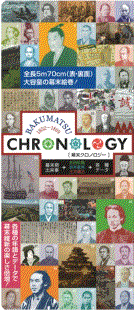 までの18年間の社会動向と松陰・龍馬・歳三のの年表を併せて掲載。
までの18年間の社会動向と松陰・龍馬・歳三のの年表を併せて掲載。 応仁の乱 - 戦国時代を生んだ大乱 (中公新書) 新書 ? 2016/10/25 呉座 勇一
メディア掲載レビュー
成功例の少ない「応仁の乱」で18万部。日本史研究に新たなスター誕生か
日本史上の大トピックとされていながらも、全体像を捉え難い「応仁の乱」。そんな題材を、既成史観の図式に頼ることなく、絶妙なバランス感覚で丁寧に整理した新書がヒットしている。NHK大河ドラマの歴代最低視聴率記録を長年保持していた『花の乱』(1994年)を始め、「応仁の乱」を扱ったものに成功例は少ないので、異例の現象だ。
「『応仁の乱』をテーマに選んだのは著者ご本人です。地味かもしれませんが名前を知らない日本人はおらず、そういう意味では歩留まりがよい。大ヒットはしないまでも絶対に失敗はしないテーマという認識でした。中公新書は『歴史ものに強い』というアドバンテージもありますし後は“著者力"で突破だ、と」(担当編集者の並木光晴さん)


古くは網野善彦さん、近年では磯田道史さんなど、日本史研究者には、時に、学識の確かさと読み物としての面白さを両立させるスター学者が登場する。36歳とまだ若い本書の著者は、次代の有望株だ。
「扱う題材の全体像をはっきりと理解し、その上で、読者に伝える情報を取捨選択できる。30代半ばでのこの筆力には、とても驚かされました」(並木さん)
中公新書の主な読者層は50代以上。しかし本書の売れ行きの初速はネットなどと親和性がある30代・40代が支え、そこから高年齢層に支持が広がった。これは、新たなスター誕生の瞬間かもしれない。
評者:前田 久
平成31年度の教師力アップセミナープログラム
第3回(通算124回) 9月7日(土) 10:00~12:00
山田 貞二(一宮市立浅井中学校長)社楽の会にも来ていただきました。
第4回(通算125回) 10月14日(月・祝) 10:00~15:00(一日)
野口 芳宏(植草学園大学名誉教授・君津市文化協会会長)説明は不要ですね。
第5回(通算126回) 11月9日(土) 10:00~12:30
和田 裕枝(授業と学び研究所フェロー)野木森 広(愛知教育大学教職大学院特任教授)
ここも説明不要です。
第6回(通算127回) 1月18日(土) 10:00~12:00
佐藤 正寿(東北学院大学文学部教育学科教授)「地域と日本のよさを伝える授業」をメインテーマに、社会科を中心とした教材開発・授業づくりで知られています。
第7回(通算128回) 2月8日(日) 10:00~12:00
山本 良和(筑波大学附属小学校教諭)日々の授業でどのように「しこみ」、「しかけ」を設定していくのか。模擬授業を通して講演していただきます。
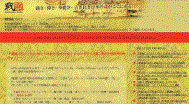
 日本史
日本史