1 東京散歩
10月30日から11月1日にかけて所用で東京へ行ったので、その取材の内容を紹介します。
土曜日には、大森貝塚、そしてそのあたりの解説が詳しい品川区博物館へ、
平成8年4月に開園した大森貝塚遺跡庭園には「大森貝塚碑」やモース博士の胸像、貝層の剥離標本などあり、縄文時代・大森貝塚につ

いて学習できるようになっています。
私は、地質ナビを見ながら、地面の高低に注目していました。
昔の海岸線に沿って、貝塚が見つかっています。
大森貝塚は明治10年(1877)にアメリカから来日した動物学者エドワード・シルヴェスター・モース(Edward Sylverster Morse 1838~1925)によって発見された貝塚で、日本で最初に学術調

査が行われたことから「日本考古学発祥の地」と言われています。
さらに北に進むと、品川歴史館があります。
日本考古学発祥の地といわれる大森貝塚と、東海道第一番目の宿場として栄えた品川宿を中心にした常設展示では、原始・古代から現代にいたるまでの品川の歴史を学ぶことができます。
https://www.city.kita.tokyo.jp/hakubutsukan/、そして大河ドラマ記念館に行きました。
東京の区立博物館のクオリティは高い!
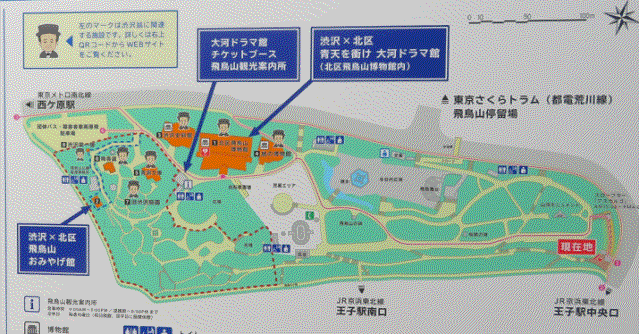
この図の左上のあたりが邸宅で、全体が丘になっています。
丘の南側に、かつて、王子製紙の工場がありました。栄一の邸宅は、製紙工場を見下ろす場
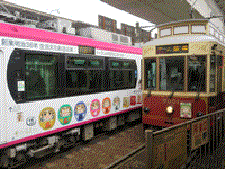
所に合ったのです。栄一にとって重要なことがよく分かります。
そして、都電荒川線に乗車。
都電荒川線は東京に残る唯一の都電で、三ノ輪橋~早稲田間(12.2km・30停留場)を運行しています。地域の身近な足として長年親しまれ、沿線には、桜やバラなど花の見どころや歴史・文化に触れられる名所旧跡、生活感あふれる昔ながらの商店街など多様で魅力あるスポットが満載です。「東京さくらトラム」という愛称で呼ばれています。
続いて、国立映画アーカイブ&特別展の円谷英二展に行きました。国立映画アーカイブは、独立行政法人国立美術館が運営する、日本で唯一の国立映画機関です。映画フィルムや映画関
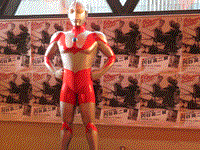
連資料を可能な限り収集し、その保存・研究・公開を通して映画文化の振興を図っています。
映画会は日常的に、定期的に特別展を行っています。現在の円谷英二展は少々がっかり。特撮の装置を見たかった!
その後、霞ヶ関にある「領土・主権展示館」に行きました。社会科教師にはぜひ行ってほしいところです。これをみると、北方四島、尖閣、竹島のどれもが日本の固有の領土であることは、歴史的にも国際法的にも明確です。(北方2島は微妙だが…)
教材研究には最適です。

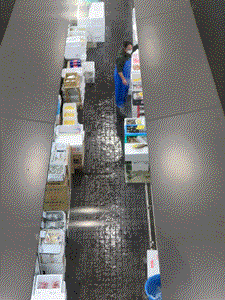
1日(月)は、朝5時から豊洲の卸売市場を見学。
まず、右上の水産仲卸売り場を見学。すき間からしか見えなくて、がっかり。
この先が不安になりました。
しかし、水産卸売棟では感激。マグロのセリを詳しい人の説明付きで見ることができました。
ちょっと語れるようになりました。6時45分

ごろには終わるので、行くならそれまでに行ってください。
軽くデータを解説すると、生のマグロ200尾ほどは5時半から始まりますが、見えません。
冷凍マグロは1000尾ほどで、5時45分から1時間ほどで終わります。日本一のセリです。
卸売りが5社、仲卸が200人ほどいます。
値段は、キロ1万円まで。重さは60キロ前後。ざっと、20万から100万の間でしょう?

部屋全体が10度ほどに保たれ、すべて電動車で運びます。築地は密閉できなかったので、ずいぶん優れています。
青果棟もいきましたが、たいしたことはありません。やはりマグロです!
朝食は刺身定食。おいしかった!

8時からは、毎日見ている、D
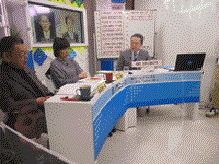
HCスタジオでの「虎ノ門ニュ
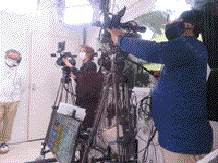
ース」を道路から見学。
衆議院選挙帳票日翌日なので、多くの人が集まっていました。
放送の仕組みも分かりました。
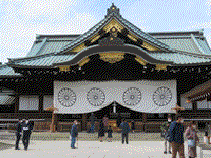
そして、靖国神社と遊就館へ

行きました。遊就館は30年ぶ
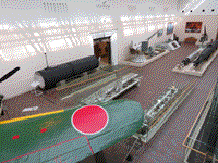
りですが、その充実ぶりに驚きました。日本一の戦争に関する展示館になりました。
写真と友に展示されている戦死者の手紙には涙が出ます。広島の平和記念資料館、知覧の特攻平和会館、そして遊就館は日本人なら一度は行きたいところです。
ついでに、千鳥ヶ淵戦没者墓苑でもお祈りをささげてきました。
最後は、日ごろ社会科の資料でお世話になっている国立公文書館へ行ってきました。
ここのデジタルアーカイブはすごい! 「平成」「令和」のあの文字の原本も展示されています。
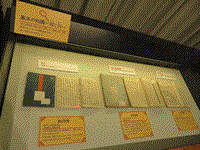
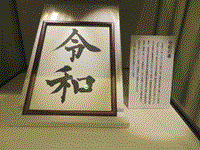
社会科教師は足で稼げ!
よくいうことですが、今回、再認識しました。
コロナも終わりそうです。どしどし取材に出かけましょう!。
2 加藤高明を見なおす まずは先行研究から
愛知県出身の第24代内閣総理大臣、加藤高明を見なおしたいと考えています。まずは、簡単な紹介。
デジタル版 日本人名大辞典+Plus「加藤高明」の解説
加藤高明 かとう-たかあき
1860-1926 明治-大正時代の外交官,政治家。
安政7年1月3日生まれ。岩崎弥太郎の娘婿。三菱本社勤務から官界をへて政界に転じ,明治33年第4次伊藤内閣外相となる。大正4年第2次大隈(おおくま)内閣外相として,中国に対華二十一ヵ条要求を受諾させた。5年憲政会総裁。13年護憲三派内閣を組織し,普通選挙法・治安維持法を制定。翌年単独内閣を組織。大正15年1月28日死去。67歳。尾張(おわり)(愛知県)出身。東京大学卒。旧姓は服部。
出生に詳しい論文
「加藤高明―特に彼の外相及び首相としての功罪―」 小笠原 眞
人間文化: 愛知学院大学人間文化研究所紀要, 2008 - ※ 現物を配付しました。
「加藤高明の外交構想と憲政会 -一九一五~一九二四-」
奈良岡 聰智 『国際政治』2004 巻 139 号 p. 74-90,L10
「加藤高明内閣成立の底流と幣原外交--国際的自立と内外融和への挑戦」
宮田昌明 - 日本研究, 2006 - nichibun.repo.nii.ac.jp
今後も紹介していきます。
3 無料で参加できる研究発表会を紹介!
・ 岐阜大学教育学部附属小中学校 教育研究会 11月6日(土)オンライン
自己実現に向かう児童生徒の育成 -新領域「どう生きる科」と教科等の学びをつなぐ-
第8回 個別最適な学び研究会(中山芳一先生ご講演)11/6(土)
演題は「非認知能力と個別最適な学び」
・ 岐阜市立陽南中学校 研究発表会 令和3年 11月12日(金)対面
「未来社会を切り拓く生徒の育成」~学びをつなぎ,問い続けるための指導を通して~
三重大学教育学部附属小学校 第40次公開研究会 11月24日(水)
学びに向かう力を育む授業 ~ 各教科等の特質を生かした授業改善 ~
第36回山梨大学教育学部附属特別支援学校公開研究会(オンライン開催)
日時:令和4年1月26日(水)~2月6日(日) <YouTubeによる限定配信>
主題:個に応じた支援の探求~ICTの活用をとおして~
4 第二百五回国会における岸田内閣総理大臣所信表明演説 教育関連部分
いつものように、教育関連を抜き書きしてみます。
一 はじめに
二 第一の政策 新型コロナ対応
三 第二の政策 新しい資本主義の実現
(前略)
まず、成長戦略の第一の柱は、科学技術立国の実現です。
学部や修士・博士課程の再編、拡充など科学技術分野の人材育成を促進します。世界最高水準の研究大学を形成するため、十兆円規模の大学ファンドを年度内に設置します。デジタル、グリーン、人工知能、量子、バイオ、宇宙など先端科学技術の研究開発に大胆な投資を行います。民間企業が行う未来への投資を全力で応援する税制を実現していきます。
(中略)
第二の柱は、中間層の拡大、そして少子化対策です。
中間層の拡大に向け、成長の恩恵を受けられていない方々に対して、国による分配機能を強化します。
大学卒業後の所得に応じて「出世払い」を行う仕組みを含め、教育費や住居費への支援を強化し、子育て世代を支えていきます。
保育の受け皿整備、幼保小連携の強化、学童保育制度の拡充や利用環境の整備など、子育て支援を促進します。こども目線での行政の在り方を検討し、実現していきます。
四 第三の政策 国民を守り抜く、外交・安全保障
五 新しい経済対策
六 おわりに
5 文部科学省関係資料
(1)児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
(2)コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議(第6回)配布資料
(3)幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会(第4回)配付資料
(4)個別の教育支援計画の参考様式について
(5)「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」有識者会議(令和3年度)配付資料







 いて学習できるようになっています。
いて学習できるようになっています。
 査が行われたことから「日本考古学発祥の地」と言われています。
査が行われたことから「日本考古学発祥の地」と言われています。
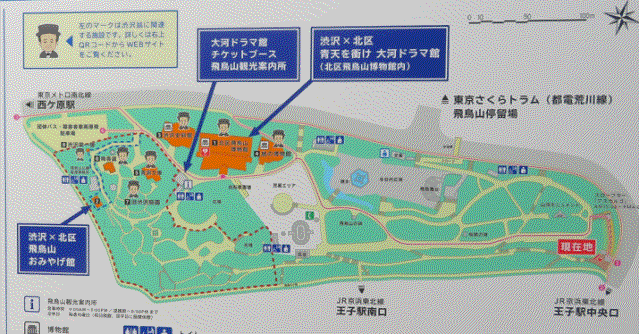 この図の左上のあたりが邸宅で、全体が丘になっています。
この図の左上のあたりが邸宅で、全体が丘になっています。
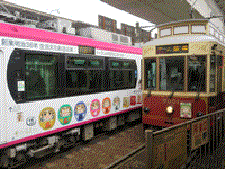 所に合ったのです。栄一にとって重要なことがよく分かります。
所に合ったのです。栄一にとって重要なことがよく分かります。
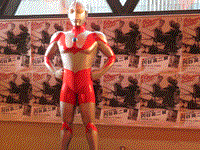 連資料を可能な限り収集し、その保存・研究・公開を通して映画文化の振興を図っています。
連資料を可能な限り収集し、その保存・研究・公開を通して映画文化の振興を図っています。


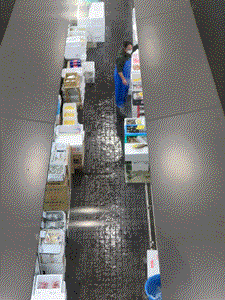 1日(月)は、朝5時から豊洲の卸売市場を見学。
1日(月)は、朝5時から豊洲の卸売市場を見学。
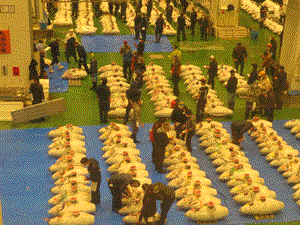
 ごろには終わるので、行くならそれまでに行ってください。
ごろには終わるので、行くならそれまでに行ってください。
 部屋全体が10度ほどに保たれ、すべて電動車で運びます。築地は密閉できなかったので、ずいぶん優れています。
部屋全体が10度ほどに保たれ、すべて電動車で運びます。築地は密閉できなかったので、ずいぶん優れています。
 8時からは、毎日見ている、D
8時からは、毎日見ている、D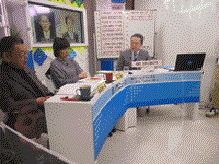 HCスタジオでの「虎ノ門ニュ
HCスタジオでの「虎ノ門ニュ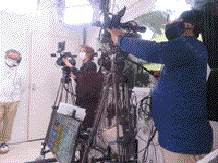 ース」を道路から見学。
ース」を道路から見学。
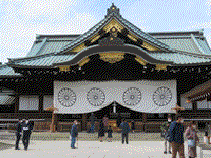 そして、靖国神社と遊就館へ
そして、靖国神社と遊就館へ 行きました。遊就館は30年ぶ
行きました。遊就館は30年ぶ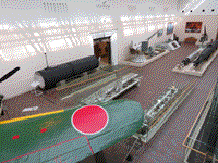 りですが、その充実ぶりに驚きました。日本一の戦争に関する展示館になりました。
りですが、その充実ぶりに驚きました。日本一の戦争に関する展示館になりました。

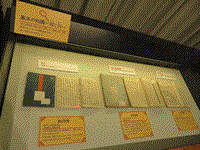
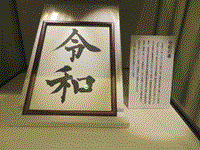 社会科教師は足で稼げ!
社会科教師は足で稼げ!