第564回 社楽の会報告 第563回 第565回へ TOPへ
報告者 土 井
2022年6月30日(木)、社楽の会を布袋北学習等供用施設で開催しました 。
参加者(勤務校)は、土井(名古屋芸術大)、高橋先生・伊藤先生(岩北小)、吉田先生(岩東小)、谷田先生(大西小)、安形先生,,勝村先生、近藤先生(犬山中)、高木先生(犬北小)、杉田先生(布袋小)、髙木先生(池野小)、寺谷先生(扶桑町教委)、野口先生(犬山市教委)、坪内先生(江南市教委)の14名でした。
土井の資料を紹介します。
1 『社会科教育』(明治図書)10月号原稿案
2 書籍紹介『子どもに確かな力がつく授業づくり7の原則×発問&指示』
3 第2回 荘園への招待 資料紹介
4 岐阜市立加納小学校 研究発表会
5 NITS独立行政法人教職員支援機構より
6 文部科学省 関係資料 |
次回は、7月14日(木)19:00 から行います。
1 『社会科教育』(明治図書)10月号原稿案 7月14日締め切り
テーマ 思考力・判断力を鍛える!深い学びに導く地理発問づくり
「思考力」に視点を当てて書いてみました。意見をいただきました。
2 書籍紹介『子どもに確かな力がつく授業づくり7の原則×発問&指示』小林康宏
別紙で紹介しました。
3 第2回 荘園への招待 資料紹介
6月4日に受講しました。講師は、名城大学教授の伊藤俊一先生。
テーマは、荘園と気候変動。近年の古気候学研究の進展によって過去の気候変動がかなり正確にわかるようになり、史料からわかる実態と突き合せることで、荘園が気候変動に翻弄された様子が明らかになってきました。古気候学の研究成果について解説するとともに、平安時代の大旱魃、鎌倉時代の冷害、室町時代の集中豪雨などの実態がわかります。
4 岐阜市立加納小学校 研究発表会
6月25日(土)、岐阜市立加納小学校 研究発表会へ行ってきました。
加納小学校のあたりは、古くより中山道の要衝として栄えてきました。
中山道の53番目の宿が加納宿。中山道六十九次の中では、本庄宿(埼玉県本庄市) 、高宮宿(滋賀県彦根市) 、熊谷宿(埼玉県熊谷市) 、高崎宿(群馬県高崎市) に次ぐ5番目に大きな宿です。
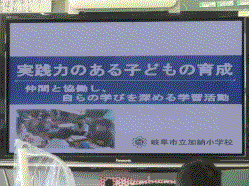
公武合体で、徳川に嫁ぐことになった1861年、皇女和宮親子内親王はこの加納宿に宿泊しました。

1601年、徳川家康の命により岐阜城が廃城となり、代わりに築城されたのがこの加納城です。岐阜城の廃材も使われました。
戦国時代が終わり、東海道の名古屋城と並び、中山道の守りとしたのでしょう。
私は、道徳の授業を2本見て、分科会にも参加しました。加納小学校の道徳研究には定評があり、久しぶりにその世界を垣間見ました。何より、この時期に授業公開していただけたことに感謝します。
5 NITS独立行政法人教職員支援機構より
(1)プログラミング教育の具体的実践 #2 ~実際のプログラミングを通したプログラミング的思
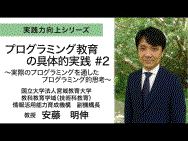
考~:実践力向上シリーズ No4
「コンピュータを用いるプログラミング的思考とはどういうことか」について解説した後、その必要性と「デジタル」な言語活動、「アナログ」な感性の良さとの対比等について解説しています。
(2)プログラミング教育の具体的実践 #3 ~授業実践事例にみるプログラミング教育の要点~:
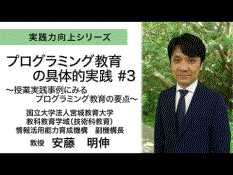
実践力向上シリーズ No5
図工や国語、音楽等における、プログラミング教育の授業実践事例について、動画や写真、児童の感想等を交えながら、教師の働きかけを含めた授業の要点について解説し、さらに指導案の書き方にも触れています。
(3)プログラミング教育の具体的実践 #4 ~実践からみるプログラミング教育の可能性~:実践
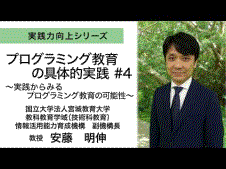
力向上シリーズ No6
プログラミング教育における、STEAM教育やコンピュータサイエンス教育としての視点について、理科や技術等における具体的な授業実践事例を交えながら、解説しています。
6 文部科学省 関係資料
(1)GIGAスクール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専門家会議(第5回)資料
【資料1】第1回から第4回会議までの主な御意見等 (PDF:284KB) PDF
【資料2】株式会社EDUCOM御発表資料 (PDF:3.7MB) PDF
【資料3】スズキ教育ソフト株式会社御発表資料 (PDF:2.5MB) PDF
【資料4】株式会社システムディ御発表資料 (PDF:2.3MB) PDF
【資料5】GIGAスクール構想の下での校務の情報化に係る論点整理に向けた検討資料 (PDF:676KB) PDF
【参考資料】GIGAスクール構想の下での校務の情報化に係る論点整理に向けた検討資料(第4回会議資料) (PDF:408KB) PDF




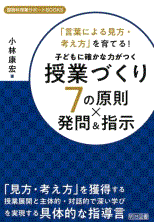
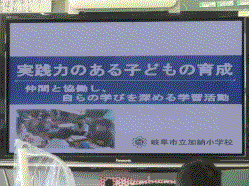
 1601年、徳川家康の命により岐阜城が廃城となり、代わりに築城されたのがこの加納城です。岐阜城の廃材も使われました。
1601年、徳川家康の命により岐阜城が廃城となり、代わりに築城されたのがこの加納城です。岐阜城の廃材も使われました。
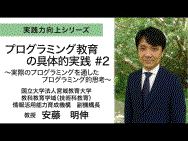 考~:実践力向上シリーズ No4
考~:実践力向上シリーズ No4
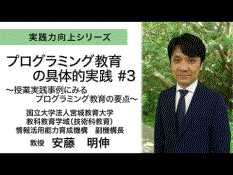 実践力向上シリーズ No5
実践力向上シリーズ No5
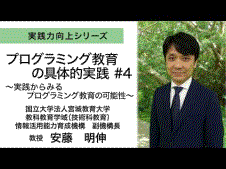 力向上シリーズ No6
力向上シリーズ No6