1 ChatGPT4に指導案を見てもらおう! 指導案を多面的に検討するプロンプト
指導案について意見をもらうことは大切なことです。今は、それがChatGPT4でできるのです。
実際の授業研究で使われた指導案で試してみました。
-------------------------------------
#命令書:
あなたは小学校の教員です。以下は小学校4年生の算数科
「式と計算の順じょ」の指導案です。多面的な意見がほしいです。
#条件:
・A先生は肯定的な意見を述べてください。
・B先生は否定的な意見を述べてください。
・またB先生は自身の意見に対する改善方法を提案してください。
#指導案: 貼付します ←ワードのデータを添付
#出力文:
--------------------------------------
出力文
A先生の意見(肯定的な意見)
この指導案は、小学校4年生の「式と計算の順じょ」単元の学習内容を効果的に進めるために非常に適切です。以下の点で優れていると思います:
計算の基本ルールの理解を強化:この指導案では、四則の混合した式や( )を使った式を用い、計算の順序を理解させることを目的としています。児童が乗法と除法、加法と減法の関係を学ぶことで、計算の基礎的な理解が深まります。
問題解決力の向上:問題文の内容に基づいて立式し、計算の方法を考えることで、児童の問題解決能力が養われます。特に「未知数を□として立式する」活動は、児童の思考力や表現力を伸ばす良い機会です。
具体的な指導方法の提示:指導過程には、児童が理解を深めるための具体的な学習活動や指導の留意点が詳細に記されています。特に、関係図を使った視覚的なアプローチは、児童が概念をより明確に捉えやすくする効果的な方法です。
協働学習の促進:ペアでの説明活動など、協働学習を取り入れている点も評価できます。これにより、児童は互いに意見を交換しながら学び合うことができ、学習の深化が図られます。
B先生の意見(否定的な意見)
一方で、この指導案には改善の余地もあると考えます。以下の点で課題があると思います:
児童の多様な理解度に対応しきれていない:クラスには算数が得意な児童と苦手な児童が混在していますが、指導案では個別支援の計画がやや不十分です。特に算数が苦手な児童にとっては、関係図の理解や演算の順序においてつまずく可能性があります。
実生活との関連性の不足:この単元では、計算の順序やルールの理解が主な目標ですが、児童が日常生活でどう活用するかの具体例が不足しているように感じます。実際の場面での応用を意識させることで、学習内容がより深く定着する可能性があります。
評価方法の多様性が限定的:評価基準がワークシートや発言に基づくものに偏っているため、児童の多様な理解や思考を十分に評価できていないかもしれません。より多様な評価方法を導入することで、児童一人ひとりの学習成果を的確に把握できるでしょう。
改善方法の提案
個別支援の強化:算数が苦手な児童向けに、より具体的でステップごとの指導計画を用意し、学習内容の理解をサポートする必要があります。例えば、関係図を使った説明が難しい場合は、よりシンプルな例から始めて段階的に進めるようにするなどの工夫が考えられます。
実生活との関連付け:学習内容を実生活の問題に結びつけるアクティビティを取り入れることで、児童にとってより意味のある学びになります。例えば、買い物の計算や時間の計算など、身近な場面での活用例を示すと効果的です。
多様な評価方法の導入:ワークシートや発言に加えて、例えば児童が自分で作成した関係図や問題を使ったプレゼンテーションなど、多様な形式で学習成果を評価する方法を導入することで、より包括的な評価が可能になります。
このような改善を行うことで、より効果的な授業展開が期待できるでしょう。
練習問題を具体的に作成するプロンプト
#命令書:
あなたは小学校の教員です。以下は小学校4年生の算数科「式と計算の順じょ」の指導案です。この学習に準拠した練習問題を作ってください。
#条件:
・練習問題は10問 。
・簡単な問題から、やや難しい問題まで作る。
・解答の解き方も載せる。
#指導案: 貼付します
#出力文:
--------------------------------
小学校4年生「式と計算の順じょ」に準拠した練習問題
以下に10問の練習問題を作成しました。問題は簡単なものからやや難しいものまで順に並べてあります。それぞれの問題の解答例も示しています。
練習問題
1 □にあてはまる数を求めましょう。
□ × 3 = 18解答例: 18 ÷ 3 = 6。よって、□ = 6。
2 □にあてはまる数を求めましょう。
20 ÷ □ = 5解答例: 20 ÷ 5 = 4。よって、□ = 4。
3 次の計算をして、答えを求めましょう。
4 + 3 × 5解答例: 3 × 5 = 15、次に4 + 15 = 19。よって、答えは19。
4 □にあてはまる数を求めましょう。
□ - 7 = 13解答例: 13 + 7 = 20。よって、□ = 20。
5 次の式の答えを求めましょう。
(8 - 3) × 4解答例: 8 - 3 = 5、次に5 × 4 = 20。よって、答えは20。
6 □にあてはまる数を求めましょう。
□ ÷ 6 = 7解答例: 7 × 6 = 42。よって、□ = 42。
7 次の計算をして、答えを求めましょう。
5 × (2 + 8) ÷ 2解答例: 2 + 8 = 10、次に5 × 10 = 50、最後に50 ÷ 2 = 25。よって、 答えは25。
8 次の式の答えを求めましょう。
15 - (4 × 2) + 3解答例: 4 × 2 = 8、次に15 - 8 = 7、最後に7 + 3 = 10。よって、答えは10。
9 □にあてはまる数を求めましょう。
(□ + 5) × 3 = 30解答例: 30 ÷ 3 = 10、次に10 - 5 = 5。よって、□ = 5。
10次の計算をして、答えを求めましょう。
(20 ÷ 4) + (3 × 2)解答例: 20 ÷ 4 = 5、次に3 × 2 = 6、最後に5 + 6 = 11。よって、答 えは11。
これらの問題は、式の立て方や計算の順序に焦点を当てており、指導案の目標に沿った内容になっています。問題の難易度も段階的に設定してあるため、
児童の理解度に合わせて活用できます。
図解を作ってくれるAI「Napkin AI」を紹介します。
「Napkin AI」に「豊臣秀吉の業績を教えて」と打ち込んだら、次の5つの見出しが並びました。それを図解してくれました。
豊臣秀吉の業績;天下統一、太閤検地、城の建設と都市の発展、文化の振興、朝鮮出兵
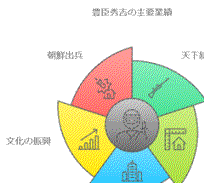
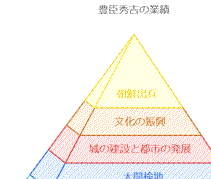
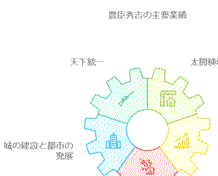
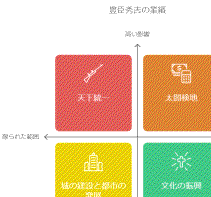
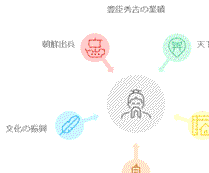
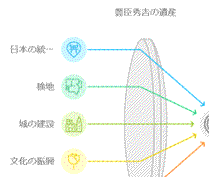
これらの他にもいろいろ作ってくれました。
試しに「社楽の会について教えて」と入力してみます。
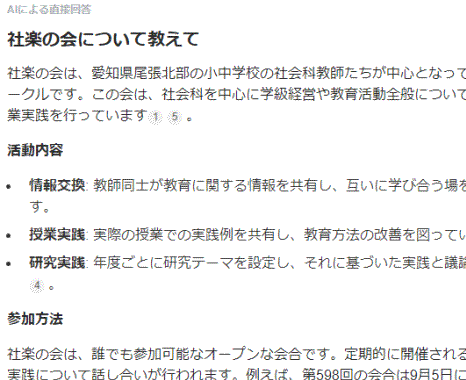
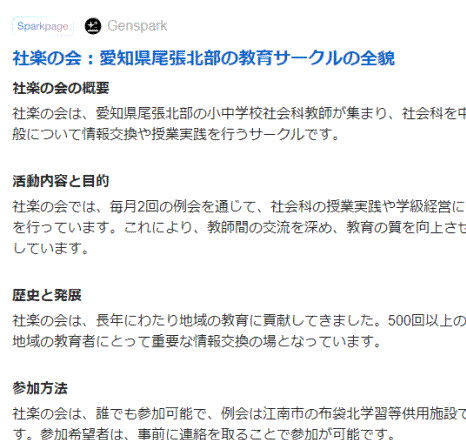
4 自動情報整理ツール「Mapify」
これはすごい!
キーワードを入れたり、PDFを貼ったり、YouTubeのアドレスを入れると、その内容を樹形図にまとめてくれます。https://mapify.so/ja/app/all
試しに「社会科問題解決学習」と入れてみると 「社会科問題解決学習」以下の5本の枝は、AIが自分で判断しています。それ以下の枝も、クラウドから探してくるのでしょう。驚異の精度です。
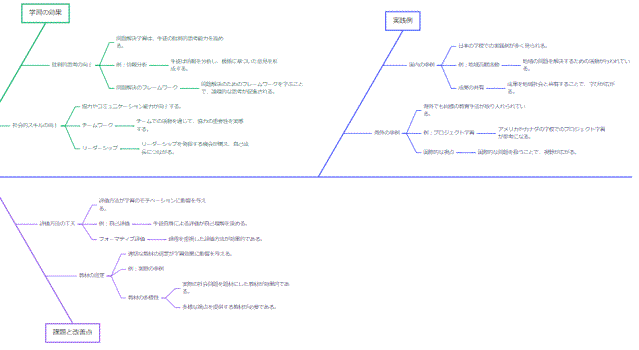
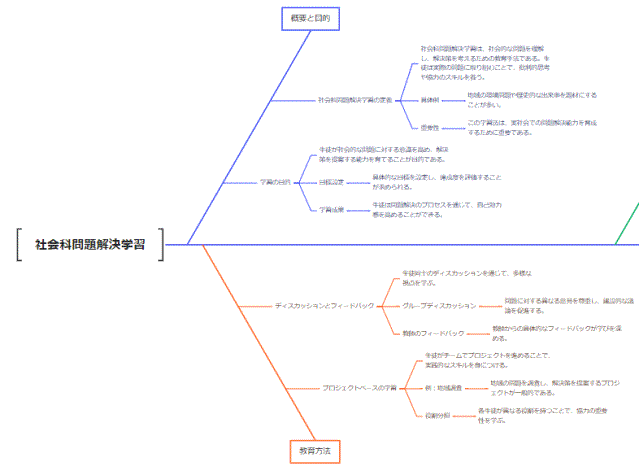
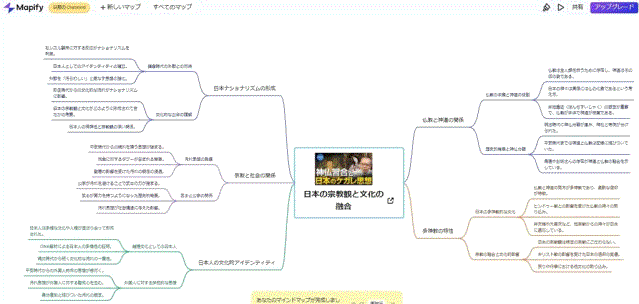
5 リーディングDXスクール実践事例 -2-
リーディングDXスクール事業は、GIGAスクールの標準仕様に含まれている汎用的なソフトウェアとクラウド環境を十全に活用し、児童生徒の情報活用能力の向上を図りつつ、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実や校務DXを行い、全国に事例を展開する事業です。地域や校種を超えて様々な取組を参考にし、学校での端末の「普段使い」による教育活動の更なる推進にお役立ててください 。数回に分けて紹介ます。
リーディングDXスクール事業ホームページ⇒https://leadingdxschool.mext.go.jp/
【指定箇所事例発表】静岡県吉田町教育委員会 平井奉子氏 (R5リーディングDXスクール事業夏季学習会)
平井先生ご登壇資料
【指定箇所事例発表】栃木県壬生町教育委員会 稲木健太郎氏・森弥生氏 (R5リーディングDXスクール事業夏季学習会)
稲木先生・森先生ご登壇資料
【指定箇所事例発表】茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校 中村めぐみ氏(R5リーディングDXスクール事業夏季学習会)
中村先生ご講演資料
【指定箇所事例発表】鹿児島県垂水市教育委員会 今村圭氏 (R5リーディングDXスクール事業夏季学習会)
今村先生ご講演資料
続きは次回