 |
 |
 |
 |
|---|
次回は12月12日18時 です。
次々回は 1月9日18時 資料集部会リハーサル

1 北名古屋市立西春小学校研究発表会報告
発表の様子を動画で紹介します。
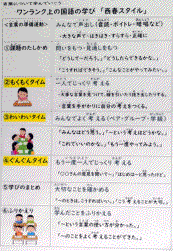
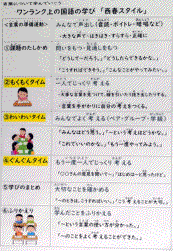
私が学校に答えたアンケートの最後の部分を紹介します。
冒頭の合唱も含めて、感動の連続でした。
このようなすばらしい西春小の子ども達だからこそさらに望むなら、「ワンランク上の振り返りとその共有」だと思いました。教材から離れた「学びそのもの」をメタ的に見て、さらに上を目指す、そんなことを考え、それを仲間と共有しさらに上を目指す。彼ら、彼女らならできると思います。
最後に、さらなる西春小学校のご発展を祈念し、久保校長先生はじめ職員の皆様方、愛すべき児童の皆さんに感謝の気持ちをお伝えして、アンケートへの回答といたします。どうもありがとうございました。
2 これからの社会科づくりで大切にしたいこと
国立教育政策研究所教育課程調査官 小倉勝登
基本的なことばかりです。丹葉地区の実践も、これら基本的なことのふり返りから行いたいと思います。
別紙で紹介します。
3 観音寺城FW
令和6年11月16日、いつものメンバー(積知積徳会)で、観音寺城周辺へFW(フィールド・ワーク)に行ってきました。
 その様子を報告しています。
その様子を報告しています。
4 第18回信長学フォーラム
令和6年11月23日じゅうろくプラザホール
1 講演 中井均先生 13:05~13:55
ほぼ知っている内容だが、小牧、岐阜、安土が聖地であるという視点は今までになかった。
他は資料参照
2 講座 松下 浩氏 13:55~14:25
まさに、昨年のおもしろ学校でやった内容。新しいものはないが、資料が充実していた。
対談 「安土城からみた岐阜」 要旨
司会;内堀 信雄(岐阜市文化財保護課)
1 なぜ安土を選んだか
松下;岐阜と京は遠い。琵琶湖の存在が大きい。近江は日本の中央。日本海と伊勢湾を結ぶ要所。琵琶湖は物流、人の流れが行われていた。その水運を掌握できる場所として選んだ。
中井;信長は京に城を造らない。秀吉や家康は造った。信長は一歩引いた滋賀県で造った。 琵琶湖はすごい。物資は港を通る。陸上より、一気に運べる。琵琶湖がバイパスになっている。
秀吉は街道重視になっていく。薬師山という信仰しているところにはいることで、支配を意識化した
司会:なぜ尾張から岐阜へ移したか。
松下:清洲は守護の権威、追放後は息のかかっていない小牧、岐阜は道三の娘婿、正当性がある。道三の遺言状でも書いてある。十分な根拠になった。齋藤氏の継承
中井:信長が城を移動、占領地に移した。美濃を掌握したから美濃に言った。どんどん西に行った。西を意識していた。岐阜にきたことに意味がある。尾張の城は終わり。しかし、岐阜は信忠に移した。織田の城。安土は天下の城。岐阜は個人の城。
2 天主の意味
松下:令和の大調査、去年の段階で、天主台のふもとから建物の礎石が見つかった。この建物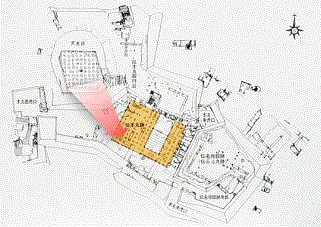 が何かはわからない。
が何かはわからない。
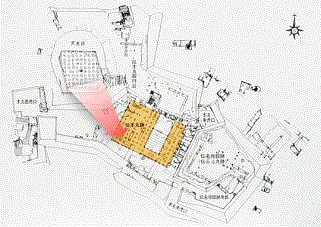 が何かはわからない。
が何かはわからない。
天主台の石垣の崩壊状況が確認できた。自然に崩れたのではなく、人為的に崩した。破城、目立つ場所を壊した。天正13年に安土城が廃城。秀吉が織田家の意味合いを失う。八幡山に新たに築いた。秀吉にとって安土城はあってはならない。
中井:礎石の建物は発見。今までわからなかった。チェック機関ではない。あそこから天主にあがる玄関があってもおかしくない。注目したい。
石が焼けている。天主に属した建物。要になる。
司会:破城の最上部の並んでいる石は、整頓したのでは?
中井:信長自身が天主を作るのは、前例がほしい。まず、義昭で作る。その後に坂本城、徐々に将軍の城みたいなコピーが出て、安土で天下人としての城をつくった。
天主は大事。生活の場にしていたのは意味がある。それ以後は、天主にすんでいない。江戸時代にもすまない。
松下:安土城は天下人の城でなくてはならない。それ以降の大きい城を見ても驚かないが、当時の人では驚き。全段層石垣。高層建築。石垣は、石、人を集める。動員力、軍事力の現れ。
天主には、狩野永徳のふえうま絵、金具、当代随一の職人が関わってる。当時の最高峰が集約されている。軍事力と文化力を掌握せいてる。見ている人にどう思わせるか。
司会:岐阜城の天主は?
松下:天主の出現は難しいが、古いのはカネミきょうき 坂本城が古い、岐阜城はそれ以上なので、天守はない?あってもいい。三層ぐらいのものか。
中井:岐阜城については、今の天守台は今のもののため。その下に石垣があった。そこに何があったのか?天守だと思う。信長段階の天守がのっていたと考える。資料がないので、考古学的に考える。ただ、いつ作られたかが課題。永禄12年に、義昭に作った後で、細川に勝竜寺城、次に坂本城。勝竜寺城と坂本城は、同じ工人が作っている。岐阜は、その後、元亀3年ごろにつくったのでは?
司会:元亀2年に岐阜茶会があった。微妙な時期。どこで開かれたのか?山頂の可能性も。
中井:坂本も細川も、天守で茶会をやってい
3 安土城の伝秀吉邸とは何か?
松下:秀吉の屋敷ではない。秀吉邸の理由は、本能寺の後に安土に入ったからでは?江戸図には何らかに関わりのある人が名前にでている。江戸図の天主周辺は有名な人はいない。あの城は信長のプライベート空間で近い人だけが住んでいる。秀吉邸は何か。天皇の行幸先だと思う。天正4年頃から考えていた。今の大手道は行幸のための道。百々橋のほうが普段使い。
中井:安土城の平成の発掘の時、伝秀吉邸はA、徳川はBにしたらと提案した。当時の秀吉が
あそこに敷地をもらえるわけがない。まず信長の居住空間で、公的なもてなしの場かも。両側には、信孝など一門の屋敷では。
司会:岐阜城の山麓巨館メタバースが作られている。永禄10年ごろ。巨石を並べた入り口というのは?朝倉にも巨石入口があった。
松下:岐阜城は、領国支配の拠点。義昭は、立政(りゅうしょう)寺で対面した。義昭の御所は、木戸の外。中に入れないのでは。巨石は注目すべき。来人におおといわせる。お客を迎える場所でもあった。
中井:朝倉の一乗谷にも驚く。岐阜の場合は、巨石を積むのが権威を示すやり方だった。小牧から移り、新たな拠点を示した。
司会:岐阜城の山麓には池がある。安土城ではどうか?
松下:安土城の池について宣教師が書いている。庭は権威の象徴。小京都のような館をつくったが、これまでの調査では見つかっていない。伝前田邸の上段部かと思ったが確証はない。あるとしたら、黒鉄門より内。これまではない。発掘してないのは二の丸、もしくは八角平。
中井:庭のもつ意味は大きい。当時は庭を見てお茶を飲み連歌をよむ。江戸の屋敷もかならずある。安土だけないのはあり得ない。岐阜は、池が階段状に見つかっている。安土は、各屋敷にもあったと思う。朝倉氏の庭は小さく、別に大きな庭がある。本丸御殿の中に庭があってもいい。小さな庭を造っているのでは。いわば、琵琶湖が庭の池。景観もふまえて考えたい。
司会:今までの調査の見直しも必用。琵琶湖もその通り。今後の安土城の発掘に期待したいこと。
松下:15年間開いて、令和の発掘が始まった。平成は20年で終わった。令和は20年以上やりたい。これから、ひとつでも新しい謎を解明したい。
中井:掘れば掘るほどわからなくなる。一乗谷には研究所がある。それが大事。調査研究し、整備が必要。安土も研究所を建てて半永久的に調査が進むことw望みたい
司会:安土城と岐阜城の関係は
松井:安土は安土、岐阜は岐阜
中井:岐阜は信長の城。安土は天正4年の城。それぞれが城郭革命。両方とも重要な城だ