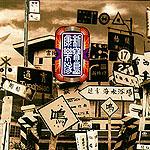
第1集
どことなく「ゆでめん」風ジャケット

第1集の中の気に入っている写真。「台湾鐵路之旅」という雰囲気。考えてみると「鐵路之旅」というのは近代の産物で、どこにいっても「国家と僕」みたいな感覚に襲われる。
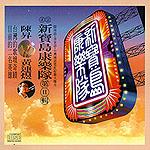
第2集
これを林森北路の間口9尺奥行き6尺という屋台みたいな店で買ったのが始まりでアリマス。 思い返すと「黄昏的故郷」が入っていたので買ってしまったのかも知れない。

第3集
歌詞僅供詞意参考、非正式台語、客語之意。請専家学者海量包涵。謝謝!と「言語のコンピレ−ション」について断わっています。もっとイージーでヨイのに。
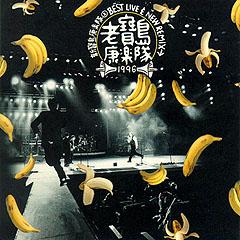
ライブ版
ステージではスタンダードもやっている。黄さんのサックスがヨイ。
久しぶりの今月の歌は「新寶島康楽隊」の「在這恬的暗輔頭」(輔はウソ字です。車を日にしたのが本当の字です。)ですっ。
「新寶島康楽隊」は2年前に台北の夜店みたいなレコード屋で買って来て
気に入り、買い揃えた台湾のデュオです。
最初は彼等の歌う歌のなかでも「非情城市」以来、台湾でも一部で流行っているらしい、
戦前の日本時代の歌謡曲っぽいテイストの曲が気に入っていたのですが、
ここ暫く彼等のファーストアルバムを仕事場に流していて、
もう少し場末風の、或いは東海岸風(台湾の)の曲がとてもリラックスできることに気が付きました。
といっても歌詞が解る訳ではありません。 CDのジャケットには「閔南話客家話北京話綜藝大公演」(閔はウソ字です。門の中に虫を入れてミンと読んで下さい。ミンナム語というのが、まあ、平地の台湾語らしい)と謳われているのですが、 私はどれも解りません。彼の地ではこのような言語能力の無い奴は半人前に違いない。 2枚目のアルバムではこの文句が「閔南語客家語台湾国語霓虹綜藝大曝光」 と変えられているところがなかなか難しいのでありますが、最近の国民党政府を気にしなくてもヨイ、 という彼の地の新しい波が感じられる音楽です。 「音楽は辺境から来る」と言われますが、彼等は先ず言葉から実践している様なのです。
実はこれを近所の中国語教室をやっている中華料理屋の奥さんに日本語にして貰うように頼んでみましたが、
そこで話をしていてもどうもずれる。中国語の解る人々にとっては中国語が世界共通言語であることが当然、
という大前提に立っているような気がして、居心地が悪いのです。
門南語も客家語も韓国語も日本語も台湾の原住民の言葉もタガログ語も辺境の言語であり、
何もそんなものを大切にしなくたって、中国語があれば困らないのに、というやつです。
天安門前が世界の中心と、天下取りを演じてしまう、
北京政府と改革派学生の両方が等しく立っている土俵を感じてしまいます。
そこへ行くと「新寶島康楽隊」はこの中国語の壁を軽やかに乗り越えているのです。
そこには1895年以来百年近い血塗られた現代史があるのですが、
そうした過去の上に揺るぎ無く立つ、確かなローカリズムを感じさせます。
原住民の伝統民謡そのまま、と言う訳ではありませんが、
プリミティブなリズムセクションのうえでおおらかに歌っている歌が多いのですが、
これに今風の暮らしをおちょくった様なナンバーが適当にちりばめられています。
最初に耳に止まった日本時代風も殊更に演出して、というより、
「今の台湾の暮らしにはこんなものも混じっているのヨ」と極く自然体で混ぜてしまっています。
どうも「新寶島康楽隊」の魅力のひとつは「多様性」という事にもあるようです。 「閔南話客家話北京話」という歌詞が多様なだけでなく、メロディーも実に多様で、 それが借り物でなく、彼等にとっての「普通の音楽」と化しています。
昔、沖縄に「チャンプルーズ」というバンドがありましたが、どうもあれの元祖は台湾かもしれない。 台湾の原住民は40万人ほどだそうですが、言語が20種類以上あって、隣村と話をするのに年寄りは日本語、 若者は中国語を使っておる。という話が「土人が裸足で」みたいな取り上げられ方をすることがありますが、 実は「鶏声聞こえて、相通ぜず」という「小国寡民」の理想を実現しているとも言えるのです。 冒頭の「在這恬的暗輔頭」にしても路地でヨッパライのおっさんが犬と子供にこづかれながら 「人生なんてこんなもんよ」と言っている、ノデハナイカと思われる歌なのですが、実に自然体で、 人生は普通であることが幸福なのだ、みたいな癒しに満ちておるのでアリマス。言葉が解らなくても、 感じてしまうことができる歌です。
NHKの衛星ニュースによれば、スペイン政府が官報をカタラン語でも発行することになったそうです。 どうも西欧社会でも「標準語」と言うのは近代国家と二人三脚みたいなところがあるのではないかと思います。 そこへ行くと台湾の人々はそんなことは気にしない。 「使用言語が様々なので、台湾人は思想がいいかげんだ。」などと言われても気にしないのでありましょう。 言葉なんて完全に通じなくても人は幸せになれる部分があるのです。 などと思いながら道を歩いておったら、何故か八百屋の店先に「台湾バナナ」と大書してあり、 つい買って帰って食べてしまいました。うーん、感じながら食べると、フィリピンのチキータバナナよりもうまいような気がする。
PS
「出来たら電話します。」と言われて2週間ほど経つのだが、やはり中華料理店から連絡はない。
そこのご主人も何となく大志を抱く国際ビジネスマンで、中華料理屋は事業資金稼ぎに過ぎない、という感じだったのだ。
旅のエリートと土着民のえーからかげんさの対比である。
実は同じことは台湾まで行かなくても身の回りにはある訳で、
浜松の土着民と結婚した「旅のエリート」である「マスオさんの家」の打ち合わせに行ってつくづくそれを感じてしまった。
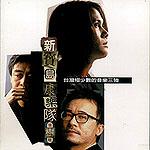
第4集
これが1996.12なので、その後2年程お便りが無い、ということになります。
その間に台北の飲み屋のオバサンが 「あの子は絶対に山の(原住民の)子だよ。」 と言っていた安室奈美江ちゃんは、ヒットをとばしたあげく、「お母さん」しちゃうわ、 金城武君は香港からやって来るわ、張恵妹ちゃんは日本のTVに出るわと、 状況の方がヲジサンバンドを追いこしてしまっている様でもあります。
しかし私の様なヲジサンにとっては「新寶島康楽隊」の軽く言語、つまりは近代国家の壁を越えてしまう「イージーリスニングフォーク」 の方が聞いていて心地良いのです。
第舞集
第6集
pagetop
出放題
版元であるROCK RECORD*1のウエブサイト(但し北米の、台北のサイトは中国語システムがないと化け字である。) を覗いて見て、もう一枚出ているのを発見。タワーレコードから取り寄せて見た。 96.12のリリースであるから、それほど新しいわけではない。しかしこの第4集もなかなかの出来である。 新たに排灣族*2のファンキーボーイを加えて益々快調に歌い上げている。 張恵妹ちゃんもたしか排灣族ではなかったかと思うが、阿VON君の歌うネイティヴ風の歌もなかなかヨイ。 しかし歌詞カードの方はついにローマ字並記となってしまった。
阿VON君のネイティヴソングとともにこのアルバムで気に入ったのは「車輪埔」 コンテンポラリーな感じのイージーリスニングな歌なのですが、 実は歌い出しの「叫著我 叫著我」と言うのは台湾の国民的スタンダードナンバーである「黄昏的故郷」のもじりでありまして、 この曲は「呼んでいる 呼んでいる赤い夕日の故郷が、、」という春日八郎か誰かが歌っていたのと同じ曲なのですが、 あれはいったい誰が造った歌なのでしょう。
じつはこのアルバムで排灣族と供に日本語が初登場しているのです。 しかしそのタイトルも「有楽町人生」なる歌に出てくる日本語たるやあの「さよなら・再見」*3に出てくる類の日本語でありまして、 「ワタクシダイジョウブ、アナタマダイジョウブ」とやられると決して良い気持ちはしないのですが、 まあここら辺が現在の東アジアで普通のニホンゴなのでしょう。
さらにゴチャ混ぜぶりはとどまるところを知らず、 「大哥个話」の曲調は「サヨンの鐘」*4と化してしまい、 聞くほうはただあきれ、台湾というのは凄いところだ。と感心するのであります。
第6集というのを見かけたので入手。2006リリースのようです。 「新寶島康楽隊」というのはワタクシ的には"cross ethnic easy listening"で、期待通りの仕上がりです。ベストソング集がオマケについて総集編という作りです。1987年の戒厳令解除、1991年からの民主化とともにブレークした台湾の多言語国歌としての歩みを音楽に表現した「新寶島康楽隊」はすでに歴史の一部、ということになるのでしょう。
戒厳令布告58年を前に台北市内に聳えていた中正記念堂も「台湾民主記念館」と名前を変えたようです。単一言語による国家に疑問を抱かない日本人には不思議な、ひょっとすると21世紀の世界を先取りした「国家言語発展法」というものも作られつつあるようで、「新寶島康楽隊」もメンバーそれぞれの道を進むのでしょう。
映画にもなっていて、先日静岡で開かれた「台湾映画祭」で見た。well-madeな出来であったが、
最後の言葉の絡まる所は字で読んだ方がこんがらかった感じが面白かった。
黄春明 著/1973/福田桂二 訳/めこん刊1979
日本人の買春旅行をおちょくる好著
日本好きのオヤジと、山西出身の老兵と言うのが加わっていて、
老兵がもっと何かしでかすのではないかと思ったのだが、何もなくて残念。