4-4. 下田湊
1.所在
下田港は南の狼煙崎と隆起台地の須崎半島にはさまれた天然の良港である。
下田湾の中でも西側の稲生沢川河口の内港に、漁船の碇泊所やドックが集中、さらに東に隣接して、
魚市場や漁協等の水産施設、そして観光船の発着所と続く。
湾北側の国道135号 線沿いには下田温泉のホテルや旅館が弁天島にかけて多い。
北西の伊豆急下田駅からも近く、1km程で、途中のまちなみは基盤目状に整い、道路のそこそこに明治の面影を残すナマコ壁の民家が残っている。
2.地形
稲生沢川が下田湾に注ぐ河口に作った沖積平野に、市街地が形成され、南に小高い城山、
北東には天城の支脈、高根山、寝姿山、西北には下田富士、相ノ山と、三方を山に囲まれ、
東南が下田湾に面して開かれている。
北東に長九郎の支脈、池の段山、谷津山などを結ぶ山嶺で河津町と境し、南部は、青野山、志戸山の分水嶺で南伊豆町と接する。
3.沿革
後北条氏は秀吉との対立の推移の中で、天正16年に下田城の築城にかかり、
秀吉方の水軍に備えて、下田城を大型水軍根拠地として整備した。
しかし天正18年、戦いに破れ、下田城を開城、後北条氏に変わって、
関八州と伊豆を領有した徳川家康による下田市域の支配が始まる。
江戸の政治的、経済的発展にともない、盛んになってきた海上交通の要地として、
下田湊が注目され、元和2年(1616年)下田奉行が設置される。
元和9年、須崎から大浦に遠見番所が移され、さらに寛永13年に改築して、
船改番所として、上下廻船を検問することとなった。
先進地域畿内と江戸を結ぶ物資輸送が重大さを増すと、
下田は軍事、警察的機能に加えて、経済的役割も担った。
当時下田は入津3千隻、縄地金山の盛況もあって、家数千軒、人口5千人の繁栄を誇ったという。
しかし、幕府の享保改革により、享保5年下田番所の浦賀引移りが申し渡された。
公儀番所という特権を失った下田の衰退は著しかったが、
江戸・大阪間の日和待ち湊として生きることと、
一方で発展する大消費都市江戸の需要を充たす地場産業の振興に活路を見いだした。
こうして勃興してきたのが、綿屋吉兵衛に代表される廻船問屋であった。
江戸へは伊豆石や伊豆炭、 材木や天草、蚫等の特産物が積み出された。
また海上交通の要衝である伊豆の海岸には、しばしば難破船が漂着した。
手伝った漁民には報奨金が支払われたので、海岸の領有は 磯物の権利ともからんで重要な問題であった。
幕末の寛政5年(1793年)老中松平定信は海防見分のため伊豆を巡視した。
これを受けて御台場築造が計画されたが完成を見なかった。
天保13年(1842年)下田奉行が復活し、翌年ようやく御台場が完成したが、一年の生命で廃止となった。
嘉永7 年(1854年)のペリーの再来航、そして日米和親条約の締結により下田開港が決まると、
下田が外交の表舞台に立って、最も脚光を浴びた時代となる。
a
ペリーの後を追いかけるように来航したロシア使節プチャーチンのディアナ号は
大地震後の津波により大破し、修理のため戸田に回航途中に沈没した。
安政3年(185 6年)には、ハリスがアメリカの日本総領事として、
下田に着任し、玉泉寺を領事館とした。
ハリスにより日米通商条約が調印されると、横浜開港にともない、
下田は閉鎖、下田奉行所も廃止され、下田はもとの港町に戻っていった。
近代に入り、明治20年代以降、近代産業が展開、明治31年には下田ドックか設立された。
交通面では明治28年天城トンネルが開通、大正15年下田自動車が営業開始、
昭和8年に伊東〜下田間の東海岸線の道路が開通した。
この時期東京湾汽船による、東京〜大島〜下田航路も始まった。
中央から遠い下田であったが、昭和36年の伊豆急開通により東京圏と直結し、
観光を中心とする都市へ大きく転換し、伝統的な産業形態は一変した。
|
|

大日本帝國陸地測量部
明治19年測量、明治22年刊
二万分一地形圖「下田町」「神子元島」より
|
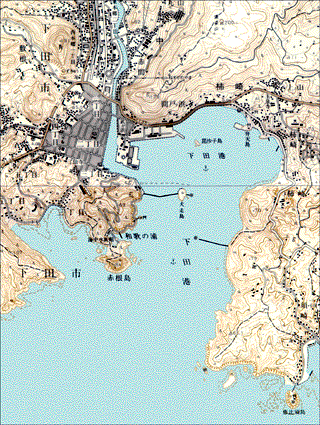
国土地理院
昭和58年改測、昭和59年刊
1:25,000地形図「下田」「神子元島」より
|
| |